
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」〔最終回〕(2023年7月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第32回](2023年6月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第31回](2023年5月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第30回](2023年3・4合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第29回](2023年2月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第28回](2022年12月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第27回](2022年11月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第26回](2022年9・10合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第25回](2022年8月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第24回](2022年7月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第23回](2022年6月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第22回](2022年5月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第21回](2022年3・4合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第20回](2022年2月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第19回](2021年12月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第18回](2021年11月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第17回](2021年9・10合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第16回](2021年8月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第15回](2021年7月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第14回](2021年6月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第13回](2021年5月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第12回](2021年3・4合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第11回](2021年2月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第10回](2020年12月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第9回](2020年11月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第8回](2020年9・10合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第7回](2020年8月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第6回](2020年7月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第5回](2020年6月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第4回](2020年5月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第3回](2020年3・4合併号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第2回](2020年2月号)
- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第1回](2019年12月号)
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」〔最終回〕~2023年7月号
英国の正式名称は、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(UK)」であり、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという4つの国からなる立憲君主制の国である。これまで、英国の大半を占めるイングランドを中心に産業革命などについて語ってきたが、全体の1割にも満たない人口、経済規模のスコットランドも、英国産業革命において大きな役割を果たしている。
今回は、イングランドとたびたび戦いを繰り広げてきたスコットランドの苦難の歴史とともに、スコットランドの目線から産業革命の意義を考える。
1.イングランドとフランスの狭間で揺れ動くスコットランドの苦難(11~18世紀)
(1)「ローランド」と「ハイランド」の地域格差
スコットランドの起源は、843年にスコットランド系ケルト人の国「アルバ」とアイルランド系ケルト人の「ダルリアダ王国」が合同して生まれた「統一アルバ王国」に遡る。北海道とほぼ同じ面積、人口を有するスコットランドは、南の「ローランド(低地地方)」と北の「ハイランド(高地地方)」に大きく分かれる。緯度の割に温暖なローランドは、農業の中心が大麦やオーツ麦であり、またイングランドに接することから、その恩恵を受けて商工業が発展し、首都エディンバラやグラスゴーなど都市や大学が集中している。住民の所得水準は比較的高く、プロテスタント信者が多い。
一方、寒冷多雨のハイランドは、スコットランドの約3分の2の面積を占める山岳地帯で、深い谷と入江で分断されている。人口密度が低く、放牧以外にほとんど産業らしきものがなく、あまり大きな都市は存在しない。この国のシンボルである民族衣装のキルトや民族楽器のバグパイプはすべてハイランド産であり、伝説の怪獣ネッシーで有名なネス湖もある。18世紀半ばまで独自のケルト文化やゲール語、氏族制的な自治が残っており、ローランドと異なりカトリック信者が多い。
(2)カトリック国フランスとの長年の同盟関係から宗教改革による長老派教会の成立へ
1066年にイングランドでノルマン朝が成立以降、早くもフランスに接近していたスコットランドは、イングランドのエドワード1世(在位1272~1307)による侵略を恐れ、1295年にイングランドに敵対するフランスと同盟を結ぶ。フランスと同じカトリックを信仰するスコットランド王室は、プロテスタントを弾圧したが、その後カトリック教会の腐敗に対する批判が強まり、プロテスタントによる宗教改革運動が始まる。
1560年に、フランス出身の神学者ジャン・カルヴァン(1509~1564)から直接学んだスコットランド人のジョン・ノックス(1510頃~1572)によって長老派教会※1が創立されると、スコットランド最大の教派となる。牧師と信者から選ばれた長老によって民主的に運営される長老派教会は、国王を頂点とするイングランド国教とは性格的にかなり異なったものであった。
(3)同君連合※2に期待したスコットランドの落胆
カトリック教徒のスコットランド女王メアリ・ステュアート(在位1542~1567)は、フランス国王フランソワ2世に嫁いだが、1560年に夫が亡くなり、未亡人となってスコットランドに戻る。その後再婚し、1566年に長男を出産するが、メアリ自身の結婚問題で1567年に女王を退位させられ、生まれたばかりの長男がジェームズ6世(在位1567~1625)として即位する。メアリは、その後イングランドに亡命するが、エリザベス女王暗殺計画への関与で1587年に処刑されてしまう。
1603年にエリザベス女王が崩御すると、イングランドの王位継承権をもつメアリの遺児ジェームズ6世がイングランド国王ジェームズ1世となる同君連合が成立し、イングランドのステュアート朝が始まる。王権神授説を掲げて、絶対王政の強化を目指すジェームズ1世は、国王を首長とするイングランド国教会を信奉し、それ以外の教派を排除しようとした。この国王の豹変は、スコットランド長老派を落胆させる。
(4)ピューリタン革命でイングランドに翻弄され、クロムウェルに征服されるスコットランドの苦境
次の国王に即位した息子チャールズ1世(在位1625~1649)は、スコットランド長老派教会にイングランド国教の司教制度や儀式を強制したため、スコットランドで反乱が起こり、イングランドの国王軍と戦争になる。1639年と1640年の戦いで大敗した国王軍は、多額の戦費を無駄にしたうえに、スコットランド側に賠償金を支払うことになる。その結果、イングランドでは国王と議会の激しい対立が生じ、1642年にピューリタン革命(~1649)が勃発する。
スコットランドは、長老派教会の導入を条件にイングランド議会と軍事同盟を結んでいたが、この条件を反故にされた上にスコットランド出身の国王チャールズ1世が、オリバー・クロムウェル(1599~1658)によって1649年に処刑されてしまう。これに憤慨したスコットランドの貴族たちは、処刑された国王の息子チャールズ2世をスコットランド国王に即位させると宣言する。この動きにイングランド議会は、1650年にクロムウェルを総司令官としてスコットランドへ進撃させる。カトリック勢力の援軍が期待できないうえに、国王支持派と長老派の内部対立があるスコットランド軍は大敗する。クロムウェルの独裁による共和政が始まり、スコットランドの苦難の日々が始まる。
(5)王政復古と名誉革命~ステュアート朝の国王ジェームズ2世を追放されたスコットランドの怒り~
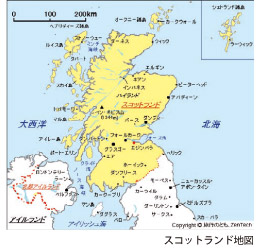 1658年に独裁政治を行ったクロムウェルが死去すると、チャールズ2世(在位1660~1685)が亡命先のフランスから戻り王政復古となる。国王はフランス亡命中にカトリック信仰に傾倒しており、これまでチャールズ2世を支援してきたスコットランド長老派教会の期待はまたもや失望に変わる。
1658年に独裁政治を行ったクロムウェルが死去すると、チャールズ2世(在位1660~1685)が亡命先のフランスから戻り王政復古となる。国王はフランス亡命中にカトリック信仰に傾倒しており、これまでチャールズ2世を支援してきたスコットランド長老派教会の期待はまたもや失望に変わる。
1685年に即位した弟のジェームズ2世(在位1685~1688)も、前王と同じくカトリックを信仰していた。これに危惧を抱いたイングランド議会は、ジェームズ2世を追放し、代わってプロテスタントのジェームズ2世の娘メアリ2世(在位1689~1694)をその夫ウィリアム3世(在位1689~1702)とともにイングランド国王に即位させ、1688年に名誉革命を断行する。
スコットランドは、自国出身にもかかわらず長老派を弾圧する国王ジェームズ2世に強い不満があり、「プロテスタントのウィリアム3世をスコットランド王に迎える」ことを渋々受け入れたが、「カトリック教徒の国王ジェームズ2世を強引に退位させた」イングランド議会の対応に憤慨する。特にカトリック勢力が多く残るハイランドは、カトリック教徒であるジェームズ2世の子孫を英国王位へ復帰させることを目指すジャコバイト※3の支持基盤となる。
(6)狡猾なイングランドとの合併に追い込まれたスコットランドの
ジェームズ2世に重用されていたハイランド地方の貴族やジャコバイトが集まり、1689年に「ジャコバイトの反乱」を起こす。この反乱は簡単に制圧されるが、ジャコバイトの反イングランドの動きは収まらなかった。スコットランドに臣従を求める国王ウィリアム3世は、1692年にその意思表示をしないハイランド地方の有力氏族であるマクドナルド一族の住民38人をグレンコーで虐殺する。しかし、スコットランドへの見せしめに行った「グレンコーの虐殺」は、逆に国王ウィリアム3世への不信感を強め、さらに過激なジャコバイト運動に繋がっていくことになる。
スコットランドの反抗に手を焼いたイングランド議会は、スコットランドとの完全な合併を狙い、「応じない場合には外国扱いにして貿易を規制し、これまでの経済的優遇措置を取り消す」と恫喝した。
その頃スコットランドでは、パナマのダリエンに植民地を建設する大規模な開発計画の失敗で、国内経済は大きな打撃を受けていた。
こうした厳しい経済状況の中で、「イングランドとの合併もやむなし」と考えるスコットランド人も大勢いたので、1707年に合同法※4が可決され、イングランドとスコットランドが合併する。合併後、スコットランドの長老派教会と教育制度は残されたが、連合議会でのスコットランド側の発言権は殆どなくなってしまう。また、スコットランドは、合併されたにもかかわらず、イングランドや植民地への輸出に関税を掛けられるなど外国扱いされたため、対イングランド感情は更に悪化する。
(7)ジャコバイトの反乱の終焉とハイランドの荒廃
イングランドでは、1714年にドイツのハノーバー選帝侯であるジョージ1世(在位1714~1727)が即位し、フランスに亡命していた
また、利益率の高い牧羊経営に目を付けた地主たちによる「ハイランド・クリアランス」※6で、多くの小作人がそれまで住んでいた土地から追い出され、炭鉱労働者や大都市の工場労働者となったり、アメリカやカナダなどの新天地を目指したりした。地域を担う人々がいなくなったハイランドは、一層貧しくなり荒廃した。
2.スコットランドの産業革命
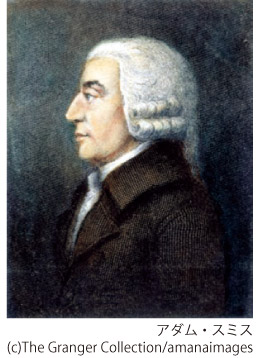 (1)長老派教会と大学が支えた教育的土壌
(1)長老派教会と大学が支えた教育的土壌
教育熱心なスコットランドでは1496年に議会で貴族などを対象に義務教育法が導入されている。長老派教会が主流となった以降は、長老派教会の牧師たちが教師となって教区学校で読み書き算数などの教育を受け持ち、聖職者の教育はグラスゴー大学(1451年創設)を始めとする国内の大学が担った。19世紀初めまでケンブリッジ大学とオックスフォード大学の2校しかなかった大国のイングランドに比して、16世紀の時点では小国のスコットランドの方が大学の数も多く、図書館も充実しており、教育水準も高かったと言われる。18世紀半ばには、ジャコバイトの乱が終焉して国内状況が落ち着き、先進的な教育が定着するようになると、学費の安いスコットランドの大学には、非国教徒に門戸を閉ざしていたイングランドからも多くの学生が入学してくる。
また人文・社会科学分野では、18世紀にスコットランド啓蒙主義が生まれる。代表する人物として、『人間本性論』などを著した哲学者デイヴィッド・ヒューム(1711~1776)や『国富論』の著者である経済学者アダム・スミス(1723~1790)がいる。この2人のもとに第一級の人材が集まると、その後のヨーロッパをリードする知的集団が形成された。
(2)実用性を重視する技術者たちと啓蒙主義
スコットランドの大学では理工学系の学問も盛んとなり、産業革命に必要な土壌が整っていった。英国の産業革命において、スコットランド人の有名な技術者や発明家、科学者たちを輩出しており、学術レベルは高かった。
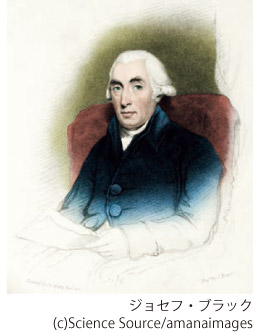 二酸化炭素の発見者として知られるジョセフ・ブラック(1728~1799)は、両親がフランスのスコットランド系のワイン商人であり、16歳でグラスゴー大学に入学してリベラルアーツを学び、1752年に医学を学ぶためエディンバラ大学へ移っている。1756年にはグラスゴー大学に教授として戻り、1766年にはエディンバラ大学の医学と化学の教授となって化学の普及に大きく貢献した。彼は、グラスゴー大学で蒸気機関の改良で知られるジェームズ・ワット(1736~1819)と知り合い資金提供しただけでなく、哲学者のディヴィッド・ヒュームや経済学者のアダム・スミスなどスコットランド啓蒙主義の知識人とも交流をもった。18世紀後半のスコットランドでは、学術クラブでの意見交換などが盛んであった。
二酸化炭素の発見者として知られるジョセフ・ブラック(1728~1799)は、両親がフランスのスコットランド系のワイン商人であり、16歳でグラスゴー大学に入学してリベラルアーツを学び、1752年に医学を学ぶためエディンバラ大学へ移っている。1756年にはグラスゴー大学に教授として戻り、1766年にはエディンバラ大学の医学と化学の教授となって化学の普及に大きく貢献した。彼は、グラスゴー大学で蒸気機関の改良で知られるジェームズ・ワット(1736~1819)と知り合い資金提供しただけでなく、哲学者のディヴィッド・ヒュームや経済学者のアダム・スミスなどスコットランド啓蒙主義の知識人とも交流をもった。18世紀後半のスコットランドでは、学術クラブでの意見交換などが盛んであった。
一方でジェームズ・ワットや製鉄技術を変革したJ.B.ニールソン(1792~1865)※7は、大学を出ていない叩き上げの技術者である。スコットランドは、階級社会の根付いたイングランドと異なり、学歴のない技術者であっても大学教授などから積極的にアドバイスや協力を得ることができたので、技術水準が非常に高かった。こうしたスコットランドの技術者たちの多くが、「雇われ外国人」として明治初期に来日し、日本の産業革命にも大きく貢献している。
(3)産業革命の進展と急激な人口増加
1750年代のスコットランドの人口は約126万人だったが、産業革命における工業化政策と都市化政策の展開によって、1801年には160万人を超え、1831年には200万人以上となり、イングランド経済に追従する形で発展する。経済成長によって1785年から1835年に輸出は9倍となり、社会的・経済的な安定から投資家は安心してスコットランドに資本投下して工場をつくり、労働者を集めて大量生産を行うようになる。
1790年に完成したフォース・クライド運河や1842年に開通したエディンバラ・グラスゴー鉄道などによって、物流や人的交流が活発となる。1830年代までは、農村部に点在していた水力を用いる綿織物工場や炭坑、金属加工業などが、物流の発達や蒸気機関の発明によって次第に都市部やその周辺部に集中するようになり、輸送コストや労働力確保の点から、グラスゴーとエディンバラの2つの大都市を核とした経済圏が形成された。
(4)産業革命の恩恵を受けた工業都市 グラスゴー
スコットランドの中西部に位置するクライド川下流の港湾都市グラスゴーには工場と人口が集中し、スコットランドで一番の大工業都市となった。
グラスゴーの人口は、1780年には4万人程度であったが、1830年には20万人、1891年には65万人とロンドンを凌ぐ増加率であった。
もともと、グラスゴーの商人は、主にフランスやオランダと交易していたが、1707年にイングランドと合併した以降はアメリカ植民地など大西洋貿易が可能となり、経済的に繁栄する。その後、1775年のアメリカ独立戦争によって、主たる貿易品目のタバコ貿易が中止となり、グラスゴーの経済は大きな打撃を受けるが、イングランドの産業革命の進展とともに、グラスゴーは綿織物工業への構造転換に成功し、マンチェスターやバーミンガムに並ぶ連合王国最大の新産業都市に発展を遂げる。
(5)知の集積都市となった首都 エディンバラ
スコットランドの東岸フォース湾に面する首都エディンバラは、スコットランドの政治文化の中心であり、中世を思わせる「旧市街」と都市計画の傑作である「新市街」の美しい町並みはユネスコの世界遺産に登録されている。元々小さな都市であったエディンバラの人口は、1707年には約3万人程度であったが、1831年には2倍の約6万人となり、旧市街で居住環境の悪化が進んだことから、近代的な新市街が開発され、貴族や著名人、銀行家など富裕層や知識人が次々と移り住んだ。
消費中心の都市のエディンバラの地場産業には、大規模工場を有する製紙工場と「ブリタニカ百科事典」で技術が評価された印刷業があり、リース港は石炭や穀物など生活物資の物流拠点となった。
イングランドに翻弄され続けてきたスコットランドであるが、1999年にスコットランド議会が復活し、自治が再開された。2014年9月にはスコットランドの独立の是非を問う住民投票が実施され、英国からの独立は賛成44.7%の僅差で否決されたが、2020年の英国のEU離脱「ブレグジット」を機にEU残留派が多いスコットランドでは独立機運が高まっている。連合王国の象徴であったエリザベス女王の崩御もあり、立憲君主制の維持や連合王国内の独立運動における今後の展開が注視される。
「却来華の軌跡」も33回目の今回が最終回となる。これまで本稿に根気よくお付き合いいただいた読者の皆様に深く感謝したい。執筆のきっかけは、「我々が第四次産業革命の最中にいると言われる中で、英国初の第一次産業革命を多面的に考察することで現代への指針が導き出せるのではないか」と考えたことであった。新型コロナウィルス感染症が中国で発見された2019年12月からスタートし、2023年5月に漸く第5類へと移行し、外出自粛が求められないようになった今回で最終回を迎えることは大変感慨深い。コロナ禍によるパンデミックの中で、社会の価値観の変化を
※1 「長老派教会」: 司教制度を廃止し、信徒の中から長老を選出して牧師を補佐させる長老制を採用する。
※2 「同君連合」: 同一の国王を戴くが、それぞれは国家として独立しており、政府や議会などの国家機構は別々に存在する国家形態。
※3 「ジャコバイト」: 名誉革命で亡命した国王ジェームズ2世とその子孫を、正統のイギリス君主として支持した人々。ジェームズ派の意で、その名称は、ジェームズJamesのラテン語形ヤコブスJacobusに由来する。
※4 「合同法(1707年)」: この合同法の可決によって同君連合は解消され、1707年5月1日にアン女王のもとでグレートブリテン王国が成立した。同時にスコットランドは議会を解散してイングランド議会に吸収された。
※5 「老僭王」: ジェームズ・フランシス・エドワード・ステュアート(1688~1766)は、ジェームズ2世の息子で老僭王と呼ばれるイングランド・スコットランドの王位請求者(自称在位:1701年9月16日~1766年1月1日)。支持者であるジャコバイトによって、イングランド王ジェームズ3世及びスコットランド王ジェームズ8世と呼ばれる。
※6 「ハイランド・クリアランス」: 18世紀から19世紀にかけ、ハイランド地方を中心とした地主たちは羊毛産業が経済を豊かにすると考え、羊の放牧のために今まで住んでいた住民を強制退去させた。悪名高き「ハイランド・クリアランス」と呼ばれ、この時に最大で10万人以上が土地を奪われた。
※7 「J.B.ニールソン」: 産業革命の源となる石炭と鉄鉱石の活用において1828年に先駆的な熱風炉精錬法を発明。炉に送風する空気をあらかじめ熱風炉で加熱して炉内に送り込むことにより、炉内の熱効率を上げた。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第32回]~2023年6月号
英国の小説家であるジョナサン・スウィフト(1667~1745)の「ガリバー旅行記」(1726)は、18世紀前半に出版された架空の旅行記として世界中の人々に親しまれている。幼い頃に読んで、小人や巨人の国で次々と困難に直面する主人公にワクワクドキドキした記憶が今も残っている。絵本も多く出版されており、子供向けの物語というイメージが強いが、当時の英国の政治や社会を痛烈に批判する内容は、大人も十分楽しめる。
この小説に登場する小人の国「リリパット王国」の大蔵大臣フリムナップは、当時の政権を担うロバート・ウォルポール(1676~1745)を風刺した姿だとされる。トーリー党
前々回から英国イングランドを中心にノルマン朝からハノーバー朝までの英国議会の歴史と、議会政治が産業革命に与えた影響を探ってきたが、今回は、実質的に英国最初の首相とされるウォルポールの生い立ちから21年間の長期安定内閣を築くまでの歩みとともに、政治の安定が貿易や商業の振興をもたらし、増えた国富によって産業革命に繋がる土台が築かれるというプロセスを辿る。
1.ウォルポールの生涯
(1)出生から学生生活(1676~1700)
ロバート・ウォルポールは、1676年にイングランド東部に位置するノーフォークの寒村ホートンに生まれた。ウォルポール家は、貴族ではないが13世紀から続く由緒ある地方の名家であり、庶民院の議員である彼の父親は、地元ではホイッグ党の重要人物として信頼されていた。学識豊かで資産の管理運営にも長けた人物であったが、19人もの子供を抱えていたので生計を切り詰めていた。
三男だったウォルポールは、聖職者になるために上流階級の子弟が多い名門イートン校に進学するが、父から十分な資金援助がなく貧乏な学生生活を強いられた。その後、ケンブリッジ大学のキングス・カレッジに進むが、2年後に兄たちが相次いで死去してしまい、ウォルポールが突然跡取りとなる。父親が体調を崩していたので、すぐに新たな跡取りとして家の財産管理を教える必要があり、彼は学業半ばで故郷に戻された。さらに、父親は早くに息子を自立させようと、息子の結婚相手として多額の持参金が期待できる裕福な材木商人の娘キャサリンを見つけてくる。
(2)結婚から政界進出まで(1700~1702)
1700年にキャサリンと結婚すると、その3カ月後に父親が50歳で死去し、ウォルポールは一家の長となる。母や4人の兄弟姉妹に加え、身重の妻までも抱えた彼は、一家を支えるために、すぐに父親と同様に政界への進出を考え、1701年には地元ノーフォークの都市選挙区から立候補し、庶民院議員となる。
妻となったキャサリンはまずまずの美人で、最初は夫婦仲も良く三男二女を授かるのだが、お嬢さん育ちで派手好きな彼女は、頻繁にオペラ劇場に通い、次々と高価な洋服や宝石などを購入する。しかも彼女は嫉妬深い性格だったので、すぐに夫婦仲が悪くなり、別居生活に入る。一方、政府の役職に就かない平議員のウォルポールは、無給に近かった。扶養家族も多いうえに、妻の散財のせいで妻の持参金もすぐに使い果たし、借金まみれとなる。
(3)アン女王時代のホイッグ党の若手有望株(1702~1710)
アン女王時代(在位1702~1714)にはスペイン継承戦争(1701~1714)※1が始まっており、トーリー党中心の戦時体制となっていた。シドニー・ゴドルフィン(初代ゴドルフィン伯爵)が政治、ジョン・チャーチル(初代マールバラ公爵)が軍事、ロバート・ハーレー(初代オックスフォード伯爵)が庶民院を主導して三頭政治を行っていた。
ホイッグ党のウォルポールは、幼馴染でイートン校の同級生であるチャールズ・タウンゼント子爵(1674~1738)を足掛かりに党の若手貴族の中に入り込み、閉鎖的な上流社会での人脈を開拓した。野党議員としてトーリー党政府に対して論争を挑み、高い討論力で相手を圧倒したことで、
1705年の総選挙で与野党が伯仲した結果、ホイッグ党の議員が閣僚として登用され、ウォルポールも1705年から1708年まで海軍本部委員会委員に、ついで1708年2月に戦時大臣に就任した。膨大な負債に
(4)敗北と失意から英雄へ(1710~1714)
1710年10月の総選挙でトーリー党が圧倒的な勝利を収めると、ホイッグ党の閣僚が次々と辞任に追い込まれる。ウォルポールも1710年10月に戦時大臣を辞任すると、それ以降はトーリー党政府を批判する急先鋒となる。政権運営にとって邪魔な存在となった彼は、1712年1月に汚職の罪で議員を除名され、半年間ロンドン塔に監禁されてしまう。汚職の事実はあったものの、獄中の間には、ホイッグ党の有力者が続々と彼のもとに駆け付け、6カ月後に釈放されたときには、ホイッグ党の殉教者として英雄扱いされた。そして、1713年8月には、議員に復帰している。
(5)ジョージ1世治下のホイッグ党の優勢と主要閣僚となるウォルポール(1714~1716)
 1714年にアン女王が死去し、ジョージ1世(在位1714~1727)が英国王に即位すると、トーリー党が退けられホイッグ政権が成立する。スタナップやタウンゼント子爵が国務大臣として入閣し、ウォルポールは陸軍支払長官に就任する。陸軍支払長官という役職は、大臣より格下だが金銭上の役得が多く、3年間の野党生活で膨らんだ自分の借金を返済しただけでなく、多額の資産を形成することができ、名より実をとった形となった。
1714年にアン女王が死去し、ジョージ1世(在位1714~1727)が英国王に即位すると、トーリー党が退けられホイッグ政権が成立する。スタナップやタウンゼント子爵が国務大臣として入閣し、ウォルポールは陸軍支払長官に就任する。陸軍支払長官という役職は、大臣より格下だが金銭上の役得が多く、3年間の野党生活で膨らんだ自分の借金を返済しただけでなく、多額の資産を形成することができ、名より実をとった形となった。
さらに、1715年1月の総選挙で圧勝したホイッグ党はトーリー党を抑え込み、1716年5月にはジャコバイト※2の復活を阻止することを狙いとした「7年任期法」によって、議員任期3年を7年に延長し、安定的政権運営を図った。ウォルポールは、1715年10月に前任者が死去したことで第一大蔵卿に就任し、主要閣僚の一人となる。
(6)党内野党から返り咲きまで(1716~1717)
前号で述べたとおり、ドイツ生まれの国王ジョージ1世は、英国よりもハノーバー選帝侯としての立場を優先し、大北方戦争(1700~1721)※3に英国を巻き込もうとした。さらに国王が、対スウェーデン戦略として宿敵フランスとの関係改善を図ろうとすると、ホイッグ党内部に分裂が生じる。ジョージ1世のハノーバーへの里帰りに随伴したスタナップやサンダーランド伯爵らの「大陸組」は、フランスとの条約を結ぼうとするが、ウォルポールやタウンゼント子爵ら英国の「留守政府組」は、ハノーバー優先策だと批判する。フランスとの条約締結が留守政府組の妨害によって1716年11月末までずれ込むと、1716年12月に国王はタウンゼント子爵をアイルランド総督へ左遷する。この結果、ウォルポールとタウンゼント子爵が下野に追い込まれる一方で、スタナップは国王から絶大な信頼を得るようになり、この頃から国王は閣議に出席しなくなる。
これ以降、ホイッグ党ウォルポール派は、党内野党として政権中枢のスタナップを批判するようになる。ウォルポールの狙いは、スタナップ政権を困らせて自分を再登用させることであり、そのためにはトーリー党とも平然と共闘した。そして、ウォルポールが、国王に反抗する皇太子(のちのジョージ2世、在位1727~1760)の一派と手を組んだことによって、庶民院の議会運営が更に難しくなっていく。その対応に疲れ果てたスタナップは、爵位を受けて貴族院へ移りたいと国王に願い出るのだが、一旦貴族院議員になると庶民院の議会には出席できなくなるので、庶民院の運営はウォルポールの思いのままとなる。
議会運営に支障が生じたスタナップ政権は、ウォルポールらとの関係修復を画策するが、そのためには犬猿の仲であった国王と皇太子を仲直りさせることが必要であった。政権に復帰したいウォルポールは、まず「国王の膨大な負債の肩代わりを庶民院で了承する」ことを引き受け、次に「皇太子へ国王との仲直りを説得する役」を皇太子妃キャロラインに依頼する。彼女は、恩義のあるウォルポールからの依頼を快諾し、1720年4月に国王と皇太子の和解が成立する。この結果、1720年6月にウォルポールは陸軍支払長官に、タウンゼント子爵は枢密院議長に返り咲く。
(7)南海泡沫事件 バブルの崩壊(1717~1720)
スペイン継承戦争の戦費調達のために債務が膨らんだ英仏は、ともにその利息の支払いに苦しんでいた。フランスでは、「ミシシッピ計画」によって、1720年に政府の債務をミシシッピ会社の株と交換することで債務の帳消しに一旦成功する。英国でも同じスキームで計画された債務帳消しが、「南海泡沫事件」であり、この2つに17世紀のオランダで起きた「チューリップ・バブル」を加えたものが世界三大バブルとされる。1720年に英国で「巨額の国債引き受けの見返りに株式を発行する許可を得る」スキームの入札が実施され、ホイッグ党寄りのイングランド銀行と競い落札したのが南海株式会社である。この会社は、1711年にスペイン領アメリカ植民地との貿易と金融事業を目的にトーリー政権の指導者によって設立されたものの、その後貿易が途絶え経営が悪化していた。1718年に金融事業である富くじ発行の大成功によって窮地を脱すると、今回の入札によって更なる利益捻出を目論んだ。落札した南海株式会社は、株式を時価で国債と交換するスキームを実施する。株価さえ高騰すれば会社の利益も増大し、さらに株価も上がるという仕組みであるので、会社は株価を吊り上げるために、さまざまな噂話や嘘話、楽観論を流布する。1720年1月に1株約100ポンドだったものが、4月からの株価上昇に伴い、会社の利益が増大すると、そのことが更に株の人気を煽り、6月には株価が1050ポンドと10倍に値上がりする。「株は儲かる」という考えが一挙に世間に広まり、貴族から庶民まで我先にと投資する株式ブームとなる。しかし、3カ月後の9月には株価が1/5に大暴落し、多くの破産者や自殺者が出る事態にまでなった。
(8)ウォルポールのライバルたちの死(1721~1722)
株価暴落で南海株式会社の役員たちの責任追及だけでなく、当社の株を賄賂として受け取っていた政治家の存在が明らかとなり、投資家から怒りの声が上がる。この国難を解決できる人物としてウォルポールが脚光を浴びる。1711年に南海株式会社設立の議案が議会に提出された時、「貿易や産業の発展から国民の眼をそらし、株式売買という危険なリスクを負う行為を奨励することは、一見大儲けできるように見えるが、実は人々を破滅に導くものだ」と議案反対の演説をした議員が、ウォルポールだったからだ。単に宿敵トーリー党の議案という理由で異議を唱えたにもかかわらず、「南海株式会社に反対した人物」という事実によって、彼は、「バブルに無縁な財政通の政治家」となり、イメージアップに繋がる。
一方、政権を担っていたスタナップは、政府の失政への激しい追求により議場で倒れ、1721年2月に脳卒中で死去する。ウォルポールは同年4月に第一大蔵卿に就任すると、南海株式会社を奴隷貿易と捕鯨を専業とする会社に縮小して再建に成功し、寛容な収拾策で政府が壊滅的な打撃を受けることを阻止する。しかし、スタナップ亡き後も政府の主導権は、未だ敵対するサンダーランド伯爵が握っており、1722年4月の総選挙でもサンダーランド派の勝利の方向が見えてきたところで、突如サンダーランド伯爵が倒れて死去する。立て続けのライバルの死去によって劣勢を挽回したウォルポールは、名実ともに国王の第一の臣下となり、実質的な首相となる。
(9)ウォルポール内閣の成立(1722~1737)
ジョージ1世は、当初自分の第一の臣下となったウォルポールの力量に危惧を覚えていたが、やがて彼に任せれば議会も政府もうまく行くと考えるようになる。ジョージ1世の信任を得たウォルポールは、国王の金や官職叙任権を巧みに利用しながら閣議を取り仕切り、国王と内閣と議会を束ねる存在となった。
しかし、1727年にジョージ1世の崩御によって即位したジョージ2世は、皇太子時代の同志であったウォルポールを更迭しようとする。政権に復帰した途端に、父親のジョージ1世に取り入ろうとする彼の風見鶏的な姿勢に強い不信感を抱いていたのだ。それを察したウォルポールは、すぐに「宮廷費70万ポンドをさらに83万ポンドに増額する」という議案を提出し、すでに過大だとして増額に反対する議会から強引に承認を得る。彼の対応にご満悦となったジョージ2世は、一転ウォルポール贔屓となり、彼の留任を決める。
王妃となったキャロラインも、この宮廷費の予算措置を大変喜び、公事も私事も全てウォルポールに相談するようになり、重要政務の国王への根回し役も買って出てくれた。
こうしてウォルポールは、事実上の首相として政権を担い、21年に及ぶ長期政権で政治的安定をもたらした。対外的には平和戦略、国内的にはトーリー党をジャコバイトとして攻撃することで、強力な政治的基盤を作り上げた。膨大な戦費が必要となる戦争を避け、国内商工業や貿易の振興、海運の保護に力を注ぎ、税収を増加させた。こうした重商主義政策による国富の増大が、産業革命を引き起こす原動力となる。1726年に英国を訪れたフランスの哲学者ヴォルテール(1694~1778)※4は、「英国の繁栄と自由を生んだ最大の理由は、商業の発展にある」と哲学書簡で称賛している。
(10)ウォルポール内閣の終焉(1737~1745)
1737年に、長らく別居生活が続いていた妻キャサリンが死去すると、翌年に長年愛人関係にあった女性と再婚するのだが、彼女は流産が原因で急逝してしまい、ウォルポールは悲嘆に暮れ病床に就く。この頃から彼の政権は盤石ではなくなり、元々文芸の保護に熱心でない彼は、新聞雑誌などへの買収と言論弾圧を行なうようになる。
1738年に、英国の貿易船の船長ジェンキンスが、西インド諸島のスペイン領で官憲によって不当に勾留され耳を切り落とされたとして、自身の耳を庶民院に証拠として提出する。世論はスペインへの報復を熱狂的に支持し、議会は開戦すべきとのムードとなる。議会の声に押されたウォルポールは、1739年にしぶしぶ宣戦布告し、「ジェンキンスの耳戦争」が始まり、さらには、ハプスブルグ家の家督継承を巡るオーストリア継承戦争※5が1740年に勃発し、立て続けに望まぬ開戦に追い込まれる。戦争が長引くと、彼の予想通り
1742年2月に庶民院で反対派が多数を占めると国王ジョージ2世の慰留や貴族院の支持があったにもかかわらず、ウォルポールは議会の信任を失ったことを理由に第一大蔵卿を辞任する。この議会の不信任を理由とする彼の辞任によって、「議会で多数を占める党派の党首が内閣を組織する」という責任内閣制の先例ができたと言われ、その後英国では、内閣が国政全般を掌握し、国民の代表である議会に対して責任をもつことになる。
2.責任内閣制の英国と絶対王政フランスの違い

官僚機構と国王軍に支えられた絶対王政下のフランスでは、貴族・地主階級と都市商工業者の利害は徹底的に対立し、1789年のフランス革命で、王室を始めとする貴族階級は暴力的に打倒された。
一方、英国にはカトリックという共通の敵がいたため、貴族および地主階級と、都市商工業者たちが一致団結して協力できた。さらに、トーリー党とホイッグ党が議会を舞台に論争と勢力争いを繰り広げたことが逆にガス抜きとなって内乱に至らなかった。大地主や貿易で富を蓄えた者に対して、次々に爵位が与えられると、貴族とジェントルマンの壁が取り払われ、身分意識の変化が生じた。このような背景から都市商工業者は、産業や学術分野にエネルギーを振り向け、18世紀以降の産業革命の原動力の1つとなったのである。
ウェストミンスター宮殿からほど近い「ダウニング街10番地」は英国首相官邸として知られているが、この建物は、1732年に国王ジョージ2世からウォルポール個人に
次回は、これまでイングランドを中心に眺めてきた産業革命をスコットランド側から考察する。
※1 「スペイン継承戦争」: 1701~1714年スペインの王位継承をめぐり、イギリス、フランスの対抗を主軸として行われた戦争。
※2 「ジャコバイト」: 名誉革命で亡命した国王ジェームズ2世とその子孫を、正統のイギリス君主として支持した人々。ジェームズ派の意で、その名称は、ジェームズ Jamesのラテン語形ヤコブス Jacobusに由来する。
※3 「大北方戦争」: 1700~1721年、スウェーデンと反スウェーデン同盟(ロシア・デンマーク・ザクセン)を結成した諸国がスウェーデンの覇権をめぐって争った戦争。ロシアがスウェーデンと戦って勝利し、バルト海の覇者となり、大国化の契機をつかんだ。
※4 「ヴォルテール」: 18世紀フランスを代表する啓蒙思想家、哲学者、文学者、歴史家。『哲学書簡』『寛容論』『カンディド』などの多くの著作を通じ、啓蒙専制君主に大きな影響を与えた。
※5 「オーストリア継承戦争」: 1740~1748年、オーストリアの王位継承をめぐって行われた国際戦争。オーストリア王女マリア・テレジアの即位に反対するバイエルン・ザクセン諸侯・フランス・スペイン王などと、イギリスを味方にしたオーストリアが対抗。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第31回]~2023年5月号
昨年9月のエリザベス2世崩御に伴って英国王として即位したチャールズ3世は、ウィンザー朝の5代目にあたり、ドイツ北部の領主の家系であるハノーバー朝の直系とされる。1714年に英国で始まったハノーバー朝は、1901年にサックス=コーバーグ=ゴータ朝※1へと引き継がれるが、1917年の第一次世界大戦の中で敵国ドイツ風の王朝名を名乗るのは好ましくないと王宮の名に
そのハノーバー朝の初代国王ジョージ1世(在位 1714~1727) と息子ジョージ2 世( 在位1727~1760)は、ドイツで生まれ育ったため英語が不得手なうえに英国の政治にほとんど関心がなかった。この 2人の国王のおかげで、今回取り上げる政治家ウォルポールが実質的な首相として21年間もの長い間英国の政治を仕切ることが可能となったのである。
前回から英国イングランドを中心にノルマン朝からハノーバー朝までの英国議会の歴史と、議会政治が産業革命に与えた影響を探ってきたが、今回は、ハノーバー朝以降に責任内閣制が可能となった背景を探るために、当時の国王であるアン女王やジョージ1世などの人柄や英国での評判、責任内閣制を作り上げたウォルポールの政治姿勢や性格について取り上げる。
1.アン女王の生涯とステュアート朝の断絶
(1)メアリ2世の妹アンが国王即位に至る経緯
英国では、1642年のピューリタン革命やクロムウェルの独裁政治(1653~1658)、チャールズ2 世(在位1660~1685)の王政復古を経て、旧教徒(カトリック)の国王ジェームズ2世(在位1685~1688)が王位を継承したが、彼の露骨な旧教復興の姿勢に危機感を持った議会が1688年に起こした無血の名誉革命によって、国王は追放され、ともに新教徒(プロテスタント)であるジェームズ2世の娘メアリ2世(在位1689~1694)とその夫であるオランダ提督オレンジ公ウィレム(即位後ウィリアム3世:在位1689~1702)が即位することになる。
しかし、2人の共同統治という異例な形となった夫婦には世継ぎができないままに、妻メアリ2世が 1694年に崩御してしまう。単独の国王となった夫ウィリアム3世の次の国王には、メアリ2世の妹であるアンに継承させることがほぼ既定路線になっていたが、フランスから虎視眈々と王位復活を狙う不穏な動きがみられた。名誉革命で追放されフランスへ亡命した元国王ジェームズ2世やその息子ジェームズ・フランシス・エドワード(老
そこでウィリアム3世は、1701年に旧教徒の彼らが王位に就けぬように「王位継承者はステュアート家の血を引く新教徒」とする王位継承法を定める。そして翌年にウィリアム3世が崩御すると、ステュアート朝ジェームズ1世の曾孫で新教徒のアン女王(在位 1702~1714)が37歳で即位する。
(2)フランスに勝利した英国の発展とスコットランド併合による大ブリテン王国の成立
アン女王が即位した18世紀初頭には、スペイン王位継承問題を巡ってフランスとの対立があり、国内には依然としてジェームズ2世を支持する勢力ジャコバイト※3が残っていたので、英国の政情は不安定であった。凡庸であったが努力家のアン女王は、必ず閣議に出席して重要な法案審議の際には議会に赴き、政治に対する国王の権限を表面上保っていた。しかし、実際の政務は、お気に入りの女官サラ・ジェニングスの夫で有能なジョン・チャーチルに任せていたことから、中小地主層の利益を代表するトーリー党中心の体制が構築された。
その後、ヨーロッパのスペイン継承戦争(1701~1714)※4と、北米植民地のアン女王戦争(1702~ 1713)※5で、英国はフランスに勝利する。これまで度々英国に楯突いていたスコットランドであったが、一連の戦争での勝利で英国の力を認めざるを得なくなり、1707年に英国との併合に応じる。
これにより、大ブリテン王国が成立し、アン女王は名実ともに英国王となった。
(3)アン女王の崩御とステュアート朝の断絶
アン女王は、1683年にデンマーク王の次男と結婚し、18人も懐妊するのだが、どの子も死産か
2.ハノーバー朝の国王ジョージ1世とジョージ2世

(1)ハノーバー朝の始まりとジョージ1世の悪評
王位継承法に基づき、ステュアート家の血筋を引 くゾフィー・フォン・デア・プファルツ(1630~ 1714、以下ゾフィーと表記する)が、ジェームズ1世の孫として唯一継承権をもっていたが、アン女王が崩御する2カ月ほど前に83歳で死去してしまう。そのため、ゾフィーの息子であるドイツのハノーバー選帝侯ゲオルク・ルートヴィヒが、54歳でジョージ1世(在位1714~1727)として即位し、ハノーバー朝が成立する。
1714年にウェストミンスター寺院で新国王の戴冠式が行われたが、その評判は散々なものであった。まず、自分の暗殺計画の噂もある不穏な英国で、王位に就くことを躊躇したジョージ1世は、アン女王崩御後 7週間も経てから英国入りしており、戴冠式には王妃ゾフィー・ドロテア(1666~1726、以下ドロテアと表記する)の姿はなかった。しかも、ドイツから不器量な愛妾2人を伴っていた。1人は、長身で非常に痩せており、英国ではメイ・ポール(五月祭の飾り柱)というあだ名であった。もう1人は、愛妾ではなく異母妹だとされているが、「エレファント(象女)」と形容されるほど異様に太っていた。しかし、国王は、このような容姿の2人を大変可愛がり、王家の衣装や宝石を惜しみなく与えている。彼の通常とは異なった審美眼は、自分の容貌へのコンプレックスとともに、天然痘の
(2)ジョージ1世の母ゾフィーに嫌われた嫁ドロテア
若い頃に、ジョージ1世の母ゾフィーは、有名な遊 び人であるツェレ公ゲオルク・ウィルヘルムから一方的に婚約を破棄され、代わりにその弟のハノーバー選帝侯エルンスト・アウグストを結婚相手に押し付けられていた。権勢欲の強い弟は、ジェームズ1世の孫という血筋に惹かれ、容姿を度外視してゾフィーと結婚し、息子ジョージ1世が生まれる。
 一方、ゾフィーとの婚約を破棄した兄のゲオルク・ウィルヘルムだが、その後彼はフランスから亡命してきた美しい平民出身のユグノー教徒エレオノールに夢中となり、身分違いの結婚を断行する。2人の間に美しい娘ドロテアを授かるが、母親の出自のため、娘は庶子※6同然として扱われた。1676年に母エレオノールが伯爵の称号を授かったことで娘ドロテアも貴族身分となると、いとこのジョージ1世との結婚話が持ち上がる。領地相続の解決のためとはいえ、姑となる母ゾフィーにすれば、自分との結婚を破談にしてプライドを傷つけた男の娘など好きにはなれず反対するのだが、結局は莫大な持参金に目が眩み不承不承ながら結婚を認める。
一方、ゾフィーとの婚約を破棄した兄のゲオルク・ウィルヘルムだが、その後彼はフランスから亡命してきた美しい平民出身のユグノー教徒エレオノールに夢中となり、身分違いの結婚を断行する。2人の間に美しい娘ドロテアを授かるが、母親の出自のため、娘は庶子※6同然として扱われた。1676年に母エレオノールが伯爵の称号を授かったことで娘ドロテアも貴族身分となると、いとこのジョージ1世との結婚話が持ち上がる。領地相続の解決のためとはいえ、姑となる母ゾフィーにすれば、自分との結婚を破談にしてプライドを傷つけた男の娘など好きにはなれず反対するのだが、結局は莫大な持参金に目が眩み不承不承ながら結婚を認める。
このジョージ1世は、以前にアン女王との縁談でも嫌われて破談となっており、女性に全く人気のない男だった。ドロテアも、いとこの中で陰気で垢抜けしない彼を最も嫌っていたので、この結婚話に大変なショックをうけるが、1682年に2人は結婚する。嫁を疎うとむ姑の存在に加え、平民上がりの妻を馬鹿にする夫との生活がうまくいくはずもなく、夫婦関係は当初から冷え切っていた。息子(のちのジョージ2世)と娘の2人を授かるものの、その結婚生活は、孤独だった。この寂しさを紛らわせるかのように、彼女は美男のスウェーデンの貴族ケーニヒスマルク伯(1665~1694)と愛人関係になり、1694年に2人はザクセンへの駆け落ちを計画するが、事前に発覚してしまう。まだ28歳のドロテアは、夫ジョージ1世に離婚を求めるが、離婚手続きが済むまでと騙されて、ドイツのアールデン城に亡くなるまで32年間も幽閉されてしまう。1714年のジョージ1世の戴冠式の際にも彼女はアールデン城に閉じ込められたままで、我が子に会うことさえも許されなかった。
(3)政治に関心がなく頻繁に里帰りするジョージ1世
ジョージ1世は、国王としての政務の評判も散々で あった。ドイツ出身ということもあり、英語が得意でなかったので、ドイツから連れてきた腹心を重用して宮廷や議会から激しい批判を受けたとされる。英国の家臣との意思疎通が十分できなかったといわれるが、これには少し誇張があるようだ。実際にはジョージ1世は多少英語を話せたようであり、宮廷内の公用語であるフランス語も当然喋れるので大臣など側近との意思疎通は十分可能だったはずである。
自分を歓迎しない英国への嫌悪感を隠さず、自分から国民に歩み寄ろうとしない国王の態度や姿勢に問題があったのだろう。妻への仕打ちや愛妾のことで国民に全く人気がない上に、積極的に英語も学ぼうという気もなかった。英国の議会政治の形態も気に食わない国王は、頻繁にハノーバーに里帰りし、1718年以降は閣議にも出席しなくなったので、結果的に政務は閣僚らに任せっきりとなる。そして、ジョージ1世は、即位時の経緯から前国王時代に優位であったトーリー党に不信感を抱き、ホイッグ党を支持するようになる。その中からウォルポールが登場するのである。
(4)夫ジョージ2世と義父ジョージ1世との
国王ジョージ1世の後継は、同じくドイツ生まれの息子ジョージ2世となる。父親より若い30歳で英国入りした息子だが、英語の能力は五十歩百歩だったようで英語が得意ではなかった。しかも父親と同じように、たびたびハノーバーへ里帰りしたので、英国ではあまり人気がなかったのだが、その不人気を挽回する女性が現れる。
1705年にジョージ2世が結婚する女性キャロライン・オブ・アーンズバック(1683~1737)である。祖母ゾフィーが見初めた彼女は、ドイツ人ながら流ちょうな英語を使い、申し分のないマナーと教養を身に付け、背が高く容姿抜群の美人だったので、英国民から大歓迎を受けた。
その彼女を悩ませたのは、犬猿の仲で諍いが絶えなかった義父ジョージ1世と夫ジョージ2世の親子仲である。愛する母を幽閉した父を許せないジョージ2世は、父親の戴冠式への出席を渋ったり、貴族院議員であった皇太子時代に国王の反対派に接近したりするなど父親の推進する政策に対して絶えず反抗的な態度をとった。それに対して父ジョージ1世は、息子の交友関係者の宮廷への出入りを禁じたり、息子の宮廷費を極端に削ったりするなど、子供染みた嫌がらせを延々と続けた。そして、キャロラインが親子の間を取り持とうとした際に手助けしたのが、ウォルポールである。
1727年、その父ジョージ1世がハノーバーへ里帰 りする途中に卒中を起こして67歳で崩御すると、44歳でジョージ2世(在位1727~1760)が英国王に即位する。
(5)国王親子に共通するハノーバー愛
ジョージ1世から123年間にわたり、英国の国王はドイツのハノーバー選帝侯を兼ねていた。ハノーバー選帝侯は、神聖ローマ皇帝の選挙に関与することができる名誉ある選帝侯の一人であるが、当然英国王の地位の方がはるかに上である。それにもかかわらず、ジョージ1世、ジョージ2世ともに、人口50万人にすぎないハノーバーを愛し、その繁栄と安寧を守るためには、英国の強大な経済力や軍事力を用いることを
3.政治家ウォルポールの人物像
英国最初の首相と言われるウォルポール(1676~ 1745)は、1721年に44歳の若さで第一大蔵卿として実質的に内閣を主導すると、21年間にわたって内閣を維持し、国王に対してではなく議会に対して責任を負う責任内閣制の基礎を築いたと言われる。実績からいえば、彼は政治家として高く評価されるべきであるが、「政治に安定をもたらした」ということ以外に褒め言葉もあまりなく、日本での知名度もないので彼の大まかな人物像に触れる。
(1)
彼の政治姿勢をまとめると以下の3点が挙げられる。
①政治姿勢は基本的に安定を求める保守的傾向が強く、人目を引くような新しい政策を大胆におこなう気持ちも創造性もなく、歴史に残るような目立った仕事はしなかった。政治姿勢も原理原則がなく、融通無碍であり、「触らぬ神に祟りなし」と演説で繰り返すなど適当なところでお茶を濁すことが多かった。
②国富を着実に増やし、平和と繁栄の礎を築いた。とにかく戦争が嫌いで、在任中はフランスとの植民地獲得戦争を避ける平和外交を行ったが、「戦争が悪である」という倫理観からではなかった。戦争が長引くと、戦費のために土地所有貴族やジェントリーは税金を払うことになり、逆に戦争をしなければ税金を安くできるので、地主層から歓迎されるという実利的な理由によるものであった。
③当時は賄賂や買収は日常茶飯事ではあったが、金銭欲が強く、政界操作、腐敗選挙、汚職政治などに積極的に関わり、道徳的にも清廉潔白ではなかった。長期政権だったこともあり、総選挙のたびに政府機密費を流用して接待に励み、公然と有権者を買収したり、官職を餌に使って有権者の取り込みを図ったりした。政権内のライバルを失脚させるためや、自分の政策を推し進めるために金銭を使った。
(2)手練手管のしたたかな性格
次に彼の内面にアプローチを試みると以下の4点が挙げられる。
①性格は陽気で社交的であり、聡明で巧みな弁舌を振うのだが、粗野で卑猥な冗談などをよく口にするなどマナーや作法は上品とは言えなかった。また、妻が大変な浪費家であり、無給の平議員の頃は借金まみれで金銭面で苦労したので、強欲で金に汚かったといわれている。
②威勢の良い言葉で大衆を扇動するような大衆迎合主義者ではなく、緻密に論理を積み上げ、相手を説き伏せるタイプだったので、大衆受けは良くなかったが、丸々と太った愛嬌のある顔のおかげで彼のめぐらす知略や権謀術数はそれほど中傷されなかった。自分の政治能力に並々ならぬ自信をもっており、権力欲も強かったが、自分の本性を隠して凡庸なイメージを振りまき、周りの警戒心を削ぐことで自分の思い通りに政界をリードする
③表面的な姿に惑わされず人間の本質を見抜く力があり、将来性のある人物を発掘し、かつ部下として使いこなした。
④お世辞を言われるのが大好きな反面、批判されることを非常に嫌い、政権の批判が出ないようにマスコミを懐柔する一方、政権批判をする新聞などは徹底的に弾圧した。そもそも文芸や文学者への関心が薄いので、文化の保護に熱心でなかった。
次回では、ウォルポールの生い立ちや21年間のウォルポール内閣の歩みとともに、政治の安定が貿易や商業の振興をもたらし、増えた国富が産業革命に繋がる土台を築くというプロセスを辿る。
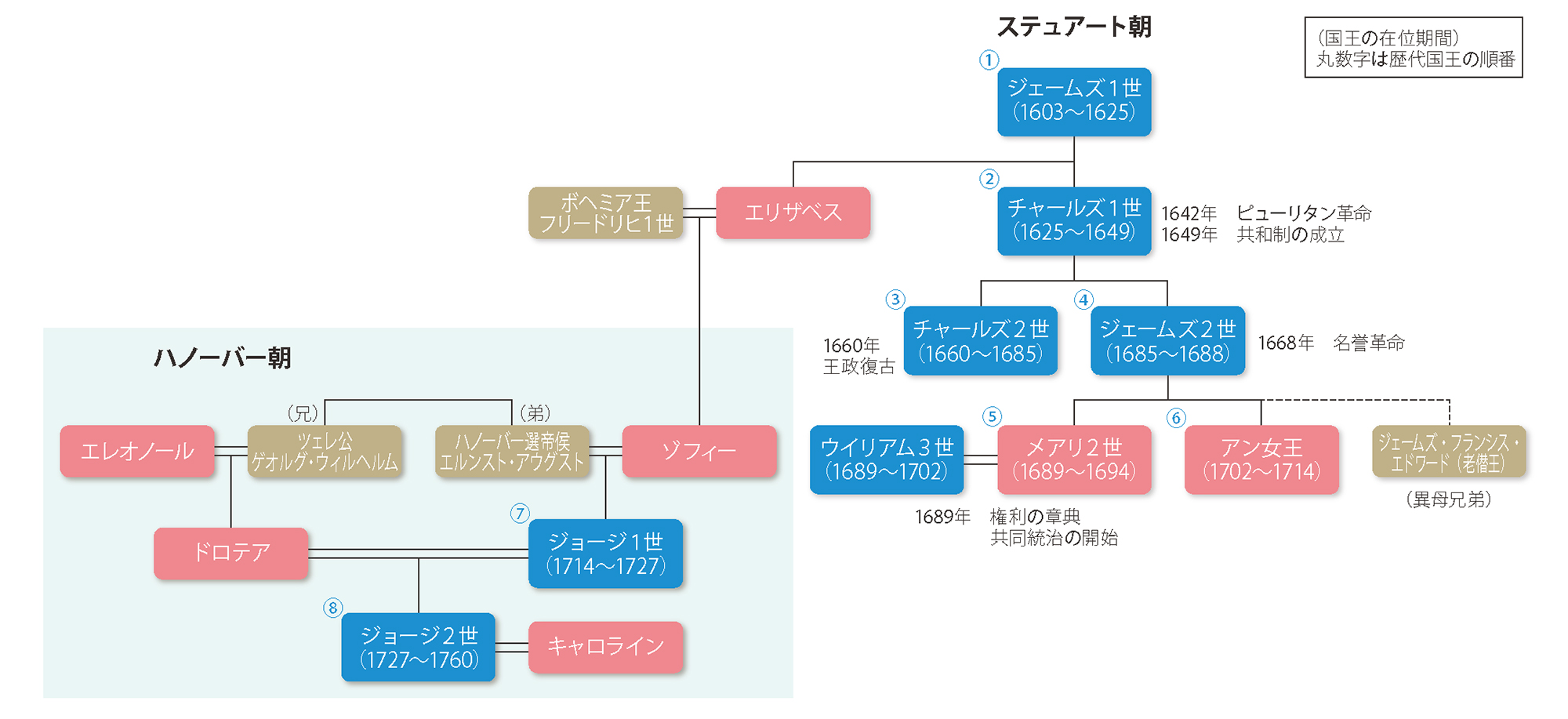
※1 「サックス=コーバーグ=ゴータ朝」: 1837年にヴィクトリア女王が即位すると、女子相続を認めないドイツのハノーバー家との同君統治の関係は消滅したので、女王崩御後の1901年にエドワード7世は、父アルバートの出身であるサックス・コーバーグ・ゴータ家の名を王朝名とした。
※2 「ジェームズ・フランシス・エドワード」: 旧教徒で老僭王と呼ばれるイングランド・スコットランドの王位請求者。ジェームズ2世の息子で、メアリ2世、アン女王にとって異母弟となる。
※3 「ジャコバイト」: 名誉革命で亡命した国王ジェームズ2世とその子孫を、正統のイギリス君主として支持した人々。ジェームズ派の意で、その名称は、ジェームズ Jamesのラテン語形ヤコブス Jacobusに由来する
※4 「スペイン継承戦争」: 1701~14年スペインの王位継承をめぐり、イギリス、フランスの対抗を主軸として行われた戦争。
※5 「アン女王戦争」: 1702年から1713年にかけて、ヨーロッパのスペイン継承戦争と並行して北アメリカ植民地で戦われたイギリスとフランスとの戦争。
※6 「庶子」: 妾が生んだ子供や結婚していない男女の間に生まれた子供。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第30回]~2023年3・4合併号
「なぜ日本では議会のことを、英語でParliament(パーラメント)ではなく、Diet(ダイエット)と呼ぶのか」、本年1月の岸田首相による施政方針演説の冒頭は、この話題から始まった。Dietの語源は「集まる日」という意味のラテン語であり、日本が明治時代にドイツ政治の仕組みをモデルとしたことから、議会の英文名もドイツと同じ「Diet」を採用したようである。一方英国では、議会は「Parliament(パーラメント)」と表記され、その語源はフランス語の「parler(会話する)」にある。
民主主義の根幹をなす議会の起源は中世ヨーロッパにあり、英独日が採用する議院内閣制の始まりは、英国ハノーバー朝にある。そして1721年から始まったウォルポール内閣による21年間の長期安定政権が、英国に産業革命の原動力となる商業の発展をもたらし、大英帝国の繁栄の礎となった。
今回から3回にわたって、英国イングランドを中心にノルマン朝からハノーバー朝までの英国議会の歴史と、ウォルポール内閣を中心に議会政治が産業革命に与えた影響を探っていく。まず1回目は、ノルマン朝から、名誉革命が起き立憲君主制の原則が確立したステュアート朝までの歴史を辿る。
1.ノルマン朝(1066~1154)からプランタジネット朝(1154~1399)まで
(1)議会の発祥 「王会(クリア・レギス)」
フランスのノルマンディー地方を支配するノルマンディー公ギヨーム2世は、イングランドを征服すると、1066年にウェストミンスター寺院でウィリアム 1世(在位1066~1087)として戴冠し、ノルマン朝が始まる。このノルマン・コンクエスト※1後に設置された「王会(クリア・レギス:Curia Regis)」が、議会の発祥とされ、アングロ・サクソン時代の賢人会議
(Witenagemot)※2を継承したと言われる。ノルマン朝の国王を補佐する政治機関である王会は、多くの諸侯などからなる大会議(the Great Council)と側近貴族からなる小会議(the Small Council)で構成されており、国王直属の封臣のみのものであったが、この大会議の中に議会誕生の兆しを見ることができる。
(2)王権を制限する「マグナ・カルタ(大憲章)」
1154年にノルマン朝が断絶すると、フランスのア ンジュー伯アンリが王位を継承し、プランタジネット朝のヘンリー2世(在位1154~1189)となった。国王は、言葉も習慣も異なる英国のアングロ・サクソン人をフランスから連れてきた少数のノルマン人によって統治しなければならなかった。そのうえ国王は、
その後、十字軍遠征に熱心だったリチャード1 世(在位1189~1199)を経てジョン(在位1199~ 1216)が国王となると、今度はフランスとの戦いに明け暮れた。過大な戦費負担に反発した貴族と都市の代表は、1215年に王権の制限、貴族の特権、都市の自由などを明文化した文書「マグナ・カルタ(Magna Carta:大憲章)」を強制的に国王に認めさせた。この時から、25人の諸侯からなる評議会が創設され、国王が戦費を税として徴収するときは、貴族と都市の代表からなる評議会の同意が必要となった。
(3)英国議会の起源 「モンフォール議会」騎士と都市の代表が初めて議会に参加
貴族たちの挙兵により、やむなく王権を制限するマグナ・カルタに署名したジョン王は、その規定をたびたび無視しようとしたが、マグナ・カルタの規定を根拠として、「新たな課税を実施するには、国王が議会を開催して議会の同意を得なければならない」という原則が徐々に出来上がっていく。また、イングランドでは貴族の日常言語がフランス語だったこともあり、 13世紀半ばから貴族と聖職者からなる評議会は、「議会(Parliament)」とよばれるようになった。
ジョン王の後を継いだ国王ヘンリー3世(在位 1216~1272)も失政続きのうえ、マグナ・カルタの規定を無視して領土奪還のための戦費として過大な税金を徴収しようとした。国王の専横に反発した諸侯や貴族が、武装して国王に課税の撤回を迫ってきたので、命の危険を感じた国王は、1258年にしぶしぶ「オックスフォード条項」を認めるが、すぐに反故にしてしまう。そこで貴族のシモン・ド・モンフォール(1208~1265)が中心となって1264年に武装蜂起して国王を捕虜とし、議会(Parliament)を開催するよう国王に要求した。1265年には、貴族・聖職者とともに地方行政区である各州(county)から代表として騎士2名と、各都市から代表2名が議会に招集された。この議会は「モンフォール議会」と呼ばれ、限定的ではあったものの州と都市の代表が国政に参加する道を開いた。議会は、王権を制限するだけでなく、政策立案も可能な機能をもつことになるのだが、その後すぐに反撃に転じた国王軍との戦いで、モンフォールとその長男が死亡したため、そうした形での議会は定着しなかった。
(4)身分制議会の典型「模範議会」課税を目的に100以上の都市から代表を招集
1295年、国王エドワード1世(在位1272~1307)は、スコットランド征服の戦費調達のために、貴族(伯爵・男爵)や高位聖職者(大司教・司教・修道院長)、各地からの州代表の騎士、各都市代表だけでなく、一般聖職者の代表も加えた「模範議会(ModelParliament)」を開催した。エドワード1世は、ヘンリー3世の時のモンフォール議会での経験をもとに、主要階級の代表全てが参加する議会を逆に利用して課税を認めさせ、戦費の調達に成功する。これ以降、ウェールズ、スコットランドへの遠征費用やフランスとの戦争のために戦費が必要となる都度、エドワード1世が議会を頻繁に開催した結果、次第に議会制度が定着していく。
中世の身分制議会の典型となった模範議会では、新興勢力である州代表の騎士や都市代表の市民も王権を支える支持基盤に加えることができた。しかし、当時の議会はあくまで国王の諮問に応えて審議するものであり、招集される代表は国民の投票で選ばれたものではなく、近代のように議会の代表が発議して立法を行うものでもなかった。また、議会に召集される代表も国王の一存で決定されたので、貴族、高位聖職者に裁判官や法律家を加えた国王評議会メンバーだけで議会を行うことが多かった。こうして有名無実化した一般聖職者の代表は、1330年頃から議会を脱退して、州の騎士や都市の市民と一緒になって「聖職者会議(Convocation)」を作り、国王評議会に属する貴族や高位聖職者とは別の会合を持ち始めるようになり、議会に分断状態が生じる。
(5)二院制度 上院・下院の成立
 戦争の多かった中世では、議会の重要な議題は戦費調達のための課税であった。課税への議会の合意を得るために、エドワード3世(在位1327~1377)は、貴族・聖職者、州の騎士、都市の代表を必ず招集して議会を行うことで議会の分断状態を解消しようとしたのだが、慣習や考え方の違いから双方の溝は埋まらず、貴族・聖職者と、州騎士・都市代表で議会を分けることになる。1341年に模範議会は、貴族・聖職者で構成される上院(貴族院:House of Lords)と、州代表の騎士と都市の代表らで構成される下院(庶民院: House of Commons)に分離された二院制議会となる。それとともに、課税だけでなく一般的な立法においても、まず下院が請願し、上院が審議して、国王が決定するプロセスが出来上がった。
戦争の多かった中世では、議会の重要な議題は戦費調達のための課税であった。課税への議会の合意を得るために、エドワード3世(在位1327~1377)は、貴族・聖職者、州の騎士、都市の代表を必ず招集して議会を行うことで議会の分断状態を解消しようとしたのだが、慣習や考え方の違いから双方の溝は埋まらず、貴族・聖職者と、州騎士・都市代表で議会を分けることになる。1341年に模範議会は、貴族・聖職者で構成される上院(貴族院:House of Lords)と、州代表の騎士と都市の代表らで構成される下院(庶民院: House of Commons)に分離された二院制議会となる。それとともに、課税だけでなく一般的な立法においても、まず下院が請願し、上院が審議して、国王が決定するプロセスが出来上がった。
エドワード3世は、フランスとの百年戦争(1337~1453)の莫大な戦費調達のために、頻繁に議会を開くようになり、ますます議会への依存度を高めることになった。特に課税への同意と請願活動に大きな役割を果すようになった州の代表は、議会での発言権が増すことになる。こうして議会制度は次第に整備されていくが、この段階での主導権は依然として国王と上院にあり、下院は請願権のみに限定されていた。
2.テューダー朝(1485~1603)
(1)絶対王政下における国王と議会の関係
その後、ランカスター朝(1399~1461)へと代わり、バラ戦争※4(1455~1485)によって一旦ヨーク朝(1461~1485)へと移るが、大陸に亡命していたランカスター家の後継者ヘンリー・テューダーがヨーク家のリチャード3世を破って、1485年にヘンリー 7世として即位し、テューダー朝を開く。百年戦争に続くバラ戦争の内戦によって、英国の封建諸侯は2つの陣営に分れ、長期化した争いにより没落した。その結果、テューダー朝では国王が国家の権力を一手に掌握したので議会を無視することも可能であったが、国王は絶対王政を補完する機関として議会を利用する。ヘンリー8世(在位1509~1547)やエリザベス1世
(在位1558~1603)は、議会を味方につけることで英国国教会を国内に根付かせるという大仕事を成し遂げることができた。こうして議会は、統治の安定に欠かせないものとなり、国王はいかなる強権も議会の承認なしには発動できなくなった。
この頃から社会は大きく変動する。農村の毛織物産業の発展に伴って、農村で土地を所有する「ジェントリー」や独立自営農民の「ヨーマン」が成長すると同時に、第1次囲い込みが進んだことで、農民は土地を離れ、都市に勃興した工場制手工業での賃金労働者となった。重商主義の下で生産性を高め、さらに毛織物を中心とした輸出産業が発展し、中世封建社会の枠組みが崩れ、近代社会へと移行する。そして新興勢力となったジェントリーやヨーマンは、議会の下院を通じて自分たちの要求を実現しようとした。
3.ステュアート朝(1603~1714)
(1)権利の請願と無議会状態
1603年に独身のエリザベス1世が死去すると、スコットランドから迎えたステュアート家のジェームズ 1世(在位1603~1625)が即位し、ステュアート朝となる。ジェームズ1世は王権神授説を掲げ、英国国教会の立場からピューリタンを弾圧したため、ピューリタンのジェントリーが多くを占める議会との対立が表面化し、1621年に議会はジェームズ1世に対する
「議会の大抗議(Protestation)」を発表する。
次のチャールズ1世(在位1625~1649)も王権神授説を受け継ぎ、旧教国スペインとの戦費調達のために課税を強化しようとしたので議会は反発し、1628年に「権利の請願」を提出。議会の同意なしの課税や不法逮捕などの禁止を請願したが、国王はその請願を無視して議会を解散した。戦費の調達を諦めた国王は、1629年に対立していたフランスと和睦し、1630年にはスペインとも和睦して三十年戦争から手を引くとともに、これ以降も10年以上にわたって議会を開催しなかった。絶対王政を維持したい国王は、王権に制限をかけようとする議会の開催を避けたかったのであろう。
(2)ピューリタン革命による君主制と上院の廃止
しかし、1639年に国王がスコットランドの反乱を鎮圧するため軍事費の調達が必要となり、1640年4月に議会を開催したが、国王への批判が続出し戦費を得ることができず、わずか3週間で「短期議会」は解散する。その後、スコットランド軍に敗北した国王は、和睦のためにスコットランドへ多額の賠償金を払わねばならず、やむなく11月に議会を招集する。この議会は、クロムウェル(1599~1658)によって解散されるまで13年間も続いたので「長期議会」と呼ばれた。1641年には議会で国王チャールズ1世への抗議文である「議会の
国王と議会の対立は決定的となり、1642年に議会派が武装して内乱が始まる。勝利したクロムウェルが主導権を握り、1649年にはチャールズ1世を処刑し、一時的ではあるが王政を倒して共和政(1649~ 1660)を実現すると、同年に行われた下院決議で君主制と上院の廃止を決定した。
その後、議会のさまざまな改革が実施されるが、安定せず、クロムウェル自身が護国卿として厳格なピューリタン精神にもとづく独裁政治を行うようになると、国民大衆の支持は得られなくなった。
(3)王政復古したチャールズ2世、そしてジェームズ2世へと続く議会との対立
1658年にクロムウェルが死去すると、政治と社会の安定を求めるジェントリーたちは、1660年にチャールズ2世(在位1660~1685)の国王復帰を認め、王政復古となる。しかし、チャールズ2世がカトリックを復興させようとしたため、議会は1673年に審査法を制定し、カトリック教徒と非国教徒の公職(官職)就任を禁止する。海上貿易の覇権をめぐってオランダとの間で第2次英蘭戦争(1665~1667)が起き、英国が敗北したこともあり、国王と議会の対立は続いた。また、カトリックへの復帰を諦めない国王は、 1670年にフランスのルイ14世とドーヴァーの密約※5を結び、さらに議会の強い反発を受ける。一方、議会では次に王位継承予定の王子もカトリックであることから、国王の世襲は絶対であるという立場の「トーリ党」※6と、プロテスタント信仰を守るためにカトリックの国王を排除すべきと主張する「ホイッグ党」※6の 2つのグループが生まれ、議会内部で対立していた。
そうした中、カトリックのジェームズ2世(在位 1685~1688)が王位を継承する。カトリック国フランスの絶対主義に憧れる国王は、カトリックを復興させようと国王軍の創設や、カトリック官僚の登用、大学のカトリック化などの政策を打ち出した。
(4)名誉革命による立憲君主政の成立メアリ2世とウィリアム3世による共同統治
 対立していたトーリ党とホイッグ党も、ジェームズ 2世の露骨なカトリック復興への姿勢に危機感を持ち、一致協力してジェームズ2世の娘メアリの夫であるオランダ提督オレンジ公ウィレムに救援を要請する。オランダの防衛と英国のカトリック化を阻止するために要請に応じたウィレムは、1688年に国王ジェームズ2世を追放し、女王に即位したメアリ2世とともに、ウィリアム3世として迎えられた。
対立していたトーリ党とホイッグ党も、ジェームズ 2世の露骨なカトリック復興への姿勢に危機感を持ち、一致協力してジェームズ2世の娘メアリの夫であるオランダ提督オレンジ公ウィレムに救援を要請する。オランダの防衛と英国のカトリック化を阻止するために要請に応じたウィレムは、1688年に国王ジェームズ2世を追放し、女王に即位したメアリ2世とともに、ウィリアム3世として迎えられた。
メアリ2世とウィリアム3世は共同統治(在位 1689~1702)となり、二人は議会の示した権利の請願を承認、「権利の章典」として公布し、立憲君主政に移行することとなる。この出来事は、英国において無血で行われた革命という意味で「名誉革命」と呼ばれ、ここに国王は「君臨すれども統治せず」という立憲君主制の原則が確立した。
ウィリアム3世は、フランスのルイ14世との植民地戦争の戦費を得るために、1694年にイングランド銀行を設立し、国債を発行して資金調達するという近代国家として画期的な財政改革を成し遂げた。さらに、ホイッグ党とトーリ党のいずれか議会の多数を占めた方に内閣を組織させるという政党政治の慣行もこの頃にできあがり、英国王が英国国教会の首長を兼ねるという英国国教会制度も再建された。
1707年には、メアリ2世の妹アン女王(在位1702~1714)のもとで、イングランド王国とスコットランド王国が併合し、大ブリテン王国となった。子供のいなかったアン女王が1714年に死去すると、ステュアート朝は断絶し、ドイツからハノーファー選帝侯のジョージ1世(在位1714~1727)を迎えてハノーバー朝が成立することになる。
ピューリタン革命から名誉革命までの革命を一括して「英国革命」と呼ぶ。この革命は、絶対王政を倒し、共和政を成立させ、次いで立憲君主政に転換するという大きな政治的変化をもたらしたのであった。
次回は、ハノーバー朝において、政治を大臣に任せる責任内閣制の始まりとなるウォルポール内閣を中心に、産業革命への影響を探る。
※1 「ノルマン・コンクエスト」: ノルマン人によるイングランド征服。1066年ノルマンディー公ギヨーム2世がイングランドを征服して王となり、ノルマン朝を創始した。
※2 「賢人会議」: アングロ・サクソン時代の英国において、貴族や聖職者などによって構成された御前会議。国政の重要事項について話し合われた。
※3 「陪審制」: この当時の陪審は、証拠の収集と調査を行い告発する機関で、現在のような証拠に基づいて事実認定を行う評決機関ではなかった。
※4 「バラ戦争」: 百年戦争敗戦の責任の押し付け合いが次代のイングランド王朝の執権争いへと発展したもので、ランカスター家とヨーク家の、30年に及ぶ権力闘争でもある。
※5 「ドーヴァーの密約」: 英国王チャールズ2世とフランス国王ルイ14世が1670年に結んだ秘密協約。チャールズ2世がルイ14世の資金援助を受けてオランダと開戦しカトリックを復活させることを約束したが、議会の反対にあって成果をあげられなかった。
※6 「トーリ党」「ホイッグ党」: トーリとは、「アイルランドの追いはぎ」、ホイッグとは、「スコットランドの反乱分子」を意味し、互いを罵るために付けられたあだ名が通称となった。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第29回]~2023年2月号
新型コロナウイルスの流行が始まった2020年から続いてきた大学でのオンライン講義が、2022年の春以降から対面授業へと戻りつつある。月日が経つのは早いもので2020年度に入学した学生は3年生になり就職活動に挑む。彼らは、オンライン授業中心の異例な大学生活の中で採用担当者に何を語ればよいか不安なのではないだろうか。
一挙にオンライン化が進んだ大学側も少子化と大学・学部の新設によって全入時代となり、学生の学力低下が懸念されている一方で、ポスト不足や雇用条件の不安定さから優秀な若手研究者が海外の大学や研究機関などへ流出しているなど、課題が山積している。国際社会で活躍する人材の育成のために「大学のグローバル化」も日本の大きな課題とされているが、学生の学びを充実するためには大学の講義形式中心の受動的な授業方法を早急に見直すほうがより大切ではないだろうか。
「英国の代表的な大学が産業革命で果たした役割」の3回目となる今回は、産業革命のテーマから少し離れるが、英国の伝統的大学オックスブリッジ(オックスフォード大学とケンブリッジ大学の併称)が上位にランクされる世界の大学ランキングを通して「大学のグローバル化」に焦点を当て、次いでオックスブリッジの教育システムを紹介することで日本の大学教育について考えてみたい。
1.大学の世界ランキングとグローバル化
(1)2022年の世界大学ランキング上位校とは
2022年10月に英国のタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)※1が発表した世界大学ランキングでは、世界1位は7年連続オックスフォード大学、第2位は米国のハーバード大学、第3位はケンブリッジ大学と英語圏である米英の大学が上位を占めており、アジアからは20位以内に被引用論文の点数が高い精華大学と北京大学(同点の16位)、国際性の点数が高いシンガポール国立大学(19位)がランクインしている。日本の大学で100位以内に入ったのは東京大学
(39位)と京都大学(68位)の2校のみであり、一般的に日本の大学は「国際性」と「論文の引用数」の項目で他国の大学に見劣るとされている。
(2)英国の大学におけるグローバル化戦略とは
そもそも1870年代までのオックスブリッジは、英国国教徒だけを入学許可していたので、プロテスタント信者が多い米国の学生たちは、信教上の入学条件のないドイツの大学へ留学しており、1863年に日本の長州藩から英国に留学した伊藤博文や井上馨など5人も、信教上の理由のためかロンドン大学に入学している。当時のオックスブリッジは、グローバルな大学とは言えなかったようである。
英国の大学で本格的なグローバル化戦略が進んだのは、1999年に当時のブレア首相が留学生による外貨獲得を目論んだ産業政策を打ち出した頃からだと言われる。2004年頃から始まった英国のTHEによる世界大学ランキングも、米国の大学と比較して知名度に劣る英国の大学が、世界中から優秀な学生を集めるためのブランディング戦略だったとされる。
「大学のグローバル化」の目的は外貨獲得にあったので、留学生の学費はかなり高く設定してある。オックスブリッジの年間授業料を例に挙げると、英国人学生の9250ポンドに対して、留学生はオックスフォード大学25740~36065ポンド、ケンブリッジ大学 21168~55272ポンドとなっている。このような留学生への高額な授業料設定にもかかわらず、英国全体の外国人留学生数は、2001年度の23万人から2018年度には48万人と倍増した。増加した主因は中国人留学生の急増であり、中国の急速な経済成長による富裕層の増大と、海外大学の学位をもつ高度人材への需要増加がその背景にある。2019年時点で世界の留学生530万人のうち中国人留学生が3分の1以上を占めている。
(3)日本のグローバル化戦略
2008年7月に日本でも国際競争力を高めるために、「留学生30万人計画」をスタートさせ、2020年を目途に30万人の留学生受入れを目指した。その結果、外国人留学生は、2001年の約8万人から2018年に目標の約30万人へと順調に増加し、そのうちの9割以上がアジア出身となっている。
その一方で、留学生にとって日本での就職環境は厳しいままだ。2017年時点で日本での就職を希望している外国人留学生が全体の約65%いるにもかかわらず、日本国内で就職した割合は約37%にすぎない。近い将来に日本の労働力不足が懸念される中で、外国人留学生のために就職支援策を更に充実させることが必要であろう。
また、日本が再び世界の中で競争力を高め、輝きを取り戻すためのグローバル人材育成を目指す「スーパーグローバル大学※2創生支援事業」が2014年に始まり、37の大学が外国語による授業科目数や受け入れ外国人留学生などの増加に取り組んでいる。しかし、 2021年時点でランキング1位のオックスフォード大学の外国人の比率が、学生で23%、教員で約40%であるのに対して、留学生が多いとされる東京大学でさえも、学生で11%、教員で15%に留まるなど、日本において大学のグローバル化が十分進展したとは言えない。
(4)大学におけるグローバル化と日本の翻訳文化
現在インターネットを使ったコミュニケーションが 世界中に普及しており、そこで利用される言語の約6割が英語であると言われる。英語はビジネスにおける国際共通語となり、非英語圏の国でも英語力のあるグローバル人材は不可欠となった。英国ヴィクトリア朝時代に大英帝国が宗主国であった旧植民地インドでは、英国人が現地の上流階級に英語や英国流の考え方を教え、宗主国に従順な現地人エリートを養成した結果、今では現地語が2000以上もあるインドにおいて、英語がビジネス上の公用語となり、世界第2位の英語話者人口となっている。
明治時代の日本も、富国強兵・殖産興業を目指す政府が、先進的な西洋の知識を効率的に吸収するために、医学と理学はドイツ、法学はフランス、工学はスコットランド、農学はアメリカ、文学はイングランドと当時各分野の最先端の国から破格の待遇で「お雇い外国人」を教師として招いたり、留学生をそれらの国へ送ったりした。外国人教師が教える当時の学校では、基礎から専門までの一貫した授業のカリキュラムがすべて外国語で行われるグローバルなものであった。しかし、日本では近代教育スタート後わずか20年足らずで外国語のテキストと外国人教師を日本語の教科書と日本人教師に置き換え、日本人による日本語の教育で充足する仕組みを作り上げることに成功する。
20世紀初頭には海外の文献を一般読者向けに翻訳 する文化が発達し、海外の研究成果や知識をいち早く日本語で読むことができるようになった。日本は最新の海外の知識をほとんど自国の言語である日本語で読める、世界的にも数少ない国なのだ。
しかし、翻訳文化の発達によって、外国語の聞く・話すスキルが重要視されなくなり、しかも日本人の母国語である日本語の言語としての難しさが外国語習得の壁となっている。そのため、幼い頃からの語学学習が必要だと叫ばれているが、日本人として日本語への深い理解がなければ海外の最新の知識を翻訳できないし、日本の歴史や文学などの造詣があってこそ外国人に対して自分の意見をしっかりと伝えられるのだということを忘れてはならない。
2.オックスブリッジに入学するまでの教育制度
(1)大学受験のためのシックスフォームとは
 英国のイングランドとウェールズは、公立と私立で異なる複線型教育制度を採っている。公立では5歳で就学し、6年間のプライマリー・スクールと5年間のセカンダリー・スクールという11年間の義務教育を終え、義務教育修了を認証する国家試験「GCSE」※3を受けた後に、大学進学・職業訓練・就職の3つの道に分かれる。大学への進学を希望する場合には、GCSEで英語、数学、理科を含む5つの科目でC以上のグレードを取得する必要がある。その後、大学進学希望者は、通常はセカンダリー・スクールに付属した学校やシックスフォーム・カレッジと呼ばれる予備校で 2年間の教育課程「シックスフォーム(Sixth Form)」に進む。私立でも、16歳でGCSEを終えるとシックスフォームの教育課程に進むが、上流階級の子弟が多いパブリックスクールでは、大学に入学する18歳までの一貫教育である場合が多い。
英国のイングランドとウェールズは、公立と私立で異なる複線型教育制度を採っている。公立では5歳で就学し、6年間のプライマリー・スクールと5年間のセカンダリー・スクールという11年間の義務教育を終え、義務教育修了を認証する国家試験「GCSE」※3を受けた後に、大学進学・職業訓練・就職の3つの道に分かれる。大学への進学を希望する場合には、GCSEで英語、数学、理科を含む5つの科目でC以上のグレードを取得する必要がある。その後、大学進学希望者は、通常はセカンダリー・スクールに付属した学校やシックスフォーム・カレッジと呼ばれる予備校で 2年間の教育課程「シックスフォーム(Sixth Form)」に進む。私立でも、16歳でGCSEを終えるとシックスフォームの教育課程に進むが、上流階級の子弟が多いパブリックスクールでは、大学に入学する18歳までの一貫教育である場合が多い。
英国で大学に入学するには、まず「A-レベル」※4と呼ばれる全国統一の学科科目別の資格試験を受験し、その試験結果によって入学できる大学が決まる仕組みとなっている。試験結果は、科目ごとに上位からA※ABCDEの6段階および不合格で評価され、大学ごとに合格ラインとなる成績が明示される。シックスフォームの教育機関では、個人の希望に応じて幅広い選択ができるようにさまざまな科目が用意されており、生徒たちはその科目の中から自分の希望する大学進学に必要な3科目を選択し、時間をかけて専門的な知識を勉強して統一試験に備える。
(2)オックスブリッジにおける入学選抜方法
オックスフォード大学は看板科目がPPE(哲学・政治・経済)※5や西洋古典学(classics)と人文系に強く、首相やビジネス分野のリーダーを輩出する一方、ケンブリッジ大学は理系に強く、ノーベル賞受賞者がこれまで100名を超えるのが特徴であるが、英国の大学制度ではこの魅力的な2校の併願はできない。オックスブリッジでは入学希望者のほとんどがA以上の成績なので学力だけでは選抜が難しく、専攻分野に関する論文提出と面接が合否を決める。まず大学主催で2~3人の大学教員による1人30分程度の面談がおこなわれ、そこでは課題に関する知識だけでなく、論理的な思考力、柔軟な発想力、豊かな表現力などが審査される。この面談では、「自分がこの学生の教官として教えたいと思うか」という面接官の主観的な判断で点数をつけるそうだ。大学の面接に合格した受験生は、続いて各カレッジ(学寮)主催の面接を受ける。そこでは入学後にカレッジで学生の個別担当となる可能性の高い教員が面接を実施し最終的な合否を決める。オックスブリッジでは、こうした独特の入学選抜方法にかなりの時間とコストを費やしている。
3.オックスブリッジの特殊な組織形態とは
(1)大学とカレッジ(学寮)の二重構造
オックスブリッジは、他の英国の大学同様に1学期 10~12月、2学期1~3月、3学期4~6月の3学期制で通常3年間である。オックスブリッジの大きな特徴は、大学とカレッジ(学寮)の複雑な二重構造にあるとされる。ここでのカレッジは、日本語で意味する単科大学のことではなく、「教育機能を備えた寮」である。英国ではパブリックスクールや専門学校にもカレッジという単語が使用されるので、その意味が混同されやすい。簡単に言うと、学園都市であるオックスフォード、ケンブリッジに所在する各カレッジの集合体がオックスフォード大学、ケンブリッジ大学となっており、大学は「学位授与機関」、カレッジは「学生の生活・勉強の場」という位置づけなので、大学としてのキャンパスは存在しない。通常は教員も学生も大学とカレッジの両方に所属することになる。
(2)中央執行機関としての大学の機能
大学は、中央執行機関として学務面のフォーマルな責任を負っており、中央政府から直接または間接的に補助金や授業料を受け取り、入学から卒業認定までの試験の実施や研究・教育の国への助成金申請なども行う。バッキンガム大学以外すべて国立大学である英国の大学では、教授・講師などの教員は、大学に公務員として雇用されており、教授、講師、助講師といった教員としての資格は、大学に帰属する。大学主催で比較的大人数の講義やゲストによる講演もおこなわれるが、必修ではなく出席や登録も義務付けられていない。日本のような単位制ではなく、学生が大学に登録するのは、3年目の終わりに実施される卒業試験の受験科目だけだそうだ。
(3)学寮としてのカレッジの機能
カレッジは独立採算の自治的組織であり、歴史のあるカレッジほど所有する不動産などからの収入が大きいので財政的に豊かである。また、カレッジは自然発生的に何百年もかけて諸学派や宗教的な共同体から生まれてきたので、それぞれに伝統と歴史があり、学校としての特色をもっている。
現在、オックスフォード大学には39のカレッジ、ケンブリッジ大学には31のカレッジがある。学生は、通常はさまざまな専攻の学生と教師が各カレッジで寝食を共にし、学業のみならず学生生活のほぼ全てを過ごすこととなる。オックスフォード大学では、1264年創立で天皇陛下も留学されたマートン・カレッジや英国首相を輩出した最大規模のクライスト・チャーチなどが有名であり、ケンブリッジ大学では、キングス・カレッジや、科学者のニュートンや哲学者ベーコンなどを輩出したトリニティ・カレッジなどが有名だ。各カレッジによって得意とする学問分野や所属する教員などの特徴は異なり、しかも在学中にカレッジの変更はできないので、オックスブリッジの入学希望者は、入学後に後悔しないように希望するカレッジの内容を事前調査しているそうだ。
多くのカレッジは、宿泊施設のほか、食堂、礼拝堂、図書館、クラブ室、喫茶室などを備えるだけでなく、サッカーやラグビー、クリケットなどスポーツに興じるための広大な芝生のグラウンドも所有している。ほとんどのカレッジには、映画『ハリー・ポッター』の撮影場所となったオックスフォード大学クライスト・チャーチの「グレートホール」のような細長い食堂がある。その一番奥には一段高くなっているハイテーブルがあり、ディナー・ジャケットや学校指定のガウンを着用するカレッジ主催の晩餐会も行われる。各カレッジ間では成績だけでなく、スポーツ対抗戦、施設、学食などさまざまな分野で競争意識が強く、学生の卒業試験の成績で各カレッジを格付けする非公式なランキング※6もあるようだが、学生が卒業する際に授与される学位の証明書には大学名しか記載されていないので、学位における各カレッジ間の優劣はない。
4.オックスブリッジにおける教育システム
(1)カレッジにおける厳しい個別指導
 オックスブリッジのカレッジでは、1~4名の学生が週に1回のペースで専攻科目について教官の個別指導を受ける。このシステムは、オックスフォード大学では「チュートリアル」、ケンブリッジ大学では「スーパーヴィジョン」と呼ばれている。課題ごとに提出する小論文は、大体A4で10枚程度、期限は1~2週間であり、1週間に2~3本書くこともあるらしい。大人数の講義形式中心の日本とは異なり、個別指導中心のオックスブリッジでは、毎週膨大な課題図書リストの中から書籍や文献を10冊ほど読み、小論文を書かせられ、提出後には教官からの厳しい質問や討議が待ち受けている。徹底的に読んで、書いて、議論することで、初めて真の思考力が育つのであろう。
オックスブリッジのカレッジでは、1~4名の学生が週に1回のペースで専攻科目について教官の個別指導を受ける。このシステムは、オックスフォード大学では「チュートリアル」、ケンブリッジ大学では「スーパーヴィジョン」と呼ばれている。課題ごとに提出する小論文は、大体A4で10枚程度、期限は1~2週間であり、1週間に2~3本書くこともあるらしい。大人数の講義形式中心の日本とは異なり、個別指導中心のオックスブリッジでは、毎週膨大な課題図書リストの中から書籍や文献を10冊ほど読み、小論文を書かせられ、提出後には教官からの厳しい質問や討議が待ち受けている。徹底的に読んで、書いて、議論することで、初めて真の思考力が育つのであろう。
(2)過酷な年度末試験と卒業試験
大学における学生の成績は、1、2年目の年度末試験と最終年度の卒業試験の結果がすべてであり、学生の個別指導での頑張りは成績に反映しない。
オックスフォード大学の年度末試験では、選択科目ごとに9問が出題され、その中から3問を選択し、3時間で論述するそうだ。これまで指導教官から課題とされた文献が試験範囲とされるので、試験準備は大変であり、大学3年間の集大成となる卒業試験では更に難度が高くなる。
オックスブリッジを卒業する難しさが
次回は、1月号の君塚氏との新春対談で話題に出たヴィクトリア朝時代の立憲君主政における議会政治の状況を辿りたい。
※1 「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」: Times Higher Education。英国のタイムズ紙が新聞の付録冊子として毎年秋に発行している高等教育情報誌。
※2 「スーパーグローバル大学」: スーパーグローバル大学として37の大学が認定され、世界大学ランキングトップ100を目指す13校と社会のグローバル化を牽引する24校がある。
※3 「GCSE」: General Certificate of Secondary Educationの略。義務教育期間の最後の学年にあたるイヤー11(16歳)の最終学期末に実施される全国統一テストで、この結果は進学や就職の判断材料になる。
※4 「A-レベル」: General Certificate of Education Advanced Levelのこと。中等教育卒業もしくは大学入学レベルにあることを示す学業修了認定であり、資格認定にはEレベル以上が必要となる。
※5 「PPE(哲学・政治・経済)」: Philosophy, Politics and Economicsの略。3年間の学位で、1年目は「哲学・政治・経済」3学科全ての基礎を勉強する。2・3年目は哲学・政治・経済の内2つ以上の学科を選択し、専門科目を8つ選び勉強する。
※6 「非公式なランキング」: オックスフォード大学の「ノリントン・テーブル」やケンブリッジ大学の「トンプキンス・テーブル」がある。
※7 「主任警部モース」: 原題はInspector Morse 。原作のコリン・デクスター(1930~2017)は、ケンブリッジ大学を卒業後、小説家を目指すためにオックスフォードに移住。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第28回]~2022年12月号
先日新聞に「ミネルヴァ大学では、定員増とともに新たな国で学寮を増やすことを検討しており、その有力先に日本が入っている」という記事が載った。米国のサンフランシスコに本部を置くミネルヴァ大学は、開校後10年足らずにもかかわらず先進的な取り組みによって世界中から注目されており、合格率も2%未満とハーバード大学などの有名校よりも難関とされている。米国以外の出身が約8割という多様な国籍の生徒たちは、各都市の学寮からアメリカの本部にいる教師とオンラインで結ばれている。授業は同時双方向で行われ、各都市では大学が提携する企業やNPOの中で実践的な課題解決などに挑む体験をする。
中世ヨーロッパの大学の起源は、都市における教師と生徒の協同組合にあり、共同生活の場である学寮が大学の中心であったが、ミネルヴァ大学も、世界の7都市に設置された学寮が、教師とともに学生が学ぶための重要な拠点となっている。
「英国の代表的な大学が産業革命において果たした役割」の2回目となる今回は、中世ヨーロッパの封建社会の都市において大学が登場し、英国にも設立されていく経緯を辿る。
1.封建社会における自治都市の発生と学校の状況
中世ヨーロッパでは、ローマ教皇庁を頂点とした「カトリック教会」と領地から租税を徴収する権利をもつ「封建領主」が絶対的な権力をもっていた。農業の発達によって余剰生産物が発生し貨幣経済が普及すると、商業や手工業の発展とともに教会と領主に支配されていた農村部の中から都市的な集落が生まれた。特にカトリック教会の教区の中心となる司教座聖堂※1が置かれた司教座都市は、宗教的、政治的に重要な地位を占め、周辺の荘園から人と物資が集まり、その多くが中世の都市の起源となった。そうした都市の多くは外周に防御施設である城壁をめぐらせ、その城壁内には教会、市庁舎、定期市などがあった。また、封建領主の支配下に置かれた荘園の農奴や手工業者が一定期間都市に移り住めば、領主の支配から解放され自由市民となることが可能であった。ドイツのことわざ「都市の空気は自由にする」は、このような都市の特徴をあらわすものである。11世紀に入ると、都市で力をもち始めた「ギルド」と呼ばれる同業者組合の親方衆が、教会や封建領主に対して都市の自治権を求めるようになった。
また、当時ラテン語の読み書きができる人間は、ほぼ聖職者に限られていたので、高等教育の担い手は、聖職者が運営する司教座聖堂学校※2や修道院学校※3が中心となり、文書の作成に関する仕事も聖職者が独占した。
2.イタリアとフランスに誕生した中世大学
その後都市の発展とともに、自治権をもった大学が自然発生的にイタリアのボローニャとフランスのパリで誕生する。こうした中世の大学は、「自由と自治」を認められた特権的な団体であり、「あらゆる地域から学生を惹きつけ、万国に通用する教授資格をもつ多数の教師が高等教育を施す」という点が特徴であった。
しかし、ヨーロッパ最古参のボローニャ大学とパリ大学を支えた設立基盤を比較すると、大学を主導する組合団体や自治権の庇護者の点などで対照的である。
(1)学生が主導する「法学」のボローニャ大学
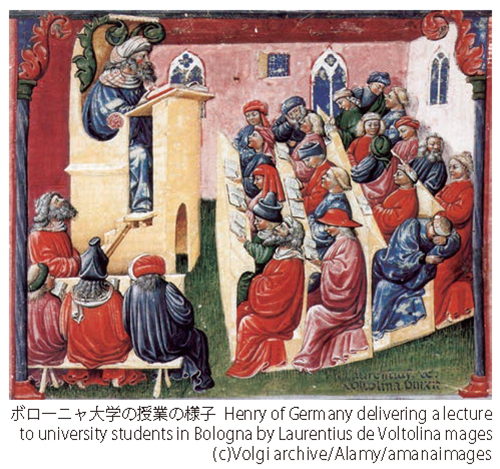 ボローニャ大学は、11世紀末頃にイタリアのボ ローニャで教会の学校から独立して、公証術を教えていたペポーや文法教師のイリネリウスが、ローマ法大全をもとに法学を教えたことが起源だと言われている。12世紀に入ると、ボローニャはヨーロッパ各地から教師と生徒が集まる法学教育の中心地となった。都市の商業活動でも日常的に文書の作成が行われるようになると、公証術として文書の作成技法や商業取引の法学的知識が必要となって社会的需要が高まっていた。文書を扱う公証人は、他の職業のような厳しい徒弟制度もなく、教養人にとって必須のラテン語も習得できるので、憧れの職業となっていたようだ。ボローニャ大学では、そのために必要な学問が学べた。
ボローニャ大学は、11世紀末頃にイタリアのボ ローニャで教会の学校から独立して、公証術を教えていたペポーや文法教師のイリネリウスが、ローマ法大全をもとに法学を教えたことが起源だと言われている。12世紀に入ると、ボローニャはヨーロッパ各地から教師と生徒が集まる法学教育の中心地となった。都市の商業活動でも日常的に文書の作成が行われるようになると、公証術として文書の作成技法や商業取引の法学的知識が必要となって社会的需要が高まっていた。文書を扱う公証人は、他の職業のような厳しい徒弟制度もなく、教養人にとって必須のラテン語も習得できるので、憧れの職業となっていたようだ。ボローニャ大学では、そのために必要な学問が学べた。
当時はキャンパスや校舎もなく、教師たちは下宿先や町の中に部屋などを借りて教室を開き生徒を集めた。そうしてボローニャに住む学生などの人口が増えた結果、下宿代や生活必需品が高騰したり、居酒屋での傷害事件などが発生したりして、日常生活での学生と都市当局との対立が生じ、教師への苦情などが出るようになる。市外から来て市民権のない学生たちは、市当局の保護を受けられないので、自衛と相互援助のために出身地ごとにギルドと同じような「同郷組合」を作った。大学に入る学生は、まず同郷組合に加入することが必要となった。12世紀末にはいくつかの同郷組合の中から代表者が選出され、それらの代表者によって運営される組合団体「ウニヴェルシタス(universitas)」を組織した。これが実質的なボローニャ大学の誕生となる。
一方で、もともと市民で同郷組合の加入対象外であった教師たちは、ウニヴェルシタスに関与できず、学生たちが大学の運営権を握るようになる。教師の存在は師弟関係というよりは単に学生の謝金で生活する雇用者となり、授業の質が悪いと見なされれば即お払い箱となったので、学生たちに逆らえなかった。こうした事態を危惧した教師たちは、学位授与権を武器に教師の権利を防衛する組合「コレギウム(collegium)」を組織した。
また、市や地元の商工業者にとって多数の学生や教師を抱えた大学の存在は大きかった。そのため市当局との交渉が難航すると、ボローニャ大学は市からの退去を
また、神聖ローマ帝国(962~1806)にとって もボローニャ大学は重要な存在だった。神聖ローマ皇帝フリードリッヒ1世(在位1152~1190)は、 1158年のハビタ勅令によってボローニャ大学で学ぶ者の権利と安全を保障している。神聖ローマ帝国は、カトリック教皇との激しい聖職叙任権闘争の中で、自身の権利を正当化するためにローマ法に根拠を求めており、ボローニャ大学のお墨付きが必要だったのである。
(2)教師が主導する「神学」のパリ大学
 フランスでも、中世初期には文化や教育などの中心は地方の教会や修道院であったが、商業・産業の発達と都市の発展にともない、都市の代表的な教育機関である司教座聖堂学校に中心が移った。12世紀に入ると、十字軍の遠征やレコンキスタ※4(国土回復運動)での接触をとおして、イスラム圏から大量のギリシャ・ローマの古典文献やアラブの先進的な知識がヨーロッパに流入した。こうした「12世紀ルネサンス」によって、カトリック教会の地位が揺らぎ始める。学問はもはや聖職者だけのものでなくなり、司教座聖堂学校でも世俗の人々を対象に教えるようになった。中でもシテ島にあるノートル・ダム大聖堂に付属するパリ司教座聖堂学校は、パリ大学の起源となるのである。
フランスでも、中世初期には文化や教育などの中心は地方の教会や修道院であったが、商業・産業の発達と都市の発展にともない、都市の代表的な教育機関である司教座聖堂学校に中心が移った。12世紀に入ると、十字軍の遠征やレコンキスタ※4(国土回復運動)での接触をとおして、イスラム圏から大量のギリシャ・ローマの古典文献やアラブの先進的な知識がヨーロッパに流入した。こうした「12世紀ルネサンス」によって、カトリック教会の地位が揺らぎ始める。学問はもはや聖職者だけのものでなくなり、司教座聖堂学校でも世俗の人々を対象に教えるようになった。中でもシテ島にあるノートル・ダム大聖堂に付属するパリ司教座聖堂学校は、パリ大学の起源となるのである。
パリ大学では、教師も学生も聖職者であったので、ボローニャ大学のような教師と学生の対立は見られなかった。また、教師も学生もパリ以外の地域から来た者が多く市民権をもたなかったので、共同で組合を組織して自衛した。その結果、パリ大学の運営の主導権を握ったのは、学生ではなく教師の団体となった。パリ大学固有の校舎がなく学生の定員というものは存在しなかったので、聴講生が多ければ多いほど給料の増える教師たちは、多くの学生が集まるような魅力的な講義となるように懸命に努力した。ヨーロッパ各地から多数の教師や学生がパリ大学に集まったが、特に神学と哲学の教師であるピエール・アベラール(1079~1142)の人気は高く、多い時には5000人の聴講生を集めたそうだ。
パリ大学が実質的なスタートとなる自治権を得た のは、1200年に起きた酒屋での喧嘩が発端であった。リエージュ司教候補者のドイツ人学生に雇われていた召使の男が、いきつけの酒屋で侮辱されたことを理由に、ドイツ人の学生たちがその酒屋を襲った。酒屋の訴えをうけたパリ市警察が犯人逮捕に向かうと学生たちは猛然と抵抗し、大乱闘のすえ、学生側に5人の死者が出た。大学側はただちに国王フィリップ2世(在位1180~1223)に警察の対応を抗議し、「警察の責任者を処罰しないなら、大学は他の場所に移動する」と通告する。国王は大学側の抗議を受け入れると同時に、「パリ市警察の権限は大学関係者に及ばないこと、大学関係者はすべてノートル・ダムの裁判権のもとにある」と認めたのであった。
こうしてパリ市から独立したパリ大学であったが、パリ司祭からの統制が依然としてあった。パリ司祭は、大学の人事や学位授与などについても干渉し、大学側が反抗すると大学関係者を全員破門にして対抗した。こうしたパリ司祭との対立に手を焼く大学側は、歴代ローマ法王など幹部が卒業生であることからローマ法王を味方につけ、1222年にパリ司祭からの独立工作に成功する。
また、パリ大学では1180年に初めて貧窮学生を受け入れるための学寮である18人収容の「十八人学寮」が誕生しており、1257年には聖職者ロベール・ド・ソルボン(1201~1274)によって神学部のために「ソルボンヌ学寮」が設置された。のちにはソルボンヌがパリ大学全体を意味するようになり、この地域一帯の学生街を「ラテン語を話す学生が集まる地区」を意味する「カルチェ・ラタン」と呼ぶようになった。
3.英国のオックスフォード大学とケンブリッジ大学の設立経緯
(1)パリ大学からの移動で誕生したオックスフォード大学
オックスフォード大学の起源については、いくつかの定説がある。
1つは、オックスフォード大学の誕生を1133年とする説である。フランスのノルマンディー公ウィリウム1世がイングランドを征服して成立した英国のノルマン朝(1066~1154)ではフランスの強い影響を受けたため、学者の多くはパリ大学で学ぶことに憧れていた。その当時からすでに学校らしきものはあったのであろうが、神学者ロベール・ピュランが、パリ大学から来講した1133年を誕生の年としている。
もう1つの有力な説が、イングランド国王ヘンリー2世(在位1154~1189)の命でパリ大学から多くの教師や学生が移動したというものだ。ノルマン朝の後を引き継いだプランタジネット朝(1154~1399)の初代国王ヘンリー2世は、英国のイングランドだけでなくフランス国内にも広大な領地をもっていた。イングランド国王としての彼は、フランス国王と同等であったものの、フランス国内の領主としては、フランス国王ルイ7世(在位1137~ 1180)の家臣という主従関係にあった。
自分の権力を強化したい国王ヘンリー2世は、 1162年に聖職者の反対を押し切って腹心のトマス・ベケット(1118~1170) をカンタベリー大司教に任命し、聖職者の権限を制限しようと企む。さっそく1164年のクラレンドン法※5によって教会裁判に制限を設けようとするが、ベケットは国王ヘンリー2世の意に反し制限の受け入れを拒否する。大司教への就任を機に、世俗的な腹心だったベケットが、敬虔な聖職者に転向してしまったのである。しかも迫害を受けてフランスに亡命したベケットは、国王ヘンリー2世に
ベケットの裏切りに激怒したヘンリー2世は、聖職者が国王や大法官※6の許可なしに大陸に渡航することを禁じ、英国内に聖職禄※7を有する者は、3カ月以内に帰国することを命じた。当時パリに住んでいた聖職身分の教師や学生が、やむなく英国に戻ってオックスフォードに移動することでオックスフォード大学が誕生することになる。このように設立された当初のオックスフォード大学は、学問や政治の中心的存在であったパリ大学やボローニャ大学に比べると、英国の片田舎にある大学にすぎなかった。ロンドン北西約100kmのテムズ川上流のオックスフォードという場所が選定された理由も、たまたま商業上重要な交通の要所で交易関係の人々が集まりやすい場所だったからと言われている。オックスフォード大学は、12世紀末には全キリスト教国で通用する学位授与権を取得し、13世紀初めにはパリ大学に次ぐローマ・カトリック教会第2の学校としての地位を与えられた。
(2)オックスフォード大学からの移動で誕生したケンブリッジ大学
パリ大学を見習って作られたオックスフォード大学では、教師と学生からなる大学の団体組織が、自治権等を巡って町当局や国家と対峙していた。 1209年には、町当局や国王と争う大事件が発生し、多くの教師や学生がオックスフォード大学を退去してケンブリッジの地に移り、新たな大学が誕生する。事の発端は、「学生が婦人を殺害したことで、町長と町民が犯人の住む学寮を襲撃し、数人の学生が逮捕される」という事件である。投獄されていた学生のうち2人を処刑することに国王が同意したと知った大学の教師と学生たちは、国王に抗議するために一斉にオックスフォードからケンブリッジの地への移動を決行した。オックスフォードからの退去で、約3000人の関係者が移動したとも言われる。
4.19世紀初めまで停滞するオックスブリッジ
英国では、名門大学であるオックスフォードとケンブリッジをミックスして「オックスブリッジ」と呼んでいるので、以降は、2校をオックスブリッジと表記する。
ヨーロッパでは中世から近世にかけて、多くの大学が設立された。14世紀には、イタリアのピサ大学やチェコのプラハ・カレル大学、ポーランドのクラクフ(現在のヤギェウォ大学)など、多くの国で大学が設立され、スコットランドでも16世紀までにグラスゴー大学やエディンバラ大学などが設立されている。
一方、英国の大半を占めるイングランドでは、 1334年から1827年までオックスブリッジ以外の大学の設立が禁止されていた。この禁止の発端となったのが、「スタンフォードの誓い」と呼ばれる出来事だ。1333年にオックスフォード大学の内部紛争から、一部の学生と教師のグループがイングランド東部のリンカンシャーにあるスタンフォードの町へ逃亡し、その地で学生を教育する学術機関を設立しようとした。この動きを看過できないオックスブリッジは、当時のイングランド王であったエドワード3世(在位1327~1377)に要請して、オックスブリッジの卒業生に「両大学以外で講義を行わない」と誓わせ、2校以外の大学の設立が困難となった。大学の権益の独占は、オックスブリッジにとって学生の質を維持するのに役立った。また、教会や支配階層の領主たちにとっても、「大学でどのような神学上の論争をしているのか」や「教会改革者となるような危険な異端者が発生していないか」を事前に察知できる意味で都合が良かった。
当然ながら、このような閉鎖的な環境では大学の活性化も望めず、さらに寮生活の強制や高額な学費に加えて、英国国教徒以外の入学を拒否したことから、学生数は減少し18世紀末にはオックスブリッジは瀕死の状態となった。しかし、英国国教の信徒のみが入学できたオックスブリッジに対抗して、人種、宗教、政治的信条にかかわりなく広く学問の門戸を開いた大学を設立しようとする声が大きくなると、1827年に
中世の大学にとって、自治権だけでなく移動の自由も重要なことであった。冒頭で触れたミネルヴァ大学も世界中を移動する大学だ。キャンパスをもたず全授業をオンラインで行うミネルヴァ大学では、従来の「大学は、キャンパスを基盤とした研究・教育の場である」という概念を覆したと言われる。大学にとって一番必要なものは、設備の整った立派な校舎などのハードではなく、学問を真剣に追求する教師と学生の存在であり、ミネルヴァ大学もオンラインを活用しながら本来の大学の使命を果たしているのである。
次回は、オックスブリッジを中心に英国の大学における教育方法の特徴と産業革命に与えた影響を探る。
※1 「司教座聖堂」: カテドラル(フランス語: Cathédrale)、大聖堂とも呼ばれる。
※2 「司教座聖堂学校」: 司祭志願者に向けて講義を行い、説教や告解での助言を通じて一般信徒を教導するための準備教育機関。
※3 「修道院学校」: 若い修道士を修道院の伝統にしたがい人格的・霊的生活へと導く。
※4 「レコンキスタ」: イスラム教徒が支配するイベリア半島を解放しようとする、キリスト教徒の国土回復運動。
※5 「クラレンドン法」: 英国内の聖職者が教皇庁に上訴することを禁ずる法律。
※6 「大法官」: イングランド・イギリスの官職。中世に創設され、イギリスに現存する最も古い官職と言われ、中世以来国家の印として押す
※7 「聖職禄」: カトリック教会において、教会職と結びついて教会財産の所領あるいは奉納物から一定の収益を得る権利。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第27回]~2022年11月号
英国民から愛された女王エリザベス2世が2022年9月8日に96歳で崩御した。英国国王としては史上最高齢であり、在位70年7カ月は歴代最長である。今年2月には在位70周年の祝賀行事「プラチナ・ジュビリー」が盛大に行われ、9月6日にはトラス氏を女性で3人目となる英国首相に任命するなど、亡くなる直前まで精力的に公務をこなした。女王に仕えた首相は、1951年のチャーチル氏から現在のトラス氏まで15人いるが、そのうち12人が名門オックスフォード大学出身者で占めている。
今回から3回にわたり、このオックスフォード大学を中心に名門ケンブリッジ大学を加えた英国の代表的な大学が、産業革命において果たした役割をテーマに考察する。第1回目は、中世ヨーロッパの大学制度の教養課程である「リベラル・アーツ」について、その源流である古代ギリシャ・ローマ文明の継承を中心に古代から中世までの流れを辿る。
1.中世の大学の源流であるリベラル・アーツとは
「リベアル・アーツ」は、日本語では一般教養や教養教育などと訳されるが、その理念的な源流は「自由人」の市民と「非自由人」の奴隷の区別があった古代ギリシャ・ローマ時代にあり、ギリシャ語の「パイディア」を訳したラテン語に由来している。「パイディア」とは、当時の自由人として必要不可欠な学問を意味し、知育・徳育・体育から成る人格教育のことである。
その後、人文科学、自然科学、社会科学を内包する基礎分野である「自由7科」が定められ、言語・論理系の3学(トリウィウム)の「文法学」、「修辞学※1」、「論理学」と、数学系4科(クワドリウィウム)の「幾何学」、「算術」、「天文学」、「音楽」から構成された。ローマ時代には、この自由7科の上位に哲学、キリスト教の誕生でさらにその上位に神学が位置づけられる学問体系となり、中世の大学では自由7科が教養教育の中核に位置付けられていく。
2.古代ギリシャ・ヘレニズム文化における学問とは
(1)知をひたすら探求する古代ギリシャ
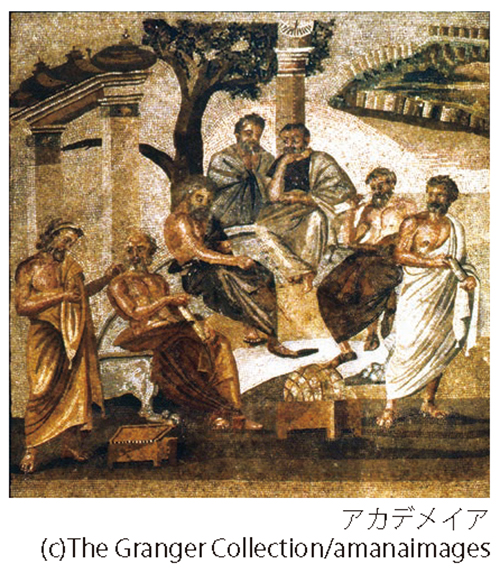 古代ギリシャでは、紀元前8世紀にエーゲ海沿岸を中心に、アテネなどの「ポリス(都市国家)」が次々と誕生し、文学のホメロス、歴史のヘロドトスとトゥキディデス、数学のピタゴラス、哲学のソクラテス、プラトン、アリストテレスなどさまざまな分野で多数の学者が輩出され、合理的で人間中心の文化が醸成された。
古代ギリシャでは、紀元前8世紀にエーゲ海沿岸を中心に、アテネなどの「ポリス(都市国家)」が次々と誕生し、文学のホメロス、歴史のヘロドトスとトゥキディデス、数学のピタゴラス、哲学のソクラテス、プラトン、アリストテレスなどさまざまな分野で多数の学者が輩出され、合理的で人間中心の文化が醸成された。
当時の学校としては、イデア論※2の哲学者プラトン(BC427~BC347)による学園「アカデメイア」、万学の祖アリストテレス(BC384~BC322)による学園「リュケイオン」が紀元前4世紀に創設されている。
(2)オリエントと融合して発展したヘレニズム文化
紀元前4世紀頃になると、マケドニア王国(BC808~BC168)がアテネなどのポリスの連合軍を破り、ギリシャを支配する。その後アレクサンドロス大王(BC356~BC323)は、東方遠征によってペルシアなどを打ち破り、ギリシャから西アジア、エジプト、インダス川流域に至る大帝国を築いた。これを機に東地中海の交易が活発となり、ギリシャ文化とオリエント文化を融合したヘレニズム文化(ギリシャ風文化)が誕生する。
大王の急死でこの大国は3つに分裂するが、その中でヘレニズム文化を引き継いだのは、プトレマイオス朝エジプト(BC305~BC30)である。アレクサンドロス大王とともにアリストテレスに学んだ初代国王プトレマイオス1世は、学問に造詣が深かったので、経済・交易の中心地となった首都アレクサンドリアの財力を背景に、王立研究所「ムセイオン」を設立し、さらに後継のプトレマイオス2世が膨大な蔵書の図書館を併設した。
巨大都市アレクサンドリアには、ギリシャ人、ユダヤ人、エジプト人などさまざまな民族が集まったことで学問的な蓄積が進み、平面幾何学のエウクレイデス(ユークリッド)、数学・物理学のアルキメデスなどの自然科学者が活躍する。
3.ローマ帝国から迫害される古代ギリシャ・ヘレニズム文化
(1)ローマ帝国の誕生から東西分裂までの流れ
次いで、ラテン民族のローマ帝国が、王政ローマ(BC753~BC509)から共和政(BC509~BC27)を経て帝政(BC27~395)に移行すると、紀元前1世紀までにヘレニズムを含む地中海全域を支配する。2世紀の五賢帝時代が最も安定し領土も最大となるが、軍人皇帝時代の混乱、ゲルマン人やササン朝ペルシア(226~651)の侵入もあって国力は次第に衰え、3世紀末にディオクレティアヌス帝(在位284~305)の専制君主制に移行する。その頃帝国内に浸透していたキリスト教は、厳しい弾圧にもかかわらず次第に信者を増やし、313年にコンスタンティヌス帝(在位 306~337)のミラノ勅令で公認され、392年にはテオドシウス帝(在位379~395)によって国教となる。
しかし衰退がとまらず一元的な支配が困難となったローマ帝国は、395年のテオドシウス帝の死を機に西ローマ帝国(395~476)と東ローマ帝国(395~1453)に分裂することになった。東ローマ帝国は、首都コンスタンティノープル(現イスタンブール)の古代ギリシャ時代の古名ビザンティオンにちなみ「ビザンツ帝国」と呼ばれるようになる(本稿では、以降「ビザンツ帝国」と記す)。
(2)ローマ帝国にとっての古代ギリシャ・ヘレニズム文化とは
ローマ帝国では、古代ギリシャの影響を受けつつ、土木・建築・法律・暦といった実用的文化の領域で独創性を発揮し、特に国家の発展に伴って整備されたローマ法は、この国の最大の文化的遺産となった。その一方で、ローマ人は直接実益に繋がらない古代ギリシャ文化には関心を示さず、文学・哲学・美術などの分野は古代ギリシャ人の模倣にとどまった。ストア派の哲学者キケロ(BC106~BC43)のように、積極的にギリシャ哲学の文献をラテン語に翻訳する人物もいたが、科学などの古代ギリシャの文献がローマ帝国の公用語であるラテン語に翻訳されることは少なかった。
ゲルマン民族など異民族の大移動を機に衰退し始めたローマ帝国が、寛容性の低いキリスト教を国教としたことを機に、異端とされた古代ギリシャ・ヘレニズム文化は厳しい状況に陥った。391年にはヘレニズム文化の中心であるアレクサンドリアの図書館が他の宗教を認めないキリスト教徒によって破壊されてしまい、そこで研究していた学者たちは路頭に迷うことになった。
4.西ヨーロッパ、ビザンツ帝国、イスラム世界における古代ギリシャ・ヘレニズム・ローマ文化
(1)キリスト教とラテン語の普及を軸としたカロリング朝ルネサンス
西ローマ帝国が476年に滅亡した後、フランク帝国を建設したメロヴィング朝(481~751)のクロヴィス(在位481~511)は、異端とされたキリスト教アリウス派からいち早くローマ教会が正統とするアタナシウス派に改宗し、ローマ教会との協力により勢力を拡大する。
当時、キリスト教の世界では、コンスタンティノープル教会とローマ教会が力を持っていたが、トップを「ローマ教皇」と呼ぶローマ教会では、西ローマ帝国が滅亡したことで、ローマ教皇がビザンツ帝国の皇帝に従属する形となった。さらにビザンツ帝国とは偶像崇拝問題※3でも対立していたので、ローマ教会はビザンツ帝国に代わる有力な政治勢力としてフランク帝国に接近した。
その頃フランク帝国では、メロヴィング朝からカロリング朝への王位継承を画策しており、ローマ教会と利害が一致した。カロリング朝の初代国王ピピン3世(在位751~768)は、王位継承を援助してもらった見返りにローマ教皇に一部領地を献上し、両者は固く結びついた。その後ピピンの子であるカール大帝(在位768~814)が、武力でヨーロッパの主要部分を統一し、ビザンツ帝国に対抗する国を建設したことから、800年に教皇レオ3世からローマ皇帝の帝冠を与えられる。これにより、ゲルマン人を皇帝とする西ローマ帝国が復活するとともに、ローマ教会は権威の誇示に成功しビザンツ帝国を牽制することができた。
カール大帝は、キリスト教国として聖職者の資質を高め、教会の発展が必要だと考えた。そこで、英国出身のアルクインなど若くて優秀な修道士を招き、教会、修道院におけるラテン語による古典文化の復興(カロリング朝ルネサンス)を目指した。学校の設置や学問の奨励も行い、中世ヨーロッパの教育の基礎である「自由7科」の発展にも寄与した。しかし、強大となった教会の権威が文化生活のあらゆる面を支配したので、すべてがキリスト教中心となり、ラテン語を読み書きできる聖職者や修道士だけが学問の担い手となった。その結果、西ヨーロッパの文化的な発展は停滞し、古代ギリシャ・ヘレニズム文化は11世紀まで忘れ去られてしまった。
(2)ヘレニズム文化を見放したビザンツ帝国
ビザンツ帝国は、ローマ皇帝権の継承者として、地中海帝国の復興とキリスト教会の統一を目指した。6世紀には、専制君主のユスティニアヌス帝(在位527~565)がイタリアなど地中海周辺の旧ローマ領を回復し、一時的に大帝国を再現するとともに、「ローマ法大全」の
 ビザンツ帝国は地理的にもともとギリシャ人が多く、宗教的にも当初寛容であったので、首都コンスタンティノープルには、キリスト教徒によって破壊されたアレクサンドリア図書館所蔵のヘレニズムの文献を抱えた学者が逃げ込んできていた。しかし、ユスティニアヌス帝がキリスト教を統治の理念としたことにより、一転して異端や非キリスト教的なものが取り締まりの対象となり、キリスト教以外の学問は厳しく禁止された。古代ギリシャ時代から続いていたアテネにあったプラトンの学園「アカデメイア」やアリストテレスの学園「リュケイオン」も529年に閉鎖された。迫害を恐れた学者たちは、プラトンやアリストテレスなどの文献を抱えて、今度は非キリスト教圏のササン朝ペルシアへ逃げた。
ビザンツ帝国は地理的にもともとギリシャ人が多く、宗教的にも当初寛容であったので、首都コンスタンティノープルには、キリスト教徒によって破壊されたアレクサンドリア図書館所蔵のヘレニズムの文献を抱えた学者が逃げ込んできていた。しかし、ユスティニアヌス帝がキリスト教を統治の理念としたことにより、一転して異端や非キリスト教的なものが取り締まりの対象となり、キリスト教以外の学問は厳しく禁止された。古代ギリシャ時代から続いていたアテネにあったプラトンの学園「アカデメイア」やアリストテレスの学園「リュケイオン」も529年に閉鎖された。迫害を恐れた学者たちは、プラトンやアリストテレスなどの文献を抱えて、今度は非キリスト教圏のササン朝ペルシアへ逃げた。
(3)古代ギリシャ・ヘレニズム文化を継承したササン朝ペルシアとアラブ・イスラム世界
ササン朝ペルシア(226~651)は、国教のゾロアスター教以外の宗教に寛容だったので、キリスト教、仏教、ユダヤ教などの信者が住んでおり、ジュンディー・シャープール(現代のイラン南西部)には学校と大きな図書館が建設されるなど積極的に学問が保護されていた。ビザンツ帝国から逃げてきた学者たちも学校で雇用され、抱えてきた文献は図書館に所蔵されたことで、古代ギリシャ・ヘレニズム文化の命脈はササン朝で保たれ、次にイスラム世界に継承されることとなる。
その後、622年にアラビア半島のメッカに生まれた預言者ムハンマド(570頃~632)がメディナにイスラム国家を建設し、約10年でアラビア半島全域を支配する。正統カリフ※4時代(632~661)、ウマイヤ朝時代(661~750)を経て誕生したアッバース朝(750~1258)は、第2代カリフのマンスール(在位 754~775)が762年に建造した新都バグダッドを中心に、8世紀末には北アフリカから中央アジアに及ぶ広大な領域を支配する。アッバース朝は、アラブ人だけに依存せず、官僚制度や法律を整備してアラブと非アラブの平等化を図り、多民族共同体国家としてイスラム帝国の維持に努めた。また、コーランにも「知識を求めよ」とあるように、アラブ人は新しい知識や学問の吸収に貪欲であったので、ササン朝に継承されていた古代ギリシャ・ヘレニズム文化は、そのままアッバース朝に引き継がれた。
第7代カリフのマアムーン(在位813~833)は、830年にバグダッドに図書館「知恵の館」を設立して、ギリシャ語やペルシア語で書かれていた文献のアラビア語への翻訳を行わせた。紙の製法が中国からイスラム社会に伝わり、紙が普及したこともアラビア語への翻訳活動に拍車を掛けた。この翻訳作業によって、ヘレニズム文化がイスラム社会に継承されただけでなく、アラビア語は学術の共通言語としての地位を確立する。
9~11世紀頃のイスラム圏では、ペルシア、インド、中国などから天文学や数学、医学などが伝わるとともに、アリストテレスを中心としたギリシャ哲学が盛んに研究され、科学が当時の最高水準に発展する。
5.古代ギリシャ・ローマ文化の再発見 12世紀ルネサンスでのラテン語翻訳
 封建制とキリスト教が中心となった中世ヨーロッパでは、アリストテレスをはじめとした古代ギリシャの知的遺産は忘れ去られた。教皇が主導権を握り国王に皇帝の位を授ける政教分離主義の「ローマ・カトリック教会」と、ビザンツ皇帝が宗教と政治の両方を主導する皇帝教皇主義の「ギリシャ正教会」に二分された。
封建制とキリスト教が中心となった中世ヨーロッパでは、アリストテレスをはじめとした古代ギリシャの知的遺産は忘れ去られた。教皇が主導権を握り国王に皇帝の位を授ける政教分離主義の「ローマ・カトリック教会」と、ビザンツ皇帝が宗教と政治の両方を主導する皇帝教皇主義の「ギリシャ正教会」に二分された。
12世紀に入ると、勢いが衰えたイスラム国家のアッバース朝に代わって、ジェノヴァやヴェネツィアなどの北イタリア都市国家が地中海貿易の主導権を握り、インドやアラビアの商人を相手とする交易が始まった。当時の気候変動による温暖化や農業技術改良によって人口が増加し、都市が発達したおかげで東西の交易が盛んとなり、イスラム世界からヨーロッパにアラビア語に訳された古代ギリシャ・ローマ文化の文献がもたらされた。
聖地エルサレムをイスラム教諸国から奪還することを目的に11世紀に始まった十字軍遠征は、アラビアの数学や科学とともに、戦利品としてアラビア語に訳された古代ギリシャ・ローマの文献を大量にイタリアへ持ち込んだと言われる。しかし、実際には略奪と
そのなかで生まれた古代ギリシャ・ローマ文化の再発見となる「12世紀ルネサンス」は、アリストテレス哲学やイスラム科学の文献が大量にラテン語に翻訳されたことから「大翻訳運動」とも呼ばれた。翻訳を担った地域は、語学の堪能なアラビア人が多かったシチリアや、旧イスラム国家でラテン語とアラビア語の両方に通じた人々が多かったイベリア半島であった。特にユダヤ人居住区のあった現在のスペインの都市トレドには、アラビア語・ギリシャ語・ラテン語に長けたユダヤ人が多かったので、翻訳活動が進んだ。
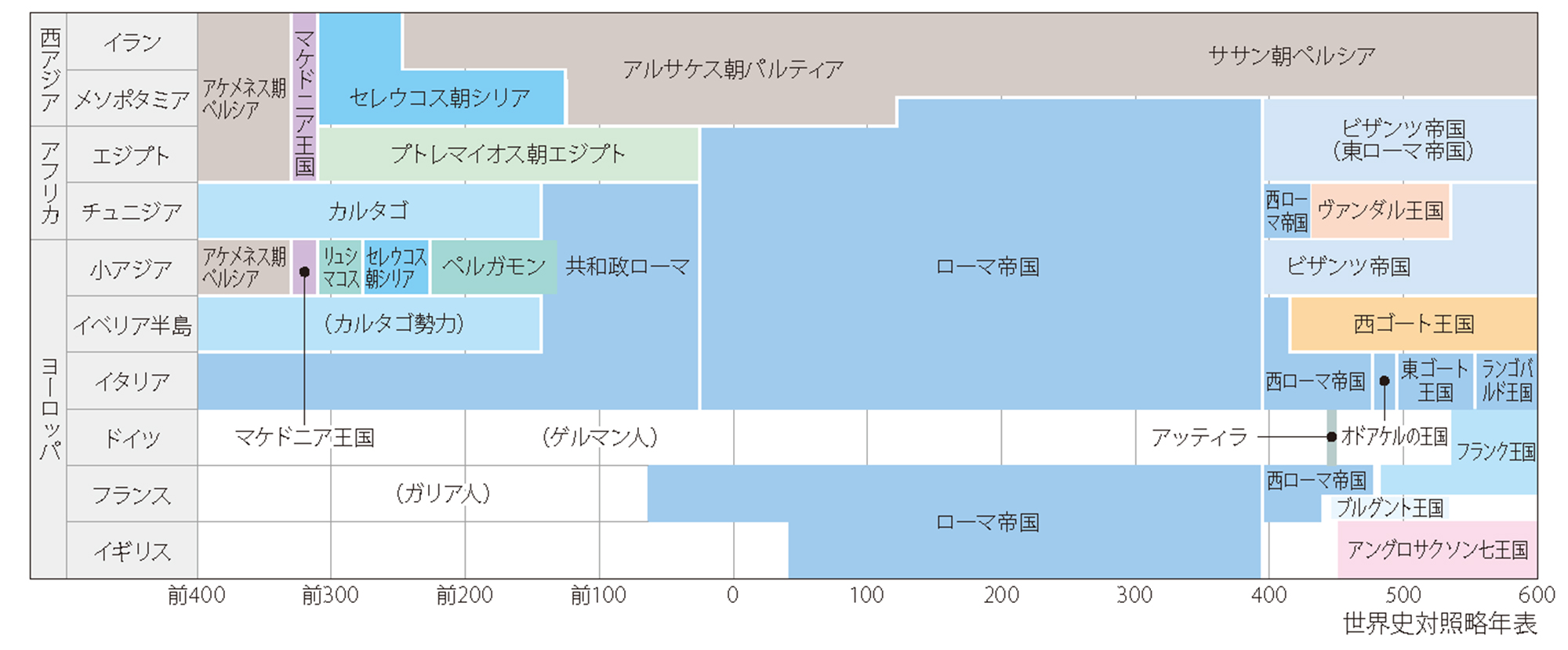
6.ラテン語への翻訳運動を機に大学の前身が誕生
交易やレコンキスタを通して古代ギリシャの文献が大量に持ち込まれたことにより、カトリック教会や修道院に属する学校(スコラ)では、キリスト教の教義を学ぶ神学をアリストテレスなどのギリシャ哲学によって理論化、体系化する「スコラ学」が盛んとなる。
こうした翻訳やキリスト教義の発展の中で、知識人における学問への欲求が高まり、まずはラテン語に翻訳するために知識階級の組合が発足した。その後、自然発生的に出現した教師や学生で構成される一種の同業者組合(ギルド)が、ラテン語で「ユニベルシタス(universitas)」と呼ばれるようになり、現在の大学の起源となる。こうして、さまざまな分野において学問に対する需要が高まり、11世紀末に法学の学生中心の世俗組織であるボローニャ大学、12世紀前半に神学の教師中心の教会組織であるパリ大学、12世紀後半にはオックスフォード大学が誕生する。
次回は、中世の大学の誕生からオックスフォード大学・ケンブリッジ大学の誕生が社会に与えた影響などを辿る。
※1 「修辞学」: 聴衆の説得・扇動・魅了を目的とする弁論・演説・説得の技術に関する学問分野。
※2 「イデア論」: 人間の認識の背後にある、完全な真実の世界をイデア界とし、その影が現実に或るものと考えた。
※3 「偶像崇拝問題」: 726年にビザンツ帝国レオ3世が出した聖像の使用を禁止する法令に対し、ローマ教皇が反発しキリスト教の東西対立の端緒となった。
※4 「正統カリフ」: カリフとはアラビア語で「正しく導かれた代理人たち」を意味し、正統カリフはムハンマド直後の後継者4代を指す。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第26回]~2022年9・10合併号
1971年の英国映画「小さな恋のメロディ」※1は、ビー・ジーズの主題歌「メロディ・フェア」とともに日本で爆発的な人気となった。天才子役と言われたマーク・レスターが少年ダニエルを、トレイシー・ハイドが少女メロディを演じた。映画の舞台となったコンプリヘンシブ・スクール※2は、入学試験のない公立中等学校であり、中流階級と労働者階級の子供たちが混在している。この映画の中では、中流階級に属するダニエルと労働者階級に属するメロディの家庭環境の違いが鮮明に描かれており、英国の階級社会を強く印象付けた。
今回は産業革命期における英国イングランドの労働者階級を主とした大衆向け教育が、教会中心から国家中心、そして義務教育へと移行していく状況を辿る。
1.産業革命期の過酷な児童労働者たち
 (1)18世紀までは、子供は「小さな大人」
(1)18世紀までは、子供は「小さな大人」
18世紀までは「子供は弱いものであり、守らねばならない」という考えは英国にはなかった。キリスト教に根差した原罪説から、人間は生まれながらにして罪を背負っており、大人より子供の方が罪深いとされた。この頃は、大人と子供の線引きがないので、子供は「小さな大人」であり、大人顔負けに堂々と喫煙、飲酒、賭け事をしている。彼らは、幼い頃からお金を稼ぐために炭坑や工場などの危険な現場で長時間働かされた。特に小さな体が有利な煙突掃除や狭い鉱山での運搬では児童が重宝されたが、窒息や火傷などの事故が絶えず、使い捨て同然に利用された(以降、学齢6~12歳相当の子供を児童と表記する)。
(2)技術革新による安価な児童労働者への需要
産業革命の技術革新によって、職人の技能の熟練度や筋力が不要となり、従順で賃金が安い女性や児童が労働に従事させられるようになる。産業革命前は、徒弟制のもとで働く人々と厳しい親方との間には多少人間的なつながりがあったが、産業資本家である工場主にとっては、「労働者は利益を生む道具」でしかなく、児童に服従と時間厳守を命令し劣悪な環境で非人間的な長時間労働を強いた。
2.19世紀までの大衆教育の状況
(1)教会を中心とした貧困な児童向け学校
19世紀半ばでも、英国で学校へ行っている児童は半数にも満たなかった。上・中流階級の児童は、パブリック・スクールを始めとする全日制の学校へ通ったが、労働者階級にはたとえ少額でも、授業料を払えないほど貧しい家庭が多かった。児童は自宅や職場で仕事をしながら父兄や年長者から読み書きや仕事の指導を受けていたが、無償もしくは少額の費用で教育を受けることができる貧困者向けの民間学校もあった。民間の宗教団体や慈善団体、あるいは裕福な個人によって、貧困児童のためにボランティアで設立された学校である。18世紀頃の教育の担い手は教会が中心となっており、国家はほとんど教育に干渉しなかったのである。
そうした民間学校のうち特徴があるものを、宗教色の強いものから順に列挙する。
(2)慈善学校(チャリティ・スクール)
17~18世紀には、英国国教会の牧師たちが児童を集めて読み書きや簡単な算数を教えていた。聖職者が教師となって私財を投じ小さな学校を開くこともあったようだ。1698年に貧困児童救済のためのキリスト教知識普及協会が設立され、18世紀に入ると「慈善学校(charity school)」が、教会区の篤志家たちの出資によって建設された。
学校では、あくまで宗教と道徳の教育が主で、知育は副次的な位置付けであった。「信仰に厚く、社会秩序を守り、上位者に服従し、自らの仕事に精励する人間」へと児童たちを育成することが目的なのである。
(3)日曜学校
1780年に慈善家ロバート・レイクス(1736~1811)が中心となって進めたのが「日曜学校運動」である。「悪徳は治癒するよりも予防する方がよい」という彼の考えから教育が最善の方法であるとして、積極的にこの運動を推進した。聖書を教科書とし、一般の人々が先生となることからスタートしたもので、宗教的役割とともに識字率向上に幅広く取り組んだ。
特に田舎では、通える学校そのものが少なかったので、日曜学校の誕生は貧しい児童にとって朗報であった。学校の授業は、週に1回のみで教師の質も低く、しかも宗教の授業が中心だったので学習効果が高いとは言えなかったが、1831年には毎週百万人を超える児童たちが参加した。
(4)貧民学校(ragged school)
1601年のエリザベス救貧法※3に由来する救貧院の中でも児童に簡単な読み書きや仕事を教えていたが、教育水準が低く、施設内では暴力や残酷な鞭打ちが日常茶飯事であった。都市部には、大人や社会から見捨てられ住む家もなく栄養不足となった児童たちが多く暮らしていたが、生活困窮からスリや万引きなどの犯罪に手を染める児童の数が増加し、治安が悪化していた。
そうしたなかで、1818年にポーツマスの靴商人であったジョン・バウンズ(1766~1839)が自分の店に貧困児童や浮浪児を集めて、読み書き算数と初歩的な職業訓練を無償で行った。これが、初期の「貧民学校(ragged school)」の一つだと言われる。聖職者ではない人たちが志願し、これまで社会的に放置されてきた最貧困層の児童のために宗教を中心とした基本的な教育を無償で施した。その運営資金は、キリスト教の人道主義を謳って富裕者からの寄付で賄ったのである。このような学校は、ロンドンだけでなく地方都市でも自然発生的に誕生し、1844年にはロンドンで貧民学校連盟が結成された。
(5)デーム・スクール
「デーム・スクール(dame school)」は、日本語に訳すと「おばさん学校」であり、一般の夫人が教師となって幼児を対象に自宅で1日数時間の授業をする小規模の私的学校である。学校ではアルファベットや新約聖書の一部だけでなく、家庭内の日常雑事も教えた。商人や労働者の子供を対象として18世紀には英国全土に広く普及した。
19世紀には工業化の影響によって工場で勤務する親が増えたため、デーム・スクールは教育ではなく勤務中の保育が目的となり、安価な託児所代わりとなった。非公式な教育の場であるが、親の要求や意見に素早く応えて融通が利いただけでなく、宗教的な道徳観を押し付けられることもなかったので人気があり、学費の面でも経済的であった。
3.19世紀における社会情勢と価値観の変化
(1)児童労働者の実態と労働環境の改善への動き
社会学者フリードリ ヒ・エンゲルス(1820~ 1895)の著書「イギリスにおける労働者階級の状態」(1845)は、産業革命期のルポルタージュの傑作であるが、その中で1833年の工場委員会による工場の実態報告を次のように記載している。
 「工場主はしばしば6歳から、たいていは8歳ないし9歳から子供を雇い始める。労働時間は、14~16時間。工場主は、監督が子供を殴ったり、虐待したりするのを許すばかりか、自ら手を下している。そして、このように労働時間が長くても、貪欲な資本家は満足しなかった。そのうえ、子供たちは夜間労働まで強いられ、2~3時間の睡眠でストレスが溜まって飲酒癖や性の乱れが著しくなり、さらに長時間労働で身障者となる者も少なくなかった」
「工場主はしばしば6歳から、たいていは8歳ないし9歳から子供を雇い始める。労働時間は、14~16時間。工場主は、監督が子供を殴ったり、虐待したりするのを許すばかりか、自ら手を下している。そして、このように労働時間が長くても、貪欲な資本家は満足しなかった。そのうえ、子供たちは夜間労働まで強いられ、2~3時間の睡眠でストレスが溜まって飲酒癖や性の乱れが著しくなり、さらに長時間労働で身障者となる者も少なくなかった」
徒弟制度のもとでは、親方から最低限のことを教わりながら仕事もできたが、工場で長時間働く児童たちには、教育を受けるような余裕はなかった。
しかし、過酷な児童労働が徐々に社会問題となり、空想的社会主義者として有名な産業資本家のロバート・オウエン(1771~1858)などによって労働条件の改善を求める運動が始まる。1833年の工場法制定を皮切りに「9歳未満児童の雇用禁止」や「13歳未満の児童を週に12時間学校に出席させること」などを雇用主に義務付け、労働条件の改善が実施された。
(2)新救貧法による貧困者の苦境と法律への批判
18世紀末に国家の救貧対策として、自分の家を持っている低所得者にも賃金を補助する「救貧院以外の救済制度」が始まった。しかし、一旦救済を受けてしまうと、労働意欲を失くして救済金をあてに生活する労働者が多くなった。さらに、農作物の不作やナポレオンとの戦争など相次ぐ災難で失業し救済対象となる者が増加した。これらの要因で救済金による国庫負担が重くなったため、英国は「救貧法」をついに改正する。
1834年に制定された「新救貧法」では、救済対象 者を「救貧院内に住む人間」に限定し、救済金額も最下層の労働者の生活レベルを下回るような水準へ引き下げた。
こうした政府の貧困者対応を強く批判したのが、 12歳の時に親の借金で過酷な重労働を経験した英国の小説家チャールズ・ディケンズ※4(1812~1870)である。大ベストセラー小説となった「オリバー・ツイスト」※5(1838)では、実体験から救貧院での過酷な日々やロンドンでの少年犯罪の状況など、当時の英国における社会問題を詳細に描いている。中流階級出身の彼は、一時的に貧困の惨めさを体験したことによって貧困者を支援するようになり、特に貧困学校には寄付金などで積極的に支援した。
ちなみに、この小説を基にしたミュージカル映画「オリバー!」(1968)では、冒頭のマーク・レスターが主演し、アカデミー賞を受賞している。
(3)ようやく教育の重要性を認識する国家
19世紀前半の英国は、国家の中核を担うジェントルマンを対象とした教育に力を入れていたが、社会的にも政治的にも力を持たない民衆に対する教育には関心がなかった。大衆には、働くために必要最低限の読み書き算数と宗教教育で十分であると国家は考えていたのだ。
しかし、ヴィクトリア朝時代(1837~1901)に入り、チャーチスト運動※6などで社会変革を求める人々は、「教育こそ絶対必要な道具であり、教育によって選挙権を賢く行使できるようになる」、そして「教育を受けた働き手がいれば生産性は高まり、国家の経済発展にもつながる」と考え始めた。こうした価値観の変化は、労働者階級の男性への選挙権の拡大だけでなく、英国が1867年のパリ万博で受けた衝撃が大きな要因であった。パリ万博でフランスやドイツなどの他国の躍進を目の当たりにして危機感を持った英国は、大衆への技術教育や知的教育をもっと積極的に実施する必要性を感じ始める。しかしながら、英国にとって大衆への教育の目的は、他国との競争に勝つためであり、国民の幸福を願っての教育ではない。あくまで国家の利益を考えた教育制度であり、国家の支配を維持・強化するための政治的手段であった。
4.マス教育の開始と義務教育への移行
(1)一斉大量教育の「ベル・ランカスター法」採用へ
大衆への教育を本格的に行うには少人数教育では受 け入れに限界があり、19世紀の初めに大量の生徒に一斉に授業を行う「ベル・ランカスター法」が考案された。その開発者が英国国教会教徒のアンドリュー・ベル(1753~1832)であり、提唱者はクエーカー教徒のジョセフ・ランカスター(1778~1838)である。費用を大幅に減らしながらも子供たちに読み書きの基礎学力をつけさせる方法として一挙に英国で広まった。
助教法(モニトリアル・システム)とも呼ばれる「ベル・ランカスター法」の内容は、「一人の教師が、助教生となる大勢の年長の生徒にその日の授業を教え、その助教生たちが、班分けされた年少の生徒を教える」というものだ。ランカスターによれば、「我々の教育方法をマスターした人間が1人いれば500人の児童を教えることが可能であり、生徒一人当たりの費用も1年でたった4~7シリングと安価になる」ということらしい。
その後ほどなく1811年に国教徒、続いて1814年に非国教徒が支援する二つの学校組織網が誕生すると、「ベル・ランカスター法」を利用した学校が次々と建ち始め、無理のない学費で労働者階級が教育を受けることが可能となった。建築費は、裕福な支援者に寄付してもらい、運営費は親から徴収したお金で十分賄えるようになったのである。
(2)社会主義者オウエンによる大量教育への批判
こうした大量教育の学校では、学習効果を出すために生徒の競争心を煽り、処罰により生徒を管理した。 12歳から15歳の助教生の役目の大半は、生徒に教えるだけではなく、大概は生徒を叩く棒を持って規律を守らせることだった。
このことに対して前述のロバート・オウエンは、「大量かつ競争と処罰による教育は、児童の相互不信と分裂を招き、敵対意識を植え込む」と激しく批判した。綿紡績工場主の彼は、自ら10歳未満の児童労働をやめ、1816年にスコットランドのニュー・ラナークに所有する工場内に「性格形成学院」を設立し、労働者の子弟のためにより良い教育環境を作った。彼は、「貧困や犯罪の原因は、個人の能力や資質ではなく彼らを取り巻く環境にあり、社会の改良によって解決すべきものだ。そして、社会の改良の第一歩は教育であり、児童たちの性格をより良いものへ形成していくには、良い環境を提供すべきだ」と考えていた。
(3)民間学校への助成開始から義務教育への道のり
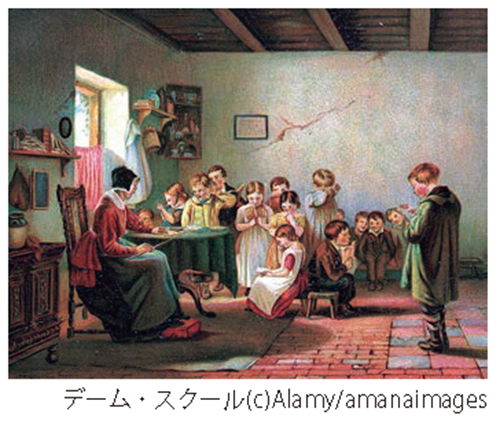 国家は教育の必要性を認識し、まず1833年に民間 の学校建設への国庫補助を始める。その後、校具や教科書など補助対象を拡大していくのだが、予想以上に出費が嵩んで国家財政が悪化した。
国家は教育の必要性を認識し、まず1833年に民間 の学校建設への国庫補助を始める。その後、校具や教科書など補助対象を拡大していくのだが、予想以上に出費が嵩んで国家財政が悪化した。
そこで1862年の改正教育令によって、補助金の使途を確認する教育委員会が設置され、生徒たちの読み書き算数の学力を精査するための試験結果を重視する出来高制度が導入される。定期的な査察と試験結果の良し悪しに基づいて国家からの助成金が増減されるようになったため、助成金が減らされると困る学校側は、生徒の学力レベル向上に必死となった。元々の学校の目的であった宗教教育は二の次となって、落ちこぼれを作らないように全体の学力レベルを底上げすることが学校の主要な目的となったのである。
この結果、宗教色の強かった学校が、学問中心の学校へと転換し、生徒全員の基本的な読み書き能力は向上したのだが、詰め込み教育だった弊害で生徒の創造性は十分育たなかったようだ。しかし、出来高制度による助成金配分を実施することで、国庫負担は大きく軽減されたのである。
(4)義務教育へ移行し、無償公立学校が誕生
1870年に教育法の制定によって、公的教育の基本となる普通初等教育が導入され、5歳から10歳までの公立学校が誕生した。就学者数は1870年の125万人から20年後には450万人へと増加した。
1880年には、5歳から10歳のすべての児童に就学が強制され、違反した場合には罰金を科した。わが子の労働力を頼りにしていた親たちは、学校に行かれると彼らがいなくなり困るので、この法律の制定に反対したようである。
1891年に公立学校での教育が無償化されると、公立学校で教育を受けることが一般的となり、これまで労働者階級が通った民間学校の大半は消えていくことになる。20世紀初頭には就学率は88%に達したが、 1872年の学制から始まったとされる日本の義務教育に比較すると、英国での義務教育の開始は決して早いとは言えないようだ。
(5)小説に見る階級を超えた生徒たちの交流
英国の中核を担うジェントルマンを育成する「パブリック・スクール」と貧しい労働者のための「慈善学校」の間には階級差があるので、通常人的交流はなかったが、パブリック・スクール出身のジェームズ・ヒルトン(1900~1954)が書いた人気小説「チップス先生さようなら」(1934)に、とても爽やかな生徒たちの交流の場面が出てくるので紹介したい。
1890年代にパブリック・スクールに勤務するチッ プス先生の妻キャサリンは、貧民区域にある慈善学校の生徒とのサッカーの招待試合を提案する。当時では過激で前代未聞の提案であり、無謀で危険な試合は教師全員に猛反対される。教師にとって、貧民街の少年たちはごろつき同然の存在であった。しかし、彼女の説得が成功し、試合と夕食会が行われた。慈善学校のチームメンバーを迎えた試合後の夕食会では、階級間を超えて
次回は、ここで名前を挙げた3人の出身校であるオックスフォード大学とケンブリッジ大学を中心に英国の大学と産業革命の関係を辿りたい。
※1 「小さな恋のメロディ」: 1971年の英国映画。メロディはヒロインの名前でもあり、少年少女の恋を瑞々しく描いた。英国とアメリカではヒットしなかったが、日本やアルゼンチン、チリなどラテンアメリカ諸国では大ヒットした。
※2 「コンプリヘンシブ・スクール」: 同一地域内のすべての児童、生徒が無選抜で就学し、普通教育から職業教育まで多様な教育課程を備えた5年間の総合制中等学校(11~16歳)。
※3 「エリザベス救貧法」: 貧民が労働能力の有無によって、「ワークハウスで働かせる有能貧民」、「働けず救貧院に収容される無能貧民」および「扶養する人がいない児童」と分類された救貧政策。治安維持も目的とした。
※4 「チャールズ・ディケンズ」: 英国の小説家。ユーモアとペーソスのある文体で下層市民の哀歓を描き、ヴィクトリア朝時代を代表する作家。代表作は「オリバー・ツイスト」「クリスマス・キャロル」「二都物語」「大いなる遺産」など。
※5 「オリバー・ツイスト」: ディケンズの長編小説。救貧院で虐待されながら育った孤児オリバーは、葬儀屋の徒弟や盗賊団の手下になるが善意を失わず逆境から立ち上がる。救貧院の内情を世に訴えた社会小説。
※6 「チャーチスト運動」: 1830年代後半から始まった英国の労働者階級の普通選挙権獲得運動。名称は、運動の要求書People's Charter(人民憲章)に由来する。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第25回]~2022年8月号
本年7月7日に英国のボリス・ジョンソン首相が一連の不祥事の責任を取って与党・保守党の党首を辞任すると表明した。事の発端は、コロナ禍で厳しい外出規制を要請したにもかかわらず、一昨年の5月以降何度も官邸で大規模なパーティーを開催していたジョンソン首相への国民の怒りである。米国の「ウォーターゲート」事件をもじって「パーティーゲート」疑惑事件と呼ばれている。
ジョンソン首相といえば、ボサボサの髪型がトレードマークで、気さくで親しみやすい印象をもたれているが、実は名門パブリック・スクールのイートン・カレッジを経てオックスフォード大学を卒業した超エリートである。ロンドン市長時代に髪型がきっちりセットされていたので、ボサボサの髪型は庶民性を出すための演出なのだろう。
前々回、前回ではラグビーというスポーツを通してパブリック・スクールの役割を見たが、今回は産業革命と関連付けながら社会的な位置付けを探る。
1.名門パブリック・スクールとは
(1)英国の中枢を担うパブリック・スクールの卒業生
18世紀に内閣制度が始まってから現在に至るまで、 歴代首相の約7割がパブリック・スクール出身者であり、ほかにも判事や軍のトップ層、事務次官クラスの官僚、主要企業のトップなど英国の中枢を担う要人のかなりの部分をパブリック・スクール出身者が占めている。
厳密な意味でのパブリック・スクールは、1869年に設置された校長協議会に属する当時の有名校9校からなるザ・ナイン(The Nine)※1を指すが、その後増加した学校も加えられ、現在では明確な定義はないようである。地理的には、ロンドンやその郊外などイングランドの南部に集中している。
パブリック・スクールに共通する特徴としては次のようなものがある。
①私立の中等教育機関で学費がかなり高額である
②将来オックスフォードやケンブリッジなどの名門大学に進学していくエリートを輩出する
③多くの学校が寄宿制で英国全土から生徒が集まる
④古い歴史と伝統がありマナーや礼儀が重視される
⑤クリケットやラグビーなどスポーツが盛んで、フェアプレイ精神やスポーツマンシップが重視される
⑥多くの学校が郊外の広大な敷地に建つなど恵まれた環境にある
⑦上下関係が厳しく、細かい校則があり、将来支配層として必要となるリーダーシップが寄宿舎生活の中で鍛えられる
⑧ラテン語などに代表される古典の教養科目が多く、かつては上流階級特有の上品な言葉遣いや発音を覚える授業があった
以上のような特徴をパブリック・スクールが備えるようになった背景を紐解いていきたい。
(2)ルーツは、聖職者育成を目的とした学校
パブリック・スクールは、貧しくて授業料が払えない子供たちに主にラテン語を無償で教えるグラマー・スクール(文法学校)として出発した。英仏の百年戦争(1339~1453)やペストの流行で多くの聖職者が亡くなったので、教会が中心となって聖職者養成※2のための学校を設立したのだ。最も歴史が古いのは、1382年創立の「ウィンチェスター・カレッジ」、次いで1440年創立の「イートン・カレッジ」である
その後、1534年にヘンリー8世( 在位1509~1547)の宗教改革によって英国国教会が成立すると、ローマ・カトリック教会からの離脱で多くの修道院が解散、もしくは財産を没収され、修道院や教会に付属していた学校の収入が途絶えてしまった。学校の運営を維持するために、貴族などの上流階級から慈善目的の寄付金を募るのだが、それだけでは資金を賄えず、次第に授業料や寮費を自己負担できる富裕な学生を受け入れるようになる。また、従来の上流階級では家庭教師に子弟の教育を任せるのが一般的であったが、子弟の社会的視野を広めようとして私費で名の知れた学校に入れるようになったこともあり、16世紀頃にはパブリック・スクールが多数創立された。
(3)19世紀のパブリック・スクールの存在価値とは
19世紀中頃になると、新興ブルジョワジーの台頭 と植民地支配のための官僚・軍人不足から、パブリック・スクールの存在が注目される。

また英国では、植民地が世界各地で急速に拡大していたため、派遣する官僚や軍人の数が、上流階級の子弟だけでは足りなくなっていたので、ジェントルマンとして修業中のアッパー・ミドル階級の子弟をその補填に充てようとした。そして植民地インドのように母国から遠く気候的にも厳しい環境の中でも耐えることのできる官僚や軍人が、パブリック・スクールで養成されたのである。
教育の目的には、ジェントルマンの素養だけでなく、官僚や軍人に求められる強靭な精神と頑強な肉体をもち、リーダーシップや決断力のある人間を育成することも求められるようになった。ちなみにハロウ校を卒業したウィンストン・チャーチル元首相(1874~1965)は、1896年に軍人としてインドへ派遣されている。
(4)生徒への厳しいスパルタ教育とその意味
軍人を養成するためか、19世紀初期のパブリック・スクールでは「鉄は熱いうちに打て」とばかりに徹底的にスパルタ教育がおこなわれた。学校生活では禁欲と抑圧が徹底され、精神的にも物質的にも大変つらいものであったが、ここでの過酷な生活に耐え忍ぶことができれば、卒業後には大概の難事は乗り切ることができるようになると考えられていたようである。
「ワーテルローの勝利は、イートン・カレッジの校庭で獲得された」という有名なウェリントン公(1769~1852)の言葉は、ナポレオン戦争で英国がフランスに勝利した際に述べたとされるが、まさにパブリック・スクールでの厳しい鍛錬を象徴する言葉であろう。
そして、パブリック・スクールを卒業し、ケンブ リッジ大学やオックスフォード大学に進学すれば、ジェントルマンとして扱われるので自由で豊かな生活が満喫できた。
(5)死語となったラテン語を学ぶ意味とは
パブリック・スクールでは歴史の古い学校ほど古典を重視し、ラテン語が必修科目となっている。古代ローマ人が使った言葉であるラテン語は、中世から近世にかけてヨーロッパの知識階級の共通語となっており、西洋文化を学ぶには欠かせない言語である。ヨーロッパで語り継がれる神話や17世紀に書かれたトマス・モア、コペルニクス、フランシス・ベーコン、デカルト、ニュートンなどの論文もすべてラテン語で書かれている。また、シェイクスピアをはじめとする文学にも頻繁にラテン語が出てくる。ラテン語を学ぶことは、文化、歴史、哲学、アートを学ぶことであり、複雑な文法をもつラテン語は、論理的思考力の訓練となるそうだ。ラテン語を必修科目とすることで、生徒たちに西洋文化を継承していく者としての自覚を促している。ジョンソン首相は、オックスフォード大学の古代ギリシャ語、ラテン語専攻である。また、後に名文家と言われるハロウ校時代のチャーチル元首相は、ギリシャ語、ラテン語が苦手だったので、それらの宿題はすべて悪友に頼む代わりに、得意の英作文の宿題については、悪友の分も引き受けていたそうである。
2.パブリック・スクールにおける教育の変化~体罰からスポーツ教育重視へ~
(1)教師の権威を維持する体罰の意味とは
英国には、「Spare the rod and spoil the child(鞭打ちの労を惜しめば、子供をだめにする)」という英語のことわざがある。旧約聖書には、「教育とは、何よりも、まず懲らしめよ」とばかりに体罰を肯定化する

パブリック・スクールを舞台とする小説や映画には、必ずと言ってよいほど体罰のシーンが出てくる。上流階級やアッパー・ミドル階級の生徒たちが、自分より低い階級に属する校長や教師を見下して指導に従わないという風潮を是正する意味でも、パブリック・スクールでの体罰は、生徒に対する彼らの権威を強化するものであった。集中力と注意力を高める効果があるとして、生徒が誤答しただけでも体罰を与えた。
(2)生徒が恐怖する理不尽な鞭打ちとは
チョコレート工場の秘密」で有名なレプトン校出身の小説家ロアルド・ダール(1916~1990)※5は、自伝「少年(Boy: Tales of Childhood)」(1984)の中でパブリック・スクールの校長から受けた体罰で「一生残る恐怖を植え付けられた」と述懐している。
ダールは、試験中にペンが折れて、隣の生徒にペン先を借りようとしたのを教師からカンニングしたと
理不尽な話ではあるが、生徒にとって恐怖であった体罰制度によって学校の規律が守られ、教師の権威も維持された。
(3)アーノルド校長によるスポーツ教育への転換
前々回でラグビー校の校長トマス・アーノルド(1795~1842)を取り上げ、1830年代のいじめが横行する学内の状況を改革する様子を書いた。学校に秩序と規律を戻すために、彼は生徒たちに社会的な義務、責任、奉仕の精神を説き、人格教育にも力を注いだ。それと同時に「健全な精神は健全な肉体に宿る」として、ラグビーなどの団体スポーツを通じてスポーツマンシップ、フェアプレイ精神を学ばせた。人気小説「トム・ブラウンの学校生活」(1857)に実在のモデルとしてアーノルド校長が登場したこともあり、彼の教育改革は他のパブリック・スクールにも広がっていった。英国に染み込んだ体罰の習慣は続くものの、パブリック・スクールは徐々にスポーツ教育に重点を移していくことになる。
(4)フランス教育への失望と英国教育への憧れ
このようなパブリック・スクールでのスポーツ教育に着目する人物がフランスに現れる。クーベルタン男爵※6ことピエール・ド・フレディ(1863~1937)である。ナポレオン戦争のワーテルローの戦い(1815)で英国に、普仏戦争(1870~1871)でプロシアに負けたフランスでは、敗戦続きで沈滞ムードが蔓延していた。また、その頃のフランスの教育では、独創性よりも知識の豊富さが重視されていた。
貴族の三男に生まれたクーベルタンは、1880年に当時の貴族のエリートコースである士官学校に入学するが、肌が合わず数カ月で退学してしまう。新たに自分が目指すべき道を見つけられず悩んでいたところ、人気小説「トム・ブラウンの学校生活」の存在を知り興味を持つ。この小説を読んだ彼は、英国パブリック・スクールでの教育方法に衝撃を受け、フランスの教育を知識偏重から心身を鍛えるものへ改革しようと決意する。1883年に若干20歳の彼は自費で初めて英国に渡り、イートン・カレッジやハロウ校、ラグビー校などのパブリック・スクールを視察に行く。
(5)英国の教育に魅了されるクーベルタン男爵
パブリック・スクールの視察では、学生たちが積極的に、かつ紳士的にスポーツに取り組む姿を見て感銘を受け、元々は大の英国嫌いだった彼は、
(6)日本にも進出する名門パブリック・スクール
いまだに階級社会が色濃く残る英国では、オックス フォード大学やケンブリッジ大学の卒業生である以上に、名門パブリック・スクール出身であることが重要視される。そして、特権的な性格をもつ名門パブリック・スクールは、近頃世界の富裕層をターゲットに海外校を増やしており、日本では、英国の名門パブリック・スクールであるハロウ校が本年8月に岩手県に、そしてラグビー校が2023年には千葉県に進出する。
ハロウ校の姉妹校である「ハロウ
ラグビー校の日本校となる「Rugby School Japan」は、千葉大学柏の葉キャンパス内に開校予定で、寄宿と通学が選択できる。750名の男女生徒を募集する予定で、小学6年生から高校3年まで7年制の教育をおこない、卒業後は海外の大学を目指す。ラグビー校にとってタイに続く海外2校目となる。
高額な学費ながら、こうしたパブリック・スクールの充実した設備、グローバルで質の高い教師陣による授業内容は、日本の富裕者層に魅力となっており、特に全寮制の人気が高いようだ。

次回は、大衆を対象とした公立学校などの状況と産業革命の関係について辿りたい。
※1 「ザ・ナイン(The Nine)」: 厳密な意味での名門パブリック・スクール9校。設立年度が古い順にウィンチェスター(1382年)、イートン(1440年)、セント・ポールズ(1509年)、シュルズベリー(1551年)、ウェストミンスター(1560年)、マーチャント・テイラーズ(1561年)、ラグビー(1567年)、ハロウ(1572年)、チャーターハウス(1611年)の9校であり、オックスフォード大学とケンブリッジ大学への進学者には、これらからの卒業生が多数を占める。
※2 「聖職者養成」: 旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語が原語であるが、古代ローマ帝国の公用語がラテン語だったことから、ローマ・カトリック教会を中心にラテン語訳聖書が用いられた。
※3 「アッパー・ミドル階級」: 中流階級の上層。企業経営者や専門職(弁護士、医師など)、高位聖職者、高級官僚、軍人などをいう。
※4 「ノブレス・オブリージュ」: 身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。
※5 「ロアルド・ダール」: 英国のカーディフにて、ノルウェー移民の両親のもとに生まれた。ブラックユーモアあふれる短編小説、児童文学の書き手。作品は「チョコレート工場の秘密」「マチルダは小さな大天才」「あなたに似た人」など
※6 「クーベルタン男爵」: ピエール・ド・フレディ。フランスの教育家であり、古代オリンピックの復興を提唱し、1894年国際オリンピック委員会(IOC)を組織、1896年に近代オリンピック第一回大会をアテネで開催した。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第24回]~2022年7月号
19世紀の文豪オスカー・ワイルド(1854~1900)※1は、ラグビーとサッカーについて「ラグビーは紳士
(gentlemen) がプレイする野蛮人(barbarian) のゲームであり、フットボール(サッカー)は野蛮人がプレイする紳士のゲームである」と評した。両者は一見全く別のスポーツに見えるが、実は源流を同じくする似た者同士なのである。
前月号は、ラグビーのルーツである「民俗フットボール」の成り立ちから衰退、そして「名門パブリック・スクールでのフットボール」が下級生いじめの温床からスポーツ教育の手段となるまでの歴史を辿った。
後半となる今回は、各パブリック・スクールでの ルール作りがきっかけとなってフットボールが現在のラグビーとサッカーに分かれていく過程を辿りながら、英国の産業革命がラグビーを中心として近代スポーツや社会に及ぼした影響を探りたい。
1.フットボールからラグビーへ
(1)フットボールのさまざまなルール
パブリック・スクールで行われたフットボールは、学校ごとにルールが異なっており、19世紀の中頃にはラグビー校の「ボールを持って走ることを認めるもの」とイートン・カレッジの「キックがプレイの中心で、ボールを持って走ることを認めないもの」に大別された。背景には、旧来の支配者層である貴族やジェントリー※2などの「上流階級」と産業革命で急激に勢力をもち始めた「アッパー・ミドル階級※3」との間で生じていた対抗意識がある。上流階級の子弟を主とするイートン・カレッジなどの「名門パブリック・スクール」は、アッパー・ミドル階級の子弟を主とするラグビー校などの「中堅パブリック・スクール」と同じルールを適用することを嫌がった。
当初ラグビー校では、フットボールのルールブックがなく、ルール上での揉め事が生じるとその都度上級生の総会で議論や論争が行われたのだが、生徒が増加しルールが複雑になったので、1844年に最終的なルールを協議するための委員会が設置された。ルール編成委員として3人の生徒が選ばれ、37条からなる 20ページのルールブックが1845年に初めて作成された。ルールブックといっても、実際にはゲームのプレイ方法を説明したものでなく、ゲーム中にしばしば争いとなるような事項に対する裁定方法を規定したものであった。
1847年には、イートン・カレッジでも独自にフットボールのルールが成文化されたが、これはどちらかといえばサッカーのルールに近かったようだ。現在のラグビー・フットボールでは、ボールをキックする際に左右のゴールポストの間のクロスバーの上を越えなければ得点にならないが、イートン・カレッジのルールでは逆に、現在のサッカー同様にキックしたボールは左右のゴールポストの間のクロスバーの下を通らなければ得点にならなかった。
ケンブリッジ大学でも1839年にラグビー校のOBが、最初のフットボールチームを組織したが、その後さまざまなパブリック・スクール出身者が加わったことから、1848年には大学独自の「ケンブリッジ・ルール」が制定された。どこのパブリック・スクール出身者でも一緒にプレイできるように、大学内だけで通用するルールを作ったのである。
(2)フットボールの人気の盛り上がりから対抗戦へそして、共通ルールの制定に向けたFAの結成
ナポレオン3世(1808~1873)統治下のフランスに脅威を感じた英国では、1859年にライフル義勇軍運動が始まり、愛国心から多くの若者が参加していた。フランスの脅威が去ると義勇軍の活動にスポーツが加わり、肉体の鍛錬にもなるフットボールが積極的に取り入れられた。その頃の英仏の敵対関係がフットボールの人気を押し上げたのだ。
また、1857年に発刊された小説「トム・ブラウンの学校生活※4」が大人気となったおかげで、フットボールは小説の舞台となったラグビー校だけのものではなく、英国中の若者を興奮させるスポーツとなり、そのブームはパブリック・スクールや大学に加えて、社会人※5にも拡がっていった。19世紀後半に設立された多くのパブリック・スクールでは、人気小説の絶大な効果でラグビー校方式のフットボールが採用された。
その後、各パブリック・スクールでは、主流であったラグビー校のルールを導入しながらも、独自に修正・変更が加えられた。ルールの変更の中で共通して最も多かったのが、ブーツのつま先で相手チームの向う脛を意図的に蹴る「ハッキング(hacking)」の禁止であった。当時、ハッキングは勇敢さや男らしさの表れとして認められていたが、危険なので怪我防止の脛当てを付けて試合に臨むチームもあったようだ。

そうなると「ホームで勝ち、アウェイで負ける」という試合結果が多くなり、統一ルール制定の機運が高まるのである。1863年にロンドンを本拠地とする 11のクラブが中心となって、「フットボール・アソシエーション(FA)」を結成し、共通のルールを作成するため、その年のうちに6回の会議が行われた。
(3)FAでのハッキングを巡るルール制定の攻防
出身校それぞれに自校のフットボールにプライドがあり、FAでのルール制定は紛糾した。「ボールを持ったまま走ること」や「脛を蹴るハッキング」などが大きな争点となり、議論は平行線を辿った。特にハッキングの禁止を巡って、ラグビー校OBを中心とした容認派が「ハッキングを禁止すればフットボールの勇敢さを失い、軟弱で意気地のないフランス人のチームにさえも負けてしまう」と声高に訴えると、それに対抗してイートン・カレッジやハロー校などの名門校OBを中心とした禁止派は「思慮分別のある紳士はハッキングのような危険な行為をしない」と異議を唱えた。
当初の会議では委員の大勢を占めるラグビー校OB を中心とした容認派が優勢であった。しかし、ハッキングの禁止を唱えるイートン・カレッジやハロー校などの名門校OBが委員として参加し、彼らが議論をリードするようになると、ハッキングを容認するラグビー校OBの委員は劣勢となっていく。
4回目の会議では、ハッキングを容認するかどうか の最終決着をつける決議が行われ、ハッキングを認める案が1票差で一旦採択されたのだが、ヨークシャー地方ハル出身の弁護士でFA書記のエベニーザー・モーリー(1831~1924)が、ハッキングの禁止を盛り込んだ最新のケンブリッジ・ルールを支持する動議を提出すると会議は混乱に陥り、結果的に何が決議されたかがうやむやになってしまった。
5回目の会議では、ラグビー校OBを中心としたハッキング容認派6名が欠席なのを好機と捉えたモーリーは、勝手に前回の決定を議事録から削除し、同じく禁止派の書記オールコックが、「ハッキングを認めるルール」を削除する動議を提出し、決議される。このような露骨な工作にラグビー校OBを中心とした容認派は怒り、6回目の会議をボイコットするが、モーリーとオールコックによって提示されたルール案は正式に承認された。これによりラグビー校OBを中心とするハッキング容認派は脱退することとなった。
(4)ハッキングへの批判の高まりとRFUの誕生
1870年、ザ・タイムズ紙に「ラグビー校のフット ボールで多発するハッキングによる負傷」に苦言を呈する投書が掲載されると、ラグビー校式フットボールに更なる逆風が吹いた。ラグビー校の在校生とOBはともにハッキングを擁護するために立ち上がるのだが、ラグビー校の校医ロバート・ファーカーソンがザ・タイムズ紙に対して「ラグビー校での試合中に少年1名が死亡した」ことを認めてしまったので、世間の非難の的となってしまう。実際の死因は、ハッキングではなく他のプレイヤーとの激突によるものであった。
そうした向かい風の中で、ラグビー校方式の支持者たちの間で統一ルールを制定する動きが出てくる。 1871年にラグビー校のプレイ・システムに基づくルールブックを作ることを目標として、「ラグビー・フットボール協会(RFU)」が結成される。21のクラブを代表する32名が会合に出席し、半年足らずで59カ条からなる新ルールが作成された。現在のラグビー・フットボール(以下ラグビーと称する)の誕生である。そして、ラグビーへの批判に応えて、あれほど固執したハッキングを反則とし、さらに競技用靴に突き出る釘や鉄板などを取り付ける危険行為も禁止した。
RFUの委員会は、イングランド南東部で専門職に就 くアッパー・ミドル階級から選ばれ、14名全員が20歳から29歳のパブリック・スクール卒業生で、うち6名がラグビー校出身であった。彼らは、ヴィクトリア朝中期に現れた若きジェントルマンであり、英国の産業革命下の最盛期を牽引する人々である。1875年には会員のクラブ数が113と当初の5倍に増加しており、ルールの統一は、多くの参加者を生み出すとともに、参加者の数によって社会的な力をもつようになった。
(5)労働者の参入とRFUのアマチュアへの固執
1880年代初めには、ラグビーはパブリック・ス クール出身者だけでなく、港湾労働者、非熟練工、工場労働者から医者、弁護士、金融家まで幅広い階層を魅了した。イングランドでは、各地の多くの職場やコミュニティ、パブ、教会などでクラブが結成され、州杯争奪戦の増加で更にその人気に拍車がかかった。こうした中で、労働者階級から才能ある若者が選手として登場する。当初RFUは、ラグビーによる道徳教育を提供できる良い機会として労働者階級の参加を歓迎したが、労働者階級の観衆が増えるにつれて、相手チームへの下品な野次が多くなり、アッパー・ミドル層の伝統的なラグビー愛好者は、これらの振る舞いに強い嫌悪感を持つようになった。
また勝利にこだわるクラブでは、ゲームに勝つために労働者階級の優秀な選手が不可欠であったので、彼らはクラブの要請で工場などの仕事をわざわざ休んでゲームに出場していた。産業革命以降は、工場などで働いた時間に基づいて労働の対価である賃金が決められる仕組みとなっているので、当然仕事を休むとその分の報酬が消え、労働者階級の選手は生活に困ってしまうのだが、アマチュアの身分では、ラグビーで報酬を得ることは禁止されており、クラブは表立って支払うことはできない。そこでクラブが秘密裏に報酬を支払う方法として、実際には仕事がないような閑職などを彼らに提供するようなケースが横行した。
しかし、あくまでアマチュアにこだわるRFUでは、この状況に危機感を覚え、1886年ついに、現金・現物給与を問わず選手への報酬支払禁止を決めた。RFUは労働者階級出身選手の大量流入を食い止めるために、ラグビーを完全にアマチュアのスポーツとしたのだ。違反と判断された場合には、対象の選手は出場停止もしくはラグビー界を追放された。
(6)プロ選手への報酬を巡ってNRFUの誕生
労働者階級の選手や観客が多いイングランド北部では、ヨークシャーとランカシャーに膨大な数のラグビー・クラブがあり、1895年には416のシニア・クラブの48%を両地域のクラブが占めた。圧倒的多数派の彼らは、ラグビー選手がその才能で報酬を得ることを認めてほしいとRFUに要求した。しかし、「ラグビーはパブリック・スクールの価値観を共有する若者のためにある」との信念をもつRFUは、報酬なしのプレイを変える気はなかった。1891年には、イングランド北部のクラブ元代表で理科教師のジェイムズ・ミラーが、ラグビーをするために失う労働時間の休業補償をRFUに打診する。「すでに大衆のスポーツとなったラグビーをプレイする労働者が、ゲームへの出場のために仕事を休んでもその時間相当分の報酬をクラブから受け取れないのは不公平である」とRFUに訴えたが、RFUに妥協する気はなく、ミラーの提案は一蹴された。その後2年間両者の間で紛争が続き、1893年にRFUの年次総会で、「アマチュアだけで構成されたクラブのみがRFUの会員となることができる」という提案が承認されると協会の分裂が決定的となった。
1895年に北部の22クラブを中心に「ノーザン・ラ グビー・フットボール・ユニオン(NRFU)」が結成され、休業補償だけでなく1898年にはプロ化が正式に認められた。ラグビーは、階級の争いによって分裂し、「ジェントルマンたちのRFU」と「労働者たちの NRFU」となった。
2.サッカーに発展したFAのフットボール
一方、ラグビー校OBを中心とするハッキング容認派が脱退した後のFAは、わずか10クラブの加盟でスタートした。ルール制定で紛糾し妥協の産物として生まれたFA方式は最初の頃にはあまり人気がなかったのだが、上流階級を中心とする名門イートン・カレッジやハロー校の卒業生が、労働者にフットボールを指導したことで、各地に労働者を中心としたクラブが結成された。彼らは、キリスト教の立場から「飲酒や賭け事といった悪弊を断ち切り、体を鍛えて健康にもなる」余暇活動を労働者に啓蒙するために、のちにサッカーとなるFAのフットボール(以下サッカーと称する)を利用していたのである。
さらに、工場法の制定で19世紀後半から土曜日が半日休みになり、その余暇を過ごす手段としてサッカーは大人気となった。サッカーが13条のルールしかない単純なもので、ボールとグラウンドさえあればお金をかけずに簡単にできたことも普及に寄与した要因だろう。
また、1885年にプロ選手を公認したことで、労働者階級の多い工業都市のプロチームがあっという間にサッカー界を支配するようになっていた。プロ化がその後のサッカー人気に拍車をかけ、英国の国民的スポーツとなり、観客も含め世界の人気スポーツとして広がった。FAの加盟クラブ数も急増し、1888年には 1000を超え、1905年には1万を上回った。
3.近代スポーツとプロ化の功罪
労働者階級の参加とプロ化への対応の違いは、ラグビーとサッカーにおける人気に大きな差をもたらした。RFUが頑なにプロ化を拒絶した理由は何だったのか。貴族などの上流階級が多いFA上層部は、労働者階級の動静にそれほど気を留めなかったために、サッカー界はプロ化の進展によって労働者のクラブに浸食されてしまった。

産業革命とともに近代市民社会が形成され、旧来の 上流階級に代わってアッパー・ミドル階級の人々が中心的な存在となると、彼らは「フェア・プレイ」の精神に基づいた社会ルールの遵守を提唱した。ラグビーにおいても、ルールを守るジェントルマンとしての振る舞いを労働者に求めた。同点でも延長戦がなく試合終了と同時に敵味方なくノーサイドとなるラグビーは、あくまでも余暇の楽しみと社交が目的であり、勝敗や賞金を求めるものではなかった。
プロ化を拒否したラグビーは、サッカーと異なり労働者よりも中流以上の人々にファンが多い。観客の層でいうとラグビーは落ち着いた中年以降の男性、サッカーはフーリガンを含む労働者風の若い男性が多いらしい。
一方で、勝利によって賞金が得られるプロ化とス ポーツの商業化が19世紀以降に進んだことで、賞金獲得を第一の目的とする勝利至上主義が蔓延し、スポーツマンシップやフェア・プレイ精神が揺らぎ、ドーピングなどの問題を発生させている。スポーツの本質は遊びだと言われている。人間は遊びの中で人為的に設定した「ルール」という困難を克服することに喜びを見出すようになった。昨今は、プロ、アマチュアを問わず、勝利のためには手段を択ばないという風潮もあるようだが、スポーツ本来の健全な精神を大事にしたい。
また、これまでの経緯により、世界中のサッカーの競技人口が約2億6千万人と世界ランキング上位となった一方で、ラグビーの人気は上昇中ではあるが 1~2千万人ぐらいの競技人口で留まっており、かなりの差がついてしまった。
次回は、クリケットやラグビーの発展に欠かせない存在となり、英国の産業革命を牽引する人材を輩出してきたパブリック・スクールについて、その制度の仕組みや社会への影響を探りたい。
※1 「オスカー・ワイルド」: アイルランド出身の詩人、作家、劇作家。英国伝来の風俗喜劇を復活したことでも知られる。代表作は、戯曲『サロメ』、小説『ドリアン・グレイの肖像』、童話『幸福な王子』など。
※2 「ジェントリー」: 中世後期の英国で下級貴族が地主化して形成した階層。貴族とヨーマン(独立自営農民)の中間に位置し、農業の商品生産化を進めて初期産業資本形成の主役となる。
※3 「アッパー・ミドル階級」: 中流階級の上層。企業経営者や専門職(弁護士、医師など)、高位聖職者、高級官僚、軍人などをいう。
※4 「トム・ブラウンの学校生活」: 1857年に刊行されたトマス・ヒューズ(1822~1896)の人気小説。ラグビーの名前の由来となったパブリック・スクールの「ラグビー校」を舞台として、架空の主人公トム・ブラウンの学校生活を描いた。詳細については前号を参照。
※5 「社会人」: パブリック・スクールのOBが、社会人となっても引き続きフットボールを楽しむためにクラブをつくって、それぞれ母校のルールにしたがってプレイした。これらのクラブは、「オールド・ボーイズ・クラブ」と呼ばれた。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第23回]~2022年6月号
ラグビーというと、1984年に放送された人気テレビドラマ「スクール☆ウォーズ~泣き虫先生の7年戦争~」※1を思い出す。当時、校内暴力が社会現象化
しているなかで、「荒廃した高校に赴任した新米教師が、信頼と愛を原動力に無名の弱小ラグビー部を変革し、数年後に全国優勝を果たすまでの奇跡」を描いた
スポーツ学園ドラマだ。このドラマの影響で、高校ラグビー部への入部希望者が急増した。
ラグビー発祥の英国でも、ラグビーの原型であるフットボールを題材に何度も映画やドラマ化された物語がある。原作となったのは、1857年に刊行されたトマス・ヒューズ(1822~1896)著作の「トム・ブラウンの学校生活」だ。この小説では、ラグビーの名前の由来となったパブリック・スクールの「ラグビー校」を舞台としており、いじめで荒れていた学校が当時のフットボールなどを利用して改革されていく様子が描かれている。
今月と来月は、「ラグビーの歴史における産業革命の影響」をテーマとして、2回に分けて探ってみたい。前半の今月は、「ラグビーの原型である『民俗フットボール』の成り立ちから衰退」、そして「いじめの温床であった『名門パブリック・スクールでのフットボール』の教育的手段への変革」までを辿る。
1.民衆が歓喜する民俗フットボール
(1)フットボールに対する誤解
キックを中心とする「サッカー」に対して、ボールを持って走ることができる「ラグビー」は、全く別物のスポーツのように思えるが、ルーツはともに同じ「民俗フットボール」である。
おのおのの正式名称は、「ラグビー」が「ラグビー・フットボール(Rugby Football)」、「サッカー」※2は「アソシエーション・フットボール(AssociationFootball)」である。「サッカー」は、正式名称を短縮したもので、欧州や南米では単に「フットボール」と呼ばれている。アメリカや豪州で「サッカー」という呼び名が普及したのは、「アメリカン・フットボール」※3、「オーストラリアン・フットボール」※4との混同を避けるためである。「フットボール」には、足を意味する単語「フット(foot)」が含まれているので、足を使う「サッカー」をイメージしやすいが、ルーツとなる「民俗フットボール(Folk Football)」は、ラグビーのように手も足も使うものであった。
(2)民俗フットボールの起源と宗教との関連性
民俗フットボールの起源は明確でなく、昔から球状のものを使った遊びは世界各地で見られる。1世紀末から5世紀初めのローマ軍が英国のグレート・ブリテン島を支配した時代には、兵隊の肉体を鍛える軍事訓練としてボールを掴んでゴールラインの向こうへボールを運ぶ乱闘「ハルパストゥム」※5が奨励された。やがて、それが大衆に広まり、村の遊び、お祭りといった娯楽に発展するのであった。
13、14世紀には、こうした娯楽が英国各地で行われ、一般に民俗フットボールと呼ばれるようになった。村同士の対抗戦となることが多かったようだが、
「ボール※6を決められた地点まで運ぶ」という以外は定まったルールもなかった。
「民俗フットボール」の開催は、主にキリスト教の「告解※7(懺悔)の火曜日」に行われた。翌日は「灰の水曜日」※8と呼ばれ、復活祭(イースター)の準備期間40日間を意味する四旬節の初日である。その日から長く辛い断食生活がスタートするので、その前日である「告解の火曜日」は、民衆が羽目を外して喧嘩沙汰を起こしても許容された。いつもは口うるさい教会もこの日は無礼講として目をつぶったので、若者たちにとっての「民俗フットボール」は、共同体における仲間の交流、仕事の息抜き、気晴らしとして絶好の機会であった。
「フットボール」という言葉が記載された最も古いものは、1314年にロンドン市長のニコラス・デ・ファーンドンが布告した「フットボール禁止令」だと言われている。これは民俗フットボールを原因とする騒乱を未然に防止するために、「ロンドン市内でフットボールをおこなった者は投獄する」というものだ。エドワード2世(在位1307~1327)が、自分の遠征中にロンドンの平穏が乱されぬように注意せよとロンドン市長に命じたことが布告の理由である。禁止令を出さねばならぬほど、民俗フットボールの人気は高かったという証左であろう。
(3)地域ごとに違う民俗フットボールのやり方

当時の民俗フットボールは、かなり荒っぽく暴力的だったので怪我人が出ることも珍しくなく死亡事故も絶えなかったので、「騒乱」「破壊」「死傷」のイメージが強かった。日本でいえば複数の村が対抗して、人や神輿などが激しくぶつかり合う喧嘩祭りのようなものだったのだろう。産業革命以前には、各地で伝統的に行われていたボール・ゲームを総称して「民俗フットボール」と呼んでいたようだ。
(4)批判・弾圧による民俗フットボールの衰退
社会騒乱を避けるため「フットボール禁止令」が、エドワード3世(在位1327~1377)、ヘンリー5世(在位1413~1422)、エドワード4世(在位1461~1483)らによって公布されたが、教会も「告解の火曜日」以外の祝日や、礼拝をすべき日曜日に開催することには批判的であった。
16世紀後半からは、勢力を強めたピューリタンによって民俗フットボールが厳しく批判されたが、ピューリタン革命(1642~1649)の指導者であるオリバー・クロムウェル(1599~1658)もケンブリッジ大学在籍時には学業よりフットボールに熱心であったらしいので、批判にもかかわらず人気は衰えなかったようだ。
その後、1660年の王政復古の時代には、勢いを失ったピューリタンに代わって、今度は社会改革運動家たちから、「民俗フットボールは時代遅れであり、近代社会の発達を阻害する」と批判され始めた。19世紀になると、治安維持を重視する行政当局も、民俗フットボールへの弾圧を強めた。
また、産業革命による農業国から工業国への転換の中で、囲い込み運動によってこれまで自由に出入りできた共有地や入会地への立ち入りが不可能となり、フットボールをはじめとする伝統的な娯楽の場所が失われ、19世紀の英国から庶民の娯楽としての「民俗フットボール」は消滅していくことになる。
2.フットボールと英国パブリック・スクール
(1)公立ではない「パブリック・スクール」とは
街の空き地から消えた民俗フットボールは、若干形を変えて19世紀のパブリック・スクールの校庭で残った。パブリック・スクールで行われた当初のフットボールは、民俗フットボール同様に暴力的なもので整備されたルールもなかった。プレーヤーが上流階級の子弟ということだけの違いである。上流階級の子弟が、民衆の娯楽を行うことには学校でも批判があったようだが、上級生を中心として
ここで、英国の「パブリック・スクール」について説明したい。パブリック(public)とあるが、英国では公立ではなく、長い伝統を持つ名門の私立中等学校である。生徒は、11、12歳から18歳ぐらいまでが対象で、寄宿学校もあるので、生徒は全国各地から集まった。最も歴史が古いのは、1382年に創立された「ウィンチェスター・カレッジ」で、貧しい家庭に生まれた子弟を将来の聖職者に教育する目的で作られた学校である。次いで、歴史が古いのは、1440年に創立された「イートン・カレッジ」であり、パブリック・スクールの代名詞ともなっている。この2校以外にも多くの学校が16世紀に創立されており、多くは上流階級からの慈善目的の寄付金などで運営され、貧しくて授業料が払えない子供たちを無月謝の給費生として受け入れる学校として出発した。その後、次第に授業料や寮費を自己負担する自費生を多く受け入れるようになり、18世紀後半から19世紀初めには裕福な貴族やジェントリー※9などに加えて、アッパー・ミドル階級※10の子弟が大半を占めるようになった。学費が高くなって、裕福な子弟向けの学校になると、財力や権力をもつ親の力を笠に着た傲慢な生徒が多くなり、自分より低い階級に属する校長や教師を見下して指導に従わないようになった。
校長や教師の権威が低下すると、一部の畏れ知らずの生徒たちが増長して学校全体を揺るがすような大騒動を引き起こした。1768年にイートン・カレッジでは、上級生に「下級生を罰する権利」を認めなかったとして、生徒たちが反抗事件を起こし、商人の息子であった校長は辞職に追い込まれた。1797年にはラグビー校でも、寮内でピストルを使用した生徒への鞭打ち刑に逆恨みした生徒たちが爆弾を使って校長室を破壊、兵士の力を借りて事態収拾を図ったという事件が起きている。当時のパブリック・スクールでは、「喧嘩を自慢する風潮」があり、学外の人々とも平気で揉め事を起こし、殴り合いのけんかで生徒が命を落とす事例もあった。こうした暴力的な環境の中でおこなわれるフットボールは、下級生へのいじめの温床ともなった。
(2)上級生による下級生への制裁手段
当時のパブリック・スクールでは、年長の生徒が学校を牛耳る状況を作り出すものとして、「プリーフェクト(prefect)」制度と「ファッグ(fag)」制度があった。「プリーフェクト」は監督生と訳され、最上級生の中から任命された彼らは、学校の秩序維持のためにさまざまな権限を与えられていたので、校長や教師を凌ぐ権力を持っていた。「プリーフェクト」はウィンチェスター・カレッジでの呼び方であり、他の学校では「プリポスター」や「モニター」とも呼ばれたようである。
一方、「ファッグ」制度は、上級生が下級生に雑用をさせる慣習のことで、下級生は、専属の召使のように靴磨き、部屋掃除、紅茶の準備までさまざまな雑用を上級生から言いつけられた。上級生は、自分の指示に従わない下級生に対して、暴力的な制裁として日常的にいじめや悪ふざけをおこなった。こうした辛い体験をした下級生も、自分が上級生になり下級生に指示する立場となると、憂さを晴らすように下級生をいじめるという悪循環となっていた。
パブリック・スクールの「フットボール」は上級生による制裁手段の一つであり、上級生は強制的に下級生をゲームに参加させた。下級生の役目は、ボールを押し込もうと突っ込んでくる上級生に対してスクラム※11を組んで防御することだが、下級生たちは、上級生から向う脛を蹴られ、服を破かれ、踏みつけにされた。我慢強く勇気があることを賞賛する「ウィンチェスター・カレッジ」のフットボールは、特に乱暴であったらしい。当時、ブーツのつま先で相手チームの向う脛を意図的に蹴る「ハッキング(hacking)」は、勇敢さや男らしさの表れとして認められていたのである。
(3)フットボールを活用したラグビー校の教育改革

改革の一環として寮生活にもメスを入れ、まず寝泊まりするだけの寮を寮監督教師(ハウスマスター)とともに共同生活する場所へと変えた。そして、年長の生徒に学校の秩序を維持することへの責任感をもたせるために、いじめの原因となっていた「プリーフェクト」と「ファッグ」の制度を逆に生徒指導の手段として利用した。上級生の中から「プリーフェクト」にふさわしい生徒を選んで任命し、その責任の自覚を促した。「プリーフェクト」は学内でエリート的存在となり、上級生全体が道徳的な模範を示すようになった。
また、校長は、生徒の所属階級層を変えた。当時産業革命で富裕な商工業者がアッパー・ミドルとして社会的な力をもつようになってきたことから、そうした彼らの子弟の入学を積極的に受け入れ、貴族の子弟の入学を断ったのである。ラグビー校はアッパー・ミドル階級の子弟の学校となり、貴族や上流階級の子弟が多く学んでいたイートン・カレッジとは対照的な存在となった。貴族やジェントリーなどの上流階級たちは、ラグビー校のような教育改革を望まず、従来のイートン・カレッジ方式のような「プリーフェクト」と「ファッグ」の制度こそが、子弟にとって将来必要となる階級間競争のスキルを習得するための格好の制度であると認識していた。
(4)ベストセラー「トム・ブラウンの学校生活」
人気小説「トム・ブラウンの学校生活」は、ラグビー校の卒業生であるトマス・ヒューズが自身の体験(在学1834~1842)に基づいて、架空の主人公トム・ブラウンの学校生活を描いたフィクションである。フランス・ドイツでも翻訳され、映画化もされた。トム・ブラウンが英国名門パブリック・スクールの一つであるラグビー校に入学し、生涯の友やアーノルド校長のような師とのめぐり合いを通して成長し、学校の中心的存在となって卒業するまでが描かれている。
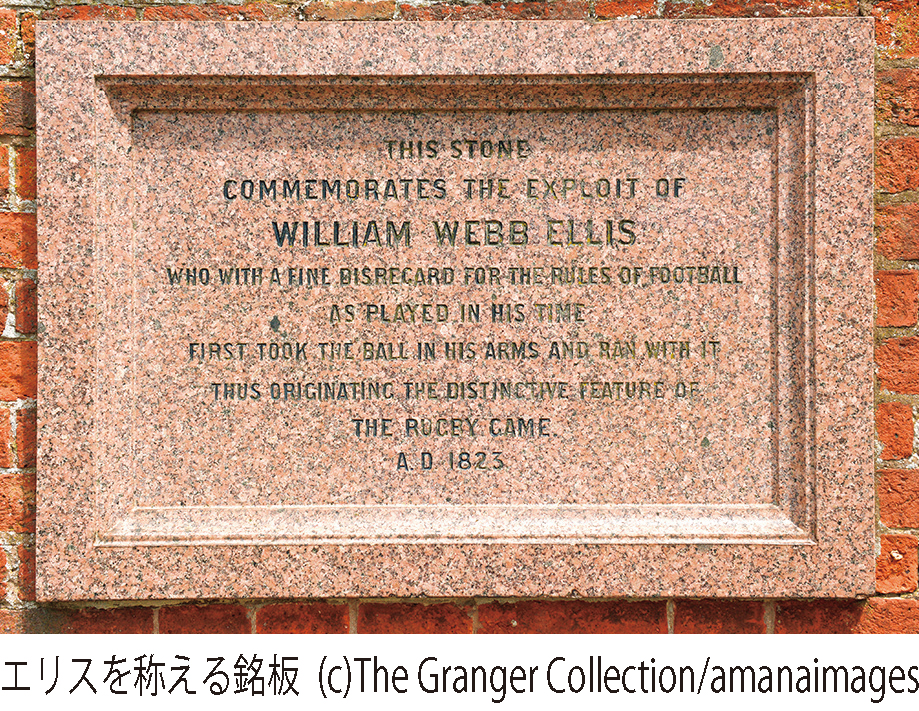
「ラグビー・フットボールは、1823年にラグビー校の生徒であるウィリアム・ウェッブ・エリスが、フットボールの試合の最中に突然ボールを手にもって走り出したことから始まった」とする有名な「エリス伝説」がある。ラグビー校のグランドそばの堀にエリスの功績を称えた記念の石の銘板(1900年に完成)があるので、「サッカーからラグビーが生まれた」ように誤解する人も多いようだ。しかし、もともと手の使用が慣習で認められていたので、少なくともエリスがフットボールで最初に手を使用した人物ではなく、実ははっきりとした根拠のない伝説なのである。事実なのは、1845年に初めてラグビー校がランニング・インをルールとして成文化したことである。しかし、ラグビー校で作られたルールには、競技場の広さやプレーヤーの数、試合時間は一切触れられておらず、スクラムやオフサイド※13の定義も曖昧であった。
後半となる次回は、フットボールがラグビーとなるまでの過程を詳しく辿り、改めて産業革命と近代スポーツの関係を考察したい。
※1 「 スクール☆ウォーズ~泣き虫先生の7年戦争~」: 京都市立伏見工業高校をモデルとして作家馬場信浩氏が執筆した「落ちこぼれ軍団の奇跡」をもとに制作されたフィクションドラマである。
※2 「サッカー(soccer)」: 1880年代にパブリック・スクールや大学で普及し始めた言葉。「Association Football」のAssociationを略したsocにcを重ね、それにerという語尾をつけたもの。erを付けるのは当時の上流階級のスラングの一種。
※3 「アメリカン・フットボール」: アメフトとも呼ばれ、サッカーとラグビーをもとに1870年頃にアメリカではじまった。
※4 「オーストラリアン・フットボール」: 正式名称をオーストラリアン・ルールズ・フットボールといい、クリケット選手がオフシーズンの冬に体力を養うためのトレーニングとして、トム・ウィルス氏が考案し、1858年からプレーされている。オーストラリアでは、最も人気のあるスポーツ。1チームは18人。
※5 「ハルパストゥム」: 「 掴む、奪う」という意味があり、ボールを蹴るより、相手からボールを奪おうとして激しくぶつかりあいながら、奪ったボールを運ぶ。
※6 「ボール」: 当時のボールの仕様はさまざまであるが、当初は、牛や豚などの膀胱がボールとして利用された。
※7 「告解」: キリスト教用語。英語でconfession。カトリック教会ではゆるしの秘跡の第1段階とされ、司祭に自らの罪を明かす行為をいう。最低年1回の告解と秘密の厳守が義務づけられている。
※8 「灰の水曜日」: 四旬節の初日に、前の年の四旬節で使った棕しゅ梠ろの枝や十字架などを焼いて灰にし、その灰を用いて神様に祈るという典礼があったことが由来。
※9 「ジェントリー」: 中世後期の英国で下級貴族が地主化して形成した階層。貴族とヨーマン(独立自営農民)の中間に位置し、農業の商品生産化を進めて初期産業資本形成の主役となる。
※10 「アッパー・ミドル階級」: 中流階級の上層。企業経営者や専門職(弁護士、医師など)、高位聖職者、高級官僚、軍人などをいう。
※11 「スクラム」: ラグビー用語の「スクラム」は、両チームの3人以上の選手が肩を組んで押し合い、足元に入れられたボールを奪い合うもの。
※12 「トマス・アーノルド」: 19世紀の英国において最も偉大な教育家、歴史家とされ、1828年から急逝する1842年までの14年間ラグビー校で校長を務める。
※13 「オフサイド」: ラグビー用語の「オフサイド」とは、いてはいけない場所でプレーをした場合の反則。プレーの状況により、オフサイドラインが定義される。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第22回]~2022年5月号
クリケットは、日本ではあまり馴染みがないが、英国では国技とされ、英国、オーストラリア、インド、南アフリカ、西インド諸島などの英連邦諸国を中心に100カ国以上で親しまれている。日本クリケット協会によれば、世界の競技人口はサッカーに次いで第2位といわれ、日本で人気のある野球よりはるかにメジャーなスポーツである。
特に世界第2位の人口を抱えるインドに愛好者が多く、その普及は、19世紀半ばに宗主国であった英国が植民地インドを統治するために、クリケットをインド人の支配層の教育に導入したことが契機だと言われている。
今回は、貿易面で英国の産業革命の原動力となった植民地インドとクリケットとの関係についてその歴史とともに辿りたい。
1.優雅で複雑怪奇なスポーツ「クリケット」
(1)クリケットの起源と歴史
クリケットの名前は、「バットでボールを叩いた時の音がコオロギの鳴き声に似ている」や「棒切れや松葉杖を表す言葉が元になった」などが語源だと言われている。13世紀頃に羊飼いの遊びとして始まったクリケットは民衆の娯楽であり、貴族などの上流階級からは関心を持たれなかったのだが、17世紀中頃にクリケットの試合を賭けの対象として興味を持つ人々が上流階級の中に現れた。そのうち、彼らは賭博のためだけでなく、自分自身でもプレイを楽しんだり、パトロンとして競技大会を運営したりするようになって、クリケットを上流階級のためのスポーツに発展させた。
まず、1787年に世界最古の会員制スポーツクラブ「メリルボーン・クリケット・クラブ(MCC)」がロンドンに設立された。翌年にはMCCによって公式ルールの制定と世界中のクリケット競技団体の組織化がおこなわれた。当初、権威主義的なMCCは、上流階級のスポーツ「クリケット」に労働者階級を出場させる
ことを快く思わず、「打者は上流階級のみとし、ボールが飛来しないと出番のない退屈な守備は労働者が担う」とするルールを定めたらしい。試合に勝つために、労働者の中からも実力のある選手を参加させたが、更衣室や食堂を別にするなど差別的な扱いをした。
1870年頃から、生活に余裕のある熟練労働者のなかに、クリケットやサッカー、ラグビーなどのスポーツを楽しむ人々が現れて、中部や北部の工業都市で教会や職場を母体とした労働者クラブが生まれると、クリケットが大衆化していった。
(2)クリケットの難解なルール※1
野球の原型とされるクリケットだが、野球のルールに近いと思って観戦すると頭が混乱する。ルールも複雑なので、ここでは野球との違いを中心にクリケットの特徴的なことだけを説明したい。
まず男子の競技場の国際規格は、横約140m、縦約130mの楕円形で野球場より大きい。楕円形の外周を「バウンダリー(境界線)」と呼び、その中央には投球や打撃が行われる長さ約20m、幅2.6mの長方形の「ピッチ」がある。ピッチの両端には「クリース」と呼ばれる「投げる」「打つ」「走る」際の基準となる長方形のスペースがあり、その中に縦棒3本と横棒2本の木で作られた「ウィケット」が立てられる。試合開始にあたって、11人で構成する2チームが、コイントスで攻守の順番を決める。
攻撃側は、2人1組の「バッツマン(打者)」が野球のバットより重い羽子板状のバットをもってピッチに入る。バッツマンの1人が「ストライカー」として「ウィケットキーパー(捕手)」側のクリースに入り、バットを構える。ボールは後方や真横など360度どこに打ち返してもよく、空振り三振もない。「デッドボール」もなく、バッツマンの当たり損である。もう1人のバッツマンは「ノンストライカー」として「ボーラー(投手)」側のクリースにバットか体の一部を入れた状態で次の打撃を待ち、残りの9人はベンチで待つ。
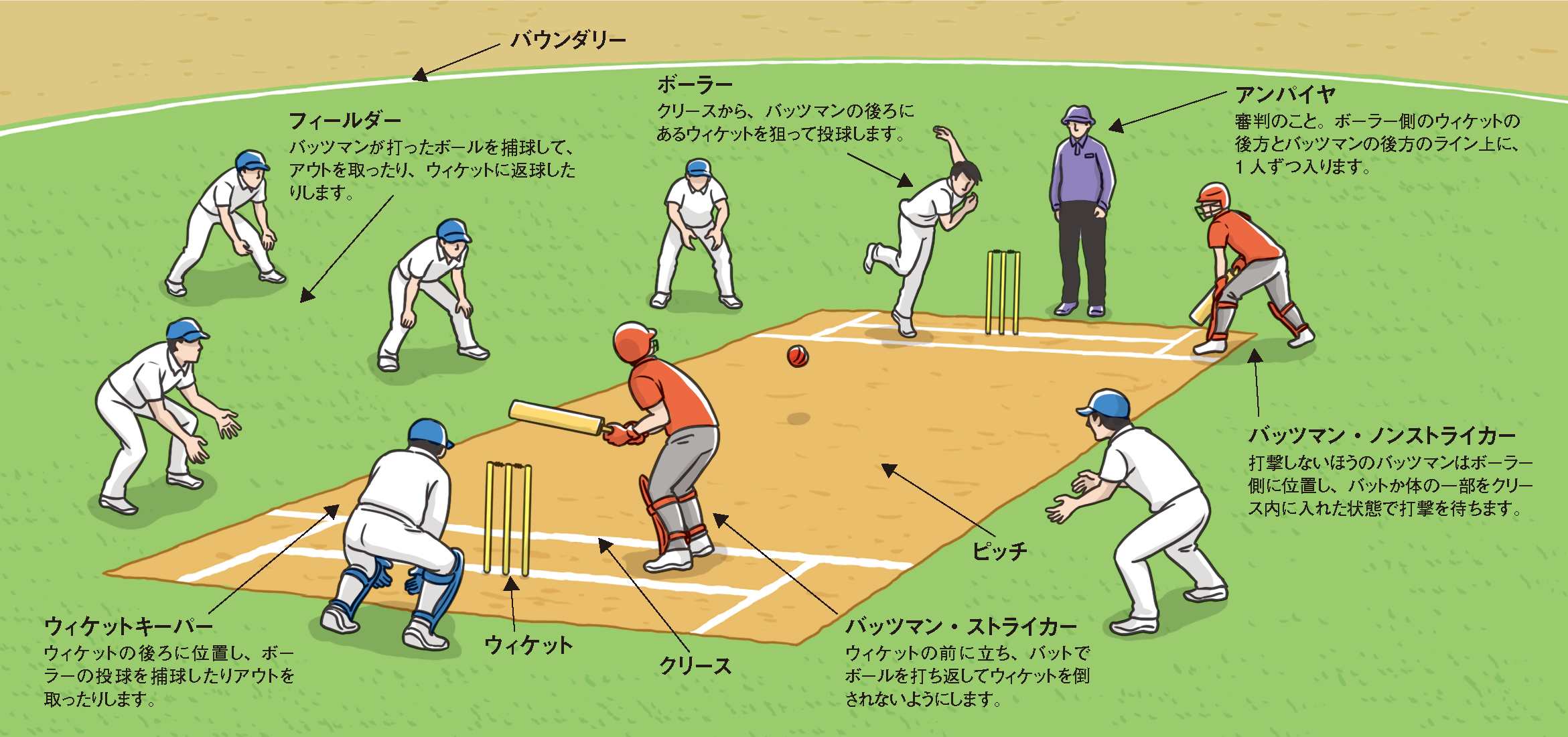
得点が入るのは、「ストライカーがゴロを打ち、打者のストライカーとノンストライカーが同時に反対側のクリースに向かってバットをもって走り、アウトにならずに2人が片道を走ると1点、1往復走ると2点が入る」、「打ったボールがバウンドしてバウンダリーを超えると4点、ノーバウンドでバウンダリーを超えると6点が入る」などの場合である。
バッツマンがアウトになるのは、「フライを打ってフィールダーに直接捕球される」、「ボーラーの投げたボールで直接ウィケットを倒される」、「バッツマン2人が同時にクリース間を走っている最中に、守備側のフィールダーからの送球によって、1人のバッツマンがクリースに着く前にウィケットを倒される」などの場合である。アウトの基準となるウィケットの倒し方は、「直接ウィケットめがけて送球して倒す」、「ウィケット近くの守備側の選手に返球して、その選手がボールを捕球したままの状態で手を使ってウィケットを倒す」の2通りある。ストライカーがゴロを打って反対側のクリースに走っても間に合わずアウトになると判断すれば、バッツマンは必ずしも走る必要はなく、走るか否かの見極めが大事である。また、「ストライカーが足を使って、ボーラーの投げたボールがウィケットにあたるのを防いだ」と審判に判定された場合にはアウトとなる。
1イニングの終了は、「守備側が規定投球数を投げ切る」もしくは「攻撃側から10アウトを取る」かのいずれかである。1イニングが終了すると攻守交代となり、得点の多いチームが勝利となる。
(3)英国人らしい試合途中のランチとティータイム
試合形式には試合時間の長さによって、最も伝統と格式がある最長5日の「テストマッチ」から7時間の「ワンデイ・インターナショナル(ODI)」、3時間の「トゥエンティ・トゥエンティ」、約90分の「T10」まで4つのタイプがあり、規定投球数やイニング数などの違いがある。
現在は、試合時間の短いトゥエンティ・トゥエンティ形式が主流になりつつあるが、長丁場のテストマッチやODIなどの試合では、午前と午後、夕方に2時間ずつ3部に分けて行われ、クリケット選手は1部ごとに休憩をとる。午前の部の後には40分のランチタイム、午後の部の後には20分のティータイムを取り、選手と選手の家族が一緒になってランチやティーをゆったりと楽しむ。こうした優雅さが、誇り高き英国人気質と合うのだろうが、せっかちな日本人気質にあまり向いているとは思えない。
また、クリケットでは公明正大を尊ぶので、反則や判定への異議などご法度である。「ボールを投げるふりをして手元にボールを隠す」ようなフェイント行為はフェアではないとして5点のペナルティを課すルールもあるので、英国では「公明正大にふるまう」ことを「play cricket」と表現するそうだ。1860年代から「健全なる精神は健全なる肉体に宿る」という考え方が拡がったこともあり、男らしさ、忍耐力、協調性、フェアプレイを求められるクリケットの精神は、スポーツマンシップとして、若者の人格形成上において重要な役割を果たすと考えられた。そして、紳士のスポーツ「クリケット」は、英国だけでなく、植民地となったインドでも浸透した。
(4)インドでのクリケット人気とプロ選手の高額年棒
「勉強をすれば王様になれるが、運動にうつつを抜かせば没落する」というインドのことわざがある。インドでは、汗を流し身体を酷使することは、身分の低い者がすることであり、身体を使うスポーツも同類と見做されてしまうらしい。そのため、中産階級以上の多くの家庭で勉学が最優先され、社会の上層になるほど身体を使わない。
スポーツに対する価値観が低いインドにあって、唯一の例外がクリケットである。世界で1、2を争う強豪国のインドでは、クリケットの競技人口が、少なくとも1億5000万人いると言われ、インドの国技であるホッケーを大きく凌ぐ人気がある。クリケットはボールと板と広場があれば、貧困層の子供たちでも、お金を掛けずにどこでも簡単に楽しめる。しかもプロになれば1年間に数億円を稼ぐクリケット選手になれるかもしれない。クリケットのプロ選手になることは、エンジニアや医者と並ぶ憧れの職業なのである。
クリケットが英国からインドに導入されたのは、19世紀後半に英国政府がインドを植民地として統治し始めた時期とほぼ一致している。次項では、まずイギリス東インド会社が登場した頃の英国とインドの関係を辿る。
2.英国と植民地インド
(1)ムガル帝国とイギリス東インド会社による支配
1600年に設立されたイギリス東インド会社は、東南アジアの香辛料をめぐるオランダとの争いに負け、やむなくイスラム系のムガル帝国※2(1526~1858)が多くを支配するインドに向かった。しばらくして人気のあった香辛料の需要が減少し、代わってインド産の綿織物が人気となったことから、英国はその綿製品を売って大きな利益を得る。その後逆に、英国の産業革命の進行とともにイギリス東インド会社によって、英国製の安価な機械織りの綿布がインド国内で販売されると、インド産の手織り製品は競争力を失い、インドの地場産業である綿織産業が衰退してしまう。
ムガル帝国の支配が有名無実化していく中で、イギリス東インド会社は、当初インドを征服して支配するような野心は抱いておらず、あくまで現地で貿易の促進を図り、あらゆる手段を尽くしてインドの富を英国へ持ち帰ることが主眼であった。しかし、七年戦争(1756~1763)で負けたフランスがインドでの力を失う中、1757年の「プラッシーの戦い」※3で勝利したイギリス東インド会社は、ベンガル地方の自由通商権と地税徴収権を獲得し、単なる貿易会社からインドを統治する政治勢力へと変質していく。1833年には、イギリス東インド会社は、商業活動を停止しインド統治を行う機関となる。
(2)セポイの乱と英領インド帝国の成立
イギリス東インド会社のインド人傭兵であるセポイ※4は、海外派兵などで不満が溜まっていた。そこに、新式のエンフィールド銃では薬包に防湿性を持たせるために、牛や豚の脂が使用されているという噂が広まる。薬包を噛めば、そこに塗ってある牛や豚の脂を口に含むことになる。ヒンドゥー教徒にとって牛は神聖な動物であり、イスラム教徒にとって豚は不浄な動物である。信仰を冒瀆されて怒りを爆発させた傭兵たちは、この銃の使用を拒否して武装蜂起をする。これが1857年に起きた「セポイの乱」である。戦いはインド各地に広がり、反乱軍が一時的に優勢となったが、最終的にはイギリス東インド会社の軍隊が辛うじて勝利を収めた。しかし、セポイの乱への対応の拙さを問題とした英国政府は、イギリス東インド会社を1858年に実質的に解散させると同時に、反乱軍の象徴的存在となったムガル帝国の皇帝バハードゥル・シャー2世にも責任を取らせて退位させた。これによりムガル帝国は滅亡し、1877年にはヴィクトリア女王を皇帝とする英領インド帝国が誕生する。
19世紀ヴィクトリア朝の繁栄は、産業革命とともに、植民地インドとインド航路のスエズ運河がもたらしたと言われる。1853年にはインドに初めての鉄道が開通し、英国人が投資して完成したインドの鉄道網は、植民地支配の拠点となる交易都市と綿花地帯を結ぶように整備された。1869年に地中海と紅海を結ぶスエズ運河が開通すると、蒸気船を利用した海運網を通じてインドの富を効率よく運び出して世界に輸出する体制が確立された。
また、当時の英国は、いち早く海底ケーブルを利用した海外との巨大な通信網を拡げており、1866年にはインドでも電信によって英国からの情報がわずか8時間ほどで入手できるようになった。インドに電信が導入されたのは、インドでの「セポイの乱」発生の報告が英国に到着するまでに40日も掛かり、情報の遅れが英国にとって最悪の事態を招いたからである。電信によって英国・インド間の迅速な情報活動が可能となり、英国によるインドの統治に大きく貢献した。
英国は、鉄道投資の利息やインドに駐在する英国人官僚の給料・年金、英国がインドの権益を守るための戦争費用などを「本国費」と称してインドから多額の富を徴収し、大英帝国を築いた。
(3)英国による間接統治のための教育とクリケット
「セポイの乱」による苦い経験から、英国は、インド全域を直接の統治下におくのではなく、旧来の支配者が名目上統治する「藩王国体制」を敷いた。本国から遠く、しかも過酷な気候であるインドを統治するため、必要最低限の英国人で最大の統治能力を発揮させるよう優秀な人材を配置することにしたのだ。広大なインドの政治・経済・社会機構の主幹部門は、「宗主国の英国から派遣された少数精鋭集団※5」と「植民地であるインドの出身者」の共同で統治された。19世紀半ばの旧インドが有する人口約2.5億人に対して、英国人による約1000人の官僚と約6万人の軍人、警察官の人員態勢は十分とはいえず、早急に英国の権益を守ってくれる現地人支配層を生み出す必要があった。
英国人支配者とインドの民衆の間の仲介人となり、英国人と同じ趣味や意見、道徳をもつインド人エリート階層を藩王の子弟から育成するための教育機関としてチーフス・カレッジと呼ばれるインド版パブリック・スクールが設立された。そこでは「英国人たれ」を合言葉に、リベラル・アーツとともにクリケットを始めとするスポーツが人格教育の手段として取り入れられた。
英国人が所属するインドの会員制クラブでも、クリケットが興じられ、メンバーが不足する際には、交友のある上流階級のインド人を参加させた。その後、インド人だけのチームが結成されると、英国対インドの定期戦が始まった。最初の頃にはインドチームは英国
チームに全く歯が立たなかったが、次第に英国チームを負かすようになる。英国人から差別的な扱いを受けているインドの民衆にとって、クリケットでインドチームが英国チームを打ち負かす試合を観戦することは痛快であり、魅了された。インド独立後も、学校や地域のスポーツクラブを通じてクリケットは定着するとともに、さらにテレビ放映の普及によって人気に火がついた。英国がインドへの支配に利用したクリケットは、インド国民の意識を高揚させるものとなった。
(4)英国から見た植民地インドへの目線
英国における当時の考え方の根底には、ヨーロッパ文明の絶対的な優越性とインド社会の後進性があった。野蛮なインドを文明化することが英国人の使命と考え、「ヒンドゥー教とカースト制度※6などによるインドのさまざまな悪弊を正し、インドに平和と幸福をもたらしたのは英国の統治のおかげである」と正当化した。
その一方で、植民地インドの恩恵を失いたくない英国は、インド人の反発が直接自分たちに向かないようにした。インド人同士での支配層と被支配層の対立やヒンズー教徒とイスラム教の宗教上の対立を煽るような分割統治を進めるとともに、インド人支配層の子弟に英国流教育を施した。英国流の教育を受けたインドの上流階級の中に、植民地として英国から多額の富を搾取されたことに反感をもたず、「英国は、インドの悪弊であるサティー※7を廃止し、学校や鉄道を作り、インドの近代化に寄与した」と英国の統治に心酔する人々を創り出した。それほどに教育の持つ影響力は大きい。
今回は、クリケットを通してインドの植民地支配におけるスポーツの役割を取り上げたが、次回は、同じく英国の代表的スポーツであるラグビーについて、パブリック・スクールとの関連性から産業革命に与えた影響を辿りたい。
※1 クリケットのルール: 日本クリケット協会のHPに記載の「クリケット入門ブック」に分かりやすく説明されている。
※2 ムガル帝国: ムガルは「モンゴルの」という意味。
※3 プラッシーの戦い: 1757年に、インドのベンガル地方プラッシーで行われた、イギリス東インド会社とフランス・ベンガル連合軍との戦い。クライブの指揮する英国軍が圧勝し、インドにおける優位を確立する。
※4 セポイ: イギリス東インド会社が組織したインド人傭兵。兵士や軍隊を意味するウルドゥー語の「シパーヒ」が英語訛りでセポイに転化した。
※5 英国がインドに派遣した少数精鋭集団: インドに派遣された著名人には、1896年に将校として駐留したウィンストン・チャーチル(1874~1965)や1906年にインド省の陸軍局下級事務官として赴任した経済学者のジョン・メイナード・ケインズ(1883~1946)などがいる。
※6 カースト制度: ポルトガル語の血統castaに由来。インド社会で歴史的に形成されたヒンドゥー教における身分制度であり、インド では「ヴァルナとジャーティ」と呼ぶ。
※7 サティー: 「 夫の亡骸とともに寡婦が焼かれて死ぬ」というヒンドゥーの慣習で1829年に法的に禁止された。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第21回]~2022年3・4合併号
テニスの世界四大大会の一つ全豪オープンが1月17日から開催された。昨年9月の全米オープン敗退後しばらくのツアー離脱を発表していた日本テニス界の期待の星、大坂なおみ選手が4カ月ぶりに参戦。全豪オープンで2019年、2021年に優勝した実績から今回2連覇が期待されたが、残念ながら3回戦で敗退した。一方、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチ選手にとって、今回の大会は全豪4連覇だけでなく四大大会で史上最多となる通算21回目の優勝がかかった歴史的大会であったが、新型コロナウイルスのワクチン問題から国外退去となり出場できなくなってしまった。
テニスの四大大会は、全豪オープン(毎年1月開催)、全仏オープン(同5月~6月開催)、英国のウィンブルドン(同6月~7月開催)、全米オープン(同8月~9月開催)を指すが、最も長い歴史を持つのが1877年に第1回大会が開催された英国のウィンブルドン大会であり、天然芝コートが使われている。
今回は、英国のウィンブルドン大会が四大大会で「テニス大会の代名詞」として別格扱いされている背景とともに、テニスというゲームの変遷と、ラケット、ボール、ネットなどの道具の進化について産業革命という視点から辿りたい。
1.テニス発祥の歴史(紀元前~1800年)
(1)フランスで生まれた「ジュ・ド・ポーム」
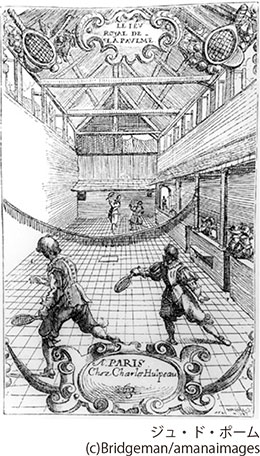 ボールを打ち合う姿が、紀元前15世紀のエジプトの壁画に描かれているそうだ。諸説あるが、テニスの原型となるのは、11世紀頃のイタリアなどの地中海諸国やペルシアで貴族や聖職者がおこなっていた「手を使ってボールを打つ」競技だったと言われる。
ボールを打ち合う姿が、紀元前15世紀のエジプトの壁画に描かれているそうだ。諸説あるが、テニスの原型となるのは、11世紀頃のイタリアなどの地中海諸国やペルシアで貴族や聖職者がおこなっていた「手を使ってボールを打つ」競技だったと言われる。
その後、同じような競技が12~13世紀のフランスの修道院で考案され、フランス語で「手のひらの遊戯」を意味する「ジュ・ド・ポーム」※1と呼ばれた。定義としては、「一個のボールを追いかけ、打ち返す、一人または数人でできる運動遊戯」ということらしい。
フランスでは、1230年に最初の屋内競技場が作られると王侯貴族や聖職者の間で流行となり、屋外・屋内を問わず至る所で行われ、あらゆる階級で人気となった。16世紀頃に絶頂期を迎えて以降、庶民の娯楽としては陰りを見せるものの、王侯貴族の中では引き続き16世紀の終わりまで盛んであった。最も熱心でプレーの上手な国王はアンリ2世(在位1547~1559)であったと言われる。
※1 ジュ・ド・ポーム(jeu de paume): フランス語でjeuが遊戯、paumeが手の平を意味する。
(2)「ジュ・ド・ポーム」が英国で「リアル・テニス」に
その後「ジュ・ド・ポーム」は、フランスと結びつきの強かったスコットランドを通じて14世紀中頃のイングランドへ持ち込まれ、テニス(tennis)と名前を変える。この語源は、フランス語の掛け声を意味する「tenez」※2が、その後訛って「tennis」※3となったという説が有力である。フランス人がサーブを行う際の掛け声を英国人がゲームの名前と聞き間違えたということらしい。
すぐに英国でも流行となり、百年戦争(1337~1453)の頃にはテニスにうつつを抜かす兵士が増えた。兵士を戦争の訓練に集中させたい国王は、「路上球戯の禁止令」を公布したそうだ。
当時、さまざまなタイプのテニスがあったようであるが、屋内でも屋外でも壁を利用したものが人気であった。特に王侯貴族の間では、豪華な造りの屋内で行う「リアル・テニス」に人気があった。これは、フランスの「ジュ・ド・ポーム」を引き継ぐもので、現代テニスとはかなり異なっており、19世紀以降は現代テニスと区別するために「リアル・テニス」※4と呼ばれている。現在のスカッシュ競技に似たもので、4面の不規則な壁を利用して打ち合うものである。「リアル・テニス」用の屋内コートの建設には、ボールが跳ね返るための約7mの高い壁が必要だったので莫大な費用が掛かった。また、構造上観客席※5が30名ほどしか設置できなかったので、興行収入は期待できなかった。このように屋内コートの建設・維持管理には相当な財力が必要だったので、「リアル・テニス」愛好者の中心は当然ながら王侯貴族となった。スポーツ万能の英国国王ヘンリー8世(在位1509~1547)もこのスポーツを愛好し、1528年からハンプトン・コート宮殿の敷地内に建設された屋内コート「ロイヤル・テニス・コート」でプレーした。熱心な彼は当時高価だった競技用のシューズを何足も履きつぶし、しかも競技者同士で勝敗に大金を賭けていたようだ。
※2 tenez: フランス語で「取ってくれ」、「いくぞ」という意味の掛け声。英国の文献では1400年頃に英国の詩人ジョン・ガワー(1330~1408)がヘンリー4世に捧げた詩「平和の賛美」に初めて現れた。
※3 tennis: 1600年頃に執筆されたシェイクスピアの「ハムレット」の2幕1場のオフィーリアの父親ポローアニスの台詞の中に初めて現れた。
※4 リアル・テニス: 1908年開催のロンドン・オリンピックで唯一公式競技として認められた。現在も欧州を中心に続けられている。
※5 リアル・テニスの観客席: 三方の壁面に沿って取り付けられた庇の下の狭いスペースに観客席が設置された。
(3)「リアル・テニス」における道具の進化
「リアル・テニス」用の道具は、時代とともに進化していった。
まず、ボールについては、当初は羊の皮に布、羽毛などを固く詰めたものであったようだ。現在では、コルクを真ん中に詰めて布で包んだ手製のボールが利用されている。
ラケットに関しては、16世紀頃まで手を使って打っていたという記録もあるが、初期のものはヘラのように扁平な木製の棒のようなものであり、形も大きさもバラバラだった。木製の棒だけでは手が滑るので、プレーヤーは皮手袋をはめたり、革ひもを手や手首に巻いたりして工夫をしていた。その後さらに改良され、ボールが跳ねるように木製ラケット面の中を空洞にしたり、木の枠に狩猟用の網のように弾力性のあるストリングス(紐)を交差させたりした。1550年頃になると、弦楽器と同じように羊の腸を使ったガット弦※6をラケットに張ったものが発明され、ボールがよく跳ねるようになり、競技としての人気に拍車がかかった。
※6 ガット弦: 羊の腸(ガット)を繊維状にして縒り合わせたもの。第2次世界大戦後は牛の腸を利用。耐久性に劣るのだが、性能は人工のものより優れており、現在でも多くのプロが使用。
(4)英仏における屋内型「リアル・テニス」の衰退
フランスで王侯貴族を中心に流行した「ジュ・ド・ポーム」は、17世紀に人気が衰退する。フランス国王ルイ14世(在位1643~1715)の関心が、「鬘の乱れないビリヤードに向いたため、王侯貴族も倣ってビリヤードを愛好するようになったこと」が原因らしい。1657年にはパリに114もあった屋内コートは、1780年には10数か所となり、1789年のフランス革命でさらに一掃された。競技に使われなくなった屋内コートは集会場など別の用途に使われるようになる。
英国でも、ハンプトン・コート宮殿の「ロイヤル・テニス・コート」の構造をもとにして、次々と屋内コートが作られ、「リアル・テニス」の人気は絶頂期を迎えたのだが、フランスより少し遅れて衰退が始まる。原因としては、「屋内コートの建設に費用が掛かりすぎたこと」「愛好者である王侯貴族が没落していったこと」などが挙げられる。さらには、1642年のピューリタン革命によるスポーツの禁止が追い討ちをかけ、人気が低迷した。19世紀初めには、その後使用されなくなった屋内テニスコートの多くは演劇場に変えられていったが、「リアル・テニス」の競技そのものは、英国では細々と続けられた。
2.ローン・テニスからウィンブルドン大会へ
 (1)クロッケーの流行から衰退そして芝生の活用
(1)クロッケーの流行から衰退そして芝生の活用
「リアル・テニス」に代わって、18世紀頃に人気となっていた遊戯が「クロッケー」である。日本のゲートボールの原型のようなもので、芝生のコートでコルクなどの木の球を木槌で打って出発柱と折り返し柱の間に設けた門を通過させ、ゴールを競うものである。当時、上流階級の女性は活発な身体活動を控えるべきとされ、女性に許されたスポーツは、勝敗を競わず過度な体力が必要とされない安全なものとされた。パーティ用の盛装でも安全にできる社交場の娯楽が、アーチェリーとクロッケーであった。
クロッケーには、まず競技をおこなうための「刈り込まれた芝生の庭」が必要とされた。大英帝国の全盛期ヴィクトリア朝(1837~1901)には、産業革命のおかげもあり、中流階級でも19世紀後半には郊外に芝生の庭付きの住宅が購入できるようになった。この芝生の庭と安価な道具さえあれば、簡単に男女一緒に楽しめるクロッケーは、豊かな中流階級にも瞬く間に広まった。ところが、頭の痛い問題が発生する。英国の芝生は寒冷地用で気候と相性が良く、一年中鮮やかな緑で枯れないのだが、その一方で生長が早く芝生の手入れが大変だった。特に、召使のいない中流階級の家にとって、頻繁な芝刈りは大変な負担となっていた。
この厄介な問題が芝刈り機の発明で解消される。1830年にエドウィン・ビアード・バディングが芝刈り機を発明し製造販売すると一気に国内で普及した。芝刈りの負担がなくなったことで、クロッケーの人気が高まり、1868年にクロッケーのための組織「オールイングランド・クロッケー・クラブ」が設立され、1871年にウィンブルドンで最初の「クロッケー」の大会が開かれた。しかしながら、全盛期を迎えた頃からなぜか「クロッケー」人気が急速に萎んでいく。そして、使われなくなって、すっかりさびれたクロッケー用の芝のグラウンドが「ローン・テニス」誕生のきっかけとなる。
(2)壁のない「ローン・テニス」の発明
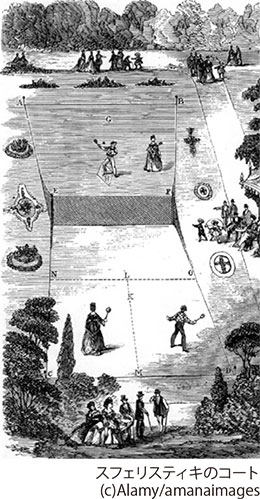 英国では、屋内でおこなう「リアル・テニス」のようなスポーツが細々と行われていたが、あまり人気が上がらず、その競技方式やルールは各地さまざまで統一されていなかった。また、クロッケー用の芝生も利用されていなかった。こうした状況を商売のネタにできないかと目論む人物たちが現れる。その一人がウォルター・クロプトン・ウィングフィールド少佐(1833~1912)である。昔からの地主とはいえ、すでに没落して貧しかった彼は、新しいテニスでひと山当てようと考えたらしい。
英国では、屋内でおこなう「リアル・テニス」のようなスポーツが細々と行われていたが、あまり人気が上がらず、その競技方式やルールは各地さまざまで統一されていなかった。また、クロッケー用の芝生も利用されていなかった。こうした状況を商売のネタにできないかと目論む人物たちが現れる。その一人がウォルター・クロプトン・ウィングフィールド少佐(1833~1912)である。昔からの地主とはいえ、すでに没落して貧しかった彼は、新しいテニスでひと山当てようと考えたらしい。
彼は、現代テニスの原型となる「スフェリスティキ」※7を考案する。この新しいテニスは、壁を利用する「リアル・テニス」とは全く異なるものだった。1874年には「古いテニス競技を新たにおこなうために改善した、持ち運びできるコート」という内容で特許を取得し、「箱入りスフェリスティキ・セット」を商品化した。顧客は、5ギニー金貨を払うと、「スフェリスティキ」のルールブックとともにゴム製のボールとガット弦を張った木製のラケット、ネットを受け取る。そして、以前クロッケー用だった芝生に支柱を立てネットを張り、白線を数本引くと簡単にコートが出来上がり、すぐプレーを開始できる。彼の考案したコートの形は、現在のような長方形のコートではなく、バックラインに比して中央のネット部分が狭くなっている砂時計のような形が特徴であった。
1874年に「ロンドン・コート・ジャーナル」誌で「数カ所のカントリーハウスで試してみたところ、健全な興奮をもたらし、同時にかなり科学的な競技であることがわかった」という記事が載る。「スフェリスティキ」を高く評価するこの記事のおかげで、新しいもの好きの人々の関心を引き、瞬く間に熱狂的なブームとなる。
愛好者たちは、この競技を「スフェリスティキ」と呼ばず、芝生(ローン)を短く刈り取ったコートでゲームがおこなわれることから、「ローン・テニス」と呼ぶようになる
ボールの弾性が、1839年にゴムの加硫※8を発見したアメリカ人のチャールズ・グッドイヤーの発明によって格段に改善され、芝生の上でも安定的に良く跳ねるようになり、テニスの面白みが増していたことも人気に拍車を掛けた。
※7 スフェリスティキ: ギリシャ語で「ボールゲーム」という意味。
※8 加硫: 生ゴムに硫黄などを混ぜて加熱すると弾性が増加する化学反応。
(3)「ローン・テニス」の女性への普及
「ローン・テニス」に最初に興味をもったのは軍人や聖職者であり、彼らは熱心にテニスに取り組んだ。特に聖職者たちは、積極的にローン・テニスを女性たちに広めたと言われている。自宅の芝生でおこなう当時の「ローン・テニス」は、社交的な場であったこともあり、女性の競技用服装はクロッケーと同じように盛装で、しかも体を締め付けるコルセットと帽子が必需品であった。1880年初頭には高価なドレスがテニスのプレーで汚れないようにエプロンを着用するのが一般的となり、さらに1884年にスポーツ用のコルセット「ユニーク・コルセット」が登場し、すこし活動的に体が動かせるようになった。こうした華麗な女性のテニス・ファッションは、雑誌で取り上げられ話題となった。1850年代以降に始まった女性の機会拡大や公的な役割の増大を求める運動の影響から、ファッションはさらに活動的なものへと変化していく。
(4)ウィンブルドン大会の始まり
ローン・テニスの人気に目を付けたのが、廃れたクロッケーに代わる競技を求めていた「オールイングランド・クロッケー・クラブ」である。1877年に、このクラブで初のローン・テニス競技会「第1回ウィンブルドン選手権大会」を開催する。開催の理由は、「壊れた芝の整備用ローラーの修理費集めに観戦チケットを1シリングで販売した」とされている。
第1回の優勝者はスペンサー・W・ゴア選手である。1921年までは、現在と異なりタイトル保持者と登録参加者のうちでの決勝戦勝者が戦う方式であった。この頃から、現代テニスのルールが確立されていく。ウィングフィールド少佐考案の砂時計型のコートもすでに姿を消して現在のような長方形のものとなった。また、従来は一方だけがサービスしていたものが、1875年から双方ともサービスをする方式に変わっていた。ウィンブルドン大会では、ウィングフィールド少佐が考案したルールは適用されず、新しいルールがこの大会のために作成された。
使用するボールについては、「空気が詰まっていて布で覆われていなければならない」とされた。これは、1870年代にテニスプレーヤーでもある英国の法廷弁護士ジョン・モイヤー・ヒースコートがボールの改良を考えたもので、ゴムボールを毛羽立ったフランネルで覆うと、コントロールしやすくバウンドも均等になった。
テニスのルールの改訂は、当初はスポーツ全般を管轄する公的機関「メリルボーン・クリケット・クラブ」がおこなっていた。その後、徐々に「オールイングランド・クロッケー・クラブ」が決めるようになり、第1回ウィンブルドン大会では、このクラブが定めたルールが採用される。また、大会と同時に名前にローン・テニスを付け加えて「オールイングランド・クロッケー&ローン・テニス・クラブ」と改称している。
第1回大会は、優勝者へ銀の優勝杯が贈られ、使用されたコートは1面のみであった。1877年第1回大会の参加選手は22人、その後1878年に34人、1879年に45人となり、観客は1877年が200人、1878年が700人、1879年が1100人と増加し続けた。当時、学校や地域の代表として競い合うものが多かったので、アマチュアの男子選手のみが個人で参加するテニス大会は珍しかったようだ。「オールイングランド・クロッケー&ローン・テニス・クラブ」は、さらなるテニス人気で1899年にクラブ名のローン・テニスの位置を変えて「オールイングランド・ローン・テニス&クロッケー・クラブ」へと名称変更している。
その後、テニス人気は英国からフランスをはじめとするヨーロッパだけでなく、アメリカやオーストラリアでも広がり、1881年に全米オープン、1891年に全仏オープン、1905年に全豪オープンが開始した。
3.さいごに
こうして、英国の「ローン・テニス」の歴史を辿ってみると、その普及に貢献した要因がいくつかあった。一つは、英国に多くある天然芝生の庭の存在である。産業革命期に政治経済だけでなくスポーツの担い手が王侯貴族から裕福な中流階級に移り、郊外の芝生の庭を取得した。次に、その芝生の刈り込みを容易にする芝刈り機が発明されると、ローン・テニス用のコートが増大した。また、女性の社会的地位の向上から、女性の参加が増加し、ローン・テニスも当初男女で楽しむ社交的な余興から活動的なスポーツに変化した。最後に、「リアル・テニス」からのテニス道具における技術革新も見逃せない。弾むゴムの発明、ラケットやガット弦などの技術改良も普及に果たした功績は大きい。産業革命期においては、新たな技術が開発されると、たちまちスポーツにも応用されて、驚くほどの変化をもたらした。
テニスは、競技人口約1億人と世界で4~5位の人気球技スポーツであるが、さらに多い競技人口約1億5000万人を有する競技が、英国の国技で野球の原形と言われるクリケットである。英国、オーストラリア、インド、南アフリカ、西インド諸島などの英連邦諸国を中心に人気がある。次回はクリケットが「紳士・淑女のスポーツ」と言われるようになった経緯や旧植民地に広がった経緯も含めて、クリケットと産業革命との関係を辿りたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第20回]~2022年2月号
昨年9月に実施された明治安田生命のアンケート結果によると、コロナ禍による在宅勤務やステイホームで多くの人が運動不足に陥り「4人に1人は体重が増え、その約8割がストレスを抱えている」という。加えて、この時期はおせち料理など正月のご馳走でさらに体重が増えるので、今年はストレス解消と生活習慣の改善を兼ねてスポーツに取り組もうとする人が多いのではないだろうか。
プロスポーツ界に目を転じると、新型コロナウイルスの感染拡大によって、選手の多くは大会中止や無観客試合で減収となり大きな打撃を受けた。その一方で、スポーツの新たな動きとして、今年9月に中国の杭州で開催されるアジア競技大会では、コンピューターゲーム、ビデオゲームを用いて競う「eスポーツ」が正式種目となった。過去にもチェスやブリッジが正式種目となっており、こうした競技をマインド・スポーツと呼ぶそうだ。大脳の筋肉を使うという意味でスポーツなのかもしれない。日本では、「スポーツ」といえば「身体的な運動」という認識が強いが、世界的に見ると「スポーツ」の定義はかなり広いようである。
今回は、「スポーツとは何か」を考えながら、英国におけるスポーツの歴史とともに産業革命との関係を辿りたい。
1.「スポーツ」の定義とは
「スポーツ」は、普段何気なく使用している言葉だが、2011年に日本で制定されたスポーツ基本法では「スポーツは、心身の健全な発達、健康および体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」と定義されている。つまりスポーツは競技・余暇活動・体力増進のために行う身体活動の全般を指し、散歩やラジオ体操、ランニング、ハイキングなど他者と競わない活動だけでなく試合会場やテレビでの観戦なども含まれており、スポーツは世界共通の人類の文化なのである。
2.「スポーツ」の言葉の起源

「スポーツ」の語源は、「あるところから別の場所へ運ぶ・転換する」を意味するラテン語の「deportare」に由来しており、英語に取り入れられると16世紀には見世物・ゲームを意味する「disport」、17世紀には遊びや愉しみを意味する「sport」となった。17~18世紀では、狩猟を代表とする「野外での身体的活動を伴う気晴らし」だけでなく「勝負事に関わる賭博や他人に見せびらかす行為、活動、見世物」などの娯楽も意味したので、われわれが現在イメージする「スポーツ」とは異なっている。
19世紀中頃になると、「スポーツ」の定義は「競技的な性格をもち、戸外で行われるゲームや運動に参加すること」を意味する言葉に変化する。変化した理由は、英国が19世紀に入ってスポーツ競技のルールや組織を整えて近代スポーツの原型を築いたからである。この頃英国で誕生し発展した競技や活動は、競馬、ゴルフ、アーチェリー、クリケット、サッカー、ラグビー、ホッケー、クローケー(ゲートボールの元となった競技)、テニス、陸上競技、水泳、漕艇、ボクシング、サイクリング、登山、バドミントン、卓球などで、現在よく知られているスポーツのほとんどが該当する。
3.中世のスポーツ

まず、キリスト教が支配する中世ヨーロッパの階級における「スポーツ」の状況から見ていく。封建領主である貴族層は、自らが所有する領地の検地や治安を兼ねた鷹狩り、狐狩り、弓術など戦闘的なものをおこなっていたが、宮廷の中ではフランス発祥でテニスの原形となるジュ・ド・ポームなどの競技も嗜んだ。下級貴族である騎士たちは、命を賭けた戦闘のために「騎士の七芸」と呼ばれる日常トレーニング(乗馬、弓術、剣術、水泳、チェス、狩猟、作法など)に余念がなかった。聖職者のうち高位の者は雑務がなく運動不足だったので、9本のピンを倒すボウリングと似た九柱戯(スキットル)などを楽しんでいたらしい。商人や職人たちは、自己防衛のために弓術やフェンシングなど戦闘的な活動に励んだ。
人口の多数を占める農民は、早朝から日暮れまで過酷な農作業に追われ休む暇もなかったが、祭礼時の気晴らしにダンスをしたり、素手で闘うボクシングや熊追い、闘鶏などの「ブラッドスポーツ」をおこなったりした。「ブラッドスポーツ」とは、人間が動物に暴力をふるったり、動物同士を戦わせたりする動物いじめのことである。また農村の年中行事として特に人気があったのが、「フォーク(民俗)フットボール」や「モブ(群衆)フットボール」である。現在のサッカーやラグビーの起源となるものだが、百人単位で行われる激しく暴力的な競技であり、大勢の選手たちによる殴る蹴るの乱闘に選手も観客も熱狂し、興奮のるつぼと化していたと言われる。
中世英国の王室におけるスポーツへの傾倒ぶりを見ると、英国国王ヘンリー8世(在位1509~1547)が、大変スポーツ好きな人物であった。王妃との離婚問題を巡って教皇と対立し、1534年に自ら英国国教会を設立したことで有名な暴君である。肖像画にある老年期の彼はひどく太っているので、スポーツマンという印象はない。しかし、若い頃はスマートで運動神経も良く、特に乗馬、狩猟、弓術に秀でていたと言われている。競技ではテニス、輪投げ、九柱戯、闘鶏などを好み、イングランドで最初の屋内球技場を建設させている。
そして、ヘンリー8世と二番目の妃であるアン・ブーリンとの間に生まれた英国女王エリザベス1世(在位1558~1603)は、弓術と乗馬が上手だったので狩猟が大好きだったようだ。さらに彼女は、スポーツ愛好家であるだけでなく、舞踏家としての才能もあり、ダンスの名手であった。
4.17~18世紀前半のスポーツとピューリタン
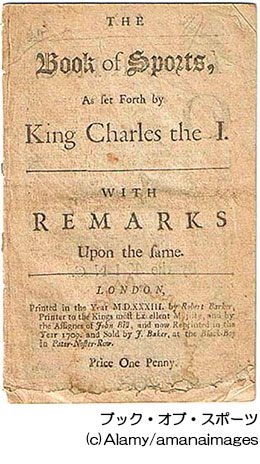
17世紀の初め頃から英国で勢力を強めた改革派プロテスタントのピューリタン(清教徒)たちは、勤勉や節約などの道徳を重んじ、飲酒や賭け事、動物いじめだけでなく、民衆の娯楽である格闘技、フットボールのような身体活動も享楽的で粗野な悪弊と敵視していた。ピューリタンにとって、娯楽は人々を怠惰にするだけでなく、時として公共の秩序を乱すものであった。スポーツ愛好家の英国国王ジェームズ1世(在位1603~1625)は、このように勤勉を過度に重視するピューリタンの活動を嫌い、1618年に「日曜と祝日の礼拝後のわが善良なる臣民の合法的娯楽を妨げてはならない」とする布告書「ブック・オブ・スポーツ」でスポーツへの抑圧を諫めた。その後、1642年のピューリタン革命後にクロムウェル(1599~1658)がスタートさせた共和制のもとでは、スポーツを含むあらゆる娯楽が禁止された。しかし、クロムウェルが亡くなり1660年に王政復古が起こると、スポーツへの抑圧はなくなった。
18世紀に入ると、富裕層が好む野外スポーツの狩猟や釣りなどだけでなく、クリケット、ボクシング、長距離競争、漕艇など近代スポーツに繋がるものも盛んとなる。フランスとの植民地争奪戦に勝利し、海外貿易で力を持ったジェントルマン※1と呼ばれる貴族や大地主(ジェントリ)たちは、舞踏会、パーティー、観劇、狩猟だけでなく、競馬やクリケットも社交の場として興じた。
※1 ジェントルマン: 貴族と大地主のジェントリを総称する。もともとは不労所得者の地主を指すが、地主以外の上位中産階級である聖職者、官吏、医者なども含めた。
5.産業革命と近代スポーツ
(1)富裕層のスポーツ
英国で近代スポーツが発祥した要因は、英国が最も早く資本主義化したからだと言われる。英国では、工業化の進展や植民地の拡大、商業の発達によって富裕層が増大すると、17世紀頃から「賭け」に対する関心が高まっていった。元来ギャンブル好きな英国人は、ボクシングやフェンシングなどの格闘技の試合結果だけでなく勝利に要した時間など、何でも賭けの対象とした。その結果近代スポーツでは、賭けの結果で揉めないように正確な時計による厳正な記録を求めるようになる。こうした記録への執着は、ニュートンに代表される科学革命によって人々の数値への関心が高まったことが多少影響しているかもしれない。
やがて、ジェントルマン階層や新興ブルジョワジー※2たちは、クリケットなど庶民の競技スポーツなども賭けの対象にできないかと考えた。そして賭けが厳正に実施されるように、競技のクラブや組織を作って競技のルールなどを定め始めた。競馬を例に挙げると、当初競馬クラブは、上流階級の人々が午後に競馬への関心を話し合う集まりにすぎなかったが、徐々に八百長に関する競馬係争の仲裁をするようになり、八百長防止に主眼を置いたルールも作成するようになった。
こうして近代スポーツを推進するために、1750年の競馬、1754年のゴルフ、1788年のクリケットの順で上流階級を中心として組織が作られた。クリケットは元々庶民を起源とするスポーツであったが、英国の貴族がクリケットの規則を体系化して上流階級向けの「紳士のスポーツ」とした。社交の場であった競馬やゴルフなどは、場所や道具の確保に莫大な費用がかかるので、参加できたのは富裕な一握りの上流階級だけであった。もっとも、長時間労働で疲労困憊している労働者にはスポーツに費やせるような時間もエネルギーもなかった。
こうして単なる遊びや娯楽が、力と技を競うものとなり、ルールや場所、用具が決められ、近代スポーツとなってさらに発展する。そして、あらゆる階級においてプレーヤーだけでなく、多くの観客、「ファン」が現れたのである。また、こうしたスポーツの隆盛もあり、1792年には最初のスポーツ専門誌「スポーティング・マガジン」が創刊され、当初は競馬と狩猟が取り上げられた。さらにスポーツに従事するコーチ、プロ選手、競技場管理者、レフェリーといった職業が専門職となりスポーツの商業化が進展する。
※2 新興ブルジョワジー: 特権や土地の所有者ではなく、商業や小土地所有によって自立できる財産を持ち、産業の発展に伴って資本を蓄えた有産階級
(2)労働者層でのスポーツ
17世紀後半から始まった第2次囲い込み運動※3によって、土地や働き口を失った人々が大量に農村から都市に工場労働者として流入した。その頃ピューリタンの「勤労を美徳」とする職業的倫理感が人々に浸透しており、工場の生産性を上げたい工場主の利害と合致した。さらに工場主は、労働者たちに工場での長時間労働だけでなく、時間の厳守や作業のスピードも求めた。英国史上最も栄華を誇ったヴィクトリア朝(1837~1901)初期には、多くの労働者が1日12時間以上働き、平日に暇な時間はほとんどなかった。19世紀前半になると労働時間の短縮を求めて労働者が動き始め、その後経済が下り坂になったこともあり、平日は10時間で、土曜日は半日の労働時間とする会社が次々と増えていった。1833年から1847年の工場法制定・改正で女性と子供の労働時間が1日最高10時間に短縮されると、工場主は労働者の1日の作業量が落ちるのではないかと心配したが、実際にはほとんど影響がなかった。その結果、工場主たちは一転して非効率な長時間労働を改善し始めた。労働時間が短縮されても、労働者は効率よく仕事をこなしたので、機械の稼働速度も上がり、作業は合理化されたのである。また工場法によって、終業時間が午後8時から平日は午後6時、土曜日は午後2時へと短縮されたことで、労働者が自由な余暇時間を過ごすものとしてスポーツ競技に取り組む余裕ができた。ほかにも、余暇に関連して旅行や園芸などのレジャー産業が誕生する。
余暇の面では、労働者の待遇は改善されたが、工場内では生産性向上を実現するために、工場主から競争心を煽られ、作業のスピードや強い集中力、高い精密さ、熟練性などを要求された。労働者が工場主から求められるものは、近代スポーツにおいて競技の選手に要求されるスピードや集中力、熟練性などの要素と似通っている。こうした価値観の類似性があったからこそ、産業革命と近代スポーツが同時期に誕生したのであろう。一方で、労働者に単純作業の繰り返しを強いる機械化社会への反発心が、人々のスポーツへの傾倒をさらに強めた面もあるように思われる。
※3 第2次囲い込み運動: 17世紀後半から18世紀にかけて農業革命にともなって効率的に多くの作物を生産するために農地の囲い込みが行われ、農民の離村を促した。
(3)スポーツの変容
人気が高かったブラッドスポーツであるが、18世紀末頃から動物いじめなど野蛮な暴力的行為への社会的批判が高まり始めた。当初、プロテスタントの一部のみが動物の虐待防止を唱えていたが、1824年に世界で最初の動物福祉を目的とした動物虐待防止協会が設立される頃から、潮目が変わった。虐待反対運動が盛り上がって1835年に動物いじめを禁ずる法律ができると、1840年代までにブラッドスポーツは消滅してしまう。また、人気のあった暴力的なフットボールは、囲い込み運動の影響によって競技用の広場がなくなり、1835年には通行に支障を与えた場合に罰金を科す「公道法」も制定されたことで衰退した。喧嘩のような「殴り合い」はこの頃から「グラブをつけたボクシング」へ変化し、労働者階級だけでなく貴族など上流層にも人気となった。ボクシングのトレーニングをしている男性たちの目的は、運動、体力の強化、楽しみ、賞金など、階級層ごとにさまざまだったようだ。
19世紀の英国で非暴力的なものに変容したのは、スポーツ競技だけではなかった。これまで国内政治は、暴力的な解決を繰り返してきたのだが、1832年以降の選挙法改正によって議会制度が整備され、国家が定めたルールの中で平和的に政策が決定されるようになった。こうして英国ではスポーツと同様に政治も、一定のルールのもとで闘うゲームのように、ルールを遵守するためのディシプリン(規律・訓練)が重要視されるようになった。
(4)鉄道網によるスポーツ協会の普及と日常生活
産業革命後ようやく労働者に経済的余裕と自由時間ができると、多くのスポーツが誕生し急速に発展した。特に1850年代以降には英国の鉄道網が出来上がったおかげで、競技会は地域レベルから全国レベルへ、そして国際レベルへと発展した。この頃からスポーツマンシップといった精神文化も備えるようになる。19世紀初頭までのスポーツ協会は家柄の良い者たちが集まる一部階級のためのものであったが、19世紀中頃からスポーツ規約の監視を担うスポーツ協会が急増し始めた。1857年に登山、1866年陸上競技、1869年水泳、1871年ラグビー、1884年ボクシング、1888年テニスと次々に国内統一の組織が設立され、近代スポーツへと繋がった。
また、日本人が健康維持のためにラジオ体操をするように、19世紀半ばには英国の多くの男性が毎朝欠かさず体操をするようになった。膝の屈伸運動や柔軟体操、腕振り運動、シャドウ・ボクシング、毎朝10分から20分のランニングなどを励行すれば全身と脳の血の巡りが良くなり、その日の滑り出しが良くなるとされたからである。その頃には、それほどお金に余裕のない人でも利用できる運動施設がどんどん増えていた。一方で1850年代以前の女性は、男性の協力者として育児と家事に専念し、「過度のスポーツは理想の女性に逆行するもの」とされたので、女性には毎日1時間汗をかかない程度に体が温まるまで元気よく歩くウォーキングが推奨された。全体として、この頃に階級に関係なく、人々の日常生活のなかにスポーツ活動が定着していったようである。
6.アマチュアリズム発祥の国
産業革命以降、労働者階級もスポーツ競技に関係し始めると、スポーツを通して上流階級と労働者階級との交流が発生した一方で、「プロ・アマ」の問題が発生した。アマチュアリズム発祥の英国で1866年に初めて制定された「アマチュア規定」では、「アマチュア」を「働く必要がなく、純粋に競技を楽しむジェントルマン階級」と定義した。一方、労働者、職人、職工たちは、たとえその競技を生業としていなくとも、日々の肉体労働でスポーツのトレーニングをしていると見做され「プロ」として扱われた上に、競技場への出入り口や更衣室、食堂は上流階級用とは区別されていた。
現在では、「スポーツを職業にする者」と「仕事の余暇で練習している者」が同じ土俵で競技するのは不公平だという考えがアマチュアリズムだとされているが、実際には労働者をスポーツ競技から排除し、ジェントルマンがスポーツを独占するための方法として考え出された。表向きは、「労働者には厳しいマナーやルールが遵守できない」とか「競技の品位を保つため」と称しているが、特権意識の強かった当時のジェントルマンたちは、階級の違う労働者と一緒にプレーすることを好まなかったので「出場資格はアマチュアに限る」と「試合での賞金・商品を目当てにしないこと」という規定を設けたのである。
今回は、スポーツの定義を考えながら、英国における中世から近代スポーツ誕生までの流れを総論的に概観したが、スポーツと産業革命との関連性だけでなく議会政治との共通点も見出すことができた。また広範な意味をもつ「スポーツ」であったが、いつの時代でも「楽しむ」という点で共通していた。
次回は、今回のスポーツ全般から各論に入り、英国の代表的なスポーツ競技を取り上げながら産業革命との関連性を辿りたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第19回]~2021年12月号
新型コロナウィルスの感染拡大で1年延期となっていた第18回ショパン国際ピアノコンクールの本選が10月に実施され、日本人出場者では、反田恭平氏が内田光子氏以来51年ぶりとなる日本人最高位の第2位、小林愛実氏も第4位を受賞した。5年に1度ワルシャワで開催される世界最高峰の国際ピアノコンクールでの日本人の快挙に盛大な拍手を送りたい。
今回のコンクールでは、4メーカー5種類の公式ピアノが揃えられており、出場者は、この中から会場で使用するピアノを選択しなければならない。今回採用された公式ピアノは、スタインウェイ2種類とイタリアのファツィオリ、日本のヤマハ、カワイの各1種類であるが、入賞者8人が使用したピアノの内訳を見ると、スタインウェイは反田氏、小林氏を含む3名、ファツィオリは優勝者を含む3名、カワイは2名となっており、各々のピアノがもつ個性の違いが、コンクールでの審査結果にも影響しているようだ。
今回は、1759年のヘンデル没後の英国を中心にヨーロッパの音楽事情を公開演奏会の状況から見るとともに、産業革命期の英国がピアノの一大産地となった経緯を辿りたい。
1.ウィーン古典派の巨匠たちと公開演奏会
(1)古典派音楽の中心都市ウィーン
18世紀のヨーロッパは、教会の権威や封建的な考え方を否定し、人間の理性を拠り所に社会の進歩を図ろうとする啓蒙思想が拡がり、旧体制や古い慣習に反対して、宗教、政治、社会、教育などの新しい秩序が生まれようとしていた。1776年に自由と独立を掲げてアメリカ合衆国が誕生し、1789年にはフランス革命が勃発、英国では産業革命が進展していた。
その頃、ヨーロッパの音楽界はバッハの死を境にバロックから古典派に移行する。18世紀中期から19世紀初頭の古典派を代表する作曲家は、フランツ・ヨー
ゼフ・ハイドン(1732~1809)、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791)、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)であるが、この3人が音楽の都ウィーンを中心に活躍したことから、「ウィーン古典派」とも呼ばれた。1789年頃、人口が80万人を超えたロンドン、50万人のパリ、40万人のナポリに続いて、23万の人口を擁したのがオーストリアの首都ウィーンであり、ドイツ語圏の中心となっていた。ハプスブルグ家を中心とした貴族や裕福な実業家が住んでいたウィーンは、音楽の愛好者が多く、若い音楽家にとっては魅力的な街であった。
この頃には裕福な市民の多いロンドンやパリなどの大都会では、市民層の繁栄とともに演奏や楽譜という商品に対価を払って音楽を消費する「聴衆」が誕生していた。さらに公開演奏会の発展により、音楽家は名声や人気に応じた収入を得られるようになった。多くの聴衆が集う大ホールに効果的な大音量の曲として書かれたのが、大人数編成のオーケストラによって演奏される多楽章構成の「交響曲」である。
この時代は、「王侯貴族などパトロンに依存する音楽家」から「聴衆からの収入によって生計を維持する音楽家」への過渡期であった。次の項では活躍した時期によって異なる3人の巨匠の境遇を見ていきたい。
(2)ロンドンで大金を稼いだハイドン
ハイドンは、モーツァルトより24歳年上であるが、二人の音楽家としてのスタート時期は同じ1760年頃である。1766年には当時のハンガリーで権力を誇ったエステルハージ侯爵の楽団長に就任したハイドンは、生活の苦労もなくかなり自由に楽しく数々の楽曲を作って名声を得るとともに、試行錯誤の中で新しいジャンルである交響曲の原型となる形を導き出した。しかし、1790年にエステルハージ侯爵が亡くなると楽団員は解雇される。60歳間近で年金生活となって
しまったハイドンは、1791年にドイツ人音楽家ヨハン・ペーター・ザロモン(1745~1815)からロンドンへの演奏旅行に誘われる。この頃ロンドンでは、800席収容の「ハノーヴァー・スクエア・ルームズ」※1など大きくて設備の整ったコンサートホールがすでに完成しており、公開音楽会が盛んに開催されていたのである。ロンドンでのハイドンの報酬は破格で、1晩で400グルデン※2を稼ぐこともあり、2年半の英国演奏旅行で2万グルデンの収入を得ている。同時期にウィーンの宮廷付作曲家であったモーツァルトの年収800グルデンと比較すると報酬の大きさが分かる。
ハイドンの成功の秘訣は、曲作りにあった。ウィーンでは音楽に知悉した上流階級の聴衆を相手に演奏できたが、ロンドンの聴衆は裕福だが音楽的素養のない市民階級だったので、演奏に飽きて寝てしまう観客も多かった。彼は、『軍隊』や『時計』など分かりやすい曲で人気を得て大成功する。この時に「ザロモン・セット」とも呼ばれる12曲からなる『ロンドン交響曲』も作曲し、生涯で100余りの交響曲を書いた。ハイドンは、英国への移住も検討したが、最終的にウィーンに戻り作曲を続け、77歳で死去した。
※1 ハノーヴァー・スクエア・ルームズ: 1774年に建築され1900年に取り壊されるまで、ロンドンを代表するコンサートホールだった。
※2 グルデン:グルデン(英語ではギルダー)は15世紀から2002年まで使われたオランダの通貨単位。外国との貿易決済にも利用された。
(3)フリーランスとなって凋落したモーツァルト
早熟な天才モーツァルトは、ザルツブルク宮廷楽団で副楽長をつとめた父レオポルトとともに、6歳(1762年)から約10年間ヨーロッパ各国の宮廷を回り、神童と呼ばれた。6歳の時にウィーンのシェーンブルン宮殿にて女帝マリア・テレジア(1717~1780)の御前でも演奏した。ロンドンには1764年から1年以上滞在し、その頃に交響曲の作曲を始めた。
束縛を嫌うモーツァルトは、特定のパトロンだけに仕えようとせず、安定した生活よりも自由に創作できる環境を望んだ。そして25歳の時に、ザルツブルクの大司教と折り合いが悪くなり、父の反対を押し切ってフリーの音楽家としてウィーンで生きることを選んだ。初めの5年間は彼の名声もあり、演奏会やピアノの個人レッスン、楽譜の出版などで収入を得ていたのだが、才能のない弟子を邪険に扱ったことから弟子の数が減り、聴衆に迎合した曲も作らなかったので、演奏会も人数が集まらず開かれなくなったようだ。音楽にかけては天才でも、日常的な生活能力に欠ける彼は、30歳頃から生活が苦しくなり、悪妻として名高いコンスタンツェのプレッシャーもあったのか家計を補うための多忙な生活で体調を崩し、1791年に35歳の若さで亡くなった。短い生涯にもかかわらず、約40の交響曲を作った。。
18世紀の末頃から印刷技術の向上により安価で読みやすい楽譜の印刷が可能となり、出版社が次々に設立されると、作曲家はまとまった楽譜での収入が得られるようになる。モーツァルトがハイドンのように長生きしていたならば、楽譜が売れて生活に窮することはなかったかもしれない。
(4)自立した音楽家ベートーヴェン
ドイツのボンで生まれたベートーヴェンは、17歳の時に最愛の母を亡くし、宮廷歌手である父のアルコール中毒が次第に深刻になると、父と二人の弟の世話と火の車の家計を支えるためにいくつもの仕事を掛け持ちする苦しい生活を送っていた。父が亡くなった1792年に、22歳の彼は音楽修行のためにウィーンに移り、短期間だがハイドンの弟子となった。その頃には彼のピアノの即興演奏は、ウィーンの音楽好きの貴族たちの間で絶賛され、まずピアニストとして名声を得て、その後に作曲家としての地位を確立することになる。
20歳代から持病の難聴が徐々に悪化していくが、33歳(1804年)の時の交響曲第3番『英雄』の発表を皮切りに、10年にわたって6つの交響曲を生みだした。第3番は、従来の交響曲の概念を書き換えたものであり、この作品が古典派からロマン派への橋渡し的作品となった。
40歳頃には聴力を完全に失うにもかかわらず、交響曲第9番をはじめとする大作を書き上げた。亡くなる56歳(1827年)までに発表した9つの交響曲はすべてが傑作である。ベートーヴェンは、一度も宮廷に仕えることなく、芸術家としての地位を確立した。聴覚障害に悩まされながら過酷な運命を乗り越えて、珠玉の作品を数多く残した彼の生涯は、伝記となって神格化され「楽聖ベートーヴェン」となる。
(5)モーツァルトとベートーヴェンの違いとは
ベートーヴェンが次々と傑作を生みだした要因の一つは、彼の生まれた時代が大きく関係している。彼は、フランス革命期の動乱、ナポレオンの権勢と失脚など激動の時代を不屈の精神で生き抜き、身分階級にとらわれない近代市民社会が形成していく渦中で社会の変化を全身で受け止めた。
一方、モーツァルトは、フランス革命勃発の2年後の1791年に亡くなったので、ベートーヴェンのような激動のなかに身を置くことはなかった。二人の音楽性の違いは、14歳の年齢差だけでなく、こうした体験の差にも起因しているのだろう。
2.人々が歌い演奏して楽しむ音楽文化
(1)ピアノの誕生
 ピアノの前身楽器は、クラヴィコードとチェンバロ(別名ハープシコード)という二つの鍵盤楽器である。クラヴィコードは長方形で鍵盤を押すと金属の突起が持ち上がり、弦を突き上げることによって音が出る楽器であり、ある程度は音の強弱をつけることができる。一方、チェンバロは、翼の形でツメ状の小さな突起で弦を引っかいて音を鳴らす。とてもか細い音だが、繊細で澄み切った独特の音を出し、バロック時代に活躍した。しかし、一般聴衆を相手とする広いコンサートホールでの演奏が増えるにしたがって、大音量で華やかな音が出せ、音の強弱もつけることができる鍵盤楽器が求められるようになった。
ピアノの前身楽器は、クラヴィコードとチェンバロ(別名ハープシコード)という二つの鍵盤楽器である。クラヴィコードは長方形で鍵盤を押すと金属の突起が持ち上がり、弦を突き上げることによって音が出る楽器であり、ある程度は音の強弱をつけることができる。一方、チェンバロは、翼の形でツメ状の小さな突起で弦を引っかいて音を鳴らす。とてもか細い音だが、繊細で澄み切った独特の音を出し、バロック時代に活躍した。しかし、一般聴衆を相手とする広いコンサートホールでの演奏が増えるにしたがって、大音量で華やかな音が出せ、音の強弱もつけることができる鍵盤楽器が求められるようになった。
1700年頃、フィレンツェのメディチ家で楽器類の管理をしていたクリストフォリは、チェンバロを基礎に、弦をハンマーで打つ新しい鍵盤楽器を作った。これが、ピアノの誕生である。イタリア生まれのピアノは、18世紀後半頃から、ハンマーの動きで英国式アクションとウィーン式アクションに分かれて製作技術が発展していった。ハイドンは1788年に自宅にピアノを購入し、ベートーヴェンは、ウィーンに移住した1792年頃に初めてピアノに触れている。
(2)英国でのピアノ製造の始まりとピアノの進化
ピアノがヨーロッパで楽器として認知されるのは18世紀後半からである。当初ピアノ製造業は、ドイツで繫栄していたが、7年戦争(1756~1763)を機に、ドイツのピアノ製造技術者は大挙して英国に移住した。そのうちの一人が、ドイツのドレスデンからロンドンに渡ってきたヨハネス・ツンペで、1761年に工房を開くとロンドンで最初にスクエア・ピアノを製作した。美しい装飾と愛らしい音色が特徴のスクエア・ピアノは、英国中流階級の女性の憧れの的となり、男性から妻や娘、婚約者への贈り物として大人気となった。
英国では、産業革命によって富裕になった市民階級がピアノを次々に買い求めて需要が急増すると、ブロードウッド、クレメンティ、カークマン、サウスウェルなどのメーカーが続々と新型ピアノを製作するようになり、1770年代には、グランド・ピアノの開発も進み、アメリクス・バッカースによって設計・開発された英国式アクションのピアノの標準型が確立された。その製法を受け継いだブロードウッドは、弦の張力を増し、頑丈な鉄製フレームで強化して力強い音を出すことに成功するとともに、機械の導入による工業化と長時間労働によってピアノの大量生産を開始した。1782年から1802年までの20年間に1000台のグランド・ピアノと7000台のスクエア・ピアノを製造販売する英国最大のピアノ製造会社となり、国内外に英国製ピアノを広めた。ベートーヴェンが亡くなった時彼の部屋にあったピアノは、ブロードウッド製である。これまでの1台ずつ手作りされていたピアノは工業生産されるようになり、19世紀には技術革新と需要によってピアノ製造業は大いに活気づいた。
初めは55鍵しかなかったピアノの鍵盤は、クラシック音楽の発展とともに音域が広がり、今では88鍵が標準となった。ベートーヴェン作のピアノ曲には、ピアノが改良されるたびに、新たに対応可能となった音域や音色が活用されている。産業革命によって、鋼鉄弦や鉄骨フレームが作られただけでなく、作曲家や演奏家の厳しい要求に応えるために音域の拡大や音量の増大、連打のスピード、強打への耐性などの技術革新が次々に実現されていった。ピアノ演奏の発展には、演奏技術の向上だけでなく楽器の改良が不可欠であった。
(3)ロマン派時代における家庭音楽の人気
ナポレオン戦争終結後の1814年のウィーン会議から、ヨーロッパ各地で革命が起きる1848年までの約30年間は概ね平穏な時代が続き、音楽演奏が幸せな家庭生活を象徴するものとなった。アマチュアである一般市民が家庭で歌ったり、楽器を弾いたりする家庭音楽が盛んになると、ピアノ演奏用の曲が作られただけでなく、各地で合唱団体が結成されて音楽祭が開催されるようになった。サロン文化※3が栄えたパリでは、ヴィルトゥオーソと呼ばれる超絶技巧の演奏家が注目の的となり、フランツ・リスト(1811~1886)やフレデリック・フランソワ・ショパン(1810~1849)がサロンの寵児となった。
ピアノという高価な家具をもつことは、金銭的にも精神的にも上流の市民としての豊かさの証であった。家庭内では連弾が興じられ、華やかで弾きやすい小品や変奏曲が流行した。19世紀中頃に大ヒットしたピアノ曲がポーランド出身のテクラ・バダジェフスカ(1834~1861)作曲の「乙女の祈り」であり、女性のピアノ人口の増加を反映している。この時代の音楽は、ピアノを通して大衆的で自由なものとして浸透した。
※3 サロン文化: 貴族や上流階級の夫人が、客間(サロン)を開放し同好の人々を招き、文化全般について自由に談話を楽しむ社交界の慣習。
(4)19世紀の英国における音楽への価値観の変化
産業革命によって生まれた新興の富裕層は、貴族と異なり自前の価値基準をもたないので、王侯貴族文化の模倣としてクラシック音楽を楽しむようになる。19世紀の英国は、世界で最もピアノが普及し、楽譜が購入される国となり、ピアノ音楽を楽しむ人口が多かった。ピアノ愛好者の増加により、最新のピアノ作品などの音楽情報に対する需要が生じ、他の国に先駆けて18世紀末以降に数多くの音楽雑誌が次々と刊行された。
一方で農村部から囲い込み運動によって都市に流入した大量の労働者たちは、合唱や合奏の音楽愛好サークルに入会してメンバーと感動を共有することで、地縁のない都市の中で新たなコミュニティを形成した。19世紀前半には禁酒運動を推進するために、炭鉱で働く労働者を中心に金管楽器と打楽器からなるブラスバンドが推奨され、労働者の娯楽となった。ブラスバンドに参加することが彼らにとってハードな労働の息抜きになり、仕事の効率も向上したことから、英国全土に一挙にブラスバンドが広がった。演奏技術が上がってくると、各地でコンクールがおこなわれるようになり一層人々に定着した。この時代の英国では、有名な作曲家は生まれなかったが、アマチュア音楽の大衆化が進み、市民社会の形成に寄与した。
(5)第二次世界大戦後の日本のピアノ文化
19世紀の英国ではピアノが富や豊かさの象徴であり、産業革命で大量生産されて普及したわけだが、戦後に日本でも同じ現象が生じている。日本で一番古いピアノは、1823年に来日したシーボルトが持ち込んだ英国製のスクエア・ピアノだそうだが、長い間日本の家庭にとって、ピアノは高嶺の花であった。しかし、第2次世界大戦後に日本のピアノメーカーは、家庭向けに「低価格で高品質なピアノ」を提供しようと、工場生産による大量生産化に取り組む。昭和30年代の高度成長期に入ると、ピアノは手が届く価格となり、情操教育への関心の高まりやピアノメーカー主催のピアノ音楽教室が展開されたこともあって、ピアノは急激に普及した。ピアノ音楽教室は、ピアノ演奏人口のすそ野拡大に寄与し、ショパン・コンクール2位の反田氏も、ピアノとの出会いはピアノ音楽教室だそうだ。平成に入ると、ある程度家庭に普及したピアノは、安価で高性能な電子鍵盤楽器の登場、住宅事情、少子化などにより飽和期に入った。
音楽は、革命などの激動や経済危機など時代の変化から大きく刺激を受けるとともに、その時代の人々の生活や思想にさまざまな影響を与えている。英国では、ヘンデル以降の作曲家と言えばエルガー(1857~1934)、ブリテン(1913~1976)、ホルスト(1874~1934)ぐらいしか思いつかないが、ポップスの世界では、20世紀後半に「英国病」と揶揄された経済低迷の中からビートルズが誕生した。
次回は、英国産業革命期のスポーツをテーマに辿ってみたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第18回]~2021年11月号
英国におけるオペラの歴史をみるとき、ヘンデルの存在が欠かせない。偉大な英国人音楽家パーセルが1695年に亡くなり、英国の柱となる音楽家が存在しなかった時期に、英国楽壇の主導権を握ったのがドイツ人音楽家ヘンデルである。彼は音楽の才能だけでなくプロデューサーとしての才能もあったので、音楽活動をはじめさまざまな事業活動を英国で展開した。今回は彼の生涯を辿りながら、産業革命を迎えようとする英国において、彼がどのような影響をおよぼしたのかを考えてみる。
1.ヘンデルの生い立ち(1685~1702)
 ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、1685年2月23日にドイツ中部のザクセン地方のハレで、すでに63歳となっていた父親にとって8番目の子供として生まれた。同じ年の3月31日にJ.S.バッハが、ハレから130㎞ほど離れたアイゼナッハで生まれている。バッハは音楽一家に生まれたので、音楽家となる運命であったが、ヘンデルは、宮廷付きの外科医兼理髪師であった父と銅細工師であった祖父から音楽家になることを猛反対された。気難しく音楽嫌いの父親は、ヘンデルには自分が若い頃に目指していた法律家の道を歩ませたかったので、幼少時から音楽に異常なほど興味を示すヘンデルに、たとえ遊びであってもチェンバロを弾くのを禁じた。それでもヘンデルは諦めずに父親の目を盗んでは鍵盤楽器をこっそりと屋根裏部屋にもちこみ、家族が寝静まった後に、練習をしていたそうだ。
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、1685年2月23日にドイツ中部のザクセン地方のハレで、すでに63歳となっていた父親にとって8番目の子供として生まれた。同じ年の3月31日にJ.S.バッハが、ハレから130㎞ほど離れたアイゼナッハで生まれている。バッハは音楽一家に生まれたので、音楽家となる運命であったが、ヘンデルは、宮廷付きの外科医兼理髪師であった父と銅細工師であった祖父から音楽家になることを猛反対された。気難しく音楽嫌いの父親は、ヘンデルには自分が若い頃に目指していた法律家の道を歩ませたかったので、幼少時から音楽に異常なほど興味を示すヘンデルに、たとえ遊びであってもチェンバロを弾くのを禁じた。それでもヘンデルは諦めずに父親の目を盗んでは鍵盤楽器をこっそりと屋根裏部屋にもちこみ、家族が寝静まった後に、練習をしていたそうだ。
7歳のヘンデルが弾くオルガンの演奏を聴いたヴァイセンフェルス公爵ヨハン・アドルフ1世がその才能に惚れ込み、彼に音楽の勉強を勧める。自分が仕える公爵に逆らえないヘンデルの父親は、翌年から息子が音楽教育を受けることをやむなく認めた。ヘンデルは、地元教会の優れたオルガニストであるフリードリヒ・ヴィルヘルム・ツァハウ(1663〜1712)のもとで、約3年間作曲とオルガン、チェンバロ、ヴァイオリンの指導を受けると、たちまちのうちに先生を凌ぐようになり、オルガニストとして活躍し始める。
2.ハンブルグ・イタリア時代(1703~1710)
ヘンデルは、12歳(1697年)で父親を亡くし、17歳(1702年)になると亡き父の意向にしたがってハレ大学で法律の勉強を渋々始めたが、同時期にハレ大聖堂でオルガニストとしての契約もしている。音楽家の夢が捨てられないヘンデルは、師匠ツァハウの勧めもあり、1年で大学を辞めて、オペラ劇場のヴァイオリンとハープシコードの奏者の職を見つけてハンブルグへ移住してしまった。
当時、圧倒的に人気があったのはイタリア・オペラであったが、富裕な住民が多く、音楽的水準の高かったハンブルグでは、1678年に「自国民による自国語のオペラを」という理念でドイツ最古となる公衆歌劇場が創設されドイツ語のオペラが作曲された。もっとも自国語と言いながらも、一つの作品のなかにドイツ語とイタリア語が混在するようなオペラが上演されていたらしい。彼は、そこで当時の劇場の中心的作曲家であったラインハルト・カイザー(1674〜1739)から指導を受けた。また、ここでヘンデルは、四つ年上のドイツ人音楽家ヨハン・マッテゾン(1681〜1764)と出会う。頭に血が昇ると見境が付かなくなる性格の二人は、オペラの上演中の些細な喧嘩から決闘騒ぎになり、マッテゾンが危うくヘンデルを刺すという事件を起こすが、その後二人はすぐに冷静になり仲直りして生涯の友となっている。
1704年、弱冠19歳のヘンデルは、ハンブルグで二つのオペラを上演しており、1作目の『アルミーラ』は何とか成功するが、2作目の『ネロ』は完全に失敗だったようだ。『アルミーラ』では、歌手でもあるマッテゾンが主役のテノールとして歌っているのだが、彼はこの時点でのヘンデルのオペラは「冗長で未熟だった」とのちに語っている。
しばらくして凋落の兆候が見え始めたハンブルグ・オペラに見切りをつけたヘンデルは、1706年に当時の音楽の最先端であるイタリアへ向かう。
イタリアでは、音楽界の大御所たちに優れたオルガン、チェンバロ奏者として歓迎されただけでなく、作曲家としても彼の作ったオペラ、カンタータ、オラトリオは高い評価を受けた。特に、イタリアでのオペラ第1作目となる『ロドリーゴ』(1708)の成功を受けて、1709年に第2作目となる『アグリッピーナ』を発表すると、連続27回上演される程の大成功を収めた。このようなイタリア・オペラ全盛期における若きヘンデルの活躍は、イタリアだけでなく、世界中に知られるようになる。また、腕利きプロデューサーに必要な社交術にも長けた彼は、スポンサーとなる裕福な公爵たちから大変贔屓にされた。
3.ロンドン時代(1711~1738)
1710年25歳のヘンデルは、イタリア音楽家アゴスティーノ・ステッファーニ(1654〜1728)の推薦によって、ハノーヴァー選帝侯の宮廷楽長に就任する。しかし、それだけで満足できない彼は、もっと大きい舞台で腕試しするために、就任後すぐに休暇を取ってロンドンへ行く。当時のロンドンでは、すでにイタリア・オペラの上演が盛んに行われており、1711年にヘンデルもオペラ『リナルド』を初演し成功をおさめた。その後ドイツのハノーヴァーに一旦戻るが、翌年再度ロンドンを訪れると、ハノーヴァーでの宮廷楽長の仕事をそのままにしてロンドンに住み着いてしまった。
しかし巡り合わせが悪いことに、1714年のアン女王(在位1702~1714)逝去により、ヘンデルの雇い主であるハノーヴァー選帝侯が、英国王ジョージ1世(在位1714〜1727)として即位する。ハノーヴァー選帝侯の宮廷楽長として職務怠慢であったヘンデルは、バツが悪く新国王に合わせる顔がなかったはずだが、1717年にはテムズ川に国王ジョージ1世を迎え、組曲『水上の音楽』を演奏するなど、国王とは良好な関係を築いた。
18世紀初頭の投機ブームのロンドンで、富裕な貴族たちから出資を募って1719年に設立されたのが、「ロイヤル音楽アカデミー」である。34歳のヘンデルは、スイス人劇場経営者ジョン・ジェームズ・ハイデッガー(1666〜1749)とともに経営に参画し、そこで監督、指揮者、劇場支配人などの役割も全部一人でこなした。国王の出資もあり、配当目当ての貴族によって瞬く間に株券は売りさばけたそうだ。アカデミー会員には、シルバーチケットを購入すると、21年間毎晩オペラが鑑賞できる特典が付与されていた。ヘンデルのビジネス・スキルはここで磨かれ、オペラ興行は1720年代前半までは好調に推移した。ちなみに39歳の時に、彼はジョージ・フレデリック・ハンデルと英国風の名前に改名し、42歳になって英国に帰化した。
ヘンデルは「ロイヤル音楽アカデミー」で積極的にオペラ活動をおこなうが、やがてさまざまな困難が生じる。まず、イタリア人音楽家ボノンチーニ(1670~1747) というライバルの存在である。オペラでの二人の闘いは、政党の争いまでに発展し、王権派のトーリー党はヘンデル派に、商人の多い議会主義のホイッグ党はボノンチーニ派と分かれて、有力な歌手同士がいがみ合うなどの対立が頻発した。また、自惚れが強く法外な報酬を要求し、しかも契約を守らないオペラ歌手の横暴にも手を焼いていた。ほかにも、通俗的な英語版オペラが強力なライバルとして現れた。1728年に英国人劇作家ジョン・ゲイ(1685~1732)によって上演された『乞食オペラ』は、上流階級のイタリア風オペラへの風刺でもあり、大変な人気を博した。ヘンデルが得意とする貴族好みのイタリア語のオペラは、手痛い打撃をこうむることになり、同年には「ロイヤル音楽アカデミー」は資金不足で倒産し、劇場も閉鎖されてしまう。
しかし、44歳のヘンデルは挫けずに倒産した翌年には新国王ジョージ2世(在位1727〜1760)の後援を受けて「新ロイヤル音楽アカデミー」を設立して再建を目指す。しかし新国王の息子であるフレデリック皇太子は、父親との折り合いが悪く、国王お気に入りのヘンデルの「新ロイヤル音楽アカデミー」のオペラ興行を目の敵にして、「貴族オペラ」を設立した。ヘンデルの公演は、スター歌手の引き抜きもあり、なかなか成功せず、協力者ハイデッガーも離れていった。結局1737年には、「新ロイヤル音楽アカデミー」と「貴族オペラ」は共倒れとなり、同じ頃に解散する。この時52歳のヘンデルは脳卒中で一時右手が麻痺となり、記憶も不確かな状態が続くと、さすがに「ヘンデルも二度と立ち上がれないだろう」とロンドンの音楽界は噂したが、元来頑強な彼は温泉治療で奇跡的な回復を遂げて、翌1738年にはオペラ『セルセ』を作曲する。しかしながら、英国でオペラが以前のような人気を取り戻すことはなかった。
ところで、オペラ『セルセ』の中の第一幕冒頭の官能的なアリアは、日本でも一時期大変な話題となった。1986年に日本のウイスキーメーカーのCMで米国人ソプラノ歌手キャスリーン・バトルが歌って大きな反響を巻き起こした『オンブラ・マイ・フ』が、まさにこの曲である。
4.オペラからオラトリオへ(1739~1748)
字幕スーパーを備えた現在のオペラ観劇と違って、当時のロンドンで上演されるイタリア・オペラは、外国語を嗜む王侯貴族には楽しめても、外国語が分からない中産階級には面白くなかったであろう。彼らには、貴族趣味のイタリア語のオペラより、母国語である英語のオペラの方が分かりやすく楽しめたはずだ。1730年代のロンドンでは、音楽における聴衆の中心層が王侯貴族から中産階級に移行し、外国語であるイタリア語のオペラは支持を得られず、下火となっていた。
そこでヘンデルは、オペラからオラトリオへと方向転換する。もともとオラトリオは16世紀後半にローマの祈祷書(オラトリオ)から始まった宗教的内容を扱う大規模な声楽曲であり、独唱、合唱、オーケストラの編成で演奏され、舞台装置や演技を伴わず教会で行われた。ヘンデルが独自に確立した英語のオラトリオは、劇場で上演され、歌手も出演料が高額なイタリアのオペラ歌手ではなく、割安な英国人歌手が起用されたので、オペラよりはるかに少ない費用で済んだ。作品自体も、宗教的だが、適度に娯楽性も織り込んだ劇的なものであった。劇場という娯楽空間で上演される彼のオラトリオは、神への冒涜だとして教会から強く非難されたが、彼は上演方法を変えなかった。
1739年に54歳のヘンデルは、オラトリオの『サウル』や『エジプトのイスラエル人』を初演する。ドラマティックな要素を強調し、合唱の役割を拡大して次々と壮麗な宗教劇を発表した。特に、1742年にアイルランド総督からの依頼によってわずか1カ月弱で作曲した『メサイア(救世主)』は、ダブリンの慈善演奏会によって初めて演奏されるとヘンデルの不朽の名曲となり、名声は揺るぎないものとなった。『メサイア』の収益によって、音楽興行で抱えていた多額の負債を何とか処理でき、窮状にあったヘンデルにとってもメサイア(救世主)となった。
5.オラトリオ『メサイア』
『メサイア』は、イエスをめぐるストーリーを抽象的だが情感豊かに描き、第1幕「イエス出現の預言~降誕」、第2幕「受難」、第3幕「復活」の全3幕で構成されている。第2幕の最後に鳴り響く『ハレルヤ・コーラス』の壮大さに、国王ジョージ2世が感動し思わず立ち上がったという逸話があり、今日でもこのコーラスを全員起立して聴く習慣がある。イントロに続いて『ヨハネの黙示録』から三つの部分に分けて作曲された『ハレルヤ・コーラス』は、四つのパートすべてが、最後には一つとなって壮大な響きを生み出している。ヘンデルのオラトリオの中では、珍しく宗教的な性格が強い作品である。
背徳的で残酷なストーリーが多いオペラに対して、道徳教育的なオラトリオは、家族ぐるみで楽しめるものであり、バッハの難解で複雑な音楽とは異なり、平易で明快な音楽だったので、中産階級に好まれたのだろう。特に『メサイア』は、キリストを信ずることによって、すべての人が救われるという大いなる喜びと賛美を告げるものだっただけに、宗教心や倫理観が高揚されたはずだ。
6.晩年(1749~1759)
1749年には国王ジョージ2世の依頼により、64歳のヘンデルは、オーストリア継承戦争の終結を祝う式典の花火を演出するために、大規模な楽器編成の『王宮の花火の音楽』を作曲し好評を得た。
しかし、白内障に悩まされていたヘンデルは、66歳の時に左眼の視力を失い、67歳の時に受けた英国人眼科医ジョン・テイラーの手術の失敗で完全に両眼の視力を失うと、作曲活動ができなくなる。ヘンデルは、その後も演奏活動だけは続けていたが、体調を崩して74歳で亡くなった。壮大な葬儀が執り行われ、本人の遺言通りに外国人としては異例のウェストミンスター寺院に埋葬された。
ここでヘンデルの人物像を描くと、生涯独身だった彼は、母国語であるドイツ語以外に英語、イタリア語、フランス語なども話せるマルチリンガルであった。そのうえ社交にも長けていたので、交友関係が広く、財界、政界、文化人など上流階級のさまざまな人々と強いパイプをもっていた。投資や蓄財にも熱心だった彼は、一時期多額の負債を抱えることもあったが、亡くなった時の銀行預金残高は1万7500ポンド(現在の価値で2〜3億円相当)もあったそうだ。また、毒舌家ながら、熱心に孤児養育院や困窮した音楽家の救済基金など慈善活動に尽力する一面もあった。
対照的なライバルとされるバッハは、二度の結婚で20人もの子供に恵まれ、一生を通じてドイツを一度も出ることなく、ストイックに教会音楽を中心に活動をした。バッハはヘンデルに会いたかったようだが、二人の面談は実現しなかった。現在ではバッハの知名度の方がはるかに高いが、存命中の18世紀では、国を超えて活躍するヘンデルの方が、国内派のバッハよりずっと人気があった。二人の共通点は、演奏者への指導の厳しさとワイン好き、そうして眼科医がジョン・テイラーであったことだ。テイラーが名医だという触れ込みに騙されて、二人とも彼の手術の失敗によって失明している。
7.ヘンデルが英国で果たした役割とは
こうして見ると、彼の74年間の生涯は、単なる音楽家というよりは、マルチなプロデューサーとして事業的才能を発揮しており、逆境にも挫けぬエネルギッシュな人物であったと思う。王侯貴族や教会などの組織に所属するというより、フリーランスで活動することを好むタイプであったので、自ら興行主となって、劇場や歌手の手配、チケット売りに至るまで手掛けた。音楽的にも、ドイツ、イタリアなどを渡り歩いてさまざまな音楽の要素を取り入れていくだけでなく、最も効果が出るように聴衆に応じた音楽を作り出す柔軟性も備えていた。こうした資質があったからこそ、異国の地で大成功を収めることができたのであろう。ヘンデルが亡くなって25年後の1784年には、大規模な「生誕100年祭」がロンドンのウェストミンスター寺院で開催されており、ヘンデルの功績が高く評価されていたことを示している。
ちょうど産業革命へ向かおうとして中産階級が台頭し始めた時期に、ヘンデルが現れた意義は大きい。彼は、18世紀の英国にイタリア・オペラやオラトリオなどの音楽作品をもたらしただけでなく、中産階級を顧客とした音楽興行を自らがプロデューサーとなって事業化した。その頃の英国では自前で音楽家を育むことより、外国の音楽家を招いて楽しむのが当たり前と考えられていた。優れた外国人音楽家は、成功を夢見て大英帝国の中心都市ロンドンを目指すようになり、19世紀には外国の著名な音楽家による演奏会が盛んに行われた。産業革命を経て、都市文化が成熟したロンドンは、一流の音楽を消費する一大音楽都市となったのである。
16世紀のイタリアで生まれて英国でも人気となったオペラは、19世紀半ばにフランスでオペレッタとなり、さらに19世紀後半には英国からの移民が多いアメリカでミュージカルとなった。オペラとミュージカルの違いは色々とあると思うが、そのうちの一つが電気的な拡声・音響システムである「マイク」の存在だろう。マイクがまだ発明されていない頃に生まれたオペラが次第に広い会場で上演されるようになると、遠くの聴衆にも声を届かせるために、体を共鳴させる特殊な発声法(ベルカント唱法)が確立された。一方で、マイクが発明された後に生まれたミュージカルでは、地声でのセリフと歌が可能となり、踊りも積極的に取り入れられた。ミュージカルを発展させたマイクの発明は、音楽における産業革命の一つと言えるだろう。
次回は、バロック時代から古典派、ロマン派時代へと移行していく中での英国の状況を辿りたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第17回]~2021年9・10合併号
最近、1970年代後半から1980年代にかけて流行した日本のシティポップが音楽配信を通して世界中で人気だそうだ。今や世界はボーダレスとなり、輸入盤を探す手間もなく、音楽配信を利用すれば世界中の音楽を手軽に聴くことができる。録音媒体の進化によって、音楽の生産者、消費者も大きく変化し、音楽は身近な存在となったが、クラシック音楽だけは日本ではどうも敷居が高いようだ。
クラシック音楽の本場であるヨーロッパでは、昔から生活に密着した音楽として皆に親しまれており、英国でもコンサートなどが頻繁に開催されるなど音楽活動が盛んである。ところが、その英国では、なぜか18世紀以降からエドワード・エルガー(1857~1934)が現れる19世紀末まで自国出身の著名な音楽家が出現していない。このように、産業革命期以降の英国に有名な英国人音楽家が現れなかったり、英国が音楽の消費地と呼ばれたりした背景や理由について、産業革命という視点から探ってみたい。
まず今回は、中世から産業革命前までのヨーロッパの音楽史を概観したのちに、中世から英国人音楽家パーセルが活躍する17世紀後半までの英国音楽の歴史を紐解いて英国独自の特徴を捉える。
1.ヨーロッパにおける音楽の歴史
(1)中世・ルネサンス時代(5世紀~16世紀)
A.西洋音楽の起源 グレゴリオ聖歌
 まず、ヨーロッパにおける音楽史を中世・ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派と4期に分けて、ここでは中世・ルネサンス時代からバロック時代までの動きを簡単に辿る。
まず、ヨーロッパにおける音楽史を中世・ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派と4期に分けて、ここでは中世・ルネサンス時代からバロック時代までの動きを簡単に辿る。
中世からルネサンスにかけてのヨーロッパでは、権威を独占するローマ・カトリック教会が社会・文化の中心であり、音楽の中心もミサ曲など教会音楽であった。教会の典礼※1のための聖歌として歌われたのが、西洋音楽の起源とされるラテン語の無伴奏曲「グレゴリオ聖歌」である。中世を代表する教皇グレゴリウス1世(在位590~604)の名にちなんだもので、実際には西ローマ皇帝となったカール大帝(在位800~814)が、ローマやガリアで使われていた聖歌を統合し制定したとされる。神に捧げる祈りである典礼の音楽は、人間の声だけを使った緩やかな曲調の単旋律(モノフォニー)とされ、その音域はほぼ1オクターブと狭かった。聖歌を歌えるのは、キリスト教の教義により原則男性のみとされ、楽器も神聖な歌詞を聴こえなくするので使われなかった。
※1 ここでは、キリスト教の教会が行う礼拝集会など公の礼拝・儀式
B.教会建築と聖歌
聖歌で単旋律が採用されたのは、前述のような理由だけでなく、教会の建築様式も影響している。10世紀末から12世紀にかけての教会は、せいぜい10数メートルの高さで窓がない石造りのドームの「ロマネスク建築」である。この建築様式では、シンプルな単旋律の歌でも音がよく響き残響時間が長かったので、荘厳な趣きが生まれた。
12世紀後半から「ゴシック建築」が教会の主流となると、ガラスや金属を使うことで建物の高さが30~40メートルとなり、横幅も広くなったので空間がかなり広がった。この構造では反響音が少なくなり、単旋律の音楽では神聖な荘厳さが十分出せなかったので、もっと音を加えるような工夫が始まった。こうしてグレゴリオ聖歌に新しい旋律を加えて歌うようになり、複数の旋律からなる多声音楽(ポリフォニー)へと発展していくことになる。
C.ルネサンスとプロテスタント音楽の発生
15世紀半ばから16世紀頃までをルネサンス音楽時代と呼ぶ。14世紀には十字軍の失敗、教会の内部分裂、教会の世俗化による堕落もあり、ローマ・カトリック教会の宗教的権威は衰えていた。さらに1517年の「95か条の論題」に始まるマルティン・ルター(1483~1546)の宗教改革が進むと、ヨーロッパ中にプロテスタントが広がり、キリスト教以前の古代ギリシャ・ローマの文化を原点とする人間中心のルネサンスの時代に移行する。
カトリック教会では、従来通りラテン語がミサに使われ、ミサ曲を歌うのも専門的な聖歌隊など聖職者のみで行われたので、信者は遠くから眺めるしかなかった。ドイツ人のルターは、聖書のみが神の言葉と考え、信者が皆理解できるように聖書をドイツ語に翻訳し、説教もドイツ語でおこなった。当時は信者の識字率が低かったので、分かりやすく歌いやすい讃美歌を積極的に活用し、全員が参加できる礼拝にした。自身で作曲を手掛けるほど音楽に精通したルターのおかげで、ルター派の教会ではドイツ語の歌詞で単旋律の歌いやすい讃美歌「コラール」をもとに、数多くの作品が作曲された。一方、カトリック教会では、15世紀半ばに世俗音楽の旋律がミサ曲に用いられ、「神への祈りのための典礼」というミサの目的が希薄化していたが、トレント公会議(1545~1563)の議論でミサ曲から世俗的な部分をなくし本来のミサに戻るべきとされた。
また、16世紀前半に貿易で繁栄していたヴェネツィアのサン・マルコ寺院で自由闊達で華やかな音楽が生まれ16世紀後半にピークを迎えている。ステレオ効果の優れた音響をもつサン・マルコ寺院の構造を生かして、いくつかのグループに分かれた合唱団が、離れた位置から交互に呼応して歌い継ぐ複合唱形式の音楽がルネッサンスとバロックとの橋渡し役となった。
D.複雑な音楽を可能とした楽譜の発展
当時のヨーロッパの音楽作品を現在に再現できるのは、楽譜の存在が大きい。楽譜は9世紀に登場した「ネウマ譜」を起源としている。ネウマとは「息」を意味する言葉で、当初のネウマ譜は音の高さなど大まかな旋律の動きを示したものだった。その後、さらにリズムや音の長さを表そうと試行錯誤した結果、13世紀後半には音符の種類を決める定量記譜法が試みられ、14~15世紀には現在の楽譜に近いものができた。楽譜の書き方がルール化されたことで全員が楽譜にあわせて歌えるようになり、複雑な音楽の作曲も可能となったが、当時の手書きで彩色された楽譜は高価な美術工芸品であり、そのコレクションは王侯貴族や教会の富の象徴となっていた。オリジナルの楽譜から手で書き写された楽譜は、転記ミスが多かったらしい。
やがて印刷技術が発達し、ヴェネツィアでペトルッチ(1466~1539)が活版印刷を用いて、人気が出そうな曲集を1501年から次々と出版すると、多くの人が楽譜を手に入れられるようになった。
(2)バロック時代(1600年~1750年)
A.イタリア・フランスの繁栄とオペラ誕生
ルネサンス時代は「調和」を重んじたが、「いびつな真珠」を意味するバロック音楽は、音量の強弱やテンポの差の対比によって誇張的で動的な効果を演出するのが特徴である。北イタリアでストラディヴァリ(1644頃~1737)などヴァイオリンの名工が現れ、素晴らしい楽器が作られると、器楽と声楽は対等な立場となり、協奏曲(コンチェルト)が17世紀終わりにはバロック音楽の代表的ジャンルとなる。12曲のヴァイオリン協奏曲を集めたヴィヴァルディ(1678~1741)の『四季』が有名である。
古代ギリシャ演劇を復活させようという動きから始まったオペラは、一握りの王侯貴族の楽しみとして、17世紀初頭にイタリアのフィレンツェに登場し、その後発展すると総合芸術としてヨーロッパ中で音楽活動の中心となる。フランスではルイ14世(在位1643~1715)に代表される絶対王制のもとで、王の権威や都市の栄光を誇示するために絢爛豪華なオペラやバレエがヴェルサイユ宮殿を中心に数多く演奏され、ルイ14世も自らバレエを踊っていた。
B.調性音楽と公開音楽会の開催
ハーモニーの面では、フランスのラモー(1683~1764)が1722年に『和声論』を出版し、同年に「音楽の父」と呼ばれるドイツ人のJ.S.バッハ(1685~1750)が24の調による前奏曲とフーガを集めた『平均律クラヴィーア曲集第1巻』を完成させた。この理論と作品により、長調と短調の「調性音楽」が確立され、1900年頃までクラシック音楽の主流となる。バッハは、大半をプロテスタントの宗教音楽のために作曲したが、鍵盤奏者としても有名であった。また、英国に帰化し、50年間ロンドンを拠点として活躍するドイツ人音楽家のヘンデル(1685~1759)も、バッハ と同じ年に生まれた。
バロック時代までの音楽家は、君主や教会の注文に応じて作曲する職人という存在にすぎなかった。当時の演奏会は、王侯貴族の邸宅などでお抱え音楽家によって演奏されるのが普通で、庶民が音楽を聴ける場は教会ぐらいであった。17世紀後半から入場料を払って鑑賞する公開演奏会が始まるのだが、値段的には高嶺の花で庶民が気軽に行けるようなものではなかった。
2.英国の音楽
(1)中世・ルネサンス時代
A.英国独自の音楽
中世の英国音楽は、他国と同様にカトリック教会の影響が強かったのだが、14世紀前後からフランスに次ぐ多声音楽の先進国として独自の展開が見られた。その頃に作られた作者不詳の「夏は来たりぬ」という歌曲は、複数のパートが同じメロディーを追いかけていくカノン形式の楽曲としては最古のものだ。また、フランスの技法「アルス・ノヴァ」※2を取り入れた英国人音楽家ダンスタブル(1390頃〜1453)の新しい音楽は、ヨーロッパ大陸に逆輸入され影響を与えた。多声音楽においても、3度や6度の音を重ねるという英国独特の柔らかい楽曲は、4度や5度の重なりの硬い響きが主流であったヨーロッパ大陸の楽曲に影響を与え、双方が融合することでルネサンス音楽の方向性を決定づけたとされる。英国と大陸との文化的な融合が生まれた背景には、英仏両国に領土をもったフランスの大諸侯アンジュー伯が、プランタジネット朝を継承し、英国王となっていたという状況が影響している。しかし、その後英国ではフランスとの百年戦争(1339~1453)やバラ戦争(1455~1485)、ペストの流行があり、音楽どころではなくなり英国の音楽はしばらく停滞する。
※2 フランスの音楽家ヴィトリが、14世紀初頭の新しい音楽のリズムの分割法と記譜法を理論的にまとめ、それをアルス・ノヴァとして発表したもの
B.音楽愛好者ヘンリー8世による英国国教会設立
テューダー朝のヘンリー8世(在位1509〜1547)の治世に入ると、音楽に復興の兆しが見える。ヘンリー8世は自身で作曲し、重臣たちと重唱を楽しむほどの音楽好きで、膨大な楽器のコレクションを持っていた。また彼は、宗教改革者ルターを批判する本を出版し、ローマ教皇から「信仰の擁護者」の称号が与えられるほど熱心なカトリック信者であったが、離婚問題を巡ってローマ教皇と対立し、1534年に英国国教会を成立させる。すべての修道院を解散させ、教会財産を没収したので、一挙にカトリック音楽の基盤が失われた。英国国教会の典礼は、当初はラテン語のままであったが、徐々に英語による典礼が一般化し、英国独自の礼拝形式とそれに伴う音楽が生み出された。16世紀初頭の代表的な英国人作曲家としては、ウィリアム・コーニッシュ(1465頃~1523)やトマス・タリス(1505頃~1585)などがいる。
(2)バロック時代
A.エリザベス1世時代の多様な教会音楽
その後、メアリ1世(在位1553~1558)の時代には一時的にカトリックに戻るが、エリザベス1世(在位1558~1603)の時代には英国国教会が再開される。音楽好きでリュートの演奏が上手だったエリザベス1世は、カトリック教徒に比較的寛容な政策をとったので、カトリック礼拝のための音楽も少ないながら作曲された。この時代は宗教的に不安定な時期であり、音楽家はカトリックとプロテスタントの間で翻弄され大変だったであろうが、音楽的にはカトリックと英国国教会双方の作品が英国で生み出された。また、17世紀初頭に英国の芸術で人気のあったのはシェイクスピア(1564~1616)に代表される演劇であり、音楽はあくまで演劇の中で歌われる添え物という存在でしかなかった。流行の面でも、大陸がバロック時代へと移行していても、ジェームズ1世(在位1603~1625)が即位した頃の英国では、一世代前のルネサンス時代そのままの音楽が盛んであった。島国の英国では、戦争などで大陸との接触がなくなると新たな流行が入ってこなくなるので、大陸ではすでに廃れた音楽技法が大切に守られて、その技法がさらに複雑で技巧的なものとなる傾向があった。
B.ピューリタン革命で停滞し王政復古で復活
1649年のピューリタン革命でクロムウェル政権が登場し共和制に移行すると、英国は音楽の低迷期に入る。ルター派より厳格なプロテスタントであるクロムウェル(1599~1658)は、演劇や音楽は人間を堕落させるものとして、教会の音楽をほぼ廃止としただけでなく、礼拝堂の合唱団を解散させたり、教会のオルガンを破壊したりした。職を失った音楽家たちは、国外へ渡った者も多かった。
1660年に王政復古となり、フランスで亡命生活をしていたチャールズ2世(在位1660〜1685)は英国に帰国すると、優雅で豪華なフランスの文化を積極的に英国へ取り入れようとした。音楽好きだった彼は、ヴェルサイユ宮殿で演奏されていた音楽を英国に取り入れるために、ルイ14世の楽隊を真似て楽団を設立し、所属する音楽家たちをフランスやイタリアに留学させた。さらに、イタリア・オペラを導入する試みも始まり、17世紀半ばにようやくバロック様式の音楽が英国でも開花した。こうして英国では音楽が盛んになり、音楽史上記録に残るものとしては世界初の公開演奏会が、1672年にロンドンで開かれた。ヴァイオリニストのジョン・バニスター(1630頃~1679)が自宅で催し、プロの演奏家に好きな曲がリクエストできる気楽な形式のものだったが、入場料1シリングは庶民にとって相変わらず高嶺の花であった。
C.天才音楽家パーセルの登場と名誉革命

 そうした時期に、英国音楽史上随一の天才とされたヘンリー・パーセル(1659~1695)が現れた。英国のモーツァルトと呼ばれ、優雅で気品高い作品を800曲以上残した。もともと王室礼拝堂のオルガニストであったパーセルだが、鍵盤楽器の独奏曲や合奏曲だけでなく、英語による声楽曲やオペラを作曲した。英国国教会特有の礼拝音楽「アンセム」をはじめ、祝典用の頌歌、歌曲、酒場の歌など数多くの作品がある。
そうした時期に、英国音楽史上随一の天才とされたヘンリー・パーセル(1659~1695)が現れた。英国のモーツァルトと呼ばれ、優雅で気品高い作品を800曲以上残した。もともと王室礼拝堂のオルガニストであったパーセルだが、鍵盤楽器の独奏曲や合奏曲だけでなく、英語による声楽曲やオペラを作曲した。英国国教会特有の礼拝音楽「アンセム」をはじめ、祝典用の頌歌、歌曲、酒場の歌など数多くの作品がある。
1688年に名誉革命が起こり、オランダのオレンジ侯は妻のメアリ2世(在位1689~1694)の共同統治者となり、ウィリアム3世(在位1689~1702)として即位する。ウィリアム3世は宮廷の音楽などへの支出を快く思わず、音楽のための予算を減らした。音楽家は良い収入を得るために、音楽活動の対象を劇場や市民に変えていったので、音楽の担い手が王侯貴族から一般市民へと次第に移行する。
そこでパーセルは、これまで演劇の添え物であった劇中挿入歌を充実し、当時上演されていた仮面劇に豪華な舞台装置を加えて音楽、舞踊を活用する「セミ・オペラ(準オペラ)」と呼ぶ演劇を5作品つくった。セミ・オペラでは劇の間に歌や舞踊が挟まれ、主な登場人物の役割は台詞だけで、歌については脇役が歌った。さらにパーセルは、トロイの王子とカルタゴの女王の悲恋を題材にした叙事詩『ディドとエネアス』という英語のオペラも作り上げた。この作品は、上演時間約1時間と短いが、全体を通して歌が歌われるものだった。しかし、この八面六臂の活躍をみせたパーセルが36歳の若さで亡くなると、それ以降独創性のある生粋の英国人音楽家は長い間生まれてこないのであるが、その背景については次号の中で詳しく触れたい。
ヨーロッパの中世以降における音楽の担い手は、権力の変遷と同様に教会、王侯貴族、富裕市民層と移行しているが、島国の英国は英国国教会の設立、ピューリタン革命、王政復古、名誉革命などを経験して、海を隔てたヨーロッパ大陸とは異なった英国独自の音楽の歩みを進めてきたことが分かる。
次回は、まず「音楽家兼プロデューサー」であるヘンデルが活躍したバロック後期を取り上げ、それにつづく古典派、ロマン派の時代のヨーロッパと英国における音楽の歴史を辿り、産業革命でさらに力をつけた裕福な市民層の動きを中心に産業革命が音楽に与えた影響などを探る。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第16回]~2021年8月号
朝の連続テレビ小説『おかえりモネ』のなかで、森林組合で働く主人公のモネこと百音は、地元の広葉樹ナラの木を利用して、地域の小学生が使う学童机を製作しようと提案する。組合の職人たちは、伐採した木を丁寧に加工して机の試作品を完成させ、市の入札に参加しようとするが、月30台の製作が限界の組合では「4200台の机を半年以内に納入」という入札の条件を満たせず暗礁に乗り上げる。モネは、丹精こめて職人が作る森林組合の机が、大量生産される低価格の大手メーカー製の机に対抗できないのが残念でならない。
19世紀に同じような悩みを抱いていたのが、前月号から続くモダン・デザインの父ウィリアム・モリス(1834~1896)である。英国の産業革命は大量生産を可能にすると同時に品質の低下をもたらした。モリスは、そうした状況を批判する一方で、モノづくりに熱心に取り組んだ。何事も徹底的に極めたい性格のモリスには、自らモノづくりのプロセスに加わることが大きな喜びであった。
今回は、彼が40歳以降に夢中となったテキスタイルや壁紙の制作、それに付随する捺染※1や染色、そして美しい書物の制作への取り組みを辿り、最後に「アーツ&クラフツ運動」が影響を与えたと言われる柳宗悦の「民藝運動」にも触れる。
1.マルチ人間ウィリアム・モリスの略歴
まずは、多才なモリスが27歳で会社を興す時期を起点に彼の生涯を簡単に辿ってみる。
1861年、新居「レッドハウス」の建設を機に「モリス・マーシャル・フォークナー商会」を設立した。インテリア、壁面装飾、彫刻一般、宝石装飾や金工、家具、押し型革細工、刺繍や家庭用品など、あらゆる工芸・芸術製品を提供し、30歳の時には最初の壁紙『格子垣(トレリス)』『ひなぎく』『果実あるいは柘榴
一方で、36歳の時には長編物語詩『地上の楽園』を刊行し、詩人としての評価を不動のものとした。中世の彩飾写本
1875年(41歳)に共同出資の「モリス・マーシャル・フォークナー商会」を解散し、モリス単独で「モリス商会」を再スタートすると、テキスタイルや壁紙を中心とした商売に転換した。テキスタイル部門では、刺繍から始まり、捺染、機械織、絨毯
50歳の頃にモノづくりの理想と現実のギャップに悩み、社会主義運動の方へ傾倒していくのだが、54歳の時、「第1回アーツ&クラフツ展」でエメリー・ウォーカーの印刷に関する講演を聴き、印刷への関心が高まる。そして、57歳の時には印刷工房「ケルムスコット・プレス」を自宅近くに設立することになる。
2年がかりで念願の『ジェフリー・チョーサー作品集』を完成させた62歳の秋、健康状態が悪化し死去する。まさにモリスの言葉通りの「美しい家と美しい書物をこよなく愛した人生」であった。
※1 染料を糊に混ぜ、直接布地に摺りつけて染色すること。特に、型を用いた模様染めをいう。プリントともいう。
※2 手書きで筆写し、彩色で飾られた本
※3 彩色で飾られた著者自身の手書きによる本
※4 西洋や中東などにおける字を美しく見せる手法で、アルファベットを独特のタッチで描く技術
2.テキスタイル
(1)捺染
まずは、英国での捺染の歴史を簡単に振り返る。17世紀の英国では、インドから渡来した染色文様の綿布であるチンツ※5が、丈夫で色彩も美しく大変人気があった。インドでは、媒染剤
1676年にウィリアム・シャーウィンが木版プリント(型押し)と媒染剤による染色技術を結び合わせてインド産チンツの模倣を可能にすると、ロンドンを中心とした水量豊かな場所に木版プリントの捺染工場が多数設置された。ところが、18世紀後半には銅板プリントの登場によって状況が一変する。銅版は、木版よりはるかに繰り返し利用ができて精巧で繊細な図柄が描けるので一挙に主流となり、神話的題材や田園風景、当時流行の中国趣味の図柄などを中心に多様なデザインのものが生産された。
その後、産業革命期に紡績機が発明され紡績業が発達すると、綿布の生産拠点がロンドンからイングランド西北部のランカシャーへ移行する。この地域は湿気が多く、湿度不足による品質のばらつきや糸切れを起こす心配がないので、英国全体の綿布を供給する一大産地となった。それと同時に地の利を生かして当地でも捺染産業が発展するのだが、ここでは木版の多色プリントの捺染工場が主体となり、花のデザインを基本とするさまざまなパターンが制作された。一方の銅版プリントが主体であるロンドンの工場主は、値下げでランカシャーに対抗しようとするが、質を落したことで逆に人気を失い1800年までにはロンドンのほとんどの業者は廃業することになった。
1815年頃から、銅版ローラー・プリンティングが普及し始めた。金属円筒の側面に絵柄を彫って回転させてプリントする方式であるが、初期は出来栄えが安定せず、安物専門の業者が粗野な絵画的パターンに利用していた。しかし、1830年頃にこれまでの植物動物系の染料に代わって鉱物染料や化学染料が現れると、銅版ローラー・プリンティングとの相性の良さから大量生産が可能となる。儲け主義のランカシャーの捺染業者は、海外市場や国内向けの安い織物を大量生産することに躍起となり、製品の染色やデザインを重視しなくなった。手間がかかる昔ながらの木版プリントの方は、さらに衰退することになるが、細々と残っていた。
※5 更紗
英語でチンツ(chintz)と呼ばれた。
※6 染料を繊維に定着させるために用いられる薬剤
(2)天然染色へのこだわり
モリスは39歳の時にすでにチンツのデザインに取り掛かっていたが、当時主流であったローラー・プリンティングによる製品の色合いに満足できなかった。彼は、「デザインの成否を決めるのは、捺染で処理された発色の出来栄えだ」と考え、チンツの捺染工程の研究に没頭した。その頃出回っていたコールタールなどから作られる速乾性の化学染料は、安く、速く、簡単に染めることができ、大量生産には最適であったのだが、当時の技術水準では品質が不安定で、色落ちや褪色
モリスは、幼い頃から中世の素晴らしい刺繍やタペストリーの一級品だけでなく、美術館でインドの捺染やペルシャの絨毯など海外の歴史的な傑作を数多く観ていたので審美眼が養われていた。自分を納得させるような美しい布をつくるには、「模様を版木の型で染める」という昔ながらの版木捺染を再現し、その当時すでに途絶えていた草木染で使う藍や茜など天然染料を復活させるしかないと考えた。しかし、当初は思うような成果が得られなかったので、あらゆる植物染料の文献を求めて徹底的に勉強するだけでなく、自ら工房で洗濯や日光などによる染めへの影響を何度も繰り返し実験した。
さらに本格的な実験に取り掛かるためには、当時のクィーンズ・スクエアの工房では手狭で設備も不十分なので、スタンフォードのリークに工房を移した。
苦労の末に完成した藍染めの色合いに感激し、ますます染色への好奇心と探求心を強めたモリスは、より質の良い製品をつくるために、豊かな自然の光と染色用の澄んだ水に恵まれた新たな工房の候補地を探し始める。そして、ついにマートン・アビーにチンツ工場として使われていた旧修道院の建物という理想的な場所を見つけ、1881年に引っ越すのであった。
これ以降、工房の完成とモリスのテキスタイル・デザインへの高い人気により、受注が急激に増えることになる。特に、近くのウォンドル川の軟水を用いた藍の抜染
彼は、常に天然の素材の美しさを最大限に生かそうと心掛けた。最良の材料で良心的に制作された彼のテキスタイルは、デザインが素晴らしいだけでなく、耐久性にも優れていた。
※7 無地染めした布に還元剤や酸化剤を含む抜染糊をプリントし、その部分の色を抜いて模様をつける染色法。ぬきぞめともいう。
(3)デザインへのこだわり
モリスのデザインは、卓越した色彩センス、草花の描写における繊細さと大胆さの結合、豊かで丹念であるが自在さを失わないパターンの創出を特徴としており、流行的なものと異なり、古典的でどの時代でも通用する普遍性を有するところが魅力である。それが今日でもなお人気がある理由であろう。壁紙やテキスタイルのデザインは、一貫して薔薇、百合、チューリップなどの野の花や、小鳥などの小動物をパターン(繰り返し模様)として使っている。これらの着想は、四季折々の草花や果樹で溢
1875年から1885年の間はテキスタイルのデザイン活動に熱中し、草花をモチーフとした彼の特徴である平面的デザインについても、壁紙やテキスタイルの特性に応じた工夫をした。平面的に張られる壁紙は、形式的な図柄の反復だけでは見る者が飽きるので、わざと自然の不規則さをデザインに取り入れ、一方でカーテンなどのテキスタイルでは、ひだを寄せたり、畳んだりした状態で見られることを意識して、生地が歪んで曲面となってもパターンが確認しやすいように、より形式的なデザインを使った。
ちなみにテキスタイルでは、既存の業者では満足できず基本的にモリスがすべての工程に関わって制作したが、壁紙においては、信頼できる木版プリントのジェフリー社に依頼している。
しかし、こうして納得がいくものを作ろうとすると製品の値段が高くなり、「最小の経費で最良のものをつくる」という商会の目的は果たせなくなり、次第に社会主義へと傾倒していくことになる。
3.美しい書物づくり
中世のヨーロッパでは識字率が低く、文字が扱えるのは修道士ぐらいだったので、修道院の写本室で、修道士が羊皮紙
そうした歴史から、モリスが学ぶオックスフォード大学のボードリアン図書館では、多くの中世写本を所蔵し、そのコレクションは世界的に有名であった。モリスは、手書きで筆写された中世の彩飾写本をその図書館で発見し、飾り頭文字(イニシャル)や縁取り、カーペットページ※8などで華麗に装飾された宗教的な内容の装飾写本に魅入られた。
ゴシック・リバイバルの流行の中で、モリスは22歳の時に著作者兼製本者となる彩飾手稿本を制作し始めた。中世後期の写本を模した彼の本は、彩色のある縁飾りと飾り頭文字のある、非常に重々しいゴシック的なものであったらしい。32歳頃から、今度はカリグラフィーの研究に入った。当初は16世紀イタリア・ルネッサンスの手習い本で勉強するが、36歳の時には読みやすく全体的に開放的で伸び伸びとした手書き書体のローマン体を研究するようになる。その研究成果を生かして自選詩集などで挿絵、装飾、飾り頭文字など華麗な飾りを付けた彩飾手稿本を制作するまでになった。装幀にも手を染めると、さらには自分で印刷を手掛けたくなった。
56歳から活字体の研究を始めると、新しい活字の字面をデザインする仕事に着手する。シンプルでがっしりした字体を好んだモリスは、15世紀のヴェネツィアで使われたローマン体の活字をもとに新しい活字体「ゴールデン活字」を創ったり、読みにくいと非難されていたゴシック体をベースに「トロイ活字」や「チョーサー活字」を考案したりした。印刷用紙にも質を追求し、自分の本には手漉きの紙を使用させた。
美しい書物を作るために、字間、行間などだけでなく、文字が配置される版面の外のマージン(余白)の比率などにもこだわり、印刷物における文字の体裁を整える活版印刷術(タイポグラフィー)を編み出した。特にページの上下左右のマージンの比率を設定する「モリスの法則」は、現在でもデザインの基本とされている。
彩飾写本、カリグラフィー、雑誌の編集、自作の詩や散文の出版などを通して魅力的な書物の在り方を考えていたモリスは、1891年(57歳)ついに印刷工房「ケルムスコット・プレス」を設立する。このプレスの傑作となる『ジェフリー・チョーサー作品集』は1895年11月にデザインが完了し、1896年6月に印刷を終えた。モリスは、彼の夢であった「美しい書物」の印刷を完成させ、その4カ月後に亡くなった。モリスの主治医は、「一人で十人分以上の仕事をこなし、そのために亡くなったのだから、病名はウィリアム・モリス病だ」と語ったそうだ。
※8 抽象文様で埋め尽くされたページのこと
4.民藝運動と柳宗悦
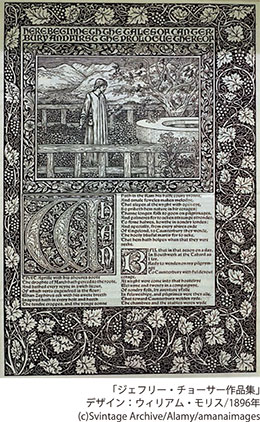
 「アーツ&クラフト運動」は、日本の「民藝運動」に影響を与えたと言われる。「民藝」とは民衆が日常に使う工芸品を指し、民藝運動は1926年に「日本民藝美術館設立趣意書」の発刊により開始された。柳宗悦(1889~1961)は、伝統によって生み出された実用的な工芸品のなかに美を見出し、英国人バーナード・リーチや濱田庄司、河井寛次郎、富本憲吉をはじめとする陶芸家などが民藝運動に参加した。
「アーツ&クラフト運動」は、日本の「民藝運動」に影響を与えたと言われる。「民藝」とは民衆が日常に使う工芸品を指し、民藝運動は1926年に「日本民藝美術館設立趣意書」の発刊により開始された。柳宗悦(1889~1961)は、伝統によって生み出された実用的な工芸品のなかに美を見出し、英国人バーナード・リーチや濱田庄司、河井寛次郎、富本憲吉をはじめとする陶芸家などが民藝運動に参加した。
柳は、「並々ならぬ修行で腕を磨いてきた職人の技は誰でもすぐにできるものではない」と職人の仕事を高く評価した。一般的に美術品には作り手の名が銘や落款で記されているが、工芸品には職人たちの名がどこにも記されていないので、名前のない工芸品の価値は正当に評価されないことが多い。そうした見方を是正したい柳は、日本が素晴らしい手仕事の国であることを実際に確認するために全国津々浦々を回り、1948年に著書『手仕事の日本』を発刊した。
またモリスと同様に柳は、「利益本位の機械生産で出来たものは粗末になりがちであり、人間が機械に使われるのでは働く人の喜びも奪ってしまう」と機械生産を批判した。「機械には心がないが、人間の手はいつも心と直接つながっているからこそ、品物に美しい性質を与える。手仕事は心の仕事である」と著書で訴えたのである。
モリスと柳はゴシックの中世美を愛する点で似ており、柳自身も「アーツ&クラフツ運動」の基本理念に共鳴していたが、美術は工芸より上等だとするモリスの考えには異議を唱えた。モリスがそう考えたのは、画家を目指していたからであろうが、モリスと柳の二人が工芸を愛し工芸の発展に多大な貢献をしたことは間違いのない事実である。
モリス商会が1940年代に倒産したあと、モリス・デザインの大部分は他社に買い取られ、「Morris&Co」というブランド名で今でも主に布製品と壁紙で販売されており、時代を超越して根強い人気がある。
次回のテーマは、産業革命期における英国のクラシック音楽についてである。英国人に帰化したドイツ人のヘンデル(1685~1759)やエルガー(1857~1934)、ホルスト(1874~1934)ぐらいしか作曲家の名前が思いつかない英国であるが、産業革命期における音楽家の置かれた状況や楽器の進歩などに焦点を当てる。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第15回]~2021年7月号
産業革命のおかげで豊かになった19世紀後半の英国では、美術鑑賞が人気となる一方で、美術画壇を牛耳るロイヤル・アカデミーは伝統を重んじるようになり、画家たちに型通りの伝統的な画法を強いるようになった。こうした風潮に反発した若い画家たちは、美術評論家ジョン・ラスキンの芸術論を精神的支柱として、第1期のラファエル前派※1を結成した。ラスキンは、近代画家論のなかで「愛すべき自然をありのままに再現すべきだ」と提唱するとともに、「工場労働者の劣悪な環境や熟練職人の厳しい状況を改善すべきだ」として機械文明を批判していた。
このラスキンとラファエル前派の画家ロセッティを慕って、オックスフォード大学を出た画家志望のウィリアム・モリスとエドワード・バーン・ジョーンズの二人が第2期のラファエル前派※1に加わることになる。さらにラスキンの考えに共鳴するモリスは、工芸・装飾美術を復興しようと「アーツ&クラフツ運動」を始める。彼は職人たちの手仕事が喪失していく状況に危機感を抱き、工芸を中心に芸術的価値を取り戻し、職人の地位向上を求める運動に熱中するのである。
今回は、ラスキンの思想を出発点とした「ラファエル前派の登場」から、ラスキンの思想的後継者たるウィリアム・モリスが「アーツ&クラフツ運動」を起こすまでの動きを辿る。まずは、モリスがラスキンやラファエル前派の画家たちと出会うまでの流れを追う。
1.ラファエル前派
(1)権威が高まってきた英国美術画壇
英国の最盛期であるヴィクトリア王朝期(1837~1901)には中産階級が力をつけてきたことで、美術への人気が高まる。ロイヤル・アカデミーの年次展覧会の年間入場者数は1830年には7万2686人であったものが、1879年には39万1190人と約50年間で5倍以上となり、美術人気の盛り上がりがうかがえる。鉄道の発達のおかげで、他の地域で展覧会が開催できるようになったことも人気を後押しした。それとともに、優秀な芸術家を育成し、芸術家の地位を向上させることを目的に設立されたロイヤル・アカデミーの権威が高まった。このアカデミーでの伝統的な手法は、初代会長レイノルズ(1723~1792)が信奉したイタリア・ルネサンス最盛期の代表的画家ラファエロ(1483~1520)※2の画法であった。
※1 ラファエル前派は画家ミレイがロイヤル・アカデミー準会員となったことを契機に一旦自然消滅したため、当初のものを第1期、復活後を第2期と呼ぶ。
※2 イタリア語ではラファエロ(Raffaello)だが、英語ではラファエル(Raphael)と発音するため、人名はイタリア語を、英国で生まれた「ラファエル前派」は英語読みを採用している。
(2)ラファエル前派の設立経緯
当時のロイヤル・アカデミーではラファエロを規範とする表現しか認められず、若い画家たちは、構図、色彩など型通りの技法を強いられて辟易
(3)ラファエル前派の擁護者ラスキンの生涯
芸術論でラファエル前派を支えたジョン・ラスキンは、1819年に裕福なシェリー酒商人の父と、敬虔
オックスフォード大学に入学後、1840年に憧れのターナーに会うと、さらに芸術への興味が高じて、1843年に若干24歳で「近代画家論第1巻」を発刊する。緻密な観察力や文章力に加えて、膨大な研究資料による評論は高い評価を受けた。彼は美術評論家として名声を上げると、世間から非難を浴びていたラファエル前派の画家たちの活動を熱心に擁護した。
また、彼は絵画美術だけでなく、建築や社会構造も研究対象とした。特に、当時粗野で不完全とされていた中世のゴシック建築物を再評価するために「ゴシックの本質」を刊行した。この本では中世の職人と19世紀の工場労働者の労働環境を比較し、「仕事の分業化により労働者の仕事は単純労働化され、自分一人では釘の1本も作れなくなった」と機械文明を批判する一方で、中世の熟練した職人の手仕事を高く評価している。
ラスキンは、父親の収入と遺産のおかげで生活の心配をする必要がなかったので、思う存分美術評論や社会活動に没頭できた。1848年に10歳年下のユーフィミア(1828~1897)と結婚するが、彼にとって妻は眺めるだけの存在で、本当の夫婦とは言えなかった。この不幸な結婚は、夫婦関係に不満を募らせていた妻ユーフィミアが、画家ミレイとの出会いで真の愛に目覚め、ラスキンとの離婚を決意するという悲しい結末が待っている。
ラスキンは1878年頃から精神を病み、1900年に永眠した。
(4)神童と呼ばれた画家ミレイの脱退
第1期ラファエル前派の幕引き役となったジョン・エヴァレット・ミレイは1829年に英国のサウサンプトンの裕福な家に生まれ、フランス近くのジャージー島で育った。美少年で幼い頃から画才があったので、彼の両親は息子の才能を伸ばすためにロンドンに転居する。
1840年に史上最年少の11歳でロイヤル・アカデミーに入学し、アカデミーの神童と呼ばれるようになるが、ミレイは「ラファエロの模倣ではなく、それ以前の絵画の初心に戻ろう」という趣旨に賛同してラファエル前派に加わり、熱心に自然観察をして写生をおこない写実性を高めた。そうした苦労が結実し、1852年のロイヤル・アカデミー展に出品した「オフィーリア」が高い評価を得る。この時のモデルとなったのが、のちにロセッティの妻となるエリザベスである。細部まで正確に描きたいミレイは、エリザベスをランプで温めただけの水風呂に入れて、4カ月以上ポーズを取らせた。ミレイの過酷な要求のせいで風邪を引いたエリザベスは、ミレイから50ポンドの慰謝料を受け取ったらしい。「オフィーリア」で名声を得たミレイは、1853年にロイヤル・アカデミーの準会員に選ばれ、体制派に鞍替えする。この時点で、ラファエル前派は一旦自然消滅することになる。
ラスキンに気に入られて資金援助も受けていたミレイは、1853年にラスキンからスコットランド旅行に誘われる。この旅行で、若くハンサムなミレイとラスキンの美しい妻ユーフィミアは恋に落ちる。ミレイと結婚したいユーフィミアは、夫の身体的理由で実際の夫婦生活はなかったとして、ラスキンとの結婚無効訴訟を申し立てた。必死の思いで翌年に離婚を成立させると、多くの非難に耐えて1855年に二人は結婚に至り、8人の子供にも恵まれ幸せな生活を送る。しかし、結婚の経緯からヴィクトリア女王に睨まれて王室からの仕事が途絶えたミレイは、大家族の生計を維持するために収入の良い大衆向けの肖像画を描くことに専念した。画才のある彼は当代きっての人気画家となり、収入も増えて裕福となる。温厚で人柄が良い彼は、1885年には準男爵位を与えられるなど社会的地位も上がり、1896年にロイヤル・アカデミー会長に任命されるのだが、同年に喉頭がんでロンドンの自宅で亡くなった。
(5)ラファエル前派の復活と画家ロセッティ
第1期活動に参加し、形を変えて第2期ラファエル前派として復活させるのがロセッティである。
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティは1828年にロンドンに生まれた。父親はイタリアからの政治亡命者で詩人かつダンテ研究家であった。ロセッティは早くから詩と絵画に才能を発揮し、17歳でロイヤル・アカデミーに入学すると、ここで出会った6人の仲間とラファエル前派を結成した。
ロセッティにとって創作上のインスピレーションの源は、女性たちとの恋愛であった。1850年にロセッティは、画家志望で帽子屋の売り子だった美しい娘エリザベス・シダル(1829〜1862)をモデルに雇う。ロセッティは彼女に詩人ダンテの恋人ベアトリーチェのイメージを見出すほど夢中になり、それ以降彼女をモデルに熱心にデッサンした。しかし、浮気性のロセッティは、1856年に娼婦ファニー・コンフォース(1835〜1906)をモデルに雇うと今度は彼女の官能的な美の虜になる。また彼は、1857年に壁画のモデルとして18歳のジェーン・バーデン(1839〜1914)を見つけだすと、首が長くすらっとした体つきと大きな眼の彼女にも好意をもった。一方でロセッティを想い続けるエリザベスは、彼の浮気のたびに心身ともに消耗させられていた。そんなエリザベスの苦しみに気づいたロセッティは、彼女への罪の意識から1860年に彼女との結婚に踏み切るのだが、1862年に彼女は薬物の過量服用で急死する。
ロセッティは、ミレイのアカデミーへの鞍替えで自然消滅していたラファエル前派を、第2期活動として再興する。写実面で力不足の彼は、細密な風景画に飽きて、豊かな肉体を備える成熟した女性の絵ばかり描くようになる。第2期のラファエル前派は写実主義ではなく、清らかさと神秘的な雰囲気を併せもった艶めかしい魅力の女性像を題材にすることで感覚的で耽美
1856年頃、このようなロセッティを慕って画家志望のウィリアム・モリスとエドワード・バーン・ジョーンズが第2期ラファエル前派に加わる。その後1868年頃になると、妻に先立たれたロセッティは、かつてのモデルで今はモリスの妻となっていたジェーン・バーデンへの恋を再燃させる。ロセッティを崇拝すると同時に自分の妻も失いたくないモリスは、奇妙な三角関係を受け入れて、一時期モリス一家はロセッティとの共同生活をしている。奔放なロセッティであったが、その後亡き妻エリザベスへの想いから精神を病み、1882年に永眠した。
2.アーツ&クラフツ運動
(1)ウィリアム・モリスの幼少から学生時代
ここからは、第2期ラファエル前派に加わったモリスが、ラスキンの影響を受けて工芸に傾倒していく過程を辿る。ウィリアム・モリスは1834年にロンドンの北東ウォルサムストウに生まれた。父親は英国中流階級の富裕で保守的な家柄の出身であり、ロンドンのシティの金融マンであった。株で大儲けしたモリス一家は、1840年にすぐ近くのウッドフォード・ホールの大邸宅に転居した。豪華で大きな屋敷、広大で豊かな庭、それに続く美しい森など、幼い頃見た風景が彼の芸術の原点となる。彼が13歳の時に父親が亡くなり、母子家庭となって小さい家に引っ越したが、生活には困らなかったようだ。
1853年にオックスフォード大学に入学すると、親友となるメッキ職人の息子エドワード・バーン・ジョーンズ(1833~1898)と出会う。ジョーンズからさまざまな人たちを紹介されたモリスは、詩や美術、建築に目覚め、ラスキンの著作などを通してゴシック建築やラファエル前派に興味を持つことになる。階級的に差があるモリスとジョーンズであったが、大学を卒業するとロンドンへ出て共同生活を始め、ともに画家を目指した。1856年にはロセッティを慕って、二人で弟子入りすることになり、モリスの将来を大きく左右するラスキンと実際に顔をあわせることになる。
(2)ジェーン・バーデンとの結婚と新居レッドハウス
1857年にロセッティの提案で「アーサー王の死」をテーマにした壁画を描くプロジェクトが始まり、ロセッティはそのモデルにジェーン・バーデンを採用する。モリスは、モデルとしてジェーンを描くうちに次第に親しくなり、1859年に結婚する。
自分たちの新居をテムズ河の南ベクスリィヒースに建築すると決めたモリスは、建築家などの友人たちに建物の設計や内装での協力を依頼した。皆で創り上げた新居は「レッドハウス」と呼ばれ、憧れの中世を倣って美しく装飾されたインテリアデザインが評判となる。
中世のゴシックを模したレッドハウスの建築には1年を要したが、この時の経験が「自分の必要なものを自分自身で工夫して作ることを楽しむのが、理想の生活である」という意識を強くした。それと同時に大気汚染、都市の過密化と生活環境の悪化、農村の過疎化、貧富の格差拡大などから、「現代文明に対する嫌悪感」を強めた。
モリスにとって、レッドハウスは内装の実験工房となり、自らデザインした内装が評判になったことを機に本格的にデザイン制作活動に入る。これ以降、多才なモリスは、詩人、作家、デザイナー、実業家、翻訳家、カリグラファー、染織工芸家、美術館アドバイサー、園芸家、自然環境保護推進者、古書蒐集
(3)モリス商会からアーツ&クラフツ運動へ
彼は、1861年に「モリス・マーシャル・フォークナー商会」を設立する。設立メンバーには、ロセッティやジョーンズも加わった。中世のギルド制度を模範として、労働の価値と職人の地位を高めることが彼の目的であった。現在で言えばインテリアのデザインと製作を行う会社であり、他にも壁面装飾、彫刻一般、宝石装飾や金工、家具、押し型革細工、刺繍
そして、モリスが先導してきた工芸復興運動は、「アーツ&クラフツ運動」に結びついた。この運動の名前は、1887年に設立されたアーツ&クラフツ展覧会協会が、その翌年に開催した「アーツ&クラフツ展」に由来している。工芸品のための最初の展覧会である「アーツ&クラフツ展」が大成功を収めたことを機に、この工芸復興運動は英国だけでなく、ヨーロッパ大陸やアメリカにも広がることになる。この運動の特徴は手仕事の復興であるが、徹底的に機械生産を嫌い手工芸にこだわったために、モリス商会の製品は一部の金持ちしか買えない高価なものとなった。この矛盾に悩んだモリスは社会主義運動にのめり込んでいった。モリスは最後まで理想を追い続けながら、1896年に62歳で永眠する。
 ここまで辿ってみると、ラファエル前派の活動があったからこそ、モリスはラスキンに出逢い、「アーツ&クラフツ運動」を興すことになったことが分かる。また、今回の複雑な人間関係を振り返ると、ラスキンの妻ユーフィミアは彼と離婚後ミレイと結婚し、ロセッティはモリスの妻であり自分のモデルであったジェーンに恋し、ミレイの名画「オフィーリア」のモデルであるエリザベスはロセッティの妻であったということになる。
ここまで辿ってみると、ラファエル前派の活動があったからこそ、モリスはラスキンに出逢い、「アーツ&クラフツ運動」を興すことになったことが分かる。また、今回の複雑な人間関係を振り返ると、ラスキンの妻ユーフィミアは彼と離婚後ミレイと結婚し、ロセッティはモリスの妻であり自分のモデルであったジェーンに恋し、ミレイの名画「オフィーリア」のモデルであるエリザベスはロセッティの妻であったということになる。
ところで画家ミレイの名画「オフィーリア」は本当に印象深い絵画である。私も実際に観た時には、小川に沈む女性の姿がくっきりと脳裏に焼き付いた。シェイクスピアの四大悲劇の一つ『ハムレット』の一場面を題材として「匂い立つ緑と可憐な花々に囲まれ、水に沈んでいく無垢な乙女オフィーリア」を描いた絵は当時も大変な人気を得た。夏目漱石の小説『草枕』の中に「ミレイの描いた、オフィーリアの面影が忽然と出てきて…」という一節があるが、この絵をロンドンで実際に観て強い印象を受けたことから、漱石は絵画的と言われる小説『草枕』の着想を得たのだろうか。
来月は、実際にモリスが手掛けた壁紙やテキスタイルなどの工芸品を取り上げて、彼のこだわりの部分に焦点を当てたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第14回]~2021年6月号
英国出身の有名な画家といえば、風景画家のターナー(1775〜1851) と一歳違いのコンスタブル(1776〜1837)が挙げられる。
美術後進国であった英国では、18世紀初めまでは外国人画家が重用され、かつ人気があったのは肖像画であり、風景画ではなかった。ところが、19世紀に入り英国が産業革命によって絶頂期を迎えると、二人の代表的な英国人風景画家が現れたのである。
産業革命による社会・環境の変化や価値観の変容などが、美術界にどのような影響を与えたのであろうか。今回は二人の代表的な風景画家の人生を辿りながら考察する。
1.18世紀以降の風景画の位置付け
18世紀の英国画壇では、歴史画、肖像画、風俗画、風景画という油彩画の格付けは変わらず、風景画の位置付けは依然として低かった。その頃、英国の上流階級はグランドツアー(教養修得のための旅行)の記念として景勝地や歴史的建造物を細かく描写した地誌的風景画を購入していた。特にフランス人でイタリア在住画家のクロード・ロラン(1600年代〜1682)の絵は、古代建築や廃墟など歴史画の主題を融合させた格調高い「理想的風景画」として彼の死後も人気があった。また、ヴェネツィア出身の風景画家カナレット(1697〜1768)は、1746年から9年ほど英国に滞在して、ロンドンの名所を描き、人気が高かった。
19世紀に入り、英国の工業化・都市化・市民社会化によって国力が充実すると、貴族や地主などの上流階級だけでなく、商人や知的専門業者のような裕福な中流階級も絵画を購入するようになった。彼らの中には鑑賞用というよりも、財力を誇示するために、自分が保有する豪華な屋敷や広大な敷地を風景画に描くように画家へ注文する者もいたらしい。また、オランダで流行した写実的な風景画が英国でも人気が出て、購入されるようになった。
2.「ピクチャレスク」と「サブライム」の流行
18世紀後半の英国では「ピクチャレスク」と「サブライム」という独特の美学的概念が広まった。「ピクチャレスク」は「絵画的な」を意味する言葉で、著述家ウィリアム・ギルビンが理念化した概念である。一方の「サブライム」は険しいアルプスのように人々を畏怖させる風景を指し、哲学者エドマンド・バークが提唱した。こうした美学的概念が流行すると、想像力を刺激するような廃墟や起伏に富む地形、曲がりくねった古木などの荒々しい風景が人気となった。これまで関心のなかった英国の田園風景が美しいと感じられるようになると、古代ローマ時代からの温泉地であるバースや詩人ワーズワースが賛美した湖水地方などへのピクチャレスク・ツアーがブームとなった。それとともに水彩画が流行する。写真のない時代、旅人は自ら水彩絵具を携帯して、旅行先の風景を描いた。水彩画は油彩画と違って、道具が持ち運び易く、短時間で仕上げられるのが特長だ。もともと地誌的な記録用や油彩画の習作、版画の下絵であった水彩画が、英国では18世紀後半から19世紀前半に上流階級の子女の教養や趣味として広く普及していたことも、その流行を下支えした。
英国は、18世紀後半からの農地の囲い込み運動によって牧草地や共有地が畑に変わり、都市は石炭によるスモッグで著しく環境が悪化していた。自然に対する郷愁や憧憬に駆られた人々は、風景画の中に自然豊かな自分たちの原風景を求めようとしたのであろう。このように英国の人々のなかに風景画への関心が高まり、自ら趣味で描く水彩画だけでなく、購入対象の油彩画においても人気がでてきた。
また、ピクチャレスクやサブライムという独特の美学的概念は、18世紀末には感情や個性を重視する英国ロマン主義へとつながっていく。
3.国際的な美術市場の中心地となったロンドン
18世紀末のフランス革命や19世紀初頭のナポレオン戦争によって、ヨーロッパ大陸の諸国が危険な状態となり、イタリアなどへの渡航を断念せざるを得なくなったことも、英国の風景を見直し英国国内に理想郷を探し求める契機となった。
また、革命と戦争によって、ヨーロッパ諸国の貴族や富裕層は所有する名画をナポレオンに奪われるのではないかと危惧し、「略奪されるくらいなら外国に売却しよう」と考えた。その結果、英国人画商の仲介により大陸にあった名画が続々と経済大国の英国に持ち込まれた。オークション会社として「サザビーズ」が1744年に、「クリスティーズ」が1766年に設立され、ロンドンはフランス革命後の国際的な美術市場の新しい中心地となり成長する。英国の繁栄到来とともに一躍美術の中心地となるのであった。
そうした社会の変化の中で、美術後進国であった英国から19世紀後半のフランス印象派に大きな影響をおよぼした二人の画家が現れた。ここからは、ターナーとコンスタブルという二人の風景画家が芸術の国フランスの先駆的存在となった要因を探る。
4.フランス印象派に影響を与えた英国風景画家
(1)ターナーの生涯
ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーは1775年にロンドンの下町コヴェント・ガーデンの理髪店の長男に生まれた。生活は困窮し、ひどい癇癪
画家としては10歳頃から非凡な才能を示した。名所などを忠実に描く地誌画家トマス・マートンに1年ほど弟子入りして水彩画の基礎技術を身につけると、14歳(1789年)の時にロイヤル・アカデミー附属美術学校に授業料免除で入学し、翌年のロイヤル・アカデミー展覧会では水彩画で入選した。油彩画での初出展は22歳(1797年)の時で、24歳にはロイヤル・アカデミーの準会員、27歳には正会員となり、29歳の時に自身の画廊を開き、32歳にはロイヤル・アカデミーの教授となった。
貧しかったターナーは若い頃から「売れる絵」を描くことに固執していた。20歳代ですでに腕の良い水彩画家だった彼のもとには、貴族や地主から館に飾るための風景画の注文が殺到した。また、彼の美しく的確な構図の絵は、版画の下絵に向いており、当時人気のあった挿絵入り出版物用として多くの注文がきた。
彼は風景画を描くために、英国国内やヨーロッパ各地を広く旅行している。27歳(1802年)の時にスイスを訪れた際には、アルプスの険しい山並みで激しい吹雪を体験し、自然の力と雄大さに深い感動を覚えた。44歳(1819年)に初めて訪問したイタリアでは、明るい太陽とまぶしい光に満ちたヴェネツィアやフィレンツェの美しさに感動して、約半年の旅行で1500点余りのデッサンを残した。
イタリア旅行以降は光と色彩のもつ無限の可能性に目覚めて、目に見えにくい光や空気を主題に描くようになった。特に光の描き方に特徴があり、朝陽、夕陽、火事の炎まで、あらゆる種類の光を捉えて作品の中に描き込んだ。色彩による光の表現を追求していたターナーは、1840年に英訳された文豪ゲーテの『色彩論』を読んで参考にした。
多才なターナーは芸術性の高い風景画を完成するためにさまざまなテーマに挑戦している。手法も緻密で写実的な描き方から粗い筆致のものまで幅が広い。しかし、晩年には目が悪くなったこともあり、モノの形さえも光に溶け込んでしまうような混沌とした抽象的な作風に変化していった。また、若い頃のようにお金や地位に固執しなくなり、人に知られないように偽名を使って貧しい下宿暮らしをしていた。一生独身だった彼は76歳(1851年)の時にコレラが原因で永眠し、遺体はセントポール大聖堂に葬られた。彼の残された作品は遺言により国家に遺贈された。それから20年後に普仏戦争(1870〜1871)の兵役を避けてロンドンに滞在していたフランスの巨匠モネが、ターナーの英国風景画を観て大きく刺激を受けることになる。
(2)コンスタブルの生涯
ジョン・コンスタブルは、1776年にロンドンの北東にあるサフォーク州イースト・バーゴルトに裕福な製粉業者の6人兄弟の4番目の子として生まれた。7年間ほど家業を継ぐための勉強をしていたので、ロイヤル・アカデミー附属美術学校に入学したのは23歳(1799年)の時とスタートが遅く、ロイヤル・アカデミーの展覧会への初出展は26歳の時である。
父親からは画家になるなら需要の多い肖像画家を目指すように忠告されたが、純粋で頑固な性格のコンスタブルは聞き入れなかった。長い間、故郷サフォーク周辺の身近な風景を描き続けた。彼は、同じ場所でも同じ風景は二度と目にすることはできないとして、刻々と変化する英国の自然の風景、しかもひたすら身近な風景ばかりを追い続け、人気の名所旧跡や珍しい景観の絵は描かなかった。
33歳(1809年)の時に幼なじみのマリア・ビックネルと恋におちる。マリアの家族から売れない画家に娘はやれないと反対されたが、1816年にロンドンで挙式し、その後7人の子供を授かった。愛妻家である彼の結婚生活は幸せだったのだが、何の変哲もない田舎の風景画が売れるはずもなく、生活費のために肖像画の注文も若干受けていたようだ。
また、大気の揺らぎや光のきらめきなど自然の色彩を忠実に表現しようとした彼の手法はタッチが粗いので、絵が未完成のままだとか下手であると思われていた。木々に白く点描した「コンスタブルの雪」と呼ばれる描き方は、後の印象派では技法の一つとなる「筆触分割」の先駆だと言われる。「筆触分割」とは、絵具を混ぜず、細かいタッチを重ねて画面を構成する手法であり、離れて見れば自然に見える。また、18世紀まで木々を茶色で描くのが古めかしくて趣があるとされていたが、コンスタブルは細かく観察し、違いが分かるように丁寧に描いたので、木々の緑が生々しすぎると批判された。
彼は、「空はすべての絵画の基調」であり、「自然こそ、あらゆる創造力が湧き出る源泉である」と考えていた。デッサンした下絵を参考にして工房でキャンパスに絵を描くのが常識の時代に、徹底的に野外での制作にこだわった。その時代にはまだチューブ式絵具はなかったので、わざわざ豚の膀胱に絵具を詰めたものを持参して油彩画を描いた。また、雲などをスケッチする際には、日付、時間、気象状況、どの位置から描いたかなどを克明に記録するなど科学的な視点をもっており、ロンドンの郊外ハムステッドに滞在した1821年からの2年間で空の習作だけで100点近く描いた。
1821年にロイヤル・アカデミーの展覧会にサフォークの風景を描いた「干し草の車」を出品した。この出品は英国では話題にならなかったが、この絵を見たフランスの画家ジェリコーが感動し絶賛したのを機に、フランスでの関心が高まった。1824年のパリのサロン展にこの作品他12点が展示されると「干し草の車」は金賞を受賞した。フランスの画家たちはコンスタブルが生み出した粗いタッチによる鮮やかな色彩に驚嘆したのだ。コンスタブルは英国よりフランスで有名となり、パリに招待される。しかし彼は、「外国で金持ちになるよりは、貧乏なままでも英国にいたい」としてパリには行かず、故郷の絵を描き続けた。愛妻マリアに結核の疑いがあったこともパリ行きを諦めた原因と言われる。
ロイヤル・アカデミーの正会員となるのは1829年53歳の時で、その前年には愛妻のマリアを結核で亡くしていた。「遅すぎた。最早私は独りだ。この喜びを分ちあえる人はもういない」と嘆いたらしい。
1837年に急に苦痛を訴えると60歳で息を引き取った。子供たちは、売れなかったコンスタブルの大量の絵を手元に大事に保管していたが、1880年後半に最後に残った子供が保管していた絵をすべて国家に寄贈した。彼の絵はロマン派のドラクロアを始めとしてバルビゾン派や印象派の画家にも大きな影響を与えた。
(3)二人の風景画家の比較
ターナーとコンスタブルを比較する。この二人の生い立ちを見ると、ターナーは貧しい家に生まれ独身のままであったが、コンスタブルは裕福な家に生まれ7人の子供をもつ愛妻家であった。
絵の制作活動についても対照的だ。才能豊かなターナーは売れるもの、画壇に評価されるものなら何でも描き、さまざまな作風を取り入れた。題材も海や船から、産業革命の象徴である蒸気機関車までと幅広い。嵐や吹雪など激変する自然を主題にすることを好み、燃え盛る炎が作り出す大気を描くために国会議事堂の火事も主題にしている。絵を描くためには、列車の窓を開けて首を突き出し10分近くも外を見たり、暴風で揺れる船のマストに67歳の自分の体をくくりつけて、4時間もの間、海を見続けたりしたらしい。奇人のターナーにとって、自分自身の体験こそが臨場感あふれる作品を生みだす源泉だったのだろう。これに対して、コンスタブルは一貫してなじみの風景を描くことに固執し、画風や題材に著しい変化はなかった。
活動範囲については、ターナーは湖水地方やウェールズ地方などの国内だけでなく、国外ではヨーロッパ諸国や西インド諸島まで足を延ばす一方で、コンスタブルは産業革命による大都市の変化には目もくれず故郷を中心に国内にとどまり、自分の絵が絶賛されたフランスからの招待も断った。
作風については、自然の表現に長けていたという点は共通しているが、ターナーは光と色彩の効果的な表現に、コンスタブルは光と大気の忠実な再現に重点を置いた。ロイヤル・アカデミーでの評価は、地味なコンスタブルより、歴史や文学を主題に描いたターナーの方が高かった。
二人が印象派の先駆けとなることができたのは、美術後進国の英国では自由な作風が許されたからである。美術大国フランスではすでに厳格な伝統的手法のルールが確立されており、新たな作風に挑戦しようという気運は生まれてこなかったのであろう。
(4)展覧会での二人の対決エピソード
 2021年2月から、「コンスタブル展」が東京で開催されており、因縁の二人の作品対決コーナーが話題となっている。コンスタブルの「ウォータールー橋の開通式」とターナーの「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」という2枚の絵が1832年開催のロイヤル・アカデミー展を再現して並んで展示されているのだ。コンスタブルの絵は「縦130.8cm、横218cmと大きなサイズ。物語性に富んで、赤などの暖色が中心」であるのに対して、ターナーの絵は「縦91.4cm、横122cmとサイズも控えめ。青などの寒色が中心」である。
2021年2月から、「コンスタブル展」が東京で開催されており、因縁の二人の作品対決コーナーが話題となっている。コンスタブルの「ウォータールー橋の開通式」とターナーの「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」という2枚の絵が1832年開催のロイヤル・アカデミー展を再現して並んで展示されているのだ。コンスタブルの絵は「縦130.8cm、横218cmと大きなサイズ。物語性に富んで、赤などの暖色が中心」であるのに対して、ターナーの絵は「縦91.4cm、横122cmとサイズも控えめ。青などの寒色が中心」である。
当時ターナーは、展覧会が開催される前に出品した絵の確認に訪れた。そこで彼は、「自分の絵がコンスタブルの絵に迫力負けしている」と感じ、展覧会の壁にかかった自分の絵に、鮮やかな明るい赤の絵具の塊を波間に浮かぶブイの形のように描き込んだ。この赤いブイによってターナーの絵の印象が格段に強くなった。これを見たコンスタブルは「ターナーがやってきて、絵に銃をぶっ放していった」とこぼしたらしい。二人の激しいライバル意識が読み取れるエピソードである。
産業革命によって引き起こされた社会の変化は風景画の主題にも影響を及ぼした。また、英国で水彩画がブームとなった背景には、18世紀末に石鹸工業の副産物として発見されたグリセリンの存在がある。これを絵の具に添加すると乾燥せず長期保存が可能となり、水彩画の普及に一役買った。これも、産業革命による工業化の産物である。しかし、産業革命による急速な発展や大量生産・大量消費がひずみをもたらすと、新たな芸術改革運動としてラファエロ前派が現れるとともに、産業革命後の社会への批判としてウィリアム・モリスによるアーツ&クラフツ運動が始まるのである。次回はそうした運動の経緯を取り上げる。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第13回]~2021年5月号
夏目漱石の生涯を描いた伊集院静氏の小説「ミチクサ先生」が新聞で連載されており、その中に漱石が1900年10月から2年余り英国留学していた場面が出てくる。孤独で鬱陶しい生活を送っていた漱石を虜にしたのが、ロンドン・ナショナル・ギャラリーにあったウィリアム・ターナー(1775〜1851)の絵画であった。漱石はターナーの風景画を見て水墨画をイメージしたらしい。彼がよく通ったロンドン・ナショナル・ギャラリーは13世紀後半から20世紀初頭までの多数の作品を所蔵する人気の美術館だが、実は英国人画家のものは少ない。
16〜17世紀の英国は、自国の画家が軽視され外国人の画家が好まれる絵画低迷の時代であったのに対して、17世紀のオランダは絵画黄金期を迎えている。この違いを生んだ背景は何であろう。
今回は、産業革命が始まる18世紀までの歴史的事実を辿りながら、英国とオランダの相違点を比較することで、宗教、政治、商業が絵画に及ぼした影響を考察する。
1.西洋絵画の序列
英国とオランダの美術史に触れる前に、まず17世紀から19世紀にかけてヨーロッパで確立された「絵画におけるジャンル別の序列」を頭に入れておこう。上から順に歴史画→肖像画→風俗画→風景画→静物画である。
最上位の「歴史画」は、古代史、旧・新約聖書、ギリシア・ローマ神話などの古典文学、寓話などをテーマに描いた絵画であり、宮殿や教会などに飾られたので大型作品が多かった。歴史画には絵のテーマに関するさまざまな知識が不可欠なので、画家も鑑賞者も教養と品格が求められた。
2番目の「肖像画」は、王侯貴族や宗教関係者などの地位の高い人の肖像が中心だ。画家は題材となる人物そっくりに描くのではなく、依頼主がどのように自分を見せたいかを汲み取って描いている。
3番目の「風俗画」は庶民を中心に人々の日常生活の一場面を描いたもので、歴史画に比してサイズも小型の作品が多い。
4番目の「風景画」は、自然の風景、都市景観を描いた。画家にとって風景画を描くのは、歴史画の背景を描く練習になった。
そして最下位の「静物画」は、花、果物、道具など身の回りにある動かないモノを正確に写して描くだけなので、大した知識も必要でなく最下位となったらしい。
絵画の序列は画家の格付と連動し、最上位の歴史画を描く画家の評価が高くなった。たとえばイタリアでは、14世紀頃までは、画家や彫刻家は大工や金細工師と同じく職人という位置づけだったが、16世紀のルネサンス全盛期では、歴史画を描くラファエロ、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロの三大巨匠が登場し、彼らの作品は芸術品と見做
一方、美術後進国の英国では、自国の画家は職人という地位に留まったままであった。
2.英国の絵画史
(1)英国における宗教改革による影響
歴代の英国王の中でも、インテリでかつ無慈悲な専制君主として名高いヘンリー8世(在位1509〜1547)は、ローマ・カトリックと絶縁して1534年に英国国教会を樹立している。独善的な国王は男子の世継ぎが欲しくて最初の王妃であるキャサリン・オヴ・アラゴンと離婚しようとしたが、ローマ・カトリックでは離婚が禁じられており、ローマ教皇の認可が得られなかった。そこで国王は首長令を発布して自ら英国国教会の首長となることで、離婚を可能としたのである。また、カトリックの修道院に解散を命じて修道院の土地や財産を没収し国有化したので、カトリック教会の勢力は一挙に弱まった。これを機に国内でプロテスタント信者が力をもつようになると、宗教画や宗教彫刻の制作を禁ずる「イコノクラスム(聖像破壊運動)」が各地で過激化し、英国における中世の豊かな文化遺産の多くが失われてしまった。
布教活動に絵画を積極的に活用していたカトリック教会の力が弱まると、画家たちは教会という中世以来の最大のパトロンを失った。王侯貴族からの肖像画の需要は残るのだが外国人画家が好まれたので、英国人画家の大半は廃業するか国外に働き口を求めざるを得なくなり、英国美術は一層影が薄くなった。ヘンリー8世も絵画に関しては外国人の画家を重用し、特にドイツ人のハンス・ホルバイン(1497〜1543)に惚れ込んだ。ホルバインは、ヘンリー8世自身の肖像画だけでなく、宮廷関係者たちの肖像画を多数制作するとともに、細密肖像画の制作にも乗り出し、英国での細密肖像画を発達させた。
ヘンリー8世の次に即位した息子のエドワード6世(在位1547〜1553)が夭折
(2)英国ルネサンスにおける絵画の位置付け
メアリー1世は即位5年後に卵巣がんで死去し後継ぎとなる子供がいなかった。次に即位したエリザベス1世(在位1558〜1603)はプロテスタント信者であったが、カトリック信者を弾圧せず、カトリックとプロテスタントのバランスを保持して英国国教会の基礎を固めた。生涯独身を通したエリザベス1世のもとで第1次黄金期を迎えた英国は、演劇を中心とする英国ルネサンスを迎えた。芝居好きのエリザベス1世がパトロンとなって演劇を支援したからである。この時期の演劇を代表するのが「ハムレット」などで有名な劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564~1616)である。
絵画に関しては、自分の肖像画をフランドルなど外国出身の画家に数多く描かせているが、あくまで女王の威光を示すためであり、女王自身はあまり絵画への興味がなかったようだ。
16世紀後半に英国出身の有名な画家が初めて現れた。イングランド生まれの画家ニコラス・ヒリアード(1547〜1619)であるが、専門としたのは直径数センチの子牛の皮を加工した円形の生地面に水彩でモデルの胸像を描く細密肖像画である。ヒリアードは、宮廷画家ホルバインを引き継いで宮廷の細密肖像画家となったのであるが、画家としての格付けは低かった。細密肖像画の制作は、もともと手先の器用な職人が小遣い稼ぎでやる副業だったからである。完成した細密肖像画は、女王や廷臣たちが豪華な宝飾品として身につけて楽しんだり、宝石細工の箱に入れられて大切に保管されたりした。
(3)17世紀英国の宮廷画家は外国人
エリザベス1世の次に即位したジェームズ1世(在位1603〜1625)も絵画には関心が薄かった。しかし、その息子のチャールズ1世(在位1625〜1649)は歴代英国王の中でも最も熱心な美術愛好家であり、ドイツ人画家ルーベンスに父ジェームズ1世を讃える豪華な天井画を注文している。1632年にはフランドル出身の画家ヴァン・ダイク(1599〜1641)を宮廷画家として英国に招聘し、騎士の称号を与えた。引き続き、英国では外国人画家だけが優遇され、英国人画家の地位は低いままであった。その後、議会と対立したチャールズ1世はオリバー・クロムウェルを指導者とするピューリタン革命によって1649年に処刑されるが、1660年にフランスに亡命していたチャールズ2世(在位1660〜1685)が王政復古を成し遂げる。チャールズ2世は宮廷画家としてオランダのピーター・レリー(1618〜1680)や北ドイツ出身のゴドフリー・ネラー(1646〜1723)を重用した。特にネラーはハノーヴァー朝のジョージ1世(在位1714〜1727)の時代まで長く重用された。
(4)グランドツアーと外国人画家への贔屓
王侯貴族たちが外国人画家の絵画を好んだのには、17世紀初めに始まったグランドツアーの影響が強いと思われる。裕福な貴族の子弟は国内の学業が終了すると、文化が進んだイタリアやフランスへ贅沢な短期留学(グランドツアー)をして、美術の勉強だけでなく、現地で絵画を購入していた。
18世紀になるとグランドツアーでイタリアを訪れた英国貴族の間で、ローマ在住のフランス人画家クロード・ロラン(1600頃〜1682)やカナレット(1697〜1768)の風景画が大変人気となり、購入された多くの作品が英国に渡った。理想郷的なロランの絵はターナーを始めとする英国人風景画家に影響を与えた。写実的に都市を描いたカナレットの風景画はイタリア旅行の思い出として求められ、特にジョージ3世(在位1760〜1820)はカナレットのコレクターとして膨大な数の絵画を残した。
(5)18世紀からの英国人画家の台頭
1760年代は、英国で蒸気機関の発明などによる産業革命がスタートした時代であり、富裕な産業資本家たちが現れてきた時代でもある。
その頃から、ようやく英国人画家たちが台頭してくる。まずは英国近代絵画の創始者とも称されるウィリアム・ホガース(1697〜1764)である。画家、版画家、モラリストでもあったホガースは当時の政治闘争や芸術闘争に積極的に参加し、人々の社会道徳的な逸脱を嘲りの題材とした連作風俗画や「カンヴァセーション・ピース」と呼ばれる家族や友人などの集団肖像画を手掛けた。ホガースのドラマ的な連作版画は、道徳を揶揄するだけでなく、滑稽さやエロティシズムも満載であったので、大当たりした。また、カンヴァセーション・ピースは、従来の肖像画より小さいサイズであり、富の象徴である豪華な館内の様子も描かれたので、植民地貿易や産業革命によって台頭してきた裕福な中産階級の間で人気を博した。
一方、上流階級の人々を描いた代表的画家として、ジョシュア・レイノルズ(1723〜1792)とトマス・ゲインズバラ(1727〜1788)がいる。歴史画こそ絵画の頂点と考えるレイノルズはルネサンスの巨匠に倣って歴史画と肖像画を融合させ、モデルを理想化して描いた。風景画を得意とするゲインズバラは、モデル、衣装、風景の3つの要素を調和させた形式張らない新境地を拓いた。
(6)英国ロイヤル・アカデミーの創設
美術先進国であるフランスでは、ルイ14世のもとで王立絵画彫刻アカデミーが1648年に創設されていた。英国でもようやく自国の画家が力をつけてくると、優れた芸術家の育成と供給を目的に国王ジョージ3世の許可を得て、英国人画家の悲願であった英国ロイヤル・アカデミーが1768年に創設された。
外国人画家に頼らず英国人画家を養成して、画家の社会的地位を上げ、美術鑑賞を国民に啓蒙することを目的に、当初は正会員40名、準会員20名で構成された。初代院長はジョシュア・レイノルズであり、夏目漱石が愛したターナーやジョン・コンスタブル(1776〜1837)らが正会員となった。
3.オランダの絵画史
(1)17世紀のオランダにおける絵画黄金期
次に、英国と同様に宗教改革の影響をうけたオランダの絵画史を辿る。
15世紀にネーデルランド(現在のオランダ、ベルギー、ルクセンブルク)やドイツなどアルプス以北のヨーロッパで芸術が栄えた。15〜16世紀のネーデルランドは、経済的、政治的、文化的にも重要な場所であり、交易や毛織物を中心に商工業が栄えていた。絵画の輸出もあったようであり、当時の画家の巨匠にはピーテル・ブリューゲル父(1525頃〜1569)がいる。
16世紀の後半には、英国と同様にプロテスタントが多いオランダでもルターやカルヴァンなどの宗教改革によって宗教画や宗教彫刻が否定された。画家たちは大口発注者である教会からの注文が一気に消えてしまったので、新しい顧客層が必要となった。17世紀のオランダで強い発言権を持っていたのは、貴族や教会ではなく、貿易で活躍する商人を中心とした市民階級であった。市民階級の人々は、難解で重厚な歴史画ではなく、自分の家や職場に飾れる絵として集団肖像画や家庭肖像画、風俗画などを求めたので、画家たちは親しみやすい風俗画や風景画など幅広いテーマで絵画を描くようになった。また一般家庭で飾りやすいように比較的小さいサイズの絵画が人気となった。ちなみに有名なヨハネス・フェルメール(1632〜1675)の「レースを編む女」は縦24.5cm、横21cmとA4サイズに収まるくらいに小さい。
(2)オランダにおける絵画バブル
こうして、17世紀のオランダは絵画黄金時代と呼ばれ、風俗画、風景画、静物画が発展するのだが、絵画の人気が出てくると、美術品というよりは市場価値をもった商品となっていく。生産性を上げるために、画家たちは従来の時間と手間のかかる技法をやめて、主に中間色を用いる技法に換え、1日に1点の速さで絵画を完成するようになった。当時のオランダは画家の数が多かったので、各専門分野の画家たちが一枚の絵を手分けして描けるように工房での工程を分業化し、さらに生産性を上げた。17世紀中ごろの画家一人当たりの年間平均作品数は90点余りだったと言われる。
絵画の購入の仕方も発注者が直接画家の工房に来て注文するのでなく、画商やオークションのようなマーケットを通して購入できるようになったようだ。このように絵画が市場に大量に出回るようになると質の悪い絵画もでてきたが、絵画売買は裕福になった市民階級の投機の対象として熱気を帯びて、バブル状態となった。
しかし、17世紀後半にオランダの経済が衰退し、富裕な購入層が減少すると、同時期に投機対象となっていたチューリップの球根と絵画のバブルは崩壊した。17世紀末にはオランダの画家の数は激減して絵画市場は衰退していく。
4.英国とオランダの相違点とは
 英国とオランダでは16世紀の宗教改革による聖像破壊運動が同時期に起きたが、その後の17世紀において英国は絵画低迷期となり、それとは対照的にオランダは絵画黄金期となった。
英国とオランダでは16世紀の宗教改革による聖像破壊運動が同時期に起きたが、その後の17世紀において英国は絵画低迷期となり、それとは対照的にオランダは絵画黄金期となった。
英国の産業革命以前は絵画購入者となる層は王侯貴族しか存在せず絵画への需要が少なかった。しかも王侯貴族は外国人画家を重用していたので、自国の画家は育たない美術後進国であった。
オランダでは裕福な市民階級層が新たな絵画の購入者となったが、絵画は鑑賞だけでなく投機のための商品となり、バブルに陥った。プロテスタント信者の多いオランダでは、地味なファッションや質素な食事が好まれ、節制がモットーとされていた。では、なぜ投機に夢中になったのだろうか。17世紀のオランダ繁栄の原動力となった商人たちの価値観が、「絵画は商売と同様に儲けるための商品」だったからであろう。そうした風潮に影響されて、オランダの画家たちも、工業製品のように生産性を向上して儲けを増やすことに注力した。
一方、王政の続く英国の王侯貴族たちには、絵画の値上がりを話題にするのは下品なことであり、絵画を投機対象とは見ていなかったのである。
産業革命は19世紀に英国の全盛期をもたらしただけでなく、絵画の世界にも影響を与えることになる。次回は、19世紀前半に活躍したウィリアム・ターナー、ジョン・コンスタブル、そして、19世紀半ばに人気のあったラファエロ前派のダンテ・ゲイブリエル・ロセッティやジョン・エヴァレット・ミレイなどを取り上げ、絵画に及ぼした影響を探りたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第12回]~2021年3・4合併号
フィッシュ&チップスは英国名物である。
第9回に引用した林望氏の随筆『イギリスはおいしい』の中でも「英国中どこに行ってもあるものは、フィッシュ&チップスの店と中華料理店であり、英国の庶民が最も親しみを感じる食べ物はフィッシュ&チップス」と書かれている。
今回はこの英国名物がどのように産業革命と関係するかを考察する。まずフィッシュ&チップス、そして魚食、ジャガイモと各々の歴史を辿る。
1.フィッシュ&チップスとは
(1)英国人のソウルフード
フィッシュ&チップスは名前の通り、タラなどの白身魚の揚げ物(フライド・フィッシュ)とジャガイモのフライを一緒に盛った極めて単純な元祖テイクアウト料理である。起源には諸説あるらしいが、1860年に東欧からのユダヤ人移民ジョセフ・マリンがロンドンの下町イーストエンドで開業した店が世界最古のフィッシュ&チップスの店だと言われている。その後、英国の工業化とともに庶民の外食として親しまれるようになった。
1910年頃の英国には約2万5千店のフィッシュ&チップスの店があり、ピーク時の1927年には約3万5千店となった。その後、食の多様化や地域コミュニティの崩壊で家族経営の店が減少したが、現在でも1万程度の店舗は残っているようだ。今でも週に1~2回はフィッシュ&チップスを食べているそうだから、英国民にとってはまさに変わらぬソウルフードである。
(2)作り方と食べ方
フライにする魚は基本的に白身魚であり、タラやカレイ、オヒョウなどが原料に使用される。地域によってはウナギやエビ、ロブスターなども使われるようだ。魚に付ける衣は小麦粉を卵や水で溶いたもので、生地に色合いを付けるために少量の重曹や酢を加えるのが伝統的である。そして生地に苦みやサクッとした食感を加えるためにビールを入れるのがポイントらしい。衣のかけら(日本でいう天かす)はスクラップスと呼ばれて無料で客に提供される。付け合わせのチップスはフライド・ポテトのことで、アメリカのものと比べて太い。揚げ油は伝統的にヘット(牛脂)やラード(豚脂)を使用しているが、現在では健康志向で植物油が主流である。
原則、立ち食いである。注文すると新聞紙やわら半紙2~3枚をメガホンのような形に巻き付けて、そこへまず揚げた魚を放りこむ。次にシャベルのような道具でたくさんのチップスをすくって、揚げた魚の上に放り込む。さらに、茶色いモルト・ヴィネガー(醸造酢)をたっぷりと掛け、その上に塩を振り味付けをする。あとは客がメガホン形のわら半紙の根元の部分をしっかり握って、道端などで頬張る。食べていると、わら半紙に油と酢が徐々に染み出して手がベタベタになるので、油が浸みていない紙の部分で指先と口の周りを拭い、最後に残ったわら半紙をクシャッと丸めて捨てるのが正しい食べ方のようだ。
2.魚食の歴史
(1)ユダヤ人とフィッシュ・デイ(魚の日)
ユダヤ人は、かなり古い時代から、金曜日の夕食に魚料理を食べて安息日の始まりを祝ってきた。フライド・フィッシュは16世紀頃にスペイン系ユダヤ人移民が英国に持ち込んだ魚の揚げ物(ペスカド・フリット)が起源という説などから、ユダヤ移民から伝わった食べ物とされている。ユダヤ人にとっての最も一般的な魚料理は冷えたフライド・フィッシュらしい。こうしたことから、フライド・フィッシュと言えば当初ユダヤの料理とされていた。19世紀のヴィクトリア朝時代には、フライド・フィッシュの店から漂う独特の臭いがユダヤ人差別の象徴ともなっていたが、「ユダヤ人が聡明なのは彼らが食べる大量の魚のおかげである」と考える著述家もいた。
一方、ローマカトリック教では、断食日に肉を食べることは禁じられていたが、魚は対象外として食べることが許されていた。中世のカトリック教会では1年の半分近くが断食日だったので、かなりの頻度で魚を食べていたことになる。特に、キリストの磔刑の忌日として断食日である金曜日は、「フィッシュ・デイ」と呼ばれ、積極的に魚を食べたようである。
(2)漁業と魚の保存
魚は保存が難しい。古代ギリシア・ローマ時代の保存には専ら塩が用いられた。また「魚を油で揚げてから月桂樹の葉、塩、香辛料をまぶし、それから煮立たたせた酢を上から注ぐ」という保存方法も用いられた。11世紀のノルマン・コンクエストの頃には漁業で漁網が一般的に使用されるようになり、海でのニシン漁が盛んとなった。しかし、塩などを用いて生魚を保存する作業が大変だったので、ニシンなどの海水魚は海岸近辺の住民しか食べることはできず、12世紀の英国では川で獲ったウナギなどの淡水魚が一般的に食べられていたようだ。ちなみに貴族や修道院は敷地内に生け簀をもっており、淡水魚などを生きたまま蓄えていたらしい。
16~17世紀初頭には新世界の発見とともに北大西洋に新たな漁場が開発されたことで、安価なタラが簡単に手に入るようになり、プリマスなどイングランド南西部の港町がタラ漁の基地として栄えた。その頃には、課題であった魚の保存方法も向上していたと思われる。特に、塩を使って日干しした塩ダラは5年近く保存がきき、赤道を越えても腐らない数少ない食品のひとつとなったので、新大陸への長期間の航海中における貴重なたんぱく質として必需品となった。
19世紀には漁業の進歩で延縄漁や蒸気船の大型トロール漁業(底引き網)が利用されるようになり、漁獲量が大きく増加した。英国の人口が増加する中で生魚の供給量が増加したうえに値段も下がったので、魚の消費量は増加した。リバプールでは、1843年に3軒しかなかった魚屋が、1867年には50軒に増加した。大量に獲れるようになった魚は、安価で栄養豊富な労働者向けの食材となったのである。
また、19世紀前半には、魚を保存するための氷の需要が増加した。運河を利用して国内から天然の氷を集めただけでなく、ノルウェーやアメリカからも輸入し、港には氷用の倉庫も建設された。そして、1834年にアメリカ人発明家ジェイコブ・パーキンスが最初の冷蔵庫を作り、1880年代後半には機械製氷や機械冷蔵の技術が実用化されたことで、1890年代には機械で製造された氷が漁船内で魚の保存に使えるようになり、さらに遠く離れた場所に漁へ出られるようになったのだ。
産業革命期の技術進歩がもたらした蒸気船の登場と鉄道網の整備、保存方法の発達によって大都市を抱える内陸まで、新鮮な状態で大量かつ短時間で魚を運べるようになり、従来は港町でしか食べられなかった生魚が都市部でも簡単に食べられるようになった。19世紀後半には、フィッシュ&チップスの原材料となる鮮度の良い生魚が、どこでも手に入るようになったのである。
(3)産業革命を支えたフィッシュ&チップス
フライド・フィッシュとポテトチップスは元々別に販売されていた。誰が魚のフライとポテトチップスを組み合わせたかは不明だが、1870年代以降になると、労働者階級は路上やパブ、定期市でフィッシュ&チップスを買うようになり、それを売るための専門店も増えてきた。安価ですぐに食べられて、更に腹持ちが良く栄養満点であるというフィッシュ&チップスの商品性が、労働者にうまくマッチして人気となったのだ。そして、フィッシュ&チップスが庶民の外食産業として普及するにつれて、次第にフィッシュ&チップスは「ユダヤ人ゆかりの食べ物」というイメージから「労働者の食べ物」に変わっていった。産業革命によって都市で急増した労働者の食生活を支えたのが、「安い・速い・高カロリー」のフィッシュ&チップスなのである。
3.ジャガイモの歴史
(1)起源と栄養豊富な野菜
ジャガイモ発祥の地は南米アンデス山脈のほぼ中央部、標高3812メートルに位置するティティカカ湖のほとりの高原地帯だ。現地では今でもジャガイモが盛んに栽培され、乾燥芋「チューニョ」を作っている。「チューニョ」はジャガイモの有毒成分であるアルカロイド物質のソラニンを毒抜きして、長期保存を可能にしたものである。アンデスの4000メートル級の高地で生まれたジャガイモは、北ヨーロッパの寒冷地でも問題なく豊かな収穫をもたらした。また、地下茎の先端に肥大したイモを形成するので、鳥などに食い荒らされることもなかった。『国富論』のアダム・スミスも「同じ面積の耕地で、ジャガイモは小麦の3倍の生産量がある」と高く評価した。でんぷん質、無機質、ビタミンCが豊富で、寒冷地では「冬の野菜」として重要な役割を担っている。しかも、品種改良されたジャガイモは年に数回の収穫も可能となり、今では麦、米、トウモロコシと並ぶ四大作物だ。赤道直下から北極圏まで栽培されているのはジャガイモだけらしい。
スペインの冒険家が1530年代に初めてジャガイモと出会い、遅くとも1580年代にはスペインに持ち帰った。1600年頃にヨーロッパに伝わったが、食料としては人気がなく、当初はソラニンという毒をもつことから「悪魔の植物」とも呼ばれた。17世紀にはジャガイモを食べると「腹にガスがたまる」とか「ハンセン病になる」などの偏見があり、農民の多くがジャガイモに恐怖を抱いていた。
(2)アイルランドの「貧者のパン」
17世紀、ジャガイモを最初に欧州の食生活へ取り入れたのがアイルランド人である。ジャガイモはアイルランドの痩せた土壌、厳しい気候や生活条件にも適応した。ジャガイモの栽培によって、食生活は安定し、1780年に約400万人であった人口が1841年には倍の約800万人となった。
16世紀にヘンリー8世によって英国国教会が成立した以降、カトリック教徒の多いアイルランドは、英国からの厳しい圧政を被っていた。特に1649年の清教徒オリバー・クロムウエル(1599~1658)によるアイルランド侵略によってアイルランド人の土地の4割が奪われて、英国にとって安価な食糧と原材料を供給する植民地と化した。英国はアイルランドのカトリック教徒を弾圧するとともに、カトリック教会の農地や資産を没収し、元の土地保有者である農民を英国人地主の小作に転落させた。小作人となったアイルランドの農民は農地の三分の二に小麦を植え、その収穫のほぼすべてを地主に収めなければならなかった。そして、残った三分の一の劣悪な農地で、地代が徴収されないジャガイモを育て、なんとか生き延びることができた。岩盤だらけのアイルランドの農地でもジャガイモは「貧者のパン」として役割を果たし、アイルランド人を救ったのである。
(3)ジャガイモ飢饉と反英感情
しかし、1845年に「ジャガイモ飢饉」が襲う。アメリカ起源のジャガイモの病気は、まず1845年7月にベルギーで報告され、8月にはパリやドイツの西部、そしてアイルランドにも上陸する。当時アイルランドで栽培していたランパー種はこの病気に弱く、この年の被害は栽培全体の4割におよぶ大凶作となり大飢饉を引き起こした。特にアイルランドは農作物の栽培をジャガイモに集中していただけに被害が大きかった。ヨーロッパのほかの国々では、ほかの作物で補い飢饉を回避している。一方、英国はアイルランドの飢饉が最も深刻なときでさえ、税として農作物を納めさせたため、別名「英国が作った飢饉」とも呼ばれた。800万人までに増加していたアイルランドの人口が1851年には約655万人と激減した。減少したうちの100万人は移民として国を脱出した。こうした移民の子孫から誕生したのが米国大統領となったJ・F・ケネディやロナルド・レーガンである。
また、その頃の英国は産業革命による高い生産性と規模の大きさで、小規模なアイルランド産業を圧倒していた。汽船や鉄道の発達によって、アイルランドの生産者や卸売業者は苦境に陥っていたのだ。この時の英国政府のアイルランドに対する対応のまずさが、深刻で永続的な反英感情を後々まで残した。
(4)英国でのジャガイモの普及
英国ではジャガイモが広く受け入れられるまで時間を要したが、18世後半には一挙に庶民の食生活に入り込んだ。1793年に長雨と霧によってかつてない小麦の凶作に見舞われた際に、英国の首相ピットはジャガイモの効用を説いて、その栽培に対して助成金を出すなど奨励策に踏み切ったのだ。1790年代から1815年のナポレオン戦争終結までに続いた小麦などの凶作もあってジャガイモは定着し始め、19世紀前半に消費量が徐々に増加し、英国の都市や農村の労働者の家庭の食べ物として次第に食卓に上るようになった。
世界最古のフィッシュ&チップスの店ができた19世紀後半のロンドンの街頭では、皮つきのままでジャガイモを焼いた「ベイクド・ポテト」を売る店も多く登場した。ジャガイモの皮をジャケットに見立てて「ジャケット・ポテト」とも呼ばれた。
このように、ジャガイモは19世紀末には小麦パンに匹敵する普通の食料の一つとなり、労働者階級の食生活に欠かせぬものとなった。
(5)フライド・ポテトの発祥地
 英国のフライド・ポテトはフランスから伝わったという話もあるが、拍子木型に切ったジャガイモを揚げたフライド・ポテトそのものの発祥地については、ベルギー説とフランス説がある。ベルギー説ではベルギーのフランス語圏ナミュールの住民が17世紀に町の中心を流れるムーズ河が凍って魚が取れなくなった際に、小魚のようにジャガイモをカットしてフライにして食べたということが発祥だとして、ベルギーはユネスコの無形文化遺産に登録申請しようとした。一方、根拠となる資料は乏しいようだが、フランス説では「18世紀後半にパリのポンヌフ橋で路上販売されていた」とし、フランス側はベルギー説を作り話だと主張している。ベルギーにジャガイモ栽培が広まったのは18世紀半ば以降であり、17世紀のナミュールをフライド・ポテトの発祥地とするのは時代考証的に矛盾があるからだ。
英国のフライド・ポテトはフランスから伝わったという話もあるが、拍子木型に切ったジャガイモを揚げたフライド・ポテトそのものの発祥地については、ベルギー説とフランス説がある。ベルギー説ではベルギーのフランス語圏ナミュールの住民が17世紀に町の中心を流れるムーズ河が凍って魚が取れなくなった際に、小魚のようにジャガイモをカットしてフライにして食べたということが発祥だとして、ベルギーはユネスコの無形文化遺産に登録申請しようとした。一方、根拠となる資料は乏しいようだが、フランス説では「18世紀後半にパリのポンヌフ橋で路上販売されていた」とし、フランス側はベルギー説を作り話だと主張している。ベルギーにジャガイモ栽培が広まったのは18世紀半ば以降であり、17世紀のナミュールをフライド・ポテトの発祥地とするのは時代考証的に矛盾があるからだ。
私は若い頃ベルギーの銀行のナミュール支店に1カ月間の研修経験があり、その時にベルギー人から何度もフライド・ポテトの自慢をされた。実際、毎日のように食べていたフライド・ポテトは美味しくて病みつきになった。動物性油脂で二度揚げたフライド・ポテトは絶品だったので、是非ベルギー説に軍配を上げてもらいたい。
国際連合食糧農業機関の統計(2015年)によると国民一人当たりの年間ジャガイモ消費量は、英国が86kgで日本が18kgと4倍以上の差がある。
また、平均的なフィッシュ&チップスの重量は343.2gでカロリーは529kcalらしい。マクドナルドの「倍フィレオ・フィッシュ*」とフライド・ポテト(M)は重量330g、カロリー844kcalなので、これと比較するとかなり低カロリーである(フライド・ポテト(M)は135gで410kcalもある)。
産業革命がフィッシュ&チップスの普及に一役買うまでの経緯を調べて、一見無関係な発明や技術の進歩が、日常生活の中の当たり前なことに大きな影響を与えたのだと改めて認識した。現在のコロナ禍で生まれた新しい生活様式や技術・製品によって、今まで当たり前であった物事が数年後にはすっかり変わっているかもしれない。
次回は、産業革命期の芸術について、どのような動きがあったのか辿りたい。
*(メイン具材のフライド・フィッシュが2枚入ったメニュー)
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第11回]~2021年2月号
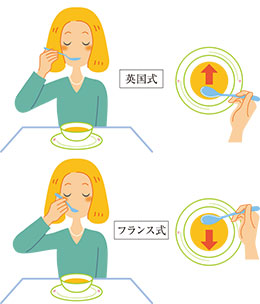 テーブルマナーには英国式とフランス式がある。スープを飲むときに音を立てないのは共通しているが、スプーンのすくい方は逆である。「英国式スープの飲み方」は皿の手前から向こう側に向けてスプーンを動かしてスープをすくい、スプーンの向きはそのままで、スプーンの横側に口をつけてスープを流し込むように飲む。スープの残りが少なくなると皿の手前を持ち上げてスープをすくう。一方、「フランス式スープの飲み方」は反対に皿の奥から手前にすくい、スープをすくった後のスプーンの先端を口に向くようにして近づけ、口に少しだけ入れてからスープを流し込むように飲む。スープの残りが少なくなると皿の奥を持ち上げてスープをすくう。それぞれ作法の根拠はあるようで、英国式では「相手に皿の裏側が見えるのは失礼」と考え、フランス式では「相手にスープがはねたら申し訳ない」と考えたそうだ。
テーブルマナーには英国式とフランス式がある。スープを飲むときに音を立てないのは共通しているが、スプーンのすくい方は逆である。「英国式スープの飲み方」は皿の手前から向こう側に向けてスプーンを動かしてスープをすくい、スプーンの向きはそのままで、スプーンの横側に口をつけてスープを流し込むように飲む。スープの残りが少なくなると皿の手前を持ち上げてスープをすくう。一方、「フランス式スープの飲み方」は反対に皿の奥から手前にすくい、スープをすくった後のスプーンの先端を口に向くようにして近づけ、口に少しだけ入れてからスープを流し込むように飲む。スープの残りが少なくなると皿の奥を持ち上げてスープをすくう。それぞれ作法の根拠はあるようで、英国式では「相手に皿の裏側が見えるのは失礼」と考え、フランス式では「相手にスープがはねたら申し訳ない」と考えたそうだ。
英国式礼儀作法が確立されたのは、英国産業革命によって大英帝国となったヴィクトリア朝時代以降だと言われる。今回は、まず世界の食事スタイルを見て、英国が模倣した美食の国フランスにおける礼儀作法の歴史をカトラリーの普及から辿
1.世界の食事スタイルの主流は手食
世界の食事スタイルは約4割が手食、約3割が箸
日本は箸文化の国であり、かなり昔から箸を使っていたようだ。平安時代までは匙
2.美食の国フランスにおける礼儀作法の歴史
(1)カテリーナ・デ・メディチが嫁ぐまで
ここからは、まずカトラリーを中心としてフランスの礼儀作法を辿る。洋食で用いる金属製ナイフ、フォーク、スプーン類を総称してカトラリーと呼ぶが、各々に歴史がある。
カトラリーの中で最も早く食卓に登場したのはナイフである。12世紀頃には食事に招いた主人が大きな肉を切り分けるために、肉切りナイフが1本だけテーブルの上に置かれた。15世紀頃からは各自が自用のナイフを持参するようになった。
スプーンといえば15世紀になるまでは、熱い汁をすくったり、煮え切った鍋から肉を取り出したりするために使われるお玉のような調理用道具しかなかった。15世紀以降に現在のように食事に使われるようなスプーンが現れたのである。
フォークは、11世紀頃イタリアのベネチアに嫁いだビザンチン帝国の王女が祝宴でフォークを取り出して食べたのが始まりと言われているが、17世紀までなかなか普及しなかった。
(2)カテリーナ・デ・メディチの登場
食通の国フランスも16世紀になるまでは食事のテーブルマナーは洗練されてはいなかった。
フランスのテーブルマナーを改善したのは、1533年にフィレンツェのメディチ家からオルレアン公(のちのアンリ2世)に嫁いだカテリーナであった。当時のフランスは、イタリアに比べるとかなり野蛮な食事風景だったらしい。最も文化的に進んだ国イタリアから来たカテリーナの眼には、フランスの宮廷人が全くの田舎者に映った。そこで彼女は宮廷のテーブルマナーを改善するために、お抱えの料理長にカトラリーの使い方などの作法書をまとめさせたと言われる。彼女はイタリアの香水やリキュール、シャーベット、パラソルなどと一緒にフォークも宮廷に持ち込み、肉類を手ではなくフォークで食べる作法を宮廷で広めようとした。しかし、当時のフォークは二股で使いづらかったので、なかなか定着しなかった。本格的に普及したのは17世紀に入り、三股や四股の扱い易いフォークが登場した以降のことだ。ようやくフォークはナイフ・スプーンとともに食事に欠かせぬカトラリーとなった。
(3)ルイ14世が確立したフランス式礼儀作法
ヨーロッパの作法の中心がイタリアからフランスへ移ったのはルイ14世(在位1643~1715)が政治の実権を握った頃だ。彼は太陽王として72年間もの長い間王位に就いて、ヴェルサイユ宮殿などの大建造物をつくり、華美な環境で文学、美術を保護するとともに、貴族たちをヴェルサイユ宮殿に集めて、礼儀作法を徹底的に守らせた。儀式を通じて国内外にルイ14世の威厳を示し、国王崇拝を維持させようとしたのだ。固定化された階級社会である絶対王政の最盛期に、儀式が大好きなルイ14世は自ら政策や個人的好みを基にフランス式礼儀作法をしっかりと確立したのであった。
しかし18世紀後半になると、絶対王政が弱体化した。ルイ16世(在位1774~1792)が王妃マリー・アントワネットとともに1789年に起きたフランス革命の下でギロチンによって処刑され、ブルボン王朝が一旦途絶えた。同時に、それまでの宮廷的なフランスの礼儀作法も消え去ることになった。革命後のフランスでは、宮廷人や貴族に代わってブルジョア階級が新しい社会の担い手となり、政治や文化の中心もヴェルサイユからパリに移った。その後に皇帝ナポレオンが登場するが、当時のフランスではブルジョア階級など新興勢力が上流階級の中心となっていたため、礼儀作法もおのずと粗野なものとなった。
3.英国式礼儀作法が確立されるまで
(1)エリザベス1世治世から裕福な英国に
ヴィクトリア朝の全盛期となるまで、英国はフランス式礼儀作法をほぼ模倣していたと思われる。
エッセイの第9回に書いたように、英国は11世紀の「ノルマン・コンクエスト(征服)」以来の経緯があり、全盛期のヴィクトリア朝時代になる頃までは上流階級の料理はフランス料理を指した。礼儀作法もフランス式を手本としたと思うが、英国の礼儀作法は洗練されていなかった。英国は百年戦争(1339~1453)でフランスに敗れたために大陸の領土を失い小国に転落していたが、エリザベス1世(在位1558~1603)の時代に、アルマダの海戦でスペインの無敵艦隊に勝利し、海上権を奪い海洋王国となった。東インド会社による植民地政策の貢献もあり、この時代の英国は絶対王政の全盛期となっただけでなく、シェイクスピアを始めとする英国文化が開花した時代でもあった。女王自身も五カ国語を流暢に話すことができ、外国の大使とも通訳なしで議論を交わせるだけの教養があった。また、王位にふさわしい装いをするために高価な贅沢品をイタリアから大量に持ち込み、宝 石や真珠を縫い付けた豪華な衣装やアクセサリーを身にまとった。
こうして英国は裕福な国となったが、当時の食事にはスプーンとナイフだけを使っていた。フォークが英国に登場したのは、1608年に旅行家トマス・コリアットがイタリアからフォークを持ち帰った時で、1603年に亡くなったエリザベス1世はフォークを知らない。フランスと同様にフォークはすぐには普及せず、1688年の名誉革命以降にフォークで食べるパスタが流行したことで、上流階級にフォークが浸透した。同時にナプキンの使用法も変化した。指で食べる際、衣服が汚れるのを防ぐために肩に掛けられていたものが、17世紀には膝の上に置かれることになった。
(2)上流階級はグランドツアーで修行へ
16世紀後半頃から、野暮な国であった英国の上流階級の子弟は学業を終えると、イタリアやフランスへ教養と礼儀作法を学びに「グランドツアー」と呼ばれる留学をした。留学は数カ月から8年の期間であり、お目付け役として家庭教師も同行した。大陸のイタリアやフランスが礼儀作法の手本とされ、英国の上流階級は礼儀作法や美術鑑賞能力の修得のためにこぞって子弟を留学させた。留学先は17世紀の初期まではイタリアだったが、のちにフランスが人気となった。フランスは、ルイ14世によって洗練された上品な礼儀作法や社交生活のマナーがしっかりと確立されていたので、留学した英国上流階級の子弟は粗野な英国人の痕跡を消そうとかなり努力をしたようだ。そうしたフランス気取りの英国人留学生を見て、フランス人は芝居や風刺画などで皮肉り嘲笑の対象とした。また、留学した子弟たちの中には英国国教会やプロテスタントの節制や禁欲の厳しい英国から、カトリックの開放的なフランスの社会に入ると道を外し、酒と女性にほとんどの時間を費やした輩もいたようだ。しかし、このグランドツアーもフランス革命(1789~1799)とナポレオン1世(在位1804~1815)の登場で一旦終焉を迎える。
(3)礼儀作法が確立されたヴィクトリア朝時代
18世紀頃から、プロテスタントの影響もあってか、「食事中には、フランス人のように会話を楽しむのではなく、遠くの席の人とは話をせず寡黙であること」といったフランスとは異なる独自の「英国式礼儀作法」がでてきた。19世紀になると、英国は領土の拡大と富の力によりヨーロッパで優位を保ち、民族的にも、道徳的にも、世界のどの国よりも優秀だと自負するようになり、大英帝国にふさわしい礼儀作法が必要だと考えるようになった。また、産業革命によって封建領主が没落する一方で、産業革命の中心となり巨大な富を集めた産業資本家などの新興勢力が現れたが、新興勢力の彼らは必ずしも洗練された礼儀作法を備えていなかった。そうした彼らを「ジェントルマン」という定義が曖昧な支配階級に属させるとともに、「ジェントルマン」にふさわしい人格、教養を備えた理想像というものが明確に定義されたのであった。
英国ではハノーヴァー朝(1714~1901)以降、「君臨すれども統治せず」として、議会政治が定着した。英国の最盛期であるヴィクトリア女王(在位1837~1901)時代には女王自身は政治に関与せず、国民にとっての精神的な支柱となることを求められた。高潔で真面目な性格の女王は、フランスのように宮廷を堕落させず、理想的な王室一家を築くことで国民から敬愛され、国民の模範となっていた。英国の支配階級である「ジェントルマン」も単に礼儀作法だけでなく、その社会階級にふさわしい信念をもち、それに恥じない行いをする人となって国民から尊敬されることが求められた。こうして英国の繁栄とともに、ヨーロッパにおける新しい礼儀作法の中心はフランスのヴェルサイユからロンドンに移った。
4.階級概念の変化がおよぼした影響とは
ここで英国の階級制度の変化を考察したい。
英国の階級は主に上流・中流・労働者階級からなる。まず、上流階級は中世以来の家系を継ぐ「王族・貴族」と中世後期に土地を集積した「ジェントリ」から構成された。「ジェントリ」は爵位を持たない大土地所有者で、最低でも1000エーカー程度の土地を所有し、労働する必要がない層である。17世紀初頭に「王族・貴族」と「ジェントリ」を合わせて「ジェントルマン」と呼ぶようになり、彼らは地代収入で生計を立てる一方で、支配階級として国会議員や判事、慈善活動など社会に貢献する役目すなわち「ノブレス・オブリージュ」の義務を担っていた。
中流階級は頭脳労働の担い手であり、商業、工業、金融業で財産を築いた「ブルジョア階級」と弁護士、医師、軍将校といった「専門職」の2種類がある。勤労と倹約が美徳とされる一方、上流階級の生活スタイルを真似することも多かった。中流階級は上層、中層、下層の3クラスに分けられ、下層では低収入で労働者階級と大差ない暮らしをしていた者が多かった。産業革命後の土地所有を基盤としないブルジョア階級もこの層に含まれ、19世紀には「ジェントルマン」を中心とする支配階級に中流階級も加えるための教育改革も進められた。
全体の大宗を占める労働者階級は、小作人、工場労働者、街頭商人といった肉体労働者で構成されたが、労働者の中でも熟練労働者は「労働貴族」と呼ばれる豊かな暮らしを送っていた。
富を貯めて土地を保有すれば「ジェントルマン」となることが可能になると、19世紀には貴族・地主以外に、植民地のプランテーションや株式の形で巨額の資産を有している者も「ジェントルマン」に加えられるようになった。そうした裕福な新興勢力を加えたジェントルマン階級層が、国会議員として政治勢力となるとともに、保有する資産が金融やサービス活動に投資され、英国経済に繁栄をもたらした。また、産業革命後には階級制度によって規制されていた社会通念が外され、庶民が貴族の生活様式を真似ても、処罰されたり批判されたりすることがなくなった。こうして階級の境目が流動的となり、階級制度が緩やかとなった。
アイルランド生まれの英国の劇作家バーナード・ショーは「マイ・フェア・レディ」の原作「ピグマリオン」で貧しい花売り娘イライザの下町訛りの矯正を題材に英国の階級社会を風刺した。皮肉屋の彼は、英国で「ジェントルマン」が支配階級として存続できたのはフランス革命やロシア革命のような社会を根底から揺さぶるような革命が起きなかったからであり、「上流階級は余暇と経済力があるから、言葉に象徴されるような教養や生活様式を維持できたのであり、一皮むけば人間の中身は皆同じである」と考えていたのだろう。
今回は、そもそも礼儀作法に問題がある私にとって大変書きづらいテーマであった。
次回は17、18世紀の産業革命当時を中心に魚料理の歴史を「フィッシュ&チップス」を題材にして辿りたい。違う分野を取り上げるつもりだったが、テレビでアガサ・クリスティーの『名探偵ポアロ』の邦題『黄色いアイリス』を観ていた時のことだ。英国料理を不味いと馬鹿にしている食通のポアロが、ドラマの最後のシーンで相棒のヘイスティングと美味しそうに英国の名物「フィッシュ&チップス」を食べる場面があったのだ。そこで英国名物についても書くべきだと思い、決断した。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第10回]~2020年12月号
英国といえば、ティー・ブレイク、アフタヌーン・ティーなど「紅茶」というイメージが強い。1773年には茶を巡って米国との間でボストン茶会事件も起きている。英国はなぜコーヒーやココアではなく、紅茶を国民的飲み物として選択したのだろう。
今回は英国の朝食とともに、英国人が発明し愛飲した「砂糖入り紅茶」を取り上げ、併せて「紅茶」と「砂糖」の歴史も辿りたい。
1.英国での朝食の位置付け
(1)英仏で違う朝食のスタイル
英国では「breakfast」つまり「断食を破る」に語源を持つ朝食は、栄養があってバラエティーに富み、量が多い食事であるフルブレックファストが好まれた。「働くために食べる」という国民性の英国では朝食が一番大事なものだったので、朝から豪華に卵、ベーコン、ソーセージなどさまざまな料理を食べるのである。「月と六ペンス」で有名な英国人作家サマセット・モーム(1874~1965)は皮肉を込めて「英国料理で一番おいしいのは朝食。1日3回朝食をとればよい」と言ったらしい。
一方、欧州大陸のフランスやイタリアでは「食べるために働く」のが国民性なので、昼食や夕食にゆっくりと時間をかけて美味しいものを食べた。ちなみにフランス語では昼食を「déjeuner」と言う。意味は英語と同様「断食を破る」ことである。そして朝食は「petit déjeuner」と言い、petit(小さい)が付く。「小さく断食を破る」朝食は正式な食事としてカウントされず、簡単にパンとコーヒーだけで済ませるコンチネンタル・ブレックファストとなったのである。フランス人は昼や夜にたくさん食べるので、朝はそんなに食べられないのだ。私が昔フランスに下宿していた時も、朝食はいつもカフェオーレ、ビスケット、ヨーグルトだけの簡単なもので、午前中ものすごく腹が減ったことを思い出す。
(2)産業革命期における労働者の朝食
しかしながら、18世紀後半の産業革命初期に豪華なイングリッシュ・フルブレックファストを食べたのは、貴族など富裕層の話である。当時の労働者の朝食は、屋台で買ったライ麦の黒パンや、牛乳とオーツ麦で作られたポリッジ(お粥)など粗末なものであったが、必ず「砂糖入り紅茶」も飲んだらしい。家族総出で働く労働者一家が遅刻せずに家を出るには、熱い湯を注ぐだけで簡単に作れる「砂糖入り紅茶」は便利であった。しかも、砂糖のカロリーで元気が出て、カフェインで脳と体がフル回転するので、工場での長時間の重労働に耐えるには恰好の飲み物であった。ヴィクトリア朝時代(1837~1901)には産業革命が進展して生活水準が向上したので、働くために必要なカロリーを十分摂取できるように英国の一般的な朝食は徐々にボリュームのある重いものとなっていく。「砂糖入り紅茶」はその後も国民的な飲み物として消費が拡大していくのだが、実は英国で最初に人気となった飲み物はコーヒーであった。
2.英国と紅茶のつながり
(1)紅茶に先行したコーヒーハウス
簡単にコーヒー伝来の歴史を辿る。コーヒー豆は原産地のエチオピアから13世紀半ばにアラビアを中心とするイスラム教国に伝わると、煎って煮出した苦みのあるコーヒーが勤行の際の眠気覚ましとして僧侶に飲まれ、一般にも広がった。その後トルコに伝わり、次いでイタリアにも伝播し、17世紀前半には英国に伝わった。この頃、英国はアラビアのモカコーヒーを英国の東インド会社を通じて輸入していた。17世紀半ばにはオランダがジャワやスマトラの植民地でコーヒー豆の栽培を始めコストダウンにも成功したので、ジャワコーヒーがモカコーヒーより安くヨーロッパに供給されるようになった。
17世紀の英国では、茶より数年早く発売されたコーヒーが最初に人気となった。コーヒーの流通とともに英国でコーヒーを提供する店「コーヒーハウス」ができた。まず、1650年にユダヤ人のジェイコブがオックスフォードで開業したのが英国初のコーヒーハウスだ。当初は男性限定で酒を供しなかったので、真面目な雰囲気で安価に楽しめる場所として大人気となり、男性同士の情報交換や議論が活発に行われる世論形成の場となった。その後、コーヒーだけでなく紅茶やココア(チョコレート)なども提供され、18世紀初めにはコーヒーハウスは3000軒を超し、隆盛を極めたが、18世紀半ばから徐々に衰退する。メニューに酒類が加わると店の雰囲気が悪くなって、女性に毛嫌いされたり、商売敵の居酒屋から敵視されたりしたことなどが衰退の原因とされている。
(2)紅茶の伝播から紅茶文化の定着へ
茶の原産地はインドであり、製造方法によって、発酵させない「緑茶」、発酵させた「紅茶」、発酵を途中で止めた「ウーロン茶」に分類され、香味も飲み方も大きく相違している。当初、英国で飲まれた茶は中国茶で、ほとんどが緑茶であったが、英国の硬水では緑茶が気の抜けたような味になった。茶には軟水が適するが、発酵茶の場合には硬水でもタンニン成分の抽出が抑えられ、渋みが出にくくなり味がマイルドになる。英国の硬水では発酵茶の方が美味しく感じられ、好まれるようになった。この発酵茶がのちに紅茶となるのである。
茶を飲む慣習は、ヨーロッパではまずオランダから始まったらしい。17世紀初めにはオランダが中国・日本などからヨーロッパに茶を輸入し始めていた。英国で茶を飲まれるようになったのは、ポルトガル王国から英国に嫁いできた王女キャサリン・オブ・ブラガンザ(1638~1705)の影響が大きい。1650年にキャサリンは、チャールズ2世(在位1660~1685)との結婚のために、銀の代わりとして当時貴重品であった茶と船7隻に満載した砂糖を持参した。茶を愛飲するキャサリンは中国や日本の茶道具や磁器も英国に持ち込み、宮廷で朝のお茶会を催した。これが王侯貴族の関心を集め、茶を嗜むことが上流階級で広まった。中国や日本から伝わった洗練された茶器や作法が東洋への憧れとなり、英国人にとって茶は一層魅力的なものとなったのである。1657年にはトーマス・ギャラウェイのコーヒーハウスで茶葉が売り出され、店でも茶を飲ませるようになった。
その後に即位するメアリー2世(在位1689~1694)やアン女王(在位1702~1714)も茶を好んだことで、茶を飲む慣習はステイタス・シンボルとして上流階級に定着し、家庭における女性の飲み物として中産階級にも広く普及する。1706年にロンドンで「トム・コーヒーハウス」を開いていたトマス・トワイニングも、1717年に女性も入店可能な英国初のティーハウス「ゴールデン・ライオン」をオープンした。インテリアに凝ったお洒落な雰囲気は女性客に大評判となった。一方、貧しい労働者にとっても茶は憧れであったが、まだ高価で手が届かず、出し殻を再利用した安い紅茶や代用品による偽物で楽しんでいた。1840年代のロンドンには、ホテルやコーヒーハウスなどから買い集めた茶殻を再利用する紅茶工場が8つもあったそうだ。17世紀半ばにコーヒーの国際競争でオランダに負けた英国は、貿易での力点をコーヒーから中国茶の輸入に移行したので、「万病に効く東洋の高価な神秘薬」と言われた茶の価格が下がり、庶民にも手が届く嗜好品となった。
(3)紅茶の消費拡大とアッサム茶の発見
東インド会社の全輸入額に占める割合を見ると、1720年にはコーヒーが8.1%、茶が4.5%とコーヒーが優勢だったが、1860年になるとコーヒーが5.7%で茶が39.5%となり、茶が断然大勢を占めるようになった。また輸入した茶の内訳は18世紀初めには緑茶55%、紅茶45%であったものが、18世紀半ばには紅茶66%、緑茶34%と紅茶へ嗜好が移行している。こうして茶がポピュラーな飲み物として定着した英国では他のヨーロッパ諸国の全消費量の約3倍の茶を消費するようになった。
茶の供給を中国に依存していた英国は、新たな栽培地を求めていた。紅茶の栽培に適した北緯45度から南緯35度までをティー・ベルトと呼ぶが、1823年に英国政府の密命を受けた英国軍人ロバート・ブルース少佐が、インド・アッサムで野生の茶を発見し、インド茶の栽培に成功する。芳醇な香りでコクがあって味が濃いアッサム茶はロンドンで好評を博し、1837年には茶の製造が始まる。味が濃いアッサム茶はミルクをたっぷり入れても茶葉の風味が損なわれず、ミルクとの相性が非常に良かったので、ミルクティーが愛好され、英国の伝統的な飲み方となったようだ。1850年にはアッサムでの茶園数は1つしかなく、生産高21万ポンド程度であったが、1871年には茶園数が295まで急増して、生産高も30倍の625万ポンドまで急増した。その後、英国はスリランカでも茶栽培に成功し、紅茶が大幅に安くなったことで更に国内で消費が拡大した。
(4)アフタヌーン・ティー
紅茶を飲む習慣は、上流階級の女性を中心に拡がったことで上品さのシンボルとなり、ヴィクトリア朝時代にはアフタヌーン・ティーが習慣となった。
英国の伝統となったアフタヌーン・ティーは1840年頃にベッドフォード公爵夫人のアンナ・マリア(1783~1857)が始めたと言われる。当時は昼食から夕食までの時間がかなり空いたので、空腹を満たすために午後4時のアフタヌーン・ティーとして紅茶と軽食をとったのが始まりであり、徐々にこの習慣は中産階級にも広まったのである。また、アンナは過去に数年であるがヴィクトリア女王の側近を務めており、女王からの信頼が厚かった。そのアンナから茶会に招待されたヴィクトリア女王は、茶会が大変気に入り宮廷内でもアフタヌーン・ティーを始めたそうである。夫アルバートと9人の子供からなるヴィクトリア女王の王室ファミリーは当時の英国女性にとって「良き家庭」のシンボルであったので、「一家団欒」と「女王の好きな紅茶」のイメージが重なり、アフタヌーン・ティーの人気につながった面もあるようだ。
3.砂糖と英国のつながり
(1)砂糖の伝播
サトウキビの原産地はインドと言われている。8世紀にはイスラム教徒が支配した地域にサトウキビの栽培と製糖技術が伝えられ、今のトルコからイタリアにかけての地中海東部の島々で栽培が盛んとなった。11世紀後半以降、十字軍の遠征やイスラム世界との交易を通じて、サトウキビ栽培と製糖の技術がヨーロッパに伝えられた。甘味と言えば蜂蜜ぐらいしか知らない当時のヨーロッパ人にとって、真っ白な砂糖は強いインパクトがあったと思われる。また、サトウキビから作る砂糖は世界的な商品となるための要件である大量生産が可能であった。
15世紀末当時の強国スペインはサトウキビの栽培よりも金・銀の獲得に注力していたが、ポルトガルは大西洋の沖にあるマデイラ島やカナリア諸島などで、アフリカ人奴隷を使ったサトウキビのプランテーションを大規模に展開した。ポルトガルは、世界的に人気のある砂糖への需要に対応するために新たな栽培地を求めて、手狭となった大西洋の島々からポルトガル領となったブラジルへと栽培地を移した。16世紀にはブラジルが世界の砂糖生産の中心となる。
17世紀になると世界の貿易ルートを押さえたオランダ人の仲介によって、英国が英国領のカリブ海の島々でも砂糖の栽培を始めた。今まで英国にとって役に立たなかった島々が一面サトウキビ畑となり、一挙にサトウキビ栽培だけのモノカルチャー社会となった。特に英国領のジャマイカが砂糖生産の中心地となり、17世紀後半には大量の砂糖をヨーロッパに輸出している。
(2)プランテーションと三角貿易
サトウキビの栽培は土地の養分を大量に消耗して土地を疲弊させるので、次々と新しい耕地を求めて移動する必要があった。また、熱帯や亜熱帯でプランテーションの砂糖を搾って煮詰める作業はかなりの重労働であり、かつ栽培には一年を通して大量の人間を必要とした。ポルトガルはアフリカのギニアやアンゴラで奴隷の獲得ルートをもっていたので、ブラジルでサトウキビのプランテーションを始めることができたのである。
英国の奴隷貿易船はアフリカへ鉄砲やガラス玉、綿織物をもっていき、奴隷と交換した。その奴隷を南北アメリカやカリブ海域で売って、砂糖に交換して母港に帰った。こうした「三角貿易」は約2カ月かけておこなわれた。西アフリカの奴隷貿易を独占した英国の王立アフリカ会社が1672~1711年に供給したアフリカからの奴隷数は約9万人であり、航海中には多数の奴隷が飢えと病気で死亡した。1694年のハンニバル号の航海では700人の奴隷のうち320人が死亡したと言われる。一方、三角貿易で稼いだ砂糖商人は蓄えた富を英国の産業などに投資したので、産業革命推進の原動力となったが、既得権益を守るために資金力で政治家になった者もいた。
(3)砂糖の効用と砂糖入り紅茶の登場
銀と同等に貴重品であった砂糖は、当初は茶と同じく薬品や儀礼用とされた。中世のイタリアでは、砂糖は熱病、咳、胸の病気、唇の荒れなどに効果があるとされた。14~15世紀には、黒死病として恐れられていたペストに砂糖が有効だと考えられていたらしい。こうして砂糖は薬、装飾品(デコレーション)、香料、甘味料、保存料などに利用された。しかし16世紀には虫歯の原因だと分かり、18世紀頃からは砂糖の過剰摂取は糖尿病などを引き起こし、体に良くないと言われ始めたようだ。
1650年にポルトガルから来た王女キャサリンが茶に砂糖を入れたと言われる。茶は宮廷で愛飲されたことで庶民の憧れとなり、更に茶や砂糖の新たな獲得ルートを海外に確保したことで大幅に価格が下がり、庶民にも「砂糖入り紅茶」が人気となった。19世紀には英国は世界一砂糖を消費する国となる。
 2016~2018年の国際統計では、年間一人当たりの紅茶消費量の世界No.1はトルコだ。かつてNo.1であった英国は世界5位である。また、同様に過去世界No.1であった砂糖消費量も健康を意識してか、2019年度の一人当たり年間砂糖消費量は世界の平均並みの26.9kgであり、欧州では少ない部類に入る。
2016~2018年の国際統計では、年間一人当たりの紅茶消費量の世界No.1はトルコだ。かつてNo.1であった英国は世界5位である。また、同様に過去世界No.1であった砂糖消費量も健康を意識してか、2019年度の一人当たり年間砂糖消費量は世界の平均並みの26.9kgであり、欧州では少ない部類に入る。
前号の「英国の食事は不味い」で英国人作家ジョージ・オーウェルのエッセイを引用したが、今回も1946年の夕刊紙に掲載された「一杯のおいしい紅茶」という記事を紹介したい。オーウェルは「完全な紅茶のいれかた」として譲れない処方を11項目挙げているのだが、最後の11項目は「紅茶にはロシア式でない限り、砂糖を入れてはいけない。せっかくの紅茶に砂糖など入れて風味を損なってしまうようでは、どうして紅茶好きを自称できよう」と忠告しているのだ。オーウェルは砂糖を入れないのは少数派であることを認めつつも、砂糖抜きを推奨している。現在の砂糖の消費量から類推すると、健康ブームもあり、砂糖抜き派が増えたことだろう。私もコーヒーも紅茶も砂糖抜き派である。
次回はヴィクトリア朝時代に確立されたと言われる英国式マナーについて辿る。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第9回]~2020年11月号
林望氏の随筆『イギリスはおいしい』(1991年)の第1章は「塩はふるふる野菜は茹でる」で始まる。日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した愉快な傑作エッセイで、国文学者の著者が英国滞在中の体験をもとに英国の食生活について執筆した。本のタイトルに反して、著者は「英国の食事が概して不味いことは世界の定評であり、私自身もある意味で認めざるを得ない」と述べ、「塩気とテクスチュア(口触り、歯触り)における無神経さが英国料理の欠陥」と結論づけている。
また、小説『動物農場』や『1984年』で有名な20世紀の英国作家ジョージ・オーウェルは1945年の夕刊紙のエッセイ『イギリス料理の弁護』で「英国料理は世界最低との定評があり、英国人自身もそう言っている」と嘆いていた。近年では、2005年の英国でのG8サミットの時、フランスのシラク大統領がドイツのシュレーダー首相とロシアのプーチン大統領とのトップ会談で英国について「料理の不味い国の人々は信用できない」と冗談を言ったことで、物議を醸した。
「英国料理は不味い」という定評が確立された要因はいくつかあると言われており、その一つに産業革命の影響が挙げられる。今回は、「不味くなった理由」に歴史上どのような背景や経緯があったのかを辿る。
1.英国料理が不味くなった要因とは
産業革命が始まる前までは、食材の少ない英国でもそれなりに豊かな食文化があったと言われる。英国料理が不味くなったのには主に4つの要因があるように思う。
1つ目は、隣国フランスとの関係である。イングランドが1066年にフランスのノルマンディー公国に征服され、フランス語を話すノルマン人が王侯、貴族となり、上流階級の料理はフランス人料理人が作ることになった。これ以降、最高の英国料理はフランス料理そのものを指すようになったようである。
2つ目は、ピューリタン革命後の節制生活である。ピューリタンの節制の精神が基本となり、「食に関心をもってはならない」との風潮ができた。
3つ目は、第二次囲い込み運動と農業革命である。この影響で農民は共有地での採集が不可能となり、生活の場としての農村や菜園は消え、同時にさまざまな食材や調理方法の伝統も消えていった。
4つ目は、産業革命と都市化の影響による生活の商業化である。自給自足していた農民が都市に流入して賃金労働者となると、料理にかけるお金と時間の余裕はなくなった。
以上の4つの要因について、詳しく見てみたい。
2.不味い料理となった4つの要因
(1)隣国フランスとの因縁の歴史
英仏が長年にわたって強いライバル意識をもっていることは有名である。そこにはドーバー海峡を挟んだ両国の長い歴史が関係している。
対抗意識のルーツは1066年の「ノルマン・コンクエスト(征服)」であろう。9世紀にアングロ・サクソン人のアルフレッド大王が統一イングランド王国の基礎を築いた。その後、イングランド王国ではスカンジナビア半島のデーン人による侵略や一時的な支配の時期はあったが、1042年にはノルマンディーに亡命していたアングロ・サクソン人のエドワード証聖王が即位した。しかし、彼が1066年に亡くなると、フランスの一部にすぎないノルマンディー公国のギヨーム2世が王位継承権を主張してヘイスティングの戦いが起きる。この戦いでノルマンディー公国が勝利し、ギヨーム2世はイングランド王国のウィリアム1世として即位して現在の英国王室の開祖となった。1086年には主要領主や聖職のほとんどがノルマン人に取って代わり、宮廷を始めとした上流階級の公用語がフランス語となった時代が1362年まで続いた。
「支配層はノルマン人、被支配層はアングロ・サクソン人」という階級構造は言語にも影響を及ぼし、動物そのものを示す言葉と食肉用を示す言葉が異なるようになる。元々アングロ・サクソン人が食べていた「鶏」は動物も肉も「chicken」なのだが、牛、豚、羊は下記のように言葉が分かれた。「アングロ・サクソン人が育てる牛」は英語の「cow」となり、「ノルマン人が食べる牛肉」はフランス語の牛「boeuf」が転じて英語の「beef」となったのである。そして、長い歳月を重ねてフランス語が英語に転化していくと同時に、イングランドに定住したノルマン人も英国の貴族として土着化していった。
| 動物(英語) | 動物(仏語) | 食肉(英語) | |
|---|---|---|---|
| 牛 | cow | boeuf | beef |
| 豚 | pig | porc | pork |
| 羊 | sheep | mouton | mutton |
しかし、ノルマン・コンクエスト以降、英国では、「腕前が良い料理人はいつの時代もフランス人」と相場が決まっており、英国貴族の多くが高給取りのフランス人料理人を置いていた。ナポレオン戦争時代の対仏感情が悪い時はさすがにフランス人料理人を雇うのを控えていたが、英国が世界の覇権を確立すると、フランスへの警戒心がなくなり、厨房に彼らを呼び戻した。長年にわたってフランス人料理人に占められた英国の厨房から、英国伝統料理を確立させることは難しかったのかもしれない。
(2)ピューリタン革命による節制生活
英国が「食に関心をもたない」ようになるのはピューリタン革命が大きく影響している。ピューリタンとは、清潔や潔白を表すpurityに由来する。ピューリタン(清教徒)はカルヴァンの影響を受けたイングランド国教会の中の改革派であり、宗教改革を徹底することで、国教会の浄化を目指し、合理主義の立場で禁欲や勤勉を説いた。1620年に一部のピューリタンが信仰の自由を求めてメイフラワー号に乗って北アメリカに移住したことは有名な話だ。
1642年のピューリタン革命では、専制政治をおこなうチャールズ1世王党派とピューリタンが主力となる議会派の間で内戦が勃発、1649年には議会派の勝利によってチャールズ1世が処刑され、共和制が実現された。その際、権力を握ったのが革命の指導者オリヴァー・クロムウェルである。このピューリタンの指導者によって、ありとあらゆる享楽が罪悪視され、スポーツ、劇場、化粧、華やかな衣装も禁止されたようだ。
特に「食事は関心を持ってはいけないもの」であった。当時の有名な牧師リチャード・バクスターの説教には「食事時間は15分もあれば十分で1時間も費やすなど馬鹿げたこと」、「おいしそうな食事は悪魔の罠なので目にすべきではなく、貧者の粗食を食べるようにすれば地獄落ちから免れる」とあるそうだ。隣の美食の国フランスについては「王様と宮廷を中心として食に拘り、堕落している」と見下げていた。
英国の支配層であるジェントルマンには「肉を茹でるか焼くだけでソースなどをかけずに食べること」が推奨され、そうしたジェントルマンの子弟が寄宿するパブリック・スクールでは粗食が徹底された。昨今では「3歳までの食経験が、その人の一生の味覚を左右する」と言われるが、当時の育児書には「食に関心を持たせないために離乳食は単調で不味くすべきである」と記載されていたらしい。まさに、「三つ子の魂百まで」だ。
その後、クロムウェルの厳格で独裁的な政治手法は国民の支持を失い、彼が亡くなった2年後の1660年には王政復古となる。クロムウェルによる11年にわたる共和制の間も、英国なりの豊かな食文化は残っていたが、「味に頓着せず、食事は単なる燃料補給」という意識が定着した。こうした意識がその後の産業革命期でさらに強くなり、英国では伝統的に「目の前にある飲み物や食べ物に無関心を装うのが行儀が良い」と考えられるようになった。
(3)囲い込み運動による伝統の食文化の消失
17世紀までは英国の人口の4分の3が農村部に住んでいた。英国の気候や土壌では野菜の種類が少なく、グリーンピースなど豆類やキャベツ、ネギ、タマネギ、レタス、はつか大根、アスパラガス、ホウレンソウぐらいしかなかった。18世紀に入っても野菜の供給は十分ではなかったが、農民は森や川などの「共有地」に自由に出入りして、薪、果実、野生鳥獣、魚、キノコなどを採取し、自給自足の生活が可能であった。村のお祭りや祝宴では季節感のある食事がさまざまな調理方法で提供され、伝統料理も伝承されていた。
しかし、17世紀後半に食糧増産のために「第二次囲い込み運動」が始まると、生活の場としての農村が急速に衰退していく。「第二次囲い込み」では、まず「三圃制農業」から「ノーフォーク農法」に転換する農業革命が進み、農業生産性が大幅に向上した。その恩恵を受けるために地主や農業資本家は共有地などの解放耕地を囲い込み、土地を集約して大規模農場経営を始めた。この運動によって「共有地」が私有地化されると、農民はそこへ立ち入って食材を採集することができなくなった。私有地となった共有地での採取は窃盗行為となるからである。
囲い込みによって、土地も働き口も失った中小規模の自営農民は、地主に雇われる農業労働者になるか、同時期に起きていた産業革命の工場労働者として都市へ流入することになる。農村では人口が激減し、存続することが難しくなると、農村で育てていた菜園や庭畑は荒廃し、豊かな食材や調理方法の伝統も同時に消えていったのであった。
(4)産業革命と都市化による生活の商業化
「第二次囲い込み」によって、働き口を失った農民が都市に大量に流入して工場の賃金労働者となったことで、1801年までにはイングランドの人口の3分の1が、1848年までには約半数が都市の住民となった。急激な人口増加に都市の住宅供給は追い付かず、不衛生なスラム街が形成された。工場の煤ばい煙えんによる大気汚染や水質汚染、コレラなどの疫病の流行によって労働者の居住環境は劣悪であった。
キッチンや水道、トイレもなく、安普請の家に暮らす中で、食生活も大きく変化する。農村では共有地で薪を拾ったり、自分で野菜を栽培したりするなど自給できたのだが、都市に住むと燃料の石炭から飲料水まで、衣食住のほとんどのものを市場や店でお金を出して買うようになった。都市では家庭はもはや生産の場ではなくなり、消費を中心とした生活の場となったのである。こうして生活の商業化が起こると、収入の少ない労働者の生活は大変であった。
都市労働者は賃金収入を増やすために、妻、子供も含めた家族全員が働くことになった。しかも工場労働者は労働時間を対価に賃金を受け取るので、朝の出勤に遅刻しないように、朝食は手間のかからない簡単なものとなった。また、工場では過酷な長時間労働なので、帰宅後ゆっくりと料理する時間もなかった。燃料費などで家計負担が増えると、食材の品質を低下させたり品数を減らしたりするので、調理法はおのずと単純なものになっていく。塩と胡椒だけの単純な味付けでも、ましな方だったのだろう。
また、都市の狭小な住宅では、食料品を保存しておくスペースもなく、食材は腐らないように半ローストにするか、下茹でするしかなかった。消化不良をさけるという理由もあるが、コレラの流行などの問題もあり、生野菜や生の果物は不衛生なので食べず、食材を十分すぎるほど加熱するのが常識となる。これについては冒頭のエッセイの中で、林望氏が「呆れるほど長い時間をかけて茹でたことでぐずぐずに崩れた野菜」と嘆いている。ちなみに徹底的に茹でるのは、口臭と放屁を防ぐための社会道徳的な防衛策だったという説もあるらしい。
3.戦争で見える英仏の食文化の違い
 都市に住む労働者たちは、とりあえず焼くか茹でただけの料理でも、胃袋さえ満たせれば味はどうでもよいという状況であった。こうした環境が戦争においても影響を与えている。1848年から発行された英国婦人雑誌『ファミリー・エコノミスト』では、英仏の違いについてナポレオン戦争での興味深いエピソードを取り上げている。記事の内容は次の通りだ。
都市に住む労働者たちは、とりあえず焼くか茹でただけの料理でも、胃袋さえ満たせれば味はどうでもよいという状況であった。こうした環境が戦争においても影響を与えている。1848年から発行された英国婦人雑誌『ファミリー・エコノミスト』では、英仏の違いについてナポレオン戦争での興味深いエピソードを取り上げている。記事の内容は次の通りだ。「1808年のナポレオン戦争スペイン戦線で英仏とも軍の食料補給に困ったことがあった。フランスの兵隊は乏しい材料の中でも肉を細切れにして叩いて伸ばしたり、辺りから野草や自生の野菜をかき集めたりした。その具材の味付けや調理方法にも工夫を凝らしてシチューを作るなど、少しでも栄養のある美味しい食事を提供しようとした。一方、英国の兵士は肉の塊を石炭の火で炙るだけで、大部分を真っ黒こげの灰にし、火がかからない部分は生のままという有様。せっかくの肉も台無しとなり、兵士は腹をすかしたままであった。その結果、フランスの兵士は英国の兵士より、はるかに強さを保持した」。
ナイチンゲールの活躍で有名なクリミア戦争(1853~1856年)でも同じようなエピソードがあり、伝統的に英国では階級を問わず「調理法の工夫が足りない」ことを示している。
英国料理の不味さの要因について、さまざまな角度から探ってきたが、味覚は主観であり、好みもいろいろである。英国のステーキやローストビーフは美味しいと評判であり、それ以外の料理にも多くのファンがいる。
冒頭で触れたジョージ・オーウェルのエッセイ『イギリス料理の弁護』にも続きがある。彼は「英国でなければ絶対手に入らない美味しいものが実に多い」と英国料理を称賛し、「独創性と材料に関する限り、英国料理を恥じるいわれはない」と断言している。ただし、「個人の家庭以外では上等な英国料理はお目に掛かれない」とし、「高級レストランやホテルはフランス料理の真似をし、安くて美味い料理を食べたい時はギリシャ、イタリア、中華料理の店に足が向く」と語っている。美味くて安い英国料理のレストランを見つけるのはなかなか難しいようだが、2013年から英国政府は「英国料理が不味い」という定評を払拭するために、英国料理の美味しさを体験するキャンペーン「Food is GREAT」を日本で実施している。また2020年のミシュランガイドでは、英国は169軒のレストランが星を受けている。
次回は産業革命によって大きく影響を受けた英国式朝食、特に砂糖入り紅茶やアフタヌーンティーを中心に引き続き食文化の歴史を辿る。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第8回]~2020年9・10合併号
チャールズ・チャップリンの傑作映画の一つ「モダン・タイムス」では、製鉄工場で働く主人公チャーリーが機械文明に翻弄される姿が描かれていた。チャーリーが歯車に巻き込まれるシーンが有名であるが、まさに労働者が機械に振り回され、時間に束縛される工業社会を風刺するものだ。英国産業革命においても、工業社会の到来とともに労働者は時間に縛られるようになった。労働者を中心として「時間に対する意識」が産業革命期において、どのように変化したのだろうか。
英国で誕生した鉄道は、大量・迅速・安価な輸送手段として発展し、人々の「時間に対する意識」を大きく変化させていった。鉄道によって人々の日常生活が便利になっただけでなく、それまでの大雑把な時間管理がきめ細かくなったのだ。また、過酷な労働環境にあった労働者が待遇改善されると、鉄道を余暇時間の活用手段として利用するようになり、旅行業が脚光を浴びるようになった。余暇時間に対する意識の変化だ。
今回は、鉄道の発展による社会の変化、時間管理の変化とともに、それにともなう余暇時間の活用と近代旅行業の創始者トーマス・クックについて辿たどる。
1.鉄道の発展による社会の変化
(1)鉄道網の形成と大量輸送
1830年に開業したリヴァプール・マンチェスター鉄道の成功はたちまち全国に知れ渡り、1840年までには主要都市間の鉄道はほぼ完成した。さらに1845年頃から、鉄道会社が投資目的で一斉に幹線につなぐ支線の建設に乗り出し、1850年には5000マイル(約8000km)の一大鉄道網が完成した。リヴァプール・マンチェスター間の輸送力は馬車の時代には駅馬車が全便満員でも1日700人までが限界であったが、鉄道ができたことで1日平均1100人と大量かつ安全に輸送できるようになった。
(2)高速化と運賃の低下による通勤圏内の拡大
鉄道の速度において、かなりの高速化が図られた。スティーヴンソンの蒸気機関車を例に速度の推移を見てみよう。1825年開通のストックトン・ダーリントン鉄道で走行した「ロコモーション1号」は平均時速6マイル(9.6km)と遅かったが、1830年開通のリヴァプール・マンチェスター鉄道で走行した「ロケット号」ではその倍の平均時速12マイル(19.2km)となった。1860年にはノース・イースタン鉄道で「改良型ロケット号」がその3倍の時速42マイル(67.2km)を達成した。
1841年に開業したロンドン・ブライトン鉄道(全長約76km)の2等クラスの往復割引切符は当初15シリングであったが、わずか8年で3シリング半にまで安くなった。1847年には労働者が沿線に多く住むイースタン・カウンティズ鉄道で、通勤圏は2ペンスという安い運賃で往復ができるようになった。また、当初高額だった鉄道の定期券は上流階級や株主向けに販売されていたのだが、運賃が安くなると19世紀後半には労働者が通勤用として利用するようになる。
鉄道によって通勤圏内が拡大すると、金銭的に余裕がある一部の労働者たちは劣悪な環境の都市部から脱出して、環境の良い郊外に移り住むようになった。
(3)鉄道による日常生活の利便性向上
これまで都市部では飲み水が不衛生でコレラや腸チフスなどに罹かかる心配があったので、水の代わりにビールやジンを飲んでいた。牛乳も腐りやすいので飲めなかった。しかし鉄道によって大量輸送が迅速にできるようになったおかげで、遠隔地でも新鮮な牛乳だけでなく、生鮮食料品も安定的に手に入るようになった。
郵便、新聞、雑誌も鉄道によって格段に速く届くようになっただけでなく、蒸気機関を利用した印刷機の性能向上で印刷物の価格も下がっていた。1840年には、成人の「読む能力」は75%、「書く能力」は60%に達していたこともあり、新聞や書籍の購読者が増え、貸本屋も流行ったらしい。ロンドンの最新のファッションも地方に短期間で浸透するようになった。
農作物については地域の収穫状況によって価格が異なっていたのだが、物流と情報伝達が速くなったおかげで、農作物の価格の差異が短期間で平準化されるようになり、都市と地方の物価格差が縮小した。
2.鉄道の発展による時間管理の変化
(1)鉄道における標準時間の設定
こうして鉄道が一般的に利用されるにしたがって、列車の定時運行が求められ、時間管理がきめ細かくなった。18世紀後半までは、各地域の時刻は日時計によって決められ、国内で統一されていなかった。ロンドンの時刻はグラスゴーより17分早かったのだが、速度の遅い馬車の時代には30分程度の違いは何ら支障がなかった。
しかし、鉄道網が各地に拡がるにつれて、二つの問題が生じた。一つ目は駅ごとに採用する時刻が異なっていたため、列車の発着時間に混乱が生じたことだ。二つ目は列車の本数が増加するにつれて、ダイヤが過密になり列車の事故やニアミスが増加したことだ。駅ごとにバラバラの時刻が利用されたままでは鉄道の時刻表を作成するのに都合が悪いので、1840年11月にグレート・ウェスタン鉄道が「グリニッジ平均時」に基づいた時刻表で標準化した。すると他の鉄道会社も次々に「グリニッジ平均時」を採用して、1855年までに鉄道全体の98%が採用し、時刻の標準化がほぼ完了した。
(2)鉄道の時刻表の普及と定時運行へ
 当初、時刻表には出発時刻のみ記載されていた。当時の蒸気機関車はスピードが一定せず、故障も多かったので、列車の到着時刻を確定できなかったのがその理由だ。しかし蒸気機関車の性能向上と利用者の要望によって、1837年のグランド・ジャンクション鉄道開通時には、停車する駅の到着時刻が時刻表に記載された。こうして鉄道会社ごとの時刻表は整備されていったのだが、英国全土を網羅した時刻表がなかった。そこに着目した印刷業者のジョージ・ブラッドショー(1801~1853)が1839年に全国鉄道時刻表を作成し、6ペンスという安い価格で出版すると、「遠距離旅行に役立つ」と旅行客の人気を集めた。
当初、時刻表には出発時刻のみ記載されていた。当時の蒸気機関車はスピードが一定せず、故障も多かったので、列車の到着時刻を確定できなかったのがその理由だ。しかし蒸気機関車の性能向上と利用者の要望によって、1837年のグランド・ジャンクション鉄道開通時には、停車する駅の到着時刻が時刻表に記載された。こうして鉄道会社ごとの時刻表は整備されていったのだが、英国全土を網羅した時刻表がなかった。そこに着目した印刷業者のジョージ・ブラッドショー(1801~1853)が1839年に全国鉄道時刻表を作成し、6ペンスという安い価格で出版すると、「遠距離旅行に役立つ」と旅行客の人気を集めた。
鉄道の登場によって、大雑把だった時間管理がきめ細かくなると同時に、高速で安くなった鉄道を利用して労働者も余暇の楽しみとして旅行に行くようになる。次章では、労働者が余暇時間を活用するようになるまでのプロセスを追う。
3.労働者が余暇時間の活用に至るまで
(1)産業革命による労働時間の変化
産業革命前、人口の大半を占める農民や職人は「仕事場」と「自宅」が一体もしくは近接しており、天候などの自然条件を見つつも時間に縛られず働いていた。自分が作ったものの対価として、「出来高払いの報酬」を受け取り、自給自足的な生活を営むのが一般的だった。
産業革命では、さまざまな発明・技術革新によって工業製品が大量生産されるとともに、工場で働く労働者が急増した。労働者の大半は農村を出て都市部に流入してきた農民や職人たちだ。彼らは毎日自宅から工場に通勤し、経営者が決めた労働時間通りに仕事をして、「その労働時間の対価として報酬を得る」という生活に激変した。つまり、時間に束縛される生活に変わり、労働時間と非労働時間、いわゆるオン・オフの区別が明確となったのだ。しかし産業革命の初期において、労働環境は過酷であった。
(2)劣悪な環境と住居を強いられた労働者
英国では19世紀に人口が急増し、離農した農民などが都市へ労働者として大量に流入したことで、都市の環境悪化と労働者の劣悪な住宅事情をもたらした。イングランドの人口は1800年の860万人から1851年には2倍の1681万人に急増。しかも人口の約半数が都市部に集中する異常事態である。
多くの労働者は三方を壁で囲まれた安やす普ぶ 請しんの長屋に住んだ。家は風通しが悪く、トイレも水道もない代物であった。人口が急増すると、さらにスモッグなどの公害が発生し、コレラ、チフスなどの疫病も蔓延するなど都市の環境は著しく悪化していた。このような劣悪な環境の中で、賃金も低く貧しい労働者たちは団結して待遇改善を求めるようになり、労働運動が始まった。
(3)労働環境の改善による余暇時間の増大
まず、幼い子供が1日15~16時間も働かされるという過酷な状況が社会的な問題となり、19世紀初めには産業資本家ロバート・オウエン(1771~1858)などから労働条件の改善を求める運動が始まった。そうした運動が実って、1833年の「工場法」の制定を皮切りに相次いで法律が見直され、労働時間の短縮や休日の増加など労働条件の改善が子供だけでなく大人にも実施された。1850年の商務省の調査では労働者の労働時間が週6日で60時間が標準となり、1867年には全国の工場に土曜半日制の勤務が適用された。ほかにも最低賃金の引上げ、食品の物価抑制などの対応も進められた。
1837~1901年の期間はヴィクトリア朝時代と呼ばれて、産業革命による経済発展が成熟期に達する大英帝国の絶頂期であったので、公園、図書館、博物館といった公共施設の設置など社会資本の整備も随分図られたようだ。
(4)飲酒に代わる余暇時間の過ごし方
一般的に「フランス人は飲むとおしゃべりをする。ドイツ人は寝てしまう。英国人は喧嘩を始める」と言われるほど、英国人は酒癖が悪いらしい。特に労働者階級は過酷な労働条件と劣悪な居住環境でストレスが溜まり、仕事が終わると毎日のように度数の高い安酒ジンを呷あおって憂さを晴らしていたので、アルコール中毒者が多かったようだ。
特に休日の日曜日に度を越した飲み方をして、月曜日が二日酔いで仕事にならない労働者の数が夥おびただしいものとなり、工場などの操業を妨げていたので経営者は困っていた。このように生産効率が落ちる月曜日は「聖月曜日」と呼ばれ、労働者のこうした悪い習慣を断ち切ることが社会的な課題となっていた。
「聖月曜日」に象徴される労働者の飲酒状況を憂慮して1830年に禁酒協会が設立されると、禁酒運動が各地で起こり全国に拡がっていった。議会も対応策としてアルコールの販売や消費を規制する法律を制定した。すると、飲酒に代わる娯楽として、ハイキング、ピクニックや海水浴など日帰り旅行が人気となった。
ブライトンは元々上流階級の保養地として有名な場所であったが、1841年のロンドン・ブライトン鉄道の開通を機に海水浴場として大人気となった。1750年代には馬車で2日もかかった距離が、鉄道によって日帰り旅行が可能な片道2時間となり、運賃も安くなったからだ。労働者階級にとって当地は絶好の行楽地となり、海水浴客が群れをなして押し寄せ大変混雑するようになった。1860年の1年間で25万人が訪れたらしい。
こうして、労働者階級にも余暇時間の活用が拡がり、近代旅行業の隆盛にも繫がっていく。
4.近代旅行業の創始者 トーマス・クック
(1)禁酒運動大会での団体旅行の大成功
世界最初の英国旅行代理店トーマス・クック社の創業者トーマス・クック(1808~1892)はバプティスト派の宣教師として熱心に禁酒運動を推進していた。酒を飲むしか余暇の過ごし方を知らない労働者に「禁酒運動大会に参加することによって余暇時間を健全な娯楽で楽しんでもらいたい」とクックは考えていたのだ。
そして、当時高額だった鉄道の運賃を鉄道会社に割引させる方法として、大人数の乗客をまとめて同じ列車に乗せることを思いつく。つまり団体割引の適用だ。さっそく運賃の価格交渉をすると、1841年開催の禁酒運動大会に行くための列車が「11マイル(18km)の往復運賃を食事・娯楽込みで1シリング」という破格な条件で設定できた。
クックは自ら「禁酒運動大会参加旅行」の宣伝、切符の販売、食事の手配、アトラクションなどの準備を整えて参加者を募集すると、バプティスト信徒の申し込みが殺到した。570名にものぼった参加者は禁酒運動大会で一日思う存分音楽やダンスなど娯楽を満喫し、企画は大成功となった。素晴らしいクックの企画力と行動力である。ちなみに団体旅行を組成するのは、クックにとってはあくまでボランティアの一環であり、無報酬で請け負ったらしい。
(2)ロンドン万国博覧会でのパック旅行の成功
さらにクックの名前が有名になったのは、1851年のロンドン万国博覧会の時であった。「世界の工場」として大英帝国の国威を示すために、ハイドパークで開催された国際的祭典である。新聞や大衆向け娯楽雑誌も万博熱をあおっていたので、会期140日間に延べ600万人もの入場者を集めた。ちなみに金曜日の入場料は2シリング半、土曜日は5シリングと高かったが、月曜から木曜の平日は1シリングと大衆価格に設定されていた。これに目を付けたクックは、博覧会用の旅行パック商品を企画・販売して、地方から16万5000人の入場者を送り込むという快挙を成し遂げた。
その後、クックは国内旅行だけでなく、海外旅行にも事業を拡大し、「団体旅行だと安く行ける」という考え方を一気に世の中に拡げ、観光の大衆化を成し遂げた。そのうえ、旅行に関連するガイドブック、鉄道の時刻表、旅行雑誌の発刊やホテルクーポン、トラベラーズチェックの発行などを行い、クックは旅行業を一大産業に押し上げたのである。
残念ながら、昨年2019年9月にトーマス・クック社はデジタル化などの時代の流れに対応できず、業績悪化で破産した。帰国できなくなったツアー中の旅行者15万人を帰還させるため、英国政府が「マッターホルン作戦」を実施したニュースはまだ記憶に新しいところである。
コロナ禍の中で、在宅勤務などのテレワークが脚光を浴びている。多くの会社が、「従業員の職場と住居が同じ」という産業革命前の職住一体・近接のスタイルを取り入れようとしている。英国産業革命を機に労働者が職住一体・近接から職住分離へ移行してきたことを考えると、今回の職住一体・近接への移行は産業革命前に逆行するようにも見える。しかしながら、現在の在宅勤務を実現可能としているのは、インターネットや情報処理技術の進歩など最新の技術革新のおかげだ。
余暇時間の活用においても、コロナ禍で海外旅行もままならない状況ではVR(仮想現実)やAR(拡張現実)による旅行の疑似体験を楽しむようになり、レジャーの考え方も変わってくるかもしれない。
英国の産業革命においても、「技術革新」だけでなく、コレラなどの「疫病の流行」が社会に大きく影響し、当時の人々の価値観や意識が変わっていった。われわれが今直面する「コロナ禍」という災厄と「AI、IoT、デジタル革新を中心とする第4次産業革命の技術」とが合わさって、これからわれわれの価値観や意識がどのように変わっていくのだろうか。
次回は、産業革命当時における住民の生活ぶり、特に食生活に焦点を当てる。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第7回]~2020年8月号
明治の初め、新しい日本と自らの前途に不安を抱いていた多くの青少年に希望の光明を与えた二大啓蒙書がある。
一つは有名な福沢諭吉の「学問のすすめ」(明治5年)だ。
もう一つは「西国立志編」(明治4年)であり、百万部以上売れたらしい。原典はサミュエル・スマイルズの「自助論」で、さまざまな階層での成功者の実例を多数挙げて集大成したものだ。1859年に英国で発刊されベストセラーとなり世界十数カ国語に翻訳された。日本では、英国留学を終えて帰国した中村正直が翻訳した。
この「自助論」に先立ってスマイルズが執筆したのが「スティーヴンソン伝」だ。炭鉱夫から「鉄道の父」となる成功譚が人気を得たことで自信をもち、「自助論」の執筆となったそうだ。今回はスティーヴンソンの生涯を辿る。
1.仕事をしながら炭鉱の技術習得へ
(1)8歳から生活費稼ぎ
 ジョージ・スティーヴンソン(1781~1848)はイングランド北部のノーサンバーランドのウィラムで4男2女の次男として生まれた。ウィラム炭鉱で揚水工として働く父親の賃金では家が貧しく、彼は学校へ行くことが叶わず8歳から炭鉱で働き始める。といっても石炭から異物となる石などを取り除く「ピッカー」という仕事で1日僅かな手当であった。少しでも条件の良い職を求めて頻繁に働き場所を変え、17歳の時ウォーター・ロウ炭鉱で「最新の蒸気機関の作業員」(排水機関の機関士)に採用される。そこでの仕事ぶりが認められ、同じ炭鉱で働く父親より手当が多くなってしまう。しかし、読み書きができなかったので、18歳から夜学で読み書きと算術の勉強を始める。
ジョージ・スティーヴンソン(1781~1848)はイングランド北部のノーサンバーランドのウィラムで4男2女の次男として生まれた。ウィラム炭鉱で揚水工として働く父親の賃金では家が貧しく、彼は学校へ行くことが叶わず8歳から炭鉱で働き始める。といっても石炭から異物となる石などを取り除く「ピッカー」という仕事で1日僅かな手当であった。少しでも条件の良い職を求めて頻繁に働き場所を変え、17歳の時ウォーター・ロウ炭鉱で「最新の蒸気機関の作業員」(排水機関の機関士)に採用される。そこでの仕事ぶりが認められ、同じ炭鉱で働く父親より手当が多くなってしまう。しかし、読み書きができなかったので、18歳から夜学で読み書きと算術の勉強を始める。
貧乏で学校に行けなかったので、あらゆる機会を利用して知識習得に努力するのだが、地元のノーサンブリア訛りが終生抜けず、論理的な説明は不得手であった。書くのもずっと苦手で、手紙の文章は息子か秘書に任せていたらしい。
(2)20歳で結婚、長男ロバート誕生
1801年に20歳でドーリー炭鉱へ移り、巻揚げ機の操作と保守を担当する「制動手」になると賃金も週1ポンドに上がる。そして富裕な農場経営者の娘エリザベスと恋に落ちるが、炭鉱夫に娘はやれないと彼女の父親から反対され結婚を諦める。次に炭鉱の宿舎で賄いをしていたアンに求婚するが、失恋。結局自分より13歳年上のアンの姉フランシスと結婚する。結婚までの紆余曲折はあったが、妻フランシスとの生活は幸せで1803年に息子のロバートが生まれた。
その頃、趣味であった時計や靴の修理を副業にする。機械いじりの才能があったのか、特に時計の修理には定評があった。1804年にキリングワースへ移りウェスト・ムア炭鉱の制動手となる。
2.不幸にめげず技術者としての才能開花へ
(1)試練の時 家族の死と父の失明
1805年に生後間もない長女を亡くし、翌年には妻のフランシスが肺結核で死去した。3歳の息子ロバートの世話は未婚の妹エリーナに頼るしかなかった。
そんな時に自身の父親が炭鉱のボイラー事故で失明してしまい、仕事ができなくなる。さらに彼が命じられた対仏戦争の兵役を他の人に代わってもらうために大金を投じたことや、面倒を見ることになった父親の借金清算もあり、貯金を使い果たしてしまう。途方に暮れ、一時は北米への移住を検討するが、一人息子の将来とこれまで築いた機械工の経歴を大事に考えて思いとどまる。そして、蒸気機関の建造技術を懸命に磨くために、炭鉱で機械を止めている毎週土曜日に蒸気機関の分解組み立てを繰り返した。
(2)貪欲な技術の修得意欲とチャンス到来
1811年、グランド・アライアンス社は炭鉱にニューコメン式蒸気機関を新規に設置したが、故障を繰り返した。誰も修理できず、頭を抱えた会社は報奨金10ポンドで改善策を募った。スティーヴンソンが必死に磨いてきた技術力を発揮するチャンスが到来する。
故障の原因を冷水の噴射装置の不備と見抜いたスティーヴンソンが見事に蒸気機関を修理したので、喜んだ会社は彼に報奨金を与えただけでなく、会社が多数保有する鉱山すべての機械設備の責任者に任命した。彼の収入は年間100ポンドの高給となり、遠距離出張用の馬も贈呈されたらしい。技術者スティーヴンソンの誕生である。
3.蒸気機関車建造への挑戦
(1)第1号蒸気機関「ブリュッヘル号」
スティーヴンソンはその後も自らの技術をさらに磨き、固定式蒸気機関などの製作を始めた。そして、トレヴィシックなどの蒸気機関車に刺激されて、いよいよ蒸気機関車の製作に入る。製作に必要な資金は会社のリデル准男爵やレーブンズワース卿など資産家が支援してくれた。
自宅近くのウェスト・ムア炭鉱の作業所で、仕事の合間を縫って蒸気機関車の製作を開始し、彼にとって第1号となる蒸気機関車「ブリュッヘル号」を1814年に完成する。
翌年に「ブリュッヘル号」は、キリングワースの軌道を総重量約30tとなる貨車を引いて平均時速約6kmで走行した。従来のトレヴィシック型に比べると牽引力が弱かったが、実用性、経済性においては問題なかった。彼はその後も懸命に改良を重ねて騒音や圧力不足という課題を解決し、石炭輸送目的の蒸気機関車を数台製造した。
(2)息子ロバートへの教育投資
無学で苦労したスティーヴンソンは、息子ロバートにはしっかりとした教育を受けさせたいと考えて、ロバートが12歳になった時、ニューキャッスルの名門カレッジ「パーシー・ストリート・アカデミー」に入学させた。労働者階級の彼にとって、中産階級が通う有名校は高嶺の花であったが、息子のためと思って高い学費も何とか工面した。しかも、息子ロバートが学校から帰宅すると、その日習ったことを親子で長時間復習していたらしい。スティーヴンソンは学校の授業を息子となぞることで、自分に足りない知識を補っていたのだ。知識習得に対すジョージ・スティーヴンソン る彼の努力は尊敬に値する。
愚鈍な印象を与える労働者階級特有の自分の訛りについて、スティーヴンソンは強い劣等感を抱いていたようだ。しかし、息子ロバートは名門校に行くことで、学問を習得するだけでなく、ノーサンブリア訛りが次第に取れていった。
4.ヘットン炭鉱軌道の成功と初恋の人との再婚
1814年以降、多くの蒸気機関車の製造に関わったスティーヴンソンはヘットン炭鉱から石炭運搬用軌道13km敷設のために1819年に技師として招かれた。
ヘットン炭鉱は英国で最大の出炭量がありながら、輸送コストが高いのがネックであった。輸送コスト改善のために、新たな軌道敷設が計画された。自走する蒸気機関車と急斜面用で車両を牽引する固定式蒸気機関を併用する方式で進められ、技師スティーヴンソンの主導のもとで完成まで2年を要した。当時の蒸気機関車のパワーでは急斜面を登ることができず、ケーブルカーのようにロープに繋いだ車両を固定式蒸気機関による巻揚げ機で牽引する必要があった。
1822年の開通時には総重量84tの貨車17両をつないだ蒸気機関車が平均時速約6kmで走行した。その時の走行の様子は新聞で報じられ、スティーヴンソンの名前が世に知られるようになる。また、この軌道のおかげでヘットン炭鉱は生産性が高まり、炭鉱の業績は大きく改善したようだ。
ちなみに、1820年にスティーヴンソンは再婚するのだが、なんと相手は父親の反対で諦めた初恋の人エリザベスであった。彼女は一途にスティーヴンソンのことを思って他の誰とも結婚せず未婚のままだったのだ。二人は結婚して幸せな家庭を築くが、子供には恵まれなかった。
5.ストックトン・ダーリントン鉄道
(1)運河派vs.馬車軌道派そして法案成立
スティーヴンソンの知名度をさらに全国区にあげたのが、ストックトン~ダーリントン間での鉄道の建設だ。
その頃、ダーラム南西部の炭鉱ダーリントンから東部にあるティーズ川河口の町ストックトンの40kmを結ぶ石炭運搬用の交通手段が検討されていた。当初は、当時主流であった運河での輸送が検討されたが、莫大な費用がかかるので計画が立ち消えとなっていた。その運河計画が1818年に再浮上するが、あわせて馬車軌道建設案も提示された。ストックトン側は運河建設の推進、ダーリントン側は馬車軌道の推進となって意見が分かれて対立するが、最終的には馬車軌道建設推進側が優勢となった。
建設のためにストックトン・ダーリントン鉄道会社が設立され、鉄道建設の法案が議会に提出されるのだが、路線を通過する地主からの強力な反対によって法案は廃案となってしまう。しかし、会社設立メンバーの一人である実業家エドワード・ピーズが中心となって議会や地主対策に金も努力も惜しまず精力的に活動したおかげで、三度目の法案提出で無事成立の運びとなった。
その直後にスティーヴンソンはピーズに自らの主任技師への採用を売り込みしたようだ。
(2)会社設立と蒸気機関車導入への計画変更
当初は馬車や固定式蒸気機関を利用する計画であったが、蒸気機関車の導入を目論むピーズはヘットン炭鉱軌道で有名になったスティーヴンソンを主任技師に採用する。1821年にピーズがストックトン・ダーリントン鉄道会社の社長となり、会社の創立総会を開催すると、蒸気機関車を導入するためにさまざまな工作をおこない、開業直前に蒸気機関車を利用する計画へ変更することに成功する。
計画変更により内容の早急な見直しが必要となったが、この鉄道の建設資金は主にピーズ社長をはじめとするクエーカー教徒の人脈からの出資によって賄われた。また、計画変更に伴う路線の測量にアカデミーを卒業したばかりの息子ロバートが加わっている。
ロバートには1822年に化学や地質学などの習得のためエジンバラ大学の短期コースに入学させている。ここでも、大学入学はロバートのためだけでなく、アカデミーの時と同じようにスティーヴンソンが化学や地質学の知識を習得する狙いもあった。大学で習ったことを親子で毎日貪欲に復習していたのだろう。こうした不断の努力が実って鉄道事業にも役立つことになる。
また、工事が開始されると、スティーヴンソンはこの路線のレールの形状や蒸気機関車走行の安全面を配慮して路線の3分の2には鋳鉄より頑丈な錬鉄製レールを、そして残りの部分は鋳鉄製レールを採用することに決定した。
(3)蒸気機関車製造会社の設立と鉄道開業
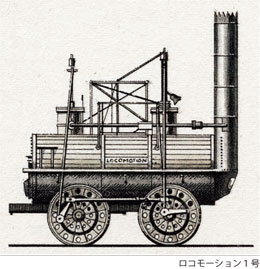 蒸気機関車の製造が近い将来一大産業になると読んだスティーヴンソンは、1823年に蒸気機関車製造の専門会社「ロバート・スティーヴンソン社」を設立する。そして、翌年には、ストックトン・ダーリントン鉄道会社から蒸気機関車2両を受注した。
蒸気機関車の製造が近い将来一大産業になると読んだスティーヴンソンは、1823年に蒸気機関車製造の専門会社「ロバート・スティーヴンソン社」を設立する。そして、翌年には、ストックトン・ダーリントン鉄道会社から蒸気機関車2両を受注した。
1825年にストックトン・ダーリントン鉄道の開通式がおこなわれ、終点のストックトンには4万人もの人が集まった。これまでにない大規模な公共交通鉄道であり、新聞にも大きく取り上げられた。「ロバート・スティーヴンソン社」が製造した重量8tの「ロコモーション1号」は約300人を乗せた客車26両と石炭を積んだ貨車12両を引いて時速19~26kmで走行した。最高速度は39kmに達したが、急勾配では依然としてパワー不足の蒸気機関車を補う固定式蒸気機関による牽引力が必要であった。
この鉄道は乗客も乗せたが、あくまで石炭輸送など貨物輸送が中心であり、開業後しばらくは石炭輸送が収入の9割を占めた。
また、この鉄道ではスティーヴンソンが軌間1435mmの錬鉄製のレールを採用したが、この1435mmのサイズがその後、世界の標準軌道間となる。
スティーヴンソンは、この鉄道の成功で全国的に知名度が上がり、各地の鉄道建設計画への助言者として引っ張りだことなった。
6.リヴァプール・マンチェスター鉄道
(1)産業革命の進展に対応できない物流手段
19世紀当時、産業革命の中心地マンチェスターは綿繊維や機械工業の一大集積地を形成し、港湾都市リヴァプールはロンドンに次ぐ代表的な港湾都市となっていた。
産業革命の進展とともに物流量が急増して、従来の運河・河川・ターンパイク(有料道路)だけでは輸送をカバーできなくなっていた。しかも両市を結ぶ従来の貨物輸送手段は運賃が高い割に輸送スピードが遅かった。特に河川や運河を利用する水上輸送は、夏の渇水、冬の凍結の場合には運航不能となる欠点があった。
(2)鉄道会社の設立と鉄道建設計画の難航
商工業者は不便で値段の高い既存の輸送業者に不満をもち、考え出したのがリヴァプール・マンチェスター鉄道計画であった。
1824年に設立されたリヴァプール・マンチェスター鉄道会社から主任技師に招聘されると、スティーヴンソンはその役職への就任を受託した。ちょうどその頃は、ストックトン・ダーリントン鉄道が完成間近で、そこの主任技師であるスティーヴンソンは多忙であったにもかかわらず、全国的に知名度が上がった自分に白羽の矢が立ったことからリヴァプール・マンチェスター鉄道会社の主任技師を掛け持ちした。
その頃でも依然として、世の中の蒸気機関車への理解は低く、地主や農場主は煙突が発する火の粉の火災や騒音による家畜への健康被害を心配していた。そのため、路線の農場経営者や地主の激しい反対運動にあい、1825年に鉄道建設の法案は却下されてしまう。会社側は法案が却下されたことをス
ティーヴンソンの責任とした。ノーサンブリア訛りのスティーヴンソンの拙い答弁能力では議会での厳しい質問の応酬に耐えられなかったと判断したのだ。階級意識の強い英国ではスティーヴンソンに対して労働階級出身の野卑な人物という差別意識も根底にあったようだ。この結果、スティーヴンソンは主任技師を解任されてしまう。
(3)法案再挑戦と主任技師への返り咲き
二度目の法案を通すため、会社は父親の高名さを見込んで、多くの運河・橋の建設で名を馳せた土木技師の子息レニー兄弟を主任技師に招くことにする。この兄弟は鉄道の専門家ではなかったが、彼らの父親の知名度の高さは効果があったようだ。鉄道推進派の綿密な法案への準備と関係者への根回しもあり、無事に法案が通過した。
1826年にリヴァプール・マンチェスター鉄道会社の第1回の株主総会を開催し、スティーヴンソンを再び主任技師に戻すことにした。議会対策のため、やむなくレニー兄弟を主任技師にしたが、鉄道建設には、叩き上げの実務家である彼の力が必要であると会社は考えていたのだ。スティーヴンソンは期待通り、建設にあたっての難関を解決していく。
まず、工事の難航が予想された湿地帯でのレール設置。「チャットモース」と呼ばれる湿地帯は試行錯誤の連続であったが、膨大な量の木材などを束ねた上に石や土を投入して路床を固めることで最終的には成功した。蒸気機関車が安定走行するには、路線を出来るだけ水平に建設することが望ましいので、3つのトンネルと46の橋梁も建設した。
工事の進展とともに、工事費が嵩み、資金不足が明らかとなるが、大蔵省からの借入や追加増資により無事資金調達する。増資については株主からの絶大な支持を得て、ほぼ全額引き受けられた。
こうして軌道の建設は幾つもの難関を乗り越えて順調に進んだ。
(4)レイトンヒル公開競争でロケット号勝利
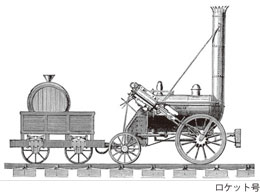 傾斜地では蒸気機関車がパワー不足になりがちなので、従来から固定式蒸気機関の牽引力をケーブルカーのように利用していた。この鉄道についても、一部の技術者の中から、部分的に固定式蒸気機関を動力に採用すべきとの意見が出る。蒸気機関車の性能に自信のあるスティーヴンソンは蒸気機関車のみの採用を強く主張する。
傾斜地では蒸気機関車がパワー不足になりがちなので、従来から固定式蒸気機関の牽引力をケーブルカーのように利用していた。この鉄道についても、一部の技術者の中から、部分的に固定式蒸気機関を動力に採用すべきとの意見が出る。蒸気機関車の性能に自信のあるスティーヴンソンは蒸気機関車のみの採用を強く主張する。
鉄道会社の社内でも意見が分かれ、どちらを採用するか決定するために、500ポンドの懸賞金を付けて一般公開競争を開催する。公開競争では機関車の時速、エンジンの重量、建造費など競争の条件を定めて、参加する蒸気機関車を公募した。
1829年のレイトンヒルでの公開競争には4社の蒸気機関車が参加する。「ロバート・スティーヴンソン社」は、息子ロバートが中心となって製造した蒸気機関車「ロケット号」を出場させた。「ロケット号」は強力なライバルを物ともせず、指定平均時速16kmを上回る19kmで往復約6時間かけて走行し、完勝するのであった。その快走を見た蒸気機関車の反対派が「ロケット号」の性能に感動して、蒸気機関車推進派に回ることになったそうだ。
(5)鉄道開業と世界初の鉄道死亡事故
1830年にリヴァプール・マンチェスター鉄道は8両の蒸気機関車を所有して営業を始める。鉄道時代の幕開けである。
開業式には首相のウエリントン公爵をはじめ、著名人が多数参列した。その開業式でハスキンソン商務大臣が蒸気機関車に轢かれて事故死するという不幸な事件が起きる。乗客たちは給水と給炭のために停車していた車両から下車して、危険と警告されていたにもかかわらず反対側のレールの上で休憩していた。そのうち反対側の線路に近づいてきた別の機関車に気付くのが遅く逃げ遅れたハスキンソンは蒸気機関車に轢かれて死亡してしまったのだ。
不幸な死亡事故はあったが、開業後の鉄道事業は順調に推移する。リヴァプール~マンチェスター間での仕事は日帰りで済ませることが可能となって、鉄道会社にとって輸送時間、輸送コストとも半分となった。鉄道は従来の貨物輸送中心から乗客輸送へ移行することになる。1831年の時点で乗客による収入が全体の65%を占めた。リヴァプール・マンチェスター鉄道は経営的にも成功して株主に高い配当が出せるようになった。
(6)大量かつ高速の乗客輸送で鉄道ブームへ
この鉄道は高速で大量の乗客を運ぶという新たな市場を切り開き、その後の鉄道ブームに繋がる。
その後二人目の妻エリザベスが1845年に死去すると、スティーヴンソンは64歳で現役を引退する。それまで海外を含め、あらゆる鉄道計画に関与した。1848年に67歳で三度目の結婚をするのだが、その年に自宅で肋膜炎のため死亡した。
スティーヴンソンの一生を眺めてみると、かなりの勉強家、忍耐強い努力家であったことが分かる。彼をサポートした息子ロバートの存在も大きい。鉄道建設には地元の支援、幅広い資金調達、優れた技術陣の3つが必要と言われるが、それらに対応する才覚も備えていたようだ。
炭鉱夫から苦心の末に鉄道の父となったスティーヴンソンの生涯をもとに執筆されたスマイルズの「自助論」の精神、すなわち「どんな階層の者でも自助・勤勉・忍耐さえすれば成功への道が開かれており、社会の発展に貢献できるのだ」という内容が万民に受け入れられたのも頷ける。
次回は、鉄道網の進展で変化したライフスタイルに触れたい。
追記:炭鉱用安全ランプの発明と屈辱
炭鉱では掘削の過程で炭化水素系の可燃性ガスが発生し坑内に漏れ出すことがある。そのガスに暗い坑内を照らすために持ち込んだランプの火が引火して爆発する事故が頻繁に起きていた。
そのガス対策として、英国を代表する科学者ハンフリー・デーヴィーとスティーヴンソンが偶然にも同じ1815年に鉱山の安全灯を発明した。
デーヴィーの安全灯はランプの芯の周りに鉄製の細かい金網をめぐらせたもの。そしてスティーヴンソンのものは多数の穴の開いた金属製の筒をランプの芯の周りに用いたものであるが、基本構造は双方同じであった。万一ガスが発生して、ランプの火が引火しても鉄の金網が火炎の熱を吸収するとともに、火炎は金網の小さい穴から金網の外へは出ていかず、外のガスには引火しない仕組みらしい。
科学知識を活かした者と経験から発想した者の違いであったが、デーヴィーは「スティーヴンソンのような無学な人間に発明できるはずがない。私のアイデアを盗用したのだ」とスティーヴンソンを告発する。数年後にスティーヴンソンの盗用疑惑が晴れても、デーヴィーは死ぬまで納得しなかったらしい。
この発明では、感謝した鉱山主がデーヴィーにお礼として2000ポンドを贈呈したが、スティーヴンソンには105ポンドしか贈呈されなかった。それを不憫に思った鉱山会社や仲間がお金を募って彼に1000ポンドを贈呈している。
経験から仕組みを理解したスティーヴンソンにとって、デーヴィーによる盗用の告発は屈辱的だったと思われる。こうした事件もあって、一層自ら勉学に励み、息子への教育熱が高まったのかもしれない。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第6回]~2020年7月号
日本では明治5(1872)年に新橋~横浜間で鉄道が開業した。当時の明治政府は鉄道発祥の英国から技術導入や資金調達をおこなった。日本の技術水準では自力製造できなかったので、英国人の鉄道技師エドモンド・モレルを招聘のうえ、英国製の車両を投入するなど全面的に英国の技術力に依存したのである。
今回は、その英国において蒸気機関が鉄道など輸送分野に広まっていくまでの過程を辿る。
1.輸送手段の変遷
(1)人・馬・運河・ワゴンウェイ
17世紀までは人や馬が直接荷物を担ぐ運搬方法が一般的であったが、未整備の陸路では輸送量に限界があり、壊れやすい物を安全に運ぶことが難しかった。特に鉱山では重量のある石炭などを運搬するので、大きな負担となっていた。そこに石炭を運ぶ新しい輸送手段として、ワゴンウェイ(貨物軌道)が生まれ、イングランド中に普及する。ワゴンウェイとは木製レールの上を馬が牽引して運搬する手押し車だ。馬1頭で7両の貨車(6t以上)が牽引可能となり、経費と時間は節約された。しかし、木製のレールは耐久性がなく1~2年で交換を要した。1738年にようやく鋳鉄を一部利用したレールが登場し、1750年代頃になると鋳鉄板を取り付けたレールが一般化して運搬できる量がさらに増大した。
また、1759年にブリッジウォーター卿によって建設された初めての近代的な運河が商業的に成功する。それを機として全国に運河網が拡がっていく。運河も重量のあるものを安全に運ぶのに適していたのだ。こうして従来からの陸路や河川に加えてワゴンウェイや運河などの交通網が発達した。
(2)世界初の公共馬車鉄道と馬の値段の高騰
1803年に世界最初の馬車鉄道会社である「サリー鉄道」が誕生する。鉱山の輸送に活躍したレールが道路にも設置され、公共の輸送手段として利用されるようになったのである。一般の利用者から利用料を徴収して貨物のみを輸送するものだ。レールを敷設することで運搬の大敵である振動を抑えることができた。クロイドン~ワンズワース間の約9.5マイルを1頭の馬が4両の貨車を引いていたらしい。
サリー鉄道の開通と同じ1803年にナポレオン戦争が勃発する。軍役で数百万頭の馬が必要となったことで、馬の利用コストが急激に上がり、馬の代わりとなる動力が必要となってくる。それにより蒸気機関車への開発ニーズが高まったのである。ジェームズ・ワットの蒸気機関の特許が1800年に失効して、新たな開発に遠慮なく取り組める環境となったこともあり、さまざまな発明家がこの分野に本格参入するようになる。
その開発者のなかで1804年に軌道上を走る蒸気機関車を世界で初めて発明し、蒸気機関車の父と呼ばれたトレヴィシックの苦闘と挫折の生涯を取り上げる。
2.蒸気機関車の父 トレヴィシック
(1)生い立ち
リチャード・トレヴィシック(1771~1833)はイングランド南西部コーンウォールで生まれた。
身長188cmの大男で逞しい体躯の持ち主だったので「コーンウォールの巨人」と呼ばれたそうだ。
彼の父親は鉱山の技術者として蒸気機関の導入と管理を担当していた。トレヴィシックは初等教育しか受けていなかったが、機械の知識が豊富な父親の影響でモノづくりに関しては抜群のセンスがあった。蒸気機関車を建造する才能に恵まれ、機械の効率性を向上させる数多くの技術革新をもたらすのであった。
(2)トレヴィシック親子とワットの特許妨害
コーンウォール地区では、高圧蒸気機関の開発が急速に進んでいた。彼の父親は利用中のワット型機関を高圧蒸気機関に改良しようとしていたが、それを察知したジェームズ・ワットは高馬力の高圧蒸気機関は危険だとして開発を阻止しようとする。しかし、トレヴィシックは1795年に父親の支援も得て独自に高圧蒸気機関を製造する。当然、ワットと共同事業者のボールトンは特許権の侵害だとして彼に使用差し止めを請求したが、シリンダーの上下を逆にして作り直すことで特許に対抗したようだ。
その後も、トレヴィシックは高圧蒸気機関の開発に取り組む中で、長きにわたってワットからの執拗な妨害に悩まされることになる。ワットは自分の特許に関わる新たな開発を常時監視し、特許侵害の訴訟や妨害工作に余念がなかったらしい。実際、多くの技術者がワットの強い妨害にあって蒸気機関の改良を断念していた。
3.蒸気自動車の製造と挫折
(1)蒸気自動車「パッフィング・デヴィル号」
トレヴィシックは蒸気機関車に先立って蒸気自動車の開発に取り組む。その端緒となったのは、近所に住むウィリアム・マードックとの出会いだ。
ワットに内緒で蒸気自動車を試作していたマードックから蒸気自動車の試作品を見せてもらったのだ。ちなみにマードック自身はボールトン・ワット商会の従業員だったので、ワットの猛反対に遭い蒸気自動車の開発を断念している。
その後、トレヴィシックはワット型蒸気機関の5分の1サイズの小型化の開発に成功したことから、蒸気自動車の試作に取り組み、完成させる。その蒸気自動車を「パッフィング・デヴィル号」と名付けて、世界初となる蒸気自動車のデモンストレーションを開催した。1801年のクリスマスイブにカムボーンの道路で7、8人を乗車させて走らせた。ひとまず走行に成功するのだが、1週間後には車輪が轍にはまって蒸気自動車が転倒してしまった。そのうえ、過熱でボイラーの水が干上がったのに気付かず、蒸気自動車が火事になるというお粗末さだった。
(2)蒸気自動車「ロンドン蒸気車」
1803年には2年前の「パッフィング・デヴィル号」では十分でなかった蒸気圧を改良した新たな蒸気自動車「ロンドン蒸気車」を製作する。この蒸気自動車は蒸気を噴き上げ、馬を怖がらせながらロンドンやその郊外の通りを順調に動き回ったのだが、結局は道路状況の悪さが災いして車台枠がねじれてしまった。また馬車よりコスト高で乗り心地も悪かったので、蒸気自動車は世間の興味を引かず、支援者たちの期待を裏切ることになる。
これを機に道路を走る蒸気自動車からレールの上を走る蒸気機関車の開発に軸足を移すことになる。
4.高圧蒸気機関の特許取得と死亡事故
(1)高圧蒸気機関の特許取得
若干時は遡るが、トレヴィシックは二度目の蒸気自動車が失敗する前年の1802年に「蒸気機関建造に関する改善方法と自走馬車とその他の目的に関する申請」という特許を取得している。特許を世の中に認めてもらうには実物を見せて納得させる必要があると考えた。そこで、すぐに高圧蒸気機関を製造し、性能の良さを立証したのである。完成した蒸気機関では毎分40回のピストン運動が可能となった。その性能が評価されて、同じ1802年にペナダレンで鉄工所を経営するサミュエル・ホムフレイから高圧蒸気機関の製造を受注する。そして出来上がった蒸気機関を貨車の台車に載せて蒸気機関車のように動かしてみせると、ホムフレイは感激してトレヴィシックの特許を買い取った。さらにホムフレイは鉄の運搬用として興味をもっていた蒸気機関車の開発支援も約束した。
(2)グリニッジの死亡事故とワットからの非難
ところが、これから本格的に開発という時に事件が起きた。翌1803年にトレヴィシックがグリニッジに設置した固定式高圧蒸気機関のボイラーが爆発して、4人の死者を出すのだ。
彼は原因を担当者の不注意による操作ミスとしたが、ワットとボールトンは高圧蒸気機関の危険性を裏付ける証拠として厳しく糾弾し、法律での規制を議会に提案した。ワットは自分の発明した蒸気機関が危険な代物と思われることを恐れていたのだ。実際、高圧蒸気機関は直接高圧の蒸気がボイラーに掛かるので、強度不足のボイラーでは耐え切れず爆発事故が多発した。その後、トレヴィシックは危険防止のために、ボイラーに2つの安全弁と水銀を利用した圧力計を設置したのだが、頑丈な鋼鉄製のボイラーが完成する19世紀後半まで危険なボイラーという悪評が続いた。
5.蒸気機関車の試作と挫折
(1)世界初の蒸気機関車「ペナダレン号」の賭け
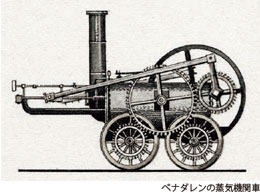 ホムフレイの支援で蒸気機関車を開発していた1804年に面白い賭けがおこなわれた。「蒸気機関車推進派ホムフレイ」対「蒸気機関車反対派クローシェイ」の対決である。
ホムフレイの支援で蒸気機関車を開発していた1804年に面白い賭けがおこなわれた。「蒸気機関車推進派ホムフレイ」対「蒸気機関車反対派クローシェイ」の対決である。
蒸気機関車を馬鹿にするクローシェイが「10tの鉄を載せて蒸気機関車がペナダレンからアベルカノンの約16㎞の距離を往復できるか」という賭けをホムフレイに仕掛ける。ホムフレイの命をうけたトレヴィシックは挑戦を受けて立った。現在の価値に換算すると10万ポンド近い大金を賭けた「ペナダレン号」の走行は1804年に実施され、大勢の群衆が集まった。自信満々のトレヴィシックは10tの鉄に加えて70人の人間をペナダレン号の5両の車両に乗せて最高時速8㎞で走行した。蒸気機関車がレールの上を走った世界初の記録となったのだが、当時の脆い鋳鉄のレールではこの重量に耐え切れなかった。途中で破損して走行不能となり、帰路は馬の助けを借りて戻る有様であった。しかし、この走行を評価したウィラム炭鉱の経営者クリストファー・ブラケットから第2号の蒸気機関車の製造依頼を受けることになる。
(2)「catch-me-who-can号」の公開と失敗

 トレヴィシックは度重なる失敗に挫けることなく、動力伝達を歯車式から連結棒で駆動するロッド式に換えた第3号の蒸気機関車を1808年に製造した。そして広告と娯楽を兼ねた一般公開を思い付き、新聞に「蒸気機関車と競争」の見出しで広告を打った。「catch-me-who-can」(捕まえられるものなら、捕まえてごらん)という機知にとんだ機関車の名前はイベントの資金スポンサーであるギルバートの妹フィリッパが付けた。ロンドンで鋳鉄製のレールを円形に敷いて周りを高い塀で囲み、入場料1シリングで約2カ月間公開した。最高時速は19㎞に達し、蒸気機関車が馬より速いことは実際に立証できたのだが、相変わらず事故や爆発を怖がって蒸気機関車に乗る人はほとんどいなかった。ここでもまた鋳鉄製の脆いレールの破損によって蒸気機関車の脱線や転覆が起きて、たびたび走行が中断したらしい。
トレヴィシックは度重なる失敗に挫けることなく、動力伝達を歯車式から連結棒で駆動するロッド式に換えた第3号の蒸気機関車を1808年に製造した。そして広告と娯楽を兼ねた一般公開を思い付き、新聞に「蒸気機関車と競争」の見出しで広告を打った。「catch-me-who-can」(捕まえられるものなら、捕まえてごらん)という機知にとんだ機関車の名前はイベントの資金スポンサーであるギルバートの妹フィリッパが付けた。ロンドンで鋳鉄製のレールを円形に敷いて周りを高い塀で囲み、入場料1シリングで約2カ月間公開した。最高時速は19㎞に達し、蒸気機関車が馬より速いことは実際に立証できたのだが、相変わらず事故や爆発を怖がって蒸気機関車に乗る人はほとんどいなかった。ここでもまた鋳鉄製の脆いレールの破損によって蒸気機関車の脱線や転覆が起きて、たびたび走行が中断したらしい。
(3)その後のトレヴィシックの人生
この一般公開が商業的に大赤字になった影響なのか、トレヴィシックはこれ以降蒸気機関車の開発への関心をなくしてしまう。腸チフスに罹ったことや、引退したワットからの嫌がらせに嫌気が差したことなどが原因とも言われている。その後、彼は1816年に単身で南米に行き一獲千金を狙って銀鉱山の開発に賭けるのだが失敗し、1827年に無一文となって英国に戻り、1833年に貧困のまま息を引き取った。
彼の失敗の原因は回転のムラや歯車の破損など蒸気機関車本体の問題もあったが、蒸気機関車の重量に耐え切れない当時の鋳鉄製レールの脆さが大きく影響した。レールの問題が解決されるのは1820年代であり、その頃にようやく頑丈な錬鉄製レールが登場するのである。
またトレヴィシックの蒸気機関車は当時として優れたものであったが、野心家でマイペースな彼には事業を成功するために周囲の人々の協力を取りまとめていくマネージメント能力が足りなかったようだ。
(4)トレヴィシックの孫たち
余談だが、トレヴィシックの孫二人がお雇い外国人として明治期の日本の鉄道発展に貢献している。孫二人が技術者として別々に来日し、蒸気機関車の製造に携わった。ともに10年以上滞在し、日本人の妻を迎えている。一人は国産初の蒸気機関車AE形の製造に、もう一人は信越本線の横川~軽井沢間のアプト式鉄道(急勾配の線路を登り昇りするための鉄道)の導入に携わった。
6.英国鉄道の父 スティーヴンソンの登場
英国では、トレヴィシックが開発を断念した後も蒸気機関車の開発は進み、蒸気機関車による鉄道網が発展するとそれまで隆盛を極めた馬車鉄道や運河が時代遅れとなっていく。
ジョージ・スティーヴンソン(1781~1848)は1830年に蒸気機関車「ロケット号」を使用した世界初の公共交通「リヴァプール・マンチェスター鉄道」を開通させたことで有名であるが、技術者としては先行技術を集大成しただけで独創性はあまりなかったと言われる。しかし、彼の息子ロバートをはじめとした優れた技術者仲間の協力、地元の賛同、幅広い資金調達によって鉄道を作り上げた。スティーヴンソンはマネージメント能力に秀でていたのだろう。発想力豊かな技術者であったがマネージメント能力が足りなかったトレヴィシックとは対照的だ。
次回はそのスティーヴンソンの生い立ちや鉄道会社設立までの苦闘を辿る。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第5回]~2020年6月号
電気料金は消費した電力ワットによって計算されるが、このワットという単位は「蒸気機関の父」ジェームズ・ワットにちなんで1889年の英国学術協会第二回総会で名付けられたそうだ。1ワットとは毎秒1ジュールに等しいエネルギーを生じさせる仕事率であり、1ジュールとは100gのモノを1m持ち上げる位置エネルギーに相当する。100gはちょうどMサイズのミカン1個だと考えるとよい。ワットは元々電力だけでなくエネルギー全般に使用できる単位なのである。
自動車のパワーを表す「馬力」も仕事率の単位であり、英国では1馬力=745.7ワットと定義される。1馬力は馬1頭が継続的に発揮できる力を示したものだが、この馬力を実測し制定したのもジェームズ・ワットである。ワットは蒸気機関の性能を同等の仕事量をこなす馬の数に換算して表示することを思いつくと動力測定装置を作り、馬に1分間作業をさせて仕事率を計測した。重さ175ポンド(約79㎏)の荷物を馬に引かせたところ1分間で188フィート(約57m)移動したので、ワットはその仕事量を1馬力と定義した。
ワットにはさまざまな発明があるが、最大の功労は、従来の蒸気機関を改良し効率を大幅に向上させたことだ。その蒸気機関が工場の機械や鉄道・船などの輸送手段に利用され、近代産業都市形成の原動力となった。
今回は、そこに至るまでの蒸気機関の発展の歴史を辿る。
1.炭鉱の強敵、水没対策
1700年の英国では石炭業を主とした鉱業が中心産業であり、石炭の生産量ではヨーロッパの80%を産出し、生産額では59%を占めていた。英国には多数の炭鉱があり、炭鉱では坑内での出水が頭の痛い問題であった。鉱山の坑道や採掘箇所が湧出する地下水で水没し、閉山に至ったケースが多くあった。表層の石炭が掘り尽され更に深く掘り進むと、坑道が帯水層に達するため、四六時中湧出してくる地下水などの坑内水を坑道から汲みだすことが必要となる。投資している炭鉱主にとっては、坑内水の排水をいかに上手に処理するかが最大の関心事であり、褒賞金を出してまで必死に排水の新技術を求めていた。
当時の対応策として利用できる動力は風車、水車、馬があったが、英国の天候条件では風車の利用は無理であった。水車も炭鉱の近くに恰好な川が必要であり、また季節によって変動する水量のため安定稼働が難しいという欠点があった。馬を動力とした巻上げ機の利用はとにかく費用が嵩み、ある鉱山では揚水のために50頭の馬が使われたという記録もある。しかも馬の巻上げ機は作業スペースが狭いと設置できず、深く掘り下げた鉱山には巻上げ機が十分機能しなかった。こうした状況の中で英国の石炭業における鉱山の排水のために、豊富な石炭を利用した蒸気機関が研究開発されることになる。
2.大気圧の利用 トマス・セイヴァリ
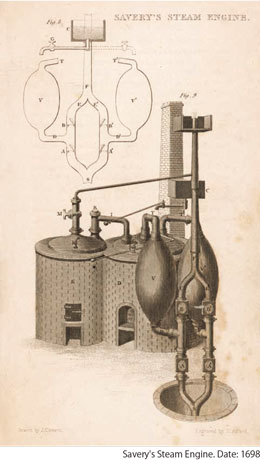 蒸気機関とは蒸気の圧力を利用して動力を得る機関であり、一般的にはボイラーからシリンダー内に高圧蒸気を導いて、その膨張によってピストンを動かすのだが、当初の発明では若干異なる。
蒸気機関とは蒸気の圧力を利用して動力を得る機関であり、一般的にはボイラーからシリンダー内に高圧蒸気を導いて、その膨張によってピストンを動かすのだが、当初の発明では若干異なる。
1698年に蒸気の技術を初めて実用化し、特許をとったのが、イングランド南西部生まれの海軍軍人トマス・セイヴァリ(1650~1715)である。炭鉱から排水するための最初の蒸気機関として有効期限1733年までの特許を得た。
セイヴァリの機関では蒸気の強い圧力を直接利用するのではなく、あくまで真空状態を作り出すために蒸気を使った。真空状態とは通常の大気圧より低い気圧で満たされた空間であるが、真空状態と大気圧との圧力差をこの機関の動力源としている。この圧力差の力を示す身近な例としては「容器の中に熱湯を注いで蓋で密閉すると、冷却後容器の中は真空となり、蓋が吸い付いて取れなくなる」現象がある。大気圧は地球を取り巻く空気の層の重さであり、海面上での標準大気圧である1013hPaでは1㎡あたり約10tの空気の重さがある。大気圧の存在とその大きさを示すものとして、1655年にドイツのマクデブルグで実施された半球の実験が有名だ。その実験は、ぴったりと合わせた2つの直径約60cm半球の銅製容器を真空ポンプで球の中を真空状態にしたうえで、この2つの容器を引き離すものだ。左右各8頭の馬で引っ張って、ようやく容器を引き離せたらしい。
セイヴァリの機関はボイラー付きサイホンのようなものであったが、炭鉱での揚水用の蒸気機関を試作して一応作動させた。しかし熱効率が悪いうえに取り扱いが複雑で故障が続出したため炭鉱ではほとんど利用されなかった。そのうえ、この機関には安全弁もなかったので金属同士の継ぎ目が蒸気圧に耐え切れずしばしば破裂して、ボイラーが爆発するような危険な代物だった。結局、セイヴァリの機関は鉱山には普及せず、ケンジントン宮やテムズ川近くの給水塔の揚水ポンプに使われただけで1705年に工房を閉じた。
3.圧力釜の活用 ドニ・パパン
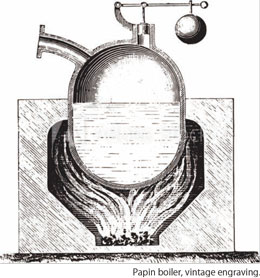 同時期にフランス出身のドニ・パパン(1647~1712)も同様な実験や試作をおこなっていた。
同時期にフランス出身のドニ・パパン(1647~1712)も同様な実験や試作をおこなっていた。
パパンは医者だったが、力学への興味が断ち切れず、ベルサイユ宮殿で技師として風車を管理していた。1671年にその宮殿でパパンはオランダ人で数学と天文学で有名だったクリスティアーン・ホイヘンスと出会い、仕事振りを評価されて助手に採用される。そして、ホイヘンスから火薬を動力とした機関の開発を命じられるのであった。
しかし、新教徒のパパンにとっては、カトリック教のフランスに住むことが不安だったので、1675年にホイヘンスの推薦状をもってロンドンに渡った。ロンドンで研究を続ける中でパパンは1679年に固い骨も柔らかくなる調理用の蒸気圧力釜を発明・実用化した。その際に、調理器の爆発を防ぐために発明した自動調節安全弁が蒸気圧の利用に繋がっていく。パパンは引き続きホイヘンスの命令にしたがって真空状態を作るために火薬の利用を研究していたが、実用化は困難であった。そこでパパンは「水が蒸気に変わる際、体積が千倍以上になる」現象に着目し、蒸気が凝結する際に発生する真空を動力機関に利用することを思いつく。しかし、蒸気の圧力を直接利用するというパパンの革新的な発想を支援してくれる資金提供者はなく、模型を作るお金にも事欠いた。また、当時は高温高圧の蒸気に耐えるような板金技術もないため、機関がバラバラに吹き飛ぶこともあり、実用化に手間取っていた。
そこへパパンにとって衝撃的な出来事が起こる。パパンに先んじて1698年にセイヴァリが揚水する蒸気機関の特許を取得したのだ。しかし、1704年にパパンはセイヴァリの機関について「ピストンなしで蒸気を利用するので熱のロスが大きく、蒸気ボイラーを保護する安全弁もない」と指摘している。パパンはイングランドの王立協会から支援を得るためにセイヴァリの改良案を含めさまざまな発明の計画書を提出するが、ことごとく無視され1712年に失意のまま亡くなった。一方、セイヴァリは「パパンの機関はシリンダーとピストンの摩擦が過剰に高まるので作動しない」と容赦ない批判をした。そういうセイヴァリの機関も前述の通り、ほとんど使い物にならなかった。双方とも設計上の欠陥があったのである。
4.世界最初の実用熱機関 ニューコメン
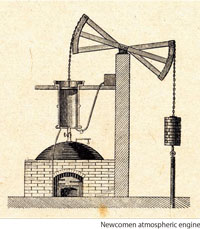 前記の二人とほぼ同時期に蒸気機関に着目して、1700年頃から実験を開始したトマス・ニューコメン(1664~1729)が1712年に商業目的で本格的な機関をバーミンガム近郊の炭鉱で初めて建造した。そして、この機関によってイングランド中西部の炭鉱業が息を吹き返すことになる。ニューコメンはイングランド南西部の没落貴族の末裔で、金物商を営んでいたのだが、馬で水を汲み上げるのに大変な費用が掛かることを知り、蒸気機関の開発に着手した。ニューコメンはセイヴァリやパパンたち先人たちの技術の長所を機関に取り入れたうえで、巨大なボイラーとシリンダーを別個に設置した。
前記の二人とほぼ同時期に蒸気機関に着目して、1700年頃から実験を開始したトマス・ニューコメン(1664~1729)が1712年に商業目的で本格的な機関をバーミンガム近郊の炭鉱で初めて建造した。そして、この機関によってイングランド中西部の炭鉱業が息を吹き返すことになる。ニューコメンはイングランド南西部の没落貴族の末裔で、金物商を営んでいたのだが、馬で水を汲み上げるのに大変な費用が掛かることを知り、蒸気機関の開発に着手した。ニューコメンはセイヴァリやパパンたち先人たちの技術の長所を機関に取り入れたうえで、巨大なボイラーとシリンダーを別個に設置した。
当初の機関はシリンダーの外側から水を掛けて冷却する仕組みであったが、試作実験中の事故が怪我の功名となって直接冷水をシリンダー内に注入させる方法を発見する。この仕組みにより、費用は馬による水の汲み出しの1/6となり、効率性が格段に良くなった。しかも以前のものに比較して故障も少なく、安心して使えるようになる。ニューコメンの機関はたちまち評判となり、ヨーロッパ中の各地の鉱山で利用され、改良型は20世紀初めまで実際に使われたらしい。しかし、揚水用の用途以外には拡がらなかった。また、ニューコメンにとって不運だったのは、セイヴァリの特許の有効期限が1733年だったので、セイヴァリと提携するしかなかったことだ。
5.分離凝縮器と回転運動式蒸気機関 ワット
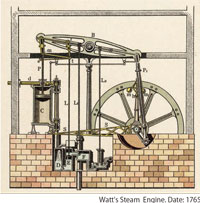 汎用的な蒸気機関の登場は18世紀後半となる。
汎用的な蒸気機関の登場は18世紀後半となる。
ジェームズ・ワット(1736~1819)はスコットランドの船大工の家に生まれた。計測機器の製造技術をロンドンで学んだあと、グラスゴー大学で科学機器製造業者として工房を開設し、1763年に大学にあったニューコメンの蒸気機関の修理を担当する。修理の過程でこの機関のさまざまな欠陥に気付き、特に効率の悪さに驚く。ワットはブラック教授のアドバイスから燃料のロスの原因は「一つのシリンダーの中で熱い蒸気と冷たい水の双方を扱う」ことだと突き止めて、解決策として冷却器を別に設置することを考案した。排気された蒸気の冷却を専門とする冷却器を置くことで、シリンダーは高温蒸気扱い専用となり、機関の効率性が格段に向上した。この冷却器がワットの名前を不朽のものにした分離凝縮器である。1769年に特許を取得して蒸気機関の実地製作に取り掛かるが、技術水準が低く、なかなか実効が上がらなかった。そのうえ資金援助者である英国の工業家ローバックが1770年に破産して開発の一時中断を余儀なくされたが、バーミンガムの企業家ボールトンの積極的な援助を新たに得たことで開発に専念して技術的問題を解消する。
また、有効期限の迫っていたワットの特許が議会の承認を得て1800年までの25年間延長されたことを機に、ワットとボールトンは1775年に蒸気機関の共同事業を始める。効率性が高くても高価で維持管理が面倒なワットの機関は当初売れなかった。それに対してニューコメンの揚水用の蒸気機関は安価で取扱いが簡単なので人気があり、また炭鉱の利用では価値のない炭屑を燃料に使えるので燃料の効率を気に掛ける必要がなかった。
そこでワットはコーンウォール地方の鉱山に狙いをつけて売り込みを掛けたところ、1776年に自身が設計した揚水用の蒸気機関で高評価を得る。この地方の鉱山で採用された理由は、銅や錫の鉱山なので炭屑がなく、燃料の石炭消費量を節減するニーズが高かったことと、深く掘られた鉱山なのでニューコメンの機関では揚水する能力が不足していたからだ。ワットの機関の石炭消費はニューコメンのほぼ1/4だったので、コーンウォール地方では順次ワットの揚水機に切り替えられて、1777~1801年のあいだに49台が設置された。
その頃、ワットはボールトンから回転運動の蒸気機関の開発を要請されて、1781年に上下運動を回転運動に転換する仕組みの特許を取得した。回転運動式蒸気機関は強い糸を紡ぐ必要のある綿工業で需要が大きく、1785年に初めて綿工場に機械の動力用として設置された。その後、大量生産を可能にしたミュール紡績機への導入でワットの機関は一気に揚水以外に販路を拡大していく。1800年の特許期限までにワットの蒸気機関は国内のさまざまな業界向けに約450台製造されたらしい。
こうして、回転運動式蒸気機関に至るまでの経緯を見ると、偉人が画期的な発明をする伝記のような話は実際には存在せず、さまざまな人々の努力が繋がって実用化されていくことが分かる。また蒸気機関が英国で発明されたのは、豊富な石炭と主要産業である鉱山業の存在が大きく関係している。
次回は英国鉄道の父スティーヴンソンを中心に蒸気機関が輸送分野に広まっていく過程を辿る。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第4回]~2020年5月号
英国産業革命の全盛期であるビクトリア朝(1837~1901年)時代にロンドンは冬に濃い霧が発生することから「霧の都」と呼ばれた。
当時、文部省から国費留学生として英国に派遣されていた明治の文豪、夏目漱石はロンドンでの出来事を次のように日記に記している。
「倫敦の街を散歩して試みに痰を吐きて見よ。真っ黒なる塊の出るに驚くべし。何百万の市民はこの煤煙とこの塵埃を吸収して毎日彼らの肺臓を染めつつあるなり。我ながら鼻をかみ、痰をするときは気のひけるほど気味悪きなり」(1901.1.4)
ロンドンの霧の正体は暖炉や蒸気機関車などの石炭の煙が濃霧と混じりあったものであった。痰が真っ黒な塊になるほど当時の大気汚染は酷かったのだ。1905年にはこの黒い霧を通常の白い霧と区別するために、smokeとfogを合成してsmog(スモッグ)と呼ぶ申し合わせをしている。
この英国の大気汚染は、産業革命の工業化によって初めて発生したのではなく、実はそれ以前からすでに英国に発生していた。薪や木炭のもとになる森林が早くに枯渇した英国は、安価な石炭を燃料として利用していたのである(木炭とは薪から水分と不純物を取り除いて炭素含有量を高くしたもの)。
石炭を原料とする蒸気機関の歴史を辿る前に、今回は英国で大量の石炭を利用するに至った歴史を探る。
1.ローマ時代における豊かな森林の消失
英国は、紀元前1世紀半ばから紀元4世紀にわたってローマ帝国の植民地であった。当時は国土の大半が森林に覆われていたので、ローマ人が森を切り開いて農地にするとともに豊富な鉄鉱石と樹木を利用して鉄の生産拠点にもなっていた。樹木が伐採されて、英国南部の森林はかなり減少したのだが、ローマ帝国の滅亡後には森林はある程度蘇生する。しかし、後進国であった英国の主要産物は木材であり、14世紀には木材の輸出が隆盛となって樹木の減少はとまらなかった。
2.国内産業の発達で森林枯渇
16世紀に入ると、英国では国内産業の発達や木造船の建造などで木材をさらに大量に消費し、森林枯渇を加速させた。
(1)製鉄をはじめとした国内産業の発達
鉄鉱石が国内に豊富にありながら、16世紀初めの英国の簡単な炉では大砲などの兵器製造は技術的に困難だった。他のヨーロッパ諸国よりも英国は産業面で立ち遅れていたのだ。
その後、ヘンリー8世(在位1509〜47)は自身の離婚問題から英国にイングランド国教会を独自に成立させたために、ローマ・カトリック教会との関係が悪くなった。そのことで外国からの侵略を警戒して早急に大砲や鉄砲などの鉄の兵器を国内生産する必要が生じた。1543年には欧州大陸から強力な燃焼力をもつ高炉を導入して、英国は鉄の鋳造大砲の製作に成功した。生産拠点はイングランド南部のサセックスにあるウィールド地方の森の中であり、鉄鉱石の鉱脈と燃料に最適なナラの木がふんだんにあった。新たに導入した高炉法のおかげで鉄の大量生産が可能となったのだが、同時に大量に木材燃料を消費するようになった。
また、エリザベス1世(在位1558〜1603)時代には財政赤字対策として、国内産業育成に力を入れたので、銅の精錬、塩、ガラス、鉛といった産業が発達するのだが、これらはどれも木材燃料を大量に必要とした。
(2)木造船の建造ラッシュ
海洋大国スペインとの対立で多くの木造艦船が建造された。ちなみに全幅17m、全長61mの平均的な大きさの戦列艦1隻の建造には約2500本もの巨大ナラを伐採したらしい。また、100t以上の大型の商船でも1577年の135隻から1592年の177隻に増えたという。これだけ建造されて、木材が伐採されれば森林が枯渇していくのも頷ける。しかも、樹木が切られた後の土地はそのまま牧草地や耕地にされて、あまり植樹されなかったようだ。
16世紀頃には、英国では森林枯渇が深刻化して、もはや熱源を樹木に依存できる状態ではなくなった。基幹産業となった鉄の製造においても、17世紀後半から18世紀にかけて深刻な木炭不足の影響で、鉄の製造が停滞した。
3.一般家庭も石炭の利用へ
英国では、昔から鍛冶屋、石鹸職人、石灰職人、製塩業者などが、薪の代わりに豊富で安価な石炭を利用していた。しかし、国内で入手可能なミッドランド産の石炭は鼻を突く煙と硫黄のような悪臭で忌み嫌われていた。そのため、1306年に王室布告で職人が炉で石炭を焚くことを禁止したりもするのだが、森林枯渇で状況は変化する。
一方、一般家庭では暖炉に薪を使用していたのだが、薪の値段が上がって石炭の利用を強いられることになる。薪の価格上昇には前述の森林枯渇の要因だけでなく、人口が急増したことも影響している。イングランド全体では人口が1500年〜1600年で325万人から407万人に急増しており、人口増加の分だけ木材燃料の需要が増加したのだ。
その結果、15世紀には石炭と薪は熱量エネルギーで見ると、ほぼ同じ価格であったものが、16世紀終わりには薪の価格が石炭価格の2倍に上昇して、一般家庭には高嶺の花となった。やむなく、一般家庭でも値段の高い薪を諦めて、石炭用の暖炉と煙突を設置して安価な石炭を燃やし始めるようになったのである。
英国の石炭の年間生産量を見てみると、1540年は約20万tであったものが、1650年には約150万t、1700年には約300万tと増加した。
17世紀後半における英国の石炭生産量は全世界の約85%を占めたらしい。産業革命への本格突入前にすでに石炭の生産・消費が高水準にあり、その頃には石炭の煤煙で大気汚染はかなり進んでいたはずである。
4.コークスの発明で大気汚染はさらに悪化へ
製鉄を除く諸工業では安価な石炭の利用が増加するのだが、製鉄では依然として高価な木炭を利用していた。それは、石炭に含まれる硫黄などの不純物が鉄を変質させるという問題があったからだ。その問題を解決したのが1709年にエイブラハム・ダービーが考案したコークス高炉法である。
石炭を高温乾留(蒸し焼き)して生成したコークスを高炉の燃料とすることで、硫黄などの不純物を取り除くことに成功した。これで製鉄の最終工程の一部を除き石炭だけで対応可能となった。さらには1783年にヘンリー・コートのパドル法により、製鉄の全工程が石炭で対応できるようになり、同時に鉄の大量生産も可能になる。
英国における鉄の生産高は1720年〜1788年の間で1万7350tから6万8300tに急増した。熱源ベースでは1720年の時点では100%木炭であったものが、1788年には約8割が石炭由来のコークスで生産されるようになった。
こうした石炭需要の増加によって、1700年頃には一人当たりの石炭使用量が年0.5t程度だったものが、産業革命が始まった1800年には一人当たりの石炭使用量は1tに達し、夏目漱石が留学した1900年には年6tにも達したらしい。 石炭のおかげで英国の森林枯渇は免れたのだが、夏目漱石が嘆くような悲惨な大気汚染はさらに悪化の一途を辿るのであった。
5.蒸気機関による石炭利用
さらに石炭需要増加に拍車をかけたのが蒸気機関である。18世紀後半に、ジェームズ・ワットの回転式蒸気機関が発明されたことで、英国は石炭を燃料とする蒸気機関と製鉄を原動力に19世紀にかけて本格的に産業革命に突入するのである。
次回はその蒸気機関の歴史について触れたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第3回]~2020年3・4合併号
第4次産業革命の最中にある現在、AI(人工知能)脅威論がニュースの話題でよく取り上げられる。このまま技術革新が進むと日本でも労働人口の49%がAIとロボットに仕事を奪われてしまうとの予測もある。今後どのようにAIとの共生を図っていくかが私たちの課題だが、英国の第一次産業革命においても同様な問題が発生していた。繊維工業、特に綿工業における技術革新によって飛躍的に機械の生産能力が高まった結果、深刻な失業問題が発生したのだ。非熟練工による大量生産が可能となったことで、零細な家内制工業は廃れて機械制工業が主流となると同時に、当時の熟練工や職工の置かれた状況も激変した。今回は産業革命期の繊維機械の変遷を辿る。
1.毛織物から綿織物へ−キャラコの大流行−
15〜16世紀は国内の良質な羊毛により、毛織物工業は英国の国民的産業であった。当時は、家族労働による家内制工業が殆どであり、妻や子供が小さな糸車を使って糸を紡いで、夫が布を織っていた。
17世紀に入るとインドの良質な綿花や綿布がイギリス東インド会社を通じて英国へ輸入された。輸入された綿布のうち、インド産の平織り綿布は輸出港の名前カリカットが訛ってキャラコと呼ばれた。キャラコは値段が安く、肌触り、吸湿性に優れ、洗濯も簡単であったため爆発的に流行した。それが面白くない毛織物業界は議会に働きかけて、1700年にはキャラコ輸入禁止法、1720年にはキャラコ使用禁止法を制定させた。入手困難となった綿織物だが、その人気はさらに過熱化して需要に供給が追い付かない状況であった。その需要に応えるためには、国内で綿織物を増産する新たな技術革新が必要となった。
2.飛び杼ひ−手織りの織布過程の高速化−
1733年にまず発明されたのが英国人ジョン・ケイの「飛び杼」である。杼とは緯糸を巻いて収めるための容器のことだが、その杼を改良したものが飛び杼だ。この飛び杼は当初毛織物の生産に利用されたが、のちに綿織物の生産にも使われた。
手織り機では経糸の間に杼(シャトル)を通して緯糸を入れる操作をするが、広幅の布の場合には二人の職工が左右で杼を受け渡すなど手間がかかった。この飛び杼を使うと、職工が織機の上部の紐を引くことで左右の送出器によって打ち出された杼が杼道上を往復する仕組みになっており、一人で広幅の布を短時間で織り上げることが可能となった。手動式の極めて単純な仕組みだが、この発明によって生産性は従来の2〜4倍になった。綿布の生産能力が上がったことで、原料となる綿糸が不足となり、今度は紡績の生産性向上が必要となった。
3.紡績機における技術革新
紡績の技術革新として、まず登場したのが手織り工出身の英国人ハーグリーヴスによって1764年頃に発明された「ジェニー紡績機」であった。これまで糸を紡ぐには綿花から繊維を引っ張り出して、綿棒に巻き付かせる手作業を1本ずつおこなっており、手間がかかっていたが、この手動式機械の登場によって6本以上を同時に紡ぐことができるようになった。しかし、手動で紡ぐ糸は細くて切れやすかったので、緯糸に利用するしかなく、強度が必要な経糸には引き続き手紡車が使用された。このジェニー紡績機は小型だったので既存の家内制工業にも向いており、急速に普及した。
次に経糸の問題を解決したのが「水力紡績機」だ。1771年に英国人床屋でかつら製造業者のアークライトによって発明され、ジェニー紡績機に比較すると技術的にかなりの進化が見られた。
まずは経糸用の丈夫な糸が製造できるようになった。加えて、これまで馬であった動力源を水車による水力に替えたことや、糸の撚りと巻き取りを同時におこない連続作業を可能としたことによって、工場での大量生産が可能となった。しかも、職工の訓練もあまり必要でなくなった。一方で難点は、太い糸しか製造できないことであった。また、水力紡績には大掛かりな設備を要するので、それらを設置する工場が必要であり、しかも水力を利用するには、工場を町から離れた急勾配の渓谷などに設置する必要があった。アークライトはダーウェント川沿いのクロムフォード工場(イングランド中部ダービシャ州)に水力紡績機を設置したのだが、実際には季節による水量の変化に苦労したようだ このダーウェント川の工場群は産業革命初期のものとして2001年に世界遺産に指定された。
4.ミュール紡績機と力織機−大量生産へ−
1779年にはジェニー紡績機と水力紡績機の長所を掛け合わせた「ミュール紡績機」が7年間におよぶ試作を経て英国人技術者クロンプトンによって発明された。このミュールの名称は英語のmuleすなわち雄ロバと雌馬との雑種であるラバに由来している。丈夫で細く、しかも安定した太さの糸が製造可能となったので、高級で人気の高い薄地の綿織物モスリン用の糸として使用されるようになる。 さらに1789年には蒸気機関を利用した改良型が完成した。これらの発明によって綿糸の生産が急激に増加して綿糸の供給が過剰となり、今度は逆に、綿織物の織るスピードが間に合わなくなった。
そこで新たな織機として登場したのが、英国人牧師カートライトによって発明された「力織機」だ。1785年に馬を動力源として発明した力織機を1787年に蒸気機関利用に改良したことで生産能力が3.5倍になったと言われる。
このように一つの技術革新による需給関係の変化が、新たなる技術革新を次々に引き起こした。そして1802年から1803年にかけて、綿織物は毛織物から英国輸出品ナンバーワンの地位を奪った。
5.ミュール革命の意義
これまで述べた機械のうち、特にミュール紡績機の登場は、強くて細い良質な糸の生産を飛躍的に増大させて、インド製品の独占状態を打破したという意味で歴史的なインパクトが大きい。また、動力源が水力のものは渓谷など水を利用できる場所に工場を設置する必要があったが、蒸気機関を利用することで平地上の大都市に大工場を設置できるようになった。都市では、原料、石炭燃料、労働力などの調達が容易であったので、次々と工場が増えて綿織物の生産量が急増した。このことは1750年から1790年の間に綿花の輸入量が276万トンから3074万トンと11倍にも増加したことからも明らかである。
そして、1820年代にはリチャード・ロバーツによる「自動ミュール紡績機」が発明される。これまでは、運転調整に熟練した成人男子一人が付きっ切りで作業するため同時に運転できるのは300錘足らずであったが、この自動化によって成人一人と子ども2〜3人で1600錘もの運転が可能となった。しかも、人間の作業は糸継ぎと機械トラブルの監視のみとなったので、紡績工場のさらなる大規模化が可能となった。
6.職工の反発
一方で、技術革新を生んだ発明家たちの余生は決して人が羨むようなものとはならなかった。
飛び杼を発明したジョン・ケイは1733年に特許を取得したが、この発明によって不要となった熟練工に恨みを買い、暴漢に襲われ、仕事場も壊された。その後、ケイはフランスに逃亡するが、織元が特許料を払わず生活的に困窮するなど、不遇な人生を送ったらしい。ジェニー紡績機を発明したハーグリーヴスも同じく職工に自宅を襲撃され、機械を壊されたのでノティンガムに引っ越した。1770年にハーグリーヴスはジェニー紡績機の特許を取得するのだが、結果的に特許料を得ることはできなかった。水力紡績機を発明したアークライトは、工場経営者、資本家として大成功を収めたが、1779年に機械化に反対する暴動でバークエーカーの新工場が破壊された。1810〜1817年頃にイングランド中部北部の紡績、織布業で起きた機械打ち壊し事件はラッダイト運動として歴史的に有名であるが、その運動の主体となったのは機械導入による失業や共同体の解体の脅威に晒された手工業者や労働者であった。
エンゲルスの「イギリスにおける労働者階級の状態」(1845年刊)は産業革命期のルポルタージュの傑作であるが、そこには新しい機械が導入されるたびに労働者が多数失業していく状況が克明に描かれている。この本の中に「妻が紡績工場で働き、家で夫が家事をする主夫となっている」事例が挙げられていた。働く男性たちを取り巻く環境が大きく変わったのである。繊維機械の自動化によって熟練工は不要となり、力仕事もなくなった。残ったのは切れた糸を紡ぐ仕事だけである。そうなると指先の柔軟性があり、骨格の小さい女性や子どもの方が工場の労働者に向いている。しかも女性や子どものほうが低賃金なので、男性を雇う必要がなくなったのだ。機械の導入により何年もの修業期間で培った技術が台無しとなった男性たちの失望や落胆ぶりは凄まじいものだったであろう。彼らは技能への誇りや社会的地位を一瞬にして喪失した。その怒りによる機械の取壊運動は苛烈を極めたが、結果的に機械化の流れは止まらなかった。
繊維機械の発明による技術革新は、仕事だけでなく職人の誇りを奪い、彼らの生活様式、家族関係や価値観を劇的に変えた。そして私たちの現代においても、まさにAIによる技術革命が起きている。AIが雇用におよぼす影響については悲観的な論調が多いが、大事なことはAIに翻弄されず、AIをあくまで自分をサポートする手段と捉えたうえで、その活用をしっかりと考えていくことであろう。次回は蒸気機関について触れたい。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第2回]~2020年2月号
気候変動対策の必要性が叫ばれる中で、2015年に合意されたパリ協定の実施を目指す国際会議COP25が昨年12月にスペインで開催された。この「パリ協定」の中に「産業革命」の4文字が次のように含まれている。「産業革命前からの世界の平均気温上昇を2度未満に抑えるために2020年以降、具体的に温室効果ガスの排出を削減することを義務付けされる」
「産業革命前」に具体的な年代特定はないが、温室効果ガスの排出という意味では英国で石炭利用の蒸気機関が始まった1800年ごろが想定されるだろう。産業革命の時代は気候変動問題においても重要な起点となるのだ。
その産業革命を推進した原動力の一つが当時の英国での急激な人口増加であり、そこには農業の革命的な変化が大きく関係している。
1.英国での急激な人口増加
産業革命時の1800年ごろ、英国では人口が急増していた。どのくらい増加したかは、英国全体の統計がないので、英国の約半分の面積を占めるイングランドのケースで説明する。1981年にケンブリッジ学派リグリーとスコフィールドによって、全部で404の教会の教区から抽出した洗礼数と埋葬数をベースに近代以前のイングランド人口動態の復元が試みられた。そこから人口の推移は1701年500万人⇒1800年860万人⇒1851年1681万人と、急激な増加であったことがわかる。1800年から約半世紀でほぼ倍増したのである。17世紀までは飢饉、内戦などの要因に加え生活環境が極めて不衛生で、ペストなど伝染病がたびたび流行し、死亡率が高く人口増加も緩やかだった。ところが、19世紀に入ると労働者階級の生活水準の向上や、衛生改革により徐々に住環境が改善、平均寿命が劇的に伸びた。さらに医療技術の発達により死亡率が低下したことや、女性が早く結婚し生まれる子の数が増えたことも人口増加の要因と言われる。そうした急激な人口増加に対して、英国の経済学者マルサスが警鐘を鳴らした。
1798年に刊行されたマルサスの「人口論」に「人口は制限されなければ幾何級数的に増加するが、生活資源は算術級数的にしか増加しないので、生活資源は必ず不足する」という有名な命題がある。人口増加はそれを養う土地の能力をいつか必ず追い越し、そうなれば悲惨な状況と大量死が待っていると予想したのである。この命題のメカニズムを一般にマルサスの罠と呼ぶ。
2.ノーフォーク農法
人口が急激に増加する以前は三圃制輪作農法が主流であった。これは、連作障害を避けるために秋播きの小麦、春播きの大麦および休閑を組み合わせたものであり、12世紀ごろから始まった。この農法の下では、村落全体で共同して耕作が行われており、この形態を開放耕地制度と呼ぶ。この、三圃制では生産できる穀物の量に限界があり、農民は冬期間の家畜用飼料も確保できなかった。やむなく秋には貴重な羊や牛を食肉用に殺していた。
ところが、1800年代の急激な人口増加に加え、フランスや米国との戦争で政府買付分として食料を確保する必要が生じたので、早急に農業の生産力を大幅に向上させ、食料の増産を図らねばならなかった。そこで生産性の高い農法としてノーフォーク農法が英国の各地で導入された。ノーフォーク農法とは17世紀後半からイングランド東部ノーフォーク州で始まった大規模農法である。同一耕地でカブ⇒大麦⇒クローバー⇒小麦を4年周期で輪作する農法であり、休墾地を置かない分だけ生産性が高い。クローバーやカブはあまり土地の養分を吸わずに成長するのに加えて、それらを家畜の越冬飼料に利用できるので冬期の飼育も可能となった。家畜の生育期間が延びたことで体が大きく成長し、家畜の平均重量は18世紀の間に倍以上になったという。さらに家畜の糞尿が肥料となり穀物の生産量も増大した。またカブは深く根を張ることで土を耕す効果があり、マメ科のクローバーは根にバクテリアの一種である根粒菌がつき、空気中の窒素を地中に窒素化合物として固定するので、土地が衰えるのを防いでくれるのだ。生産者としては良いこと尽くめなのである。17世紀の初めと比較すると、こうした農業の発達によって収穫量は約1.7倍に向上したといわれる。農機具も木製から鉄製へ、またさまざまな改良も加えられ生産性が向上し、結果として鉄の生産にも結び付いた。
3.農業革命と農村での経営形態の変化
ノーフォーク農法の拡大と共に農業革命のもう一つの柱は第二次エンクロジャー(囲い込み)である。第二次エンクロジャーは1760年から1830年にかけて進んだ。ノーフォーク農法は、高度集約農業なので大規模農場が有利であった。そこで、貴族などの大地主が、議会を主導し立法化することで、これまで共有地として用いられてきた土地を次々に囲い込んで私有化した。その結果、英国の耕作地の約20%が囲い込まれ、1830年代には共同利用していた開放耕地制度はほぼ消滅したようだ。農業の生産力が大幅に増大した一方で農場の経営形態は変容したのである。
農場の規模を大きくするほど有利なので、貴族階級の地主は大土地所有権を強化した。それらの地主は、今までのような自営農業者ではなく、高い地代が得られる農業資本家(借地農)に農地を貸した。囲い込みで土地や職を失った農民は、そのまま農場の賃労働者となるか、都市部で勃興した工場労働者となった。農村は大地主・農業資本家・農業労働者の三分割制の経営形態となり、農業の資本主義化が進んだのである。
4.都市への人口流入と社会構造
このように自営農民が都市へ流入したことによって、1700年頃は農村部に住む人々が全体の75%であったが、1800年には36%、1850年には22%にまで急激に低下したという。そのうえ人口の増加状況には偏りがあった。マンチェスター、リヴァプール、バーミンガムのような中部や北部における新興の都市で急激に増加した。このように急激で歪な都市化は、都市のスラム化など英国社会にさまざまな弊害をもたらすことになった。
しかし没落した自営農民が産業革命における労働者の重要な供給源となったことで、都市においては、工場を経営する資本家(ブルジョアジー)とともに、その工場で働く大量の労働者という新しい社会階層を出現させた。そして、地代で蓄財した地主や産業資本家は、本来なら政府が行うべきインフラ投資を積極的に行った。彼らの資金が運河建設、有料道路、港湾などの輸送事業に投資されて輸送インフラが改善した。そのおかげで、輸送の利便性が増して、商取引が一層活発化されるという好循環が生まれたのである。
英国は、半世紀で全人口が倍増する中で、同時に農業人口比率を低下させつつ、増大する非農業人口に安定的に食料を供給できた。このような離れ業が可能となったのは、産業革命と人口増加と農業革命が絶妙なタイミングで同時に起きたことにより、食物生産の状況と商取引が大きく変化したからである。産業革命によって、工業化が進み、製品を海外に販売することで、世界中から食物の輸入が可能となり、1850年頃は穀物必要量の6分の1を輸入することができた。「マルサスの罠」を超越する食料確保が可能となったのである。
英国の産業革命時で没落した自営農民が工場労働者となったように、AI技術の進展によって職を失うと予想される非熟練労働者に雇用機会を創出することが、今後日本が直面する課題となろう。それらの解決にはAI、IoTや5Gなどの技術革命分野だけではなく、さまざまな革新的な要素が多分野にわたって進展し、同時かつ複合的に絡まることが必要だと思われる。産業革命時の資本家たちのように将来を見据えて積極的なインフラ投資をするだけでなく、時代に即して私たちの社会構造全体が大きく変容することが要求されるのだ。
次回は、織機や蒸気機関などの技術革新やその前提となる資本蓄積について取り上げたい。
追記:
先般2018年製作の映画「ピータールー マンチェスターの悲劇」(マイク・リー監督)を観た。1819年8月16日の英国マンチェスターでの惨劇を映像化したものである。選挙権を求めて、セントピーターズ広場に集まった多数の民衆が虐殺されるにいたった悲劇を忠実に再現した。映画では産業革命当時の社会状況や労働者の生活ぶりが窺い知ることができて興味深い。
AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第1回]~2019年12月号
私たちは現在、第四次産業革命の最中にいると言われる。これから、私たちの暮らしはどのような変貌をとげるのだろう?
18世紀、英国発の第一次産業革命は水力や蒸気機関による工場の機械化とされ、第四次産業革命はIoT、ビッグデータとAIに代表される自律化と定義されるようだ。ちなみに、第二次産業革命は電気エネルギーに代表される大量生産であり、第三次産業革命はコンピューターに代表される自動化である。
これらの定義は、発明・発見といった技術的な側面に重きを置いたものだ。しかし、産業革命の成立要件は技術革命にのみ依存するものではない。
労働、金融資本、消費、流通、居住、農業、そして政治などの変化が複合的に絡み合うことで変革が達成されたのである。
では、その変革の成立要因とは具体的に何であろう?
具体的に要因を探るには、英国の産業革命時の社会情勢などを丹念に辿ることが必要だ。
世界に先駆けて、英国で産業革命が発生した理由も併せて紐解きたい。
歴史は未来を予言することはできないが、将来の行動のために有効な一般的な指針を提供してくれると言われる。
現在と18世紀では時代が随分と異なるので、参考になるのかとの意見もあろうが、人間の行動・心理面を含めて多面的に産業革命を探究すれば、現代への指針を導き出せるのではないかと考えた。
そのことが本稿を始める動機だ。
今回をスタートとして、英国の産業革命に関するテーマを複数回にわたり考察したい。
今回のテーマは「歴史と産業革命に対する捉え方」である。少し堅いテーマだが、今後進めるにあたっての私の基本的な考えを若干述べたい。
まず、一つ目のテーマの「歴史の捉え方」。
勿論、人により歴史認識はさまざまである。
私は、理事長就任の挨拶文の中で引用したE.H.カーの言葉を大事にしている。
英国の歴史家E.H.カーは『歴史とは何か』(岩波新書)の中で「歴史とは現在と過去との対話である。現在に生きる私たちは、過去を主体的に捉えることなしに未来への展望をたてることはできない」と論じている。
歴史は単なる過去にあった事実ではなく、自己の立場を正当化する手段として歪められる場合が多い。なぜなら、歴史は勝者によって描かれたり、その時々の政治の事情や都合によって書き換えられたりする。
そして、新たな史実の発見や技術的な進歩による科学的知見の積み重ねがあると漸く歴史的な評価が変化する。
イタリアの哲学者クローチェは「もともと歴史とは現在の眼を通して、現在の問題に照らして過去を見ることで成立する。歴史家の主たる仕事は記録することでなく、評価することである」と述べている。故に「評価した歴史家を先ず研究せよ」と言われる。足利尊氏の毀誉褒貶は時代によって変わった。
私たちが過去に学校の授業で習って、絶対的だと信じていた歴史の事象がいつの間にか変わってきている。鎌倉幕府の成立年号は今や1192年ではなく1185年らしい。
NHKの「英雄たちの選択」や「歴史秘話ヒストリア」などの歴史番組を視聴すると、敗者が後に極悪人と記述される事例や新しい科学的発見などにより新事実が判明する事例がしばしば取り上げられている。科学は普遍的であるが、歴史は個別的なのであろう。
そして、人間は今の世の中が暗いと思うと将来を悲観的に捉える傾向がある。昭和の高度成長期には輝かしい未来を夢見ていたが、少子高齢化の現在は「日本の未来は厳しい」と嘆く人が多い。
詩人ゲーテの言葉に「時代が下り坂だと全ての傾向が主観的になるが、現実が新しい時代に向かって成長している時は、すべての傾向が客観的になるものだ」とある。
昔から、先行き不透明な時代においては、過去を主観的に捉えがちである。
E.H.カーは「過去の諸事件と未来の諸目的との対話においては、過去に対する建設的な見方が必要」と論じている。第四次産業革命の到来による輝かしい未来を展望して、過去の事実を客観的かつ主体的に捉えることが求められる。
今回のもう一つのテーマは、「産業革命の捉え方」である。
さて、産業革命と名付けたのは誰なのか?名付け親の一人は、フランスの著述家アルジャンソン侯。T.S.アシュトンの著書「産業革命」の中で産業革命という言葉を作り出した人物とされている。
他には、フランスの経済学者J.A.ブランキが1837年に使用し、その後1844年にF.エンゲルスが広めたとされる。学術用語としての産業革命は、経済史家アーノルド・トインビーが自身の著作の中で使用したことで定着した。(このアーノルド・トインビーは 英国の20世紀最高の歴史家アーノルド・J.トインビーの叔父にあたる)
経済学者達の産業革命に対する捉え方はさまざまである。
まず、トインビーは理想主義的な社会改良主義の立場から「産業革命は、多くの貧困者が出現した原因である」と悲観的に捉えた。
そうした捉え方に修正を加えた本が先述のアシュトンの著書「産業革命」である。彼は、「英国における産業革命の惨禍の原因は技術的変革や経済組織の変化だけではない」と論じた。彼はこの著書の中でジョージ三世の即位(1760年)からその子ウィリアム四世の即位(1830年)に至る間の英国社会の変貌を非常に詳しく記述している。
その後、20世紀に入ると米国の経済学者W.W.ロストウが米国経済の繁栄を背景に「産業革命は豊かさの出発点である」と唱えた。彼の著書「経済成長の諸段階」(1960年)の5段階説では、産業革命時期を経済成長への離陸に向けたものとして前向きに捉えている。
さらには、1985年に経済学者のN.クラフツが産業革命期の英国経済成長を研究して従来の高い成長率を下方修正した。その結果をもって、「産業革命は存在しなかった」との産業革命否定論が出現した。
世界の工場としてパクス・ブリタニカを謳歌していた英国が「ヨーロッパの病人」あるいは「不満の冬」と呼ばれる深刻な経済停滞に陥っていたことが否定論出現の理由の一つであろう。のちに、その打開策として、鉄の女サッチャー首相の改革が登場するのだ。
こうして、トインビー、アシュトン、ロストウ、クラフツなどの産業革命に対する捉え方を比較すると、その人によってだけでなく、各々の時代背景によっても変化することが分かる。
歴史の面白さは歴史的事実を基に、どう自分の想像力を膨らますかだと思う。さまざまな歴史の出来事が世の中の触媒として、どう作用したのかを自分なりに仮説を立てることができれば本当に楽しい。
私にとって、高校までの歴史科目は年号や出来事を必死になって暗記するイメージが強く、正直苦痛だった。今から省みると、本当に勿体ない話だ。
昨年の暮れから「承久の乱」という同じタイトルで2冊の新書が相次いで発刊された。
その新書は坂井孝一氏と本郷和人氏によるものであるが、双方を読み比べてみた
歴史の捉え方という面で、後鳥羽上皇、北条義時、鎌倉幕府などに関する両者の視点や主張の違いを比較するのは大変面白かった。
最後になるが、スペイン、オランダ、フランスなどの列強国ではなく、欧州の片田舎にすぎなかった英国において「何故、最初に産業革命が起きたのか」という歴史事実は非常に興味深い。
次回は、英国第一次産業革命成立の前提条件として、まず人口面と農業面から、アプローチしたい。
