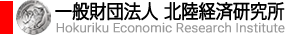人手不足・熟練者不足に備える!
高年齢者雇用を見据えた人事マネジメントセミナー
| 日 時 | 2025年10月8日(水) 9:30~16:30 |
|---|---|
| 場 所 | 各受講企業またはご自宅にて(Webミーティングシステム「Zoom」を使用) ※本研修はオンラインのみで実施いたします |
| 対 象 | 経営者・経営幹部、人事担当者 |
| 定 員 | オンライン:40名 |
| 参加費 | 賛助会員(1名):23,100円、非会員(1名):42,900円 |
| 講 師 | 株式会社寺崎人財総合研究所 代表取締役 寺崎 文勝氏 |
本年4月からの高年齢者雇用安定法改正により、すべての企業に65歳までの雇用確保が義務化され、70歳までの就業確保(努力義務)が設けられました。労働力人口の減少が見込まれ、人手不足、熟練者不足など、待ったなしの問題とともに、バブル期採用が定年年齢を迎えることで、改めて高年齢者の人材活用のあり方を見直すときが来ています。
従業員確保の対応に加え、シニア人材の経験やノウハウを活用するために、働きやすい環境づくりに制度変更することが急務となっています。また、現役世代の処遇との整合性をどうとるかも重要なテーマと言えます。
本セミナーでは、自社の高年齢者雇用のスタンスを明確化することの重要性を示した上で、高年齢者雇用制度の課題を整理します。多くの企業が採用している継続雇用制度(対象者、賃金、処遇体系等)について、人事マネジメント、正社員の人事制度との整合性、同一労働同一賃金の考え方、リスキリング、キャリア開発など、運用上のポイントを解説します。
セミナー内容
1.はじめに
①人的資本経営とはなにか
②人材版伊藤レポート2.0 とは
③人材のサステナビリティと学び直し
④ジョブ型人事とはなにか
⑤ジョブ型人事導入の主な背景と目的
⑥人事マネジメントのパラダイムシフトが進む
2.改正法と各社の対応状況
①60 歳以上雇用確保措置の実施状況
②各社の状況
3.高齢者雇用をどう考えるか
①人材マネジメントと高齢者雇用
②高齢者雇用のスタンスを決める
③人材ポートフォリオ (to-be)
④人材ポートフォリオ (as-is)
⑤作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組
⑥高年齢者の意欲・能力の維持向上のための取組
4.高齢者雇用の選択肢と各制度の特徴
①定年年齢の引き上げ
②定年制の廃止
③継続雇用制度の導入
継続雇用制度の設計と運用のポイント
継続雇用制度のポイント
5.人事制度の見直しアラインメント
①人事マネジメントの全体像
②高齢者雇用と人事制度改革
③賃金曲線とパフォーマンス曲線の関係
④40 歳定年論の再考
⑤ゼネラリストの真の価値とはなにか
⑥スペシャリストの育成と活用
⑦複線型人事制度(キャリア開発)の見直し
⑧能力処遇から職務処遇へ①
⑨賃金水準設定における「公平性」の担保
⑩賃金制度の選択肢
⑪能力処遇から職務処遇へ②
⑫職務給か役割給か
⑬人材要件定義/ 職務記述書(Job Description)
⑭職務概要および職責の作成例(営業マネジャー)
⑮能力定義の作成例(営業マネジャー)
⑯職務等級・職務給制度の導入イメージ
⑰職務等級/職務給設計の手順
⑱職務評価のバリエーション
⑲ポイント法によるジョブサイズ算出イメージ
キーワード
①請求書や受講証、オンライン受講者様へのご案内(接続URL)はE-mailにてお送りいたします。ご連絡担当者様およびオンライン受講者様のE-mailアドレスをお知らせいただきますようお願いいたします。
②請求書・受講証はご連絡担当者様宛に、原則、開催の2週間前にE-mailにてお送りいたします。
③オンライン受講の際は、カメラは常時オンでお願いします。テキスト等の資料はメールで送る場合がございますので、事前に印刷してお手元にご用意いただきますようお願いいたします。
④オンラインセミナーは記録用にレコーディングをする場合がございます。場面によっては、受講者が映る可能性がございますが、ご了承ください。
⑤キャンセルのお申し出は5営業日前までにお願いいたします。以降のキャンセルは受けできません。ただし、当研究所主催の他のセミナーへの振替受講のお申し込みをお受けいたします。
⑥最低開催人数に満たない場合は、開催を取りやめる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
⑦駐車場につきましては、事前にお送りする「受講証」でご確認ください。駐車料金は各自ご負担ください。
その他、ご不明点はTEL:076-433-1134または、e-mail:haginaka@hokukei.or.jp までご連絡ください。